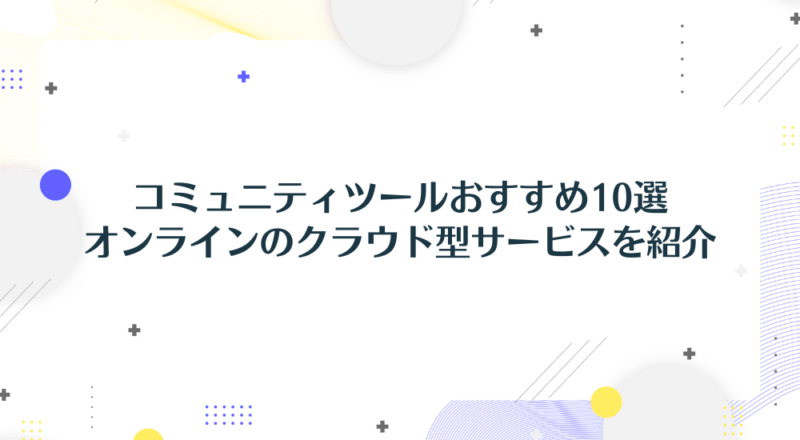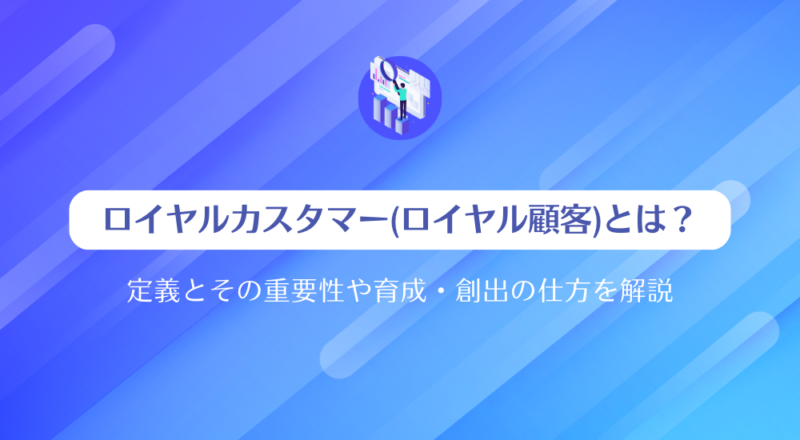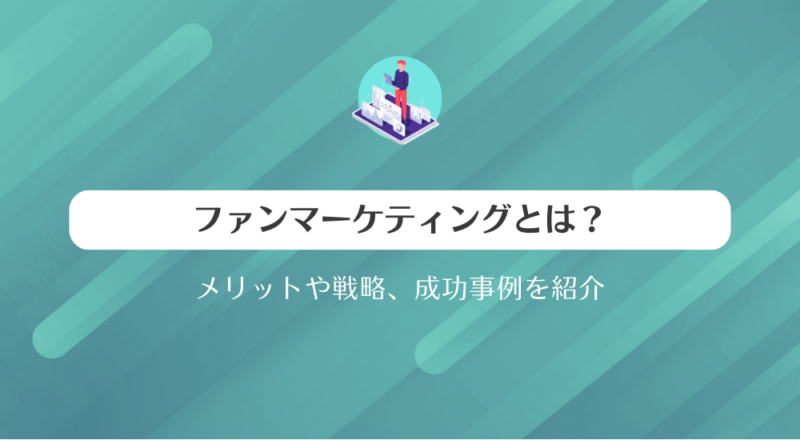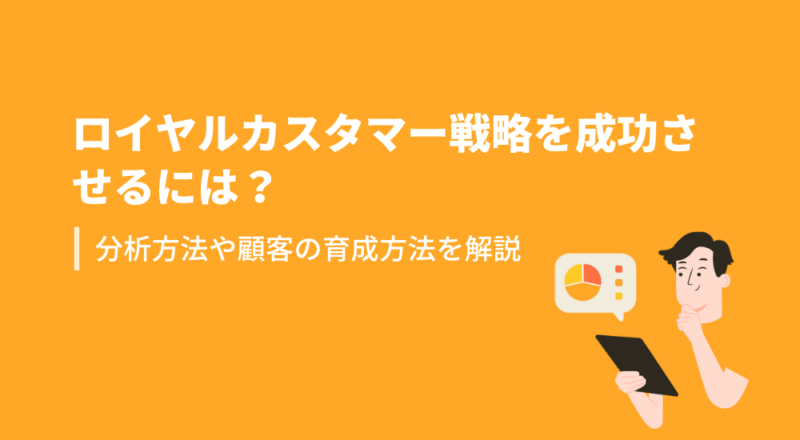2021年4月27日に開催したオンライン対談イベント『シンプルなプロダクトでもCSは必要!? 6年で顧客数を20倍にしたカスタマーサクセス戦略を大解剖!』では、Box Japanよりカスタマーサクセス部マネージャーの西田幸弘氏にご登壇いただき、株式会社Asobica取締役CCOの小父内信也氏がモデレーターを務めました。
今回イベントに参加できなかった方にもお楽しみいただけるよう、本レポートではイベントの内容をダイジェストでお届けします。
| 西田幸弘 氏(以下、西田) Box Japan カスタマーサクセス部 マネージャー 小父内信也 氏(以下、小父内) 株式会社Asobica 取締役CCO |
イントロダクション
西田:まず始めにBoxとは?というところから簡単にご紹介いたします。続いてカスタマーサクセスマネージャー(以下CSM)部門の目的や戦略、施策についてお話しします。
それからイベントタイトルにも「6年で顧客数が20倍」とありますが、お客様のフェーズが6年の間で変わっていったので、それに対してどのようにカスタマーサクセス(以下CS)が変化していったのかをお話ししたいと思います。
Boxとは
西田:Boxは2005年に設立いたしまして、本社はアメリカのレッドウットシティにあります。世界での社員数が2000名ほどです。
今全世界での導入社数が10万社くらいで、日本以外は直販ですが、日本では99%が代理店販売になります。
小父内:この代理店ビジネスについてのお話は今日の醍醐味の一つですね。
西田:そうですね。Boxから一次代理店7社に対して販売して、その7社から直接お客様に販売することもできますが、その先に二次代理店さんをおくこともできまして、二次代理店さんが210社あるという販売体制になっています。
シンプルでも奥行きが深い
西田:そして、一般的にBoxはシンプルといわれてます。皆さんがシンプルと仰るのは、おそらくUIのことを指しているものと思います。ただ、シンプルな中でも結構奥行きがあります。企業で使っていただく上できちんとセキュリティを設定して、特定のフォルダは社外の方に共有しないように設定しておくことや、そのためにアクセス権を細かく設定しておくこと、あとは他のシステムとAPI連携することなどが可能です。例えばOffice365やGoogleワークスペース、業務コミュニケーションの中で利用されるSlack、最近ブームにもなっているDocusignのような電子サインのシステムと連携して使うことができます。
このように、企業に特化したクラウドコンテンツシステムということで、見た目はシンプルでも奥行きが深いものになっています。
テレワーク時代における顧客の傾向
西田:どういったテーマでBoxを買っていただくお客様が最近多いのかというと、わかりやすく言うと6つあります。
まずはテレワークの推進です。次に、テレワークで業務をする中で気になってくるのがやはり情報漏洩対策です。そして文書管理ですが、機密情報からカタログのような誰でも見れるようなものまで色々な情報が入っていて、それをきちんとカテゴライズして管理したいというお客様もいらっしゃいます。それからPPAP、つまり添付メールを廃止する代替手段としてBoxを使っていただくというところです。あとは脱ハンコで、Boxを簡単な確認プロセスに利用していただけています。そして最後がDXになります。
小父内:ハンコのために出社する人もまだ多くいらっしゃいますからね。
西田:仰る通りですね。
西田:今世界では10万社、そのうち日本では9000社のお客様がいらっしゃいます。
小父内:1割近くですね。
西田:そうですね。そしてこちら見ていただくとわかる通り、業界特徴がないんです。
小父内:全部の業界ですね。
西田:ただ順番としては小父内さん出身のsansanさんのように最先端のテクノロジーを取り入れるような企業様から採用していただいて、最近では製造業、金融、公共といった業界のお客様もご利用いただいています。
小父内:新日本プロレスなんかも入っていますね。
西田:あっ!よく気づかれましたね。
小父内:情報やデータはどんな企業も持っているもので、だからこそ業界関係なく幅広いお客様が利用されているということですよね。
400社の契約者数がわずか6年で9000社(約20倍)に
西田:そしてここからが本題になりますが、先ほど契約者数が9000社と言いましたが、私が入社した2015年当時は400社でした。
小父内:20倍以上ですね。
西田:はい。そして2015年はCSMが2人で、導入・定着をお客様のメインテーマとして注目していました。きちんと使っていただく、そしてその上で1つでも成功事例を作っていただくことをCSMとして意識していました。
そして6年経って9000社になり、CSMは現在13名です。お客様もステージが多様化して、ご購入して間もないお客様もいらっしゃる一方で、もっと色々な業務シーンでBoxを利用したいというお客様もいらっしゃるようになりました。CSMの意識としては、顧客のステージが変わったとしてもお客様に提供できる価値は何かというところにより一層注力しています。
Boxがカスタマーサクセスに力を入れる理由
西田:BoxのCSMは何をしているのかお話しする前に、そもそもなぜBoxはCSに取り組んでいるのかをお話しいたします。まず、会社の方針の中に組み込まれています。
会社のコアバリューが7つあって、行動規範のようなものなのですが、その中でトップに書いてあることが「お客様を感動させる」”Blow our customers’ minds” です。ただ単に製品を提供するだけでなく、製品を使って感動していただくことを会社としてきちんと提供していきましょうとバリューとして掲げていることが、なぜCSMがあるのかという出発点になっています。
そしてそれを受けてCSMは、お客様がBoxを効果的に活用し、継続していただくことを目指しています。最終的にはお客様の顧客獲得につながったり、お客様自身がCSになったりして、お客様のビジネスに貢献することを追求していくことがBoxCSMのミッションになります。
顧客の内訳
西田:そして9000社の内訳ですが、様々なお客様にご契約していただいています。そこで、年間の契約金額に応じてTierで分けています。Tier1(以下、T1)60社、Tier2(以下、T2)が220社です。Scaled CSMが720社、Self-service(以下、Self-serv)8000社という形になります。
小父内:およそ9割がSelf-servなんですね。
西田:そうですね。それから、よく2割のお客様で8割の売り上げという意味で2:8の法則と聞きますよね。ほぼそれに近いです。
また、この内訳に関して、Tierの分け方自体が変わったところがあるものの今のTierに照らし合わせると2015年とほぼ同じ比率です。
顧客規模に応じたチーム作り
西田:そして、Tier分けをした上で、戦略として人の配置をどうしているのかについてですが、主に3つあります。
1つは主要のお客様に対するストラテジックエンゲージメントで、これがT1とT2の280社になります。お客様ごとに担当者を配置するハイタッチになっています。T1T2に関してアメリカからは金額ベースで分けましょうという話が持ち上がったのですが、金額ではなく業界で分けた方がナレッジが生きるので、日本は少し異なり業界ごとにCSMを配置しています。
13人のCSMのうち、ここに8人がいます。
2つ目がプログラムです。Webセミナーを月2回行っています。ニュースレターは月1回配信しています。それから、とてもよく活用してくださっているお客様を表彰しています。ここには3人のCSMがいて、そのうち2人がプログラムを回して、あとの1人はデータアナリストになっており、データを分析してプログラムに反映させるという体制になっています。
そして最後に、お客様から見えているBoxの契約先はパートナーさんになります。そのため、パートナーさんにCSMをお願いしています。
小父内:パートナービジネスをCSがやることは日本では中々ないですよね。すごく驚きました。
西田:最近は増え始めましたが、おそらく2016年にBoxが最初にやり始めたのではないかなと思っています。
西田:そして、パートナーCSMを担当する方に昨年入っていただいたのですが、この方1人が基本的に一次店7社を担当しています。
パートナーとBoxCSMで担当顧客が重なる部分も結構あります。T1&2のお客様エリアでは、パートナーとBoxのCSMの2つの体制があります。その場合は二者間で話し合って、お客様に応じてパートナーさんとBoxのどちらを前に出すべきかを、販売の経緯なども考慮した上で協議をしています。
小父内:それはTierで区切るのではなくてその都度話し合うものですか?
西田:T1T2はBoxとパートナーのCSMが話し合って分業と協業し、Scaled以下は我々からは基本的にプログラムのみを提供してパートナーさんが担当する形になっています。なので、どちらかというと広域にカバーする部分で、ScaledとSelf-servのお客様にはパートナーさん経由でCSを提供している体制になっています。
BoxカスタマーサクセスチームのKPI
そして、我々は2つKPIを持っています。
まず1つがリテンションレートです。お客様は大体一年契約なので、毎年リニューアルを迎えます。そこで契約更新されたかどうかを金額で計算して目標値との差を見ています。
もう1つはヘルススコアです。それら2つの達成率でボーナスプランを設定しています。個々人ではなくて、チームで達成できたかどうかを見ています。
小父内:パートナーさんのインセンティブはどのように設計していますか?
西田:まずパートナープログラムガイドというものがあります。その中にCSMの要件も作っていて、一次店の皆様にはCSの体制を作っていただくようお願いしています。売り上げ規模に応じて何人、という形が体制としては多いです。
あとはBox Japanと話し合いながらCSをしましょうということで、お互いに情報提供をして、BoxCSMからはノウハウ提供、パートナーからは解約リスクがある場合には教えていただくようお願いしています。
それからパートナーさんにも同じKPI、ヘルススコアを握っていただいています。それが達成できたら、翌年の契約更新については一定のディスカウントをBox Japanとして提供することを制度として設けております。
小父内:代理店というと営業代理店というイメージがすぐ湧きますが、御社は中長期の体制を構築するため、CSとして売る以上はヘルススコアも同じものを持ちましょうということが言えて、それに対するインセンティブも伴ってくるということですよね。
ちなみに二次代理店とやりとりすることはないんですか?
西田:Boxが直接することはないです。ただ二次店さんも大きくなってきているので、規模によってはコミュニケーションを取った方がいいのではないかという状況で、そこは今年取り組むべきところかなと思っています。
小父内:Self-servの8000社について、代理店経由とはどのような仕組みでしょうか?
西田:パートナーCSMというカットで言うと、パートナーさんにはScaledに注力してくださいとお願いしています。あとは我々のプログラムが後ろ盾としてありますが、Scaledの部分はパートナーCSMの方々に活躍いただきたいと思っています。
Self-servに関しては、数が多いので、そこは我々のプログラムをパートナーからお客様へご案内するなどして、Boxのリソースを有効活用していただくようお話ししています。
小父内:御社のCSMはT1T2に注力していて、Scaledの部分に関しては代理店でカバーしていきながら、9割近くを占めるSelf-servの8000社に関してはプログラムでテックタッチを推進していくということですね。
西田:そうですね。それから、パートナーさんも同じ構造になっています。そうするとSelf-servのお客様は数が多くなるので、先進的なパートナーさんは我々が行っているウェブセミナーのようなことを独自で行っていただいたりもしています。
パートナーを巻き込み、カスタマーサクセスを推進するポイント
パートナーさんにノウハウをどう提供しているのかというところで、Box Japanは認定CSM制度というものを作っています。そこでは我々のノウハウを公開しておりまして、まずキックオフでCSMとは何かについて説明しています。そして、大体10項目ほどのトレーニング内容で、合格すると認定CSMと公言できるようになっています。
小父内:このeラーニングは自社で作っているんですか?
西田:そうですね。実はBoxを使っています(笑) ビデオを見ていただいて、テストに合格すると認定、という形ですね。
小父内:質問がきていますね。インストール項目はどうやって選定されましたか?
コンテンツの内容が何を習得するノウハウなのか、という意味ですかね。
西田:Box JapanのCSMが2015年に発足して、その翌年2016年からパートナーCSM制度が始まったのですが、その1年間で学んだことを全部コンテンツ化しました。私含め3人ほどが集まって、契約した後から何が必要なのかを洗い出してコンテンツを作っていき、認定CSMの第一弾を作りました。
オンボーディングは初速ではなく、ゴール設定と伴走
小父内:6年で変化したというお話しがありましたが、このアップデートやキャッチアップは重要ですよね。
西田:そうですね。昔は契約からオンボーディングの最初の動きが大事でしたが、次にやはり当初の導入ゴールを達成したお客様が同じ状態のまま使い続けているとサービス内容に満足していただけなくなってしまう可能性があるので、きちんと次のゴール設定をして、それに向かって我々BoxCSMが支援することが大事だと思います。常にゴールを設定して、それに対するお客様のKPIを把握した上で、その設定されたゴールに向かってBoxをどう活用していくのかについてお客様と一緒に方向性や計画を立てていきます。あとはお客様のゴールに対してどういったプロジェクト体制が必要なのかや、場合によってはお客様側で体制を作っていただきます。それからユースケースに関して、Boxを業務上決まった目的に対してどのように使っていくのかを決めることと、それに対してどういったBoxの設定が必要になってくるのか。そして最後が定着化ですね。
小父内:オンボーディングから定着まで至るのにどれくらいの期間が必要ですか?
西田:期間は規模とお客様の導入の目的によって変わると思っています。一般的なヘルススコアとしては、ライセンスの配布率が80%、アクティブユーザ率が50%以上をこえると、最低ラインの定着化は完了したと判断しています。
カスタマーサクセスが支援を行うタイミング
西田:どのフェーズでCSが入るのかについてですが、一般的なものと同じで、契約するとまず有償の導入コンサルティングがあって、設定やコンテンツの移行作業などを行います。その後エンドユーザー様がご利用し始めたあたりでCSが入ります。気をつけているのはパートナーさんとの連携含めきちんと引き継ぎをすることです。そのベースとなるのがカスタマプロファイルです。導入の目的や今後の計画、体制を把握して、その上でCSとして契約が続く限りご支援させていただきます。
小父内:お客様のペルソナの設計はしているんですか?
西田:はい。特に定着化の部分で、やっぱり我々がお話しするのはIT部門の方々が多いですが、実際に利用されるのはエンドユーザー様、事業・部門の方々なので、これらの部門でどう使っていくかということをIT部門の方とも議論しながらペルソナを作っています。
西田:あとは、Boxをすごく活用してくださっているお客様を表彰しています。
年一回9月頃に開催していて、マーケティングのイベントを7月に行った後で具体的にどう利活用されているのかをお見せする場としても、こういったイベントを開催しています。
小父内:評価基準は何かあるんですか?
西田:評価項目を決めていまして、我々の役員クラスが点数ベースで評価して表彰しています。登壇&表彰企業を記事にしております。これを見ていただいた他のお客様のBox利活用の刺激にもなっているところが良い点ですね。
導入〜定着よりも、顧客への提供価値の最大化を重視
西田: お客様のステージが多様化して来ています。また採用の理由も変わってきています。最近ですと、DXや添付メールの廃止などをテーマに採用いただくケースもあります。また、Boxも製品の進化や競合製品の進化に伴って変わってきています。こういった状況が常に変化する中で、常にお客様がBoxをつかって何を解決したいのかのゴールをお客様と合意していくのが大事だと思っています。
CSMとして、2015年時点では導入、定着が大事でしたが、継続して利用しているお客様のステージの変化に応じて、ゴールを明確にして価値を最大化するというところに、CSMの手法もシフトしています。
それに合わせてCSMのスキルも変わってきていて、定着化をすることや優先度を決めて取り組むことは一番基本的なCSMに必要なスキルだと思いますが、次の段階としてお客様をきちんと理解する、お客様がどういうビジネスをしているのか、課題は何かなどの営業スキルに近いところも身につけていく必要があると思っています。
ヘルススコアをベースに、利用価値の有無を分析
西田: そして最後に、カスタマーヘルスを算出しています。これまではライセンスの配布率のように製品で測れる部分しか取っていなかったのですが、今は定性的なところもヘルススコアとして取っています。利用価値があるか、導入の決定者とコミュニケーションがとれているか、その方がBoxに対してどう思っているのか、継続してBoxをご利用する体制を構築していただけるかなどをヘルススコアとして見ています。
小父内:項目によって点数が付与されるのでしょうか?
西田:そうですね。各項目で1点2点3点とスコアリングして、1点が多いお客様は優先度が高いなどの判断基準にしています。ただヘルススコアの目指すべきところは数字ではなくて、お客様が感じていただくBoxの価値だと思います。その価値を感じていただくために押さえるべきポイントとして、ヘルススコアを一つの目安にしています。
小父内:システムの習熟度も重要な観点ですか?
西田:仰る通り重要ですね。やはりシンプルながらも奥行きが深い製品なので、隅々までご利用なさっているかは一つの指標として取れるようにしています。