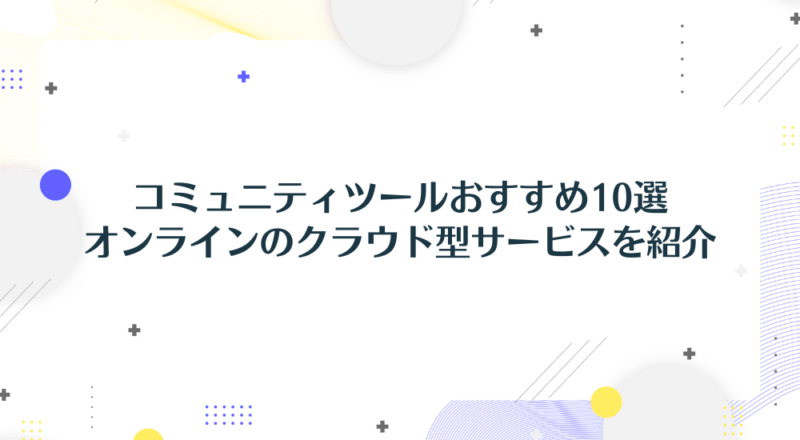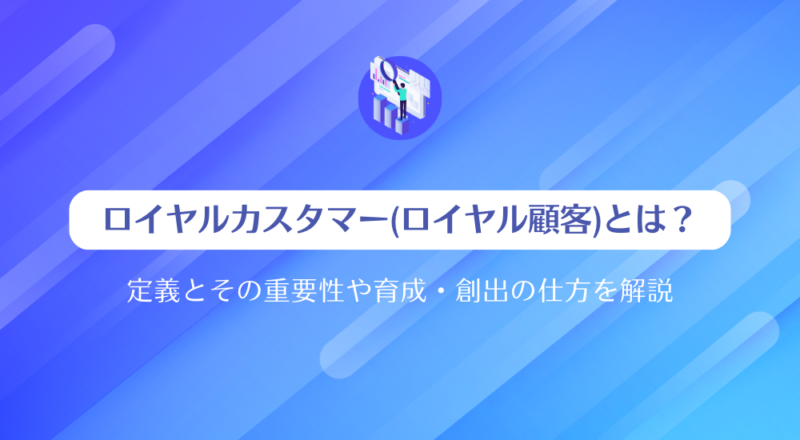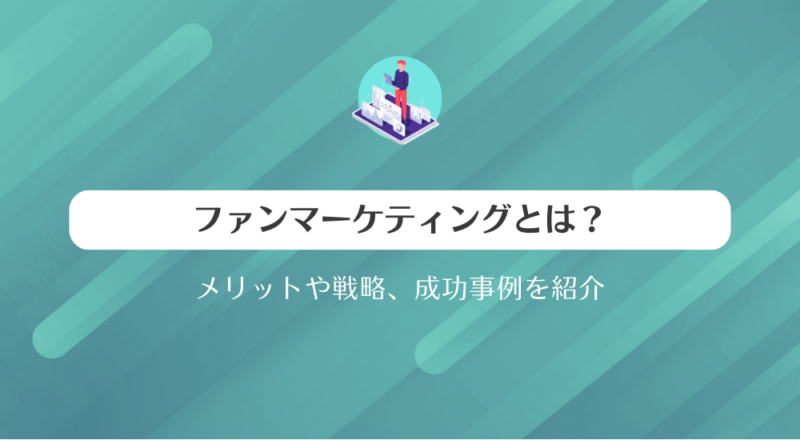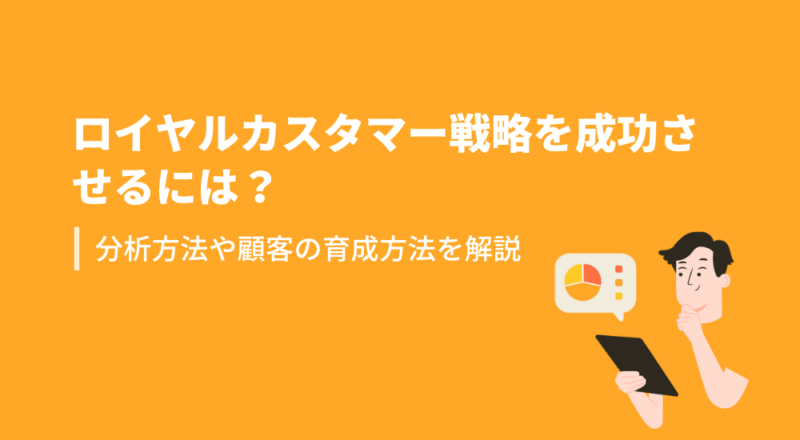ファンマーケティングという手法について、その事例や実装に向けた動きをみる時に「コミュニティ」という考え方がよく取り上げられます。
- ここでいう「コミュニティ」とは?
- どういう効果が期待できる?
- なぜ今コミュニティなのか?
これらの疑問について、前回に引き続き、Asobicaセールスマネージャー、ファンコミュニケーション研究室の室長である佐藤頌太さんにインタビュー形式で解説していただきました!
| 佐藤 頌太 新卒入社のGunosyで、CyberAgentとの合弁会社でブランド企業のブランディング貢献に従事しながら、Gunosy社の広告販売でも月間最高売上に並ぶ売上を達成しMVPを受賞。 Gunosy退職後に独立しブランドマーケティング会社を設立。大手外食チェーンや食品メーカー、ペット関連商品や金融企業のブランド成長戦略として、ブランディング施策、ファンマーケティング施策で多数実績あり。2021年度よりAsobicaに加入。 |
「コミュニティ」とは?
ー今回なんですが、ファンマーケティングを調べている時によく出会う「コミュニティ」について教えていただきたいです。そもそもここでいう「コミュニティ」ってどんな場所を指しているんでしょうか?このワードだけだと、定義が沢山ありますよね。
ここでいうコミュニティは、「同じ価値観を持つユーザーが集い、ブランドやブランドテーマについて語り合う場」を指します。これをファンマーケティングの考え方に準えるなら、「ファンが推しブランドについて語り合う場」とも表現できますね。
このコミュニティの大部分は、企業のブランドや提供するプロダクト、サービスを応援してくれる存在であるファンで構成されます。そのブランドに対する愛や、こうしたらもっと面白いのでは?というフィードバックを送り、ファンと企業、もしくはファン同士でお互いにその熱を高め合っていく。それを実現する場所が、コミュニティの位置付けになります。
ーとなると、*以前に解説していただいた、企業とファン間のベースコミュニケーションの場としても機能しそうですね。
(*参考:https://cxin.coorum.jp/interview/satou-shota-01/)
その通りです。それこそ、金銭的なインセンティブによる働きかけだけではなく、相互の熱を共有することで生まれる自発的かつ能動的なコミュニケーションも見込めます。そのブランドに対しての愛が、コミュニティにおける活動のモチベーションの源になっているわけですからね。
ー確かに。では、なぜファンマーケティングの文脈で「コミュニティ」という考え方がよく取り上げられるのでしょうか?その繋がりが難しくて……
まず軽くファンマーケティングをおさらいしましょう。僕自身の定義ではありますが、ファンマーケティングとは「お客様(ファン)との関わりを通じて事業成長を図るためのマーケティング手段」であると認識しています。ファンの声を直接聴き、プロダクトやサービス、さらに新規顧客に向けたコミュニケーションに反映させていく。そしてそれがコンテンツの質向上、更なるファンづくり、安定した売上向上(事業の着実な成長)という具合に繋がっていきます。
ここから見出される前提として、「ファンの方との双方向のコミュニケーションが成り立つ場が存在するか」が必要な要件として挙げられます。これがないとファンマーケティングを始めることすらできませんし、ブランドのファンで居続けていただくことも叶わないからです。
コミュニティに期待される効果
では本題に戻していきます。簡単に前提として進めましたが、まずはじめに多くの企業の方が、「どうしたらファンの方との双方向のコミュニケーションを実現できるのか」という課題に直面することと思います。ここで、コミュニティという考え方が、1つのソリューションとして提示されるわけです。

ーなるほど。先に説明していただいたようなコミュニティが、ファンの方とのコミュニケーションの場としての役割を果たす、ということですね。
そうです。加えて先ほど、このコミュニティという形が「自発的かつ能動的なコミュニケーションを生む」といった内容を説明しました。この要素も、双方向のコミュニケーションを実現させる上でかなり重要になってきます。
では、それがどう実現されるのか。そもそもこのコミュニティの特徴として、構成メンバーが企業、ユーザー含め、全員そのブランドのファンであるという点が挙げられます。だからこそ、発信された意見や想いに対して、共感やリアクションが得られやすいんです。それが発言への安全性の向上に繋がり、さらなる積極的な活動、そして熱狂する場へと加速していくんですね。

このようにコミュニティでは、金銭的な動機ではなく、「そのブランドが好き」という動機で発信された内容に対して共感やリアクションがつくことで、企業とファン間、さらにファン同士で双方向性をもったコミュニケーションがどんどん生み出されていきます。
簡単にまとめると、
- ファンとのベースコミュニケーションを図る場としてコミュニティが効果的に機能する
- より双方向性を持ったコミュニケーションを実現する仕組みがある(ファンとしての発信→相互の共感→さらなる発信のサイクルが生まれる)
というのが、ファンマーケティングにおいて、私たちがコミュニティに期待している部分です。

なぜ「今」コミュニティなのか
ーファンマーケティングの文脈で、なぜコミュニティが取り上げられるのか分かってきました。でもなぜ「今」コミュニティなんでしょうか?
前回、なぜ現代の社会でファンマーケティングが注目されてきたかという話をした時に、社会の変化を背景として、既存の顧客層に着目し、継続的にファンで居続けてもらう方向にシフトする必要があるのではないか、といった内容を説明しました。
しかし、これまでのSNSを用いたマーケティングは、もちろんうまくいっている施策もありますが、どうしても「一方的」になりがちなところがあるんです。Twitterの施策でいうなら、リツイートすることで割引を行ったり、商品を渡すキャンペーンだったり。キャンペーンに関する投稿のリアクションは多いのに、それ以外の情報提供の投稿に対するリアクションが極端に少ないケースは、実際よく見られます。
ー確かに企業の公式のアカウントの投稿で流れてくるものは、割引やプレゼントといった投稿が多いように思います。場合によっては、捨て垢(キャンペーンなどに応募するためだけに使うアカウント)を作っている人も少なくないですね。
ここで獲得したユーザーは、そのインセンティブを求めて集った顧客であり、そのブランドのファンではないということも多いと思います。言い換えれば、「プロダクトやサービスに価値を感じている」のではなく、「打ち出したキャンペーンに価値を感じている」状態なんです。この層にブランドに対する想いやフィードバックを求めても、本質的なものは返ってこない。しかも、そのユーザーでさえ、近年の変化に伴って獲得が困難になっているというのが現状です。
だからこそ、そのブランド自体に対して強い想いを持つファンで構成される「コミュニティ」という場所が新たに注目されているんです。
まず、発信と共感の獲得、心理的安全性の向上のサイクルのもと、双方向のコミュニケーションが実現できる。その時間や機会を通じて、ファンの方々にブランドから大切にされているという実感、共創している意識を持っていただくことができる。そして、企業側は提供するプロダクトやサービスに対する本質的なフィードバック、率直な想いを受け取ることができる_
このように、急速に変化する社会に対応するために有効な特性を兼ね備えているという点で、コミュニティが「今」注目されているのだと思います。
ーなぜコミュニティがマーケティングにおいて注目されているのか、それは社会の急速な変化の中で、企業が生き抜いていくための場として、いくつもの有用な機能を持っているからなんですね。概念をはじめ、コミュニティが今の社会でどう必要とされているのかが良くわかりました。ありがとうございました!
「ファンマーケティング」の入門。vol.2のまとめ

「カスタマーサクセスをより詳しく知りたい」あなたへ
私たちAsobicaが手掛けるカスタマーサクセスプラットフォーム「coorum」では、既存顧客の分析から試作実行までをワンストップで提案・実現し、”ファン作り”をサポートしています。
そのノウハウを活かし、ユーザーをファンに変える方法を4つの「よくある間違い」を事例に解説しました。

資料請求は無料。気軽にお申込みください。