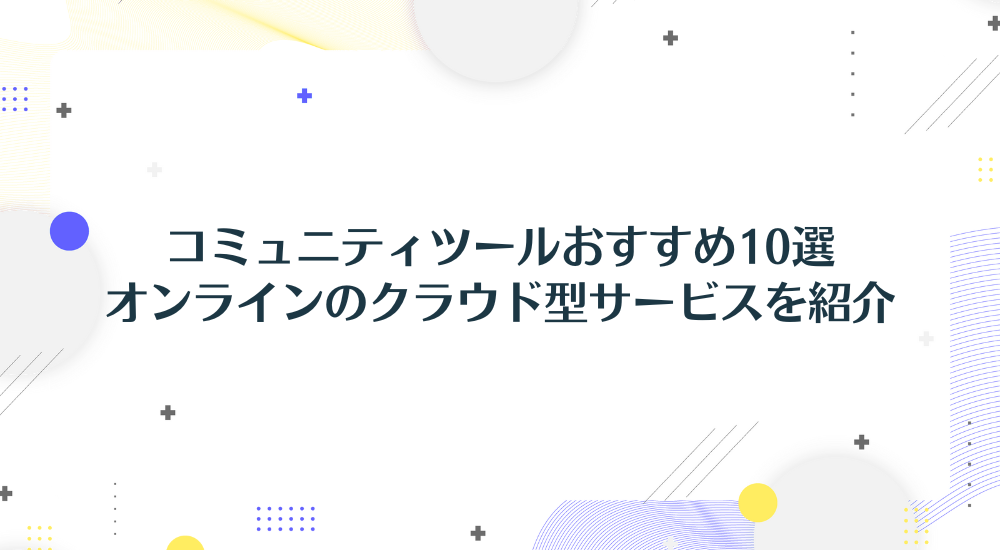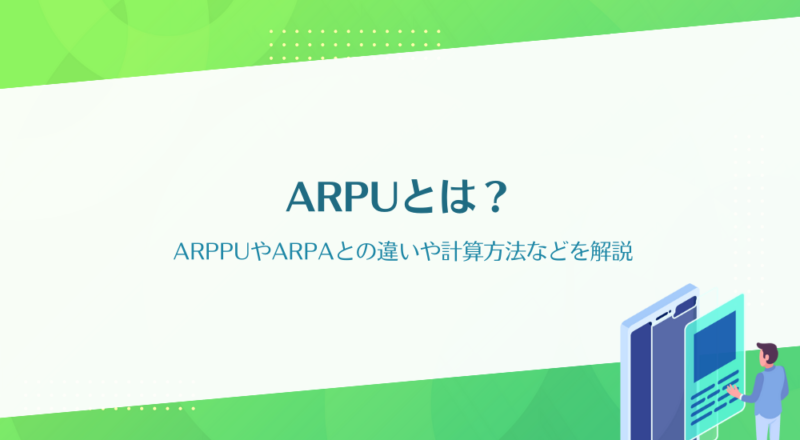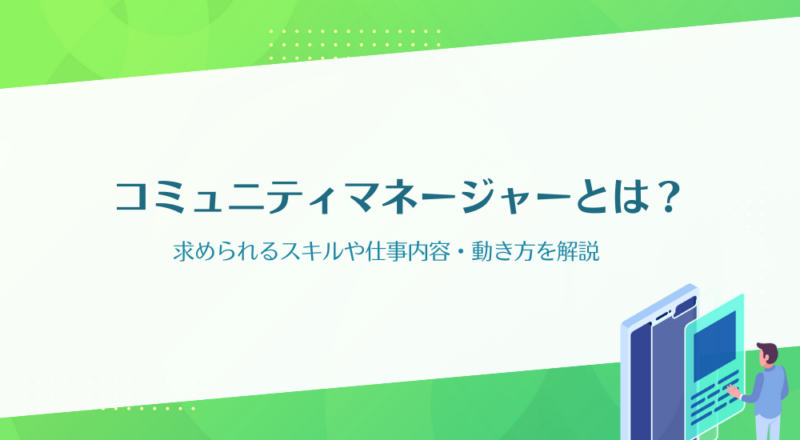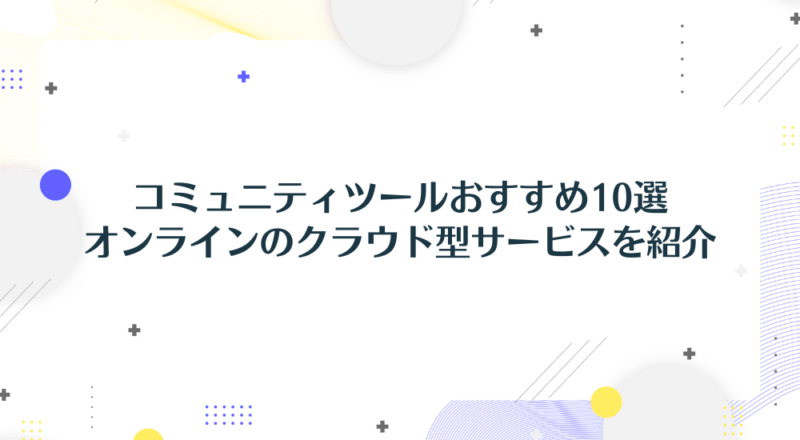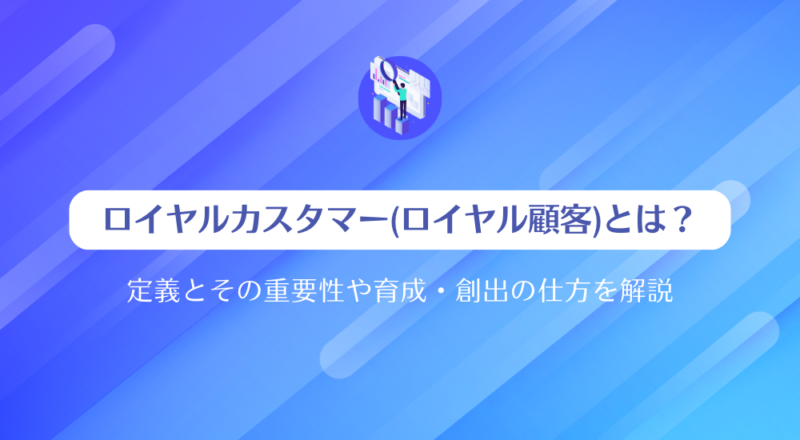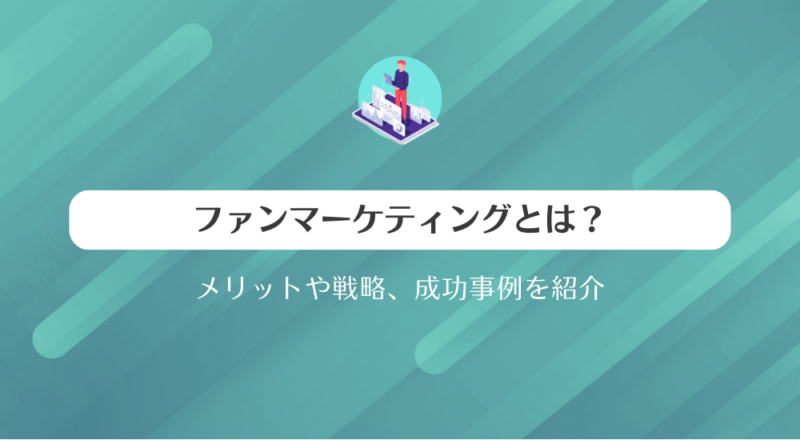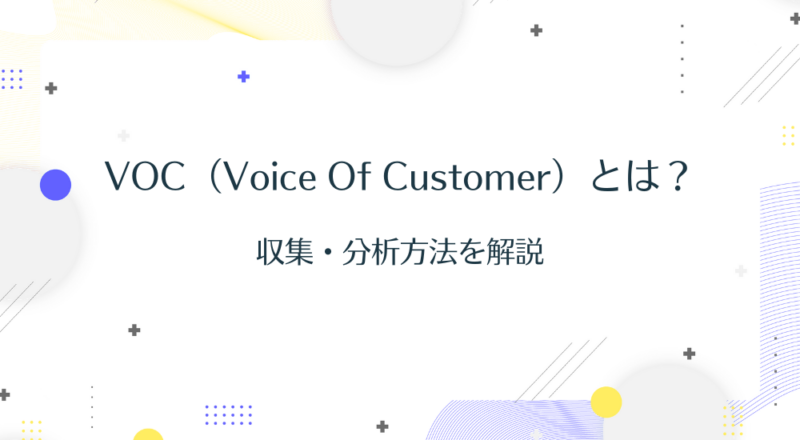コミュニティツールとは、ブランディングやロイヤル顧客の育成に役立つコミュニティサイトを、迅速かつ簡単に構築するためのツールです。
コミュニティツールは管理や運用まで一元化できるため、カスタマーサポート業務の効率化やユーザーニーズの把握にも重宝します。
今回は、コミュニティツールの意義や主な機能、メリット、デメリットから、運営ツールの選び方、おすすめのツール10選について紹介します。
コミュニティツールとは?

コミュニティツールとは、ユーザー自身が参加し、商品やサービスに関する他のユーザーの意見や要望を集約したり、利用に役立つコンテンツによってユーザーの顧客満足度を高めたりするためのオンラインスペースを、構築・管理するツールのことをいいます。
ユーザーが集まるコミュニティは、近年マーケティングにおいて大きな注目を集めているトレンドです。さまざまな企業が自社の商品やサービスなどに関するコミュニティを立ち上げ、よりスピーディーかつ正確な分析、コスト削減に役立てています。
ただコミュニティはそれぞれ異なる目的があり、仕組みや運営ルールも一通りではありません。
ツールの意義も、「商品・サービスの利用を増やすためのツール」から「ユーザーが使いやすいツール」に変化し、ツールを利用する上でもユーザーとの適切な関係を構築・維持することが重視されるようになってきました。
ユーザーコミュニティの重要性

近年のユーザーコミュニティが重視されている理由は、ユーザーコミュニティ自体に企業の目的に役立てられる重要性を持っているためだといえます。
「Facebook」や「Instagram」「X(旧Twitter)」のようなSNSは、特定の関心を持つユーザーが集まって交流を持つコミュニティの代表格です。コミュニティでは最新情報だけでなく、ユーザーの感想や意見も数多く掲載されます。
ユーザーコミュニティは適切に運用できれば、ファンやロイヤル顧客の育成にも役立つツールです。ただし、うまく活用するにはその重要性を十分理解しておく必要があります。ここでは、活用する上で知っておきたいユーザーコミュニティの重要性を詳しくご紹介します。
ユーザー同士のコミュニケーションで情報の共有ができる
特定の企業やブランド、商品のユーザーコミュニティでは、さまざまな情報がやり取りされます。ブランドとしての方向性や、商品の特徴など企業側が発信するものもありますが、とくに重要なのはユーザーが発信する情報です。
ユーザーの発信する情報には、企業が想定していない有益なものも多く、さらにユーザーコミュニティではそのような有益な情報が、ユーザー同士で共有されるという特徴があります。
例えば、商品の利用にあたり何か不具合が起こると、ユーザーは何かしらのサポートが必要と感じます。しかし、企業によるカスタマーサポートだけでは時間や人員が限られてしまい適切かつタイムリーなサポートができるとは限りません。
しかし、ユーザーコミュニティでは、同じ商品を利用する他のユーザーが独自にコミュニケーションをとってサポートができます。ユーザーコミュニティが機能すれば、企業にとってはサポートにかかる手間や時間が削減できるだけでなく、ユーザーにとっては適切かつタイムリーなサポートを受けられるという二重のメリットが得られます。
サービス・商品の改善につながる
ユーザーコミュニティでは多くのユーザーが、サービス・商品に関する感想や意見を、それぞれの視点で自由に投稿します。
投稿には、企業が想定していなかった使い方や要望、不満も少なくありません。企業にとってそんなユーザーからの投稿は、サービス・商品そのもの改善や、新たな訴求ポイントなど企業活動にとって役立つ情報です。また、これらをUGC(User Generated Content)ユーザー生成コンテンツといいます。
オンラインコミュニティツールがない頃は、アンケート調査はもちろんユーザー情報の獲得でさえ大変な労力でした。しかし、ユーザーコミュニティをうまく利用すれば、少ないコスト・手間で役立つ情報が得られます。
ここで得た数多くの情報は、いわばユーザーの「生の声」です。集約して検討すれば、セールスやマーケティングにも役立てられます。
ファン化の促進ができる
ユーザーの視点で見れば、ユーザーコミュニティに投稿した意見や要望が実際の商品に反映されるほど、企業に対して「ユーザーの視点を重視してくれる企業だ」といった印象を持ちやすくなります。
ユーザーコミュニティをうまく運用できれば、ユーザーの継続した自社商品・サービスの利用や、他の自社商品・サービスの利用といった、いわゆる「ファン化」の促進が可能です。
ファン化が促進できれば、顧客ロイヤリティの向上やファンによるユーザー拡大、つまり新規ユーザー獲得も期待できます。
ユーザーコミュニティの適切な運用は、長期間にわたる商品・サービスの利用はもちろん、顧客単価の上昇による業績アップにもつながり、企業にとって重要な役割を果たす可能性のあるツールです。

ユーザーコミュニティ運営の難点
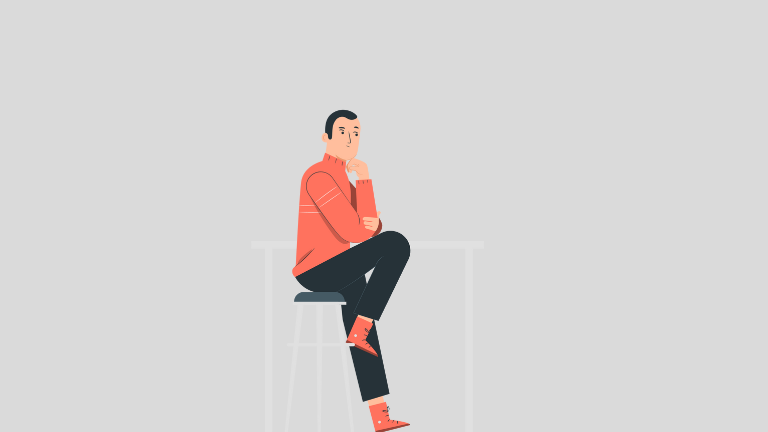
企業にとってコミュニティ運営にはさまざまなメリットがあることをご紹介しましたが、すべての企業がコミュニティの運営に成功しているわけではありません。そこで、コミュニティ運営の難点をいくつか紹介します。
コミュニティがなかなか盛り上がらない
まず「コミュニティが盛り上がらない」という難しさがあります。
コミュニティは、ただ交流の場を設けて、ユーザーを集めるだけで盛り上がるというわけではありません。そして、コミュニティが盛り上がらないと、企業はそこから十分なメリットを得ることはできないのです。
盛り上がらないコミュニティは、企業にとって利益にならないだけでなく、参加するユーザーにとってもメリットがありません。結果、せっかくユーザーが集まってくれても離脱するユーザーが多くなり、コミュニティは閑散とし、最終的に崩壊してしまうでしょう。
そのため、コミュニティの立ち上げには、企業担当者側で手をかけて運営することが大事になります。
はじめだけ盛り上がって、後が続かない
次に「コミュニティの盛り上がりが続かない」ことです。
最初のうちは、そのコミュニティの目的に積極的なユーザー(コアなユーザーやヘビーユーザーなど)が集まって、それなりの盛り上がりを見せることは珍しくありませんし、比較的簡単なことです。しかし、コミュニティが盛り上がり、成長するためにはその後の段階も重要なのです。
コミュニティの熱量は、必ずしも一定に保てるとは限りません。調理器具などの熱量も熱源や電源を維持しなければ熱が続かないように、コミュニティの熱量を維持するためには相応の材料・起爆剤が欠かせません。
また、コミュニティの成長にはメンバー数の増加が欠かせませんが、ただ人数ばかり増えてしまってもコミュニティにとってはデメリットとなります。コミュニティの熱量を、人数に比例して高く維持できなければ、立ち消えになってしまうことは避けられません。
このように、最初に盛り上がっても次第に熱量が低下し、立ち消えになってしまうことはよくあることなのです。企業はコミュニティを維持するためにも、熱量を高める材料の提供とメンバー増加のための対策を講じ、熱量と規模のバランスを考慮してマネジメントする必要があるのです。
運営者の負担が大きい
コミュニティの規模や熱量を維持できても、それが「運営側にとっての負担」になっているのであれば大問題です。
コミュニティの維持には、少なからず「運営」という立場の人間が欠かせません。コミュニティの規律を維持し、不適切な態度をとるメンバーに対しては権限を行使して排除するといった働きも必要です。また、コミュニティの熱量を高めるための情報提供やコンテンツの更新、イベントの企画・開催やメンバー補強のための対策など、運営はさまざまなことをしなければなりません。
運営側がコミュニティ運営のプロであればまだしも、多くの企業はビジネス向けのコミュニティ運営経験を持つ人材を保有していません。企業規模によっては最初から多くのメンバーが集まるコミュニティを、コミュニティ運営の素人が手探りで運営を進めなければならないケースもあります。そのケースの場合、運営側の負担があまりにも大きく、適切な運営手法を講じることができないケースも多くなるのです。
短期では収益が見込めない
コミュニティ運営は、うまく活用できれば企業側にも多くの利益をもたらす結果になるのですが、利益を得られるようになるまでには相応の時間が必要です。
その理由は「小さなコミュニティでは企業の目的を達成できない」ことにあります。例えば10人しかいないコミュニティからは、十分な情報を得られませんし、10人だけファン化してもそこまで売り上げには貢献してくれません。
企業がコミュニティ運営で相応の利益を得られるようになるためには、熱量を高く維持した人数の多いコミュニティを継続的に運営することが欠かせません。また、コミュニティメンバーからの情報が実際の商品開発や改良にフィードバックされるまでには、情報収集・分析・分析結果の具体的な行動への落とし込み・検証といったプロセスが必要なので、どうしても目に見えた利益に帰結するまでには時間がかかるのです。
うまくいくコミュニティツールの運用方法は下記記事をご参考にしてみてください。
コミュニティ運営ツールを使用するメリット

上記のように、コミュニティを運営することは簡単なことではなく、さまざまな理由で失敗してしまうことも多いと思います。そうならないためにおすすめしたいのが「ツールを利用する」ことなのですが、その理由は以下の6つです。
コミュニティ構築に関するコストを削減できる
1つ目のメリットは「コミュニティ構築に関するコストを削減できる」ことです。
目的に合ったコミュニティ運営ツールを適切に利用すれば、複雑なプログラミングなどでのプラットフォームやオンライン上の開発が必要なく、簡単にコミュニティプラットフォームが導入できます。必要なアクションを減らせば人件費をはじめとしたコストを削減できるため、より効率的なコミュニティ運営が可能です。
ただし、そのためには、さまざまなツールの中から「自社の目的に合っているもの」を選ぶ必要があります。コミュニティ運営ツールにはさまざまな機能を搭載していますが、適切に利用するためには別に費用がかかることも少なくありません。
必要な機能のすべてを利用できるのが理想ですが、予算には限度があるかと思います。ツール選びでは機能と予算のバランスを元に、検討することが大切です。
運営・サポートにかかる人員や手間の削減
2つ目のメリットは、「運営・サポートにかかる人員や手間の削減」が可能なことです。コミュニティ運営ツールは、企業と顧客のタッチポイントを一元化し、対応効率を上げ運営側の負担を軽減します。
例えば、ユーザーがFAQやヘルプ、問い合わせフォームなど目的に応じて異なる場所にアプローチしなければならない仕組みだと、適切なアプローチやアクセスが難しいだけでなく、運営側の対応もその分人員や手間が必要です。
プラットフォームやツールを一元管理すれば顧客からのアクションを集約しやすくなるため、自身で解決できるようサイト内コンテンツを充実させ、個別対応の件数を減らせます。
また、ユーザーコミュニティでは掲示板などの機能を利用すると、ユーザー同士のコミュニケーションが可能です。トラブルが起きても、ファンや同じユーザー同士で知識を共有されることもあり、企業が対応することなくコミュニティ内での解消もできます。
コミュニティ運営ツールは商品・サービスの運営だけでなく、サポート面でもかかる人員や手間の削減にも効果的です。
ロイヤル顧客につながる傾向の分析ができる
3つ目のメリットは「ツールを利用することで正確に、迅速にコミュニティの分析ができる」ことです。
コミュニティメンバーが何を求めているのか、どういった交流が最も利益をもたらしているのか、そうした分析が欠かせません。
運営ツールを利用することで、こうしたユーザーの分析がしやすくなります。また、他媒体で持っているデータを組み合わせて利用することで、より精度の高い分析を、しかも手間をかけずに完了させることができる可能性があります。
経験者によるサポートを受けられるため導入運営がスムーズ
4つ目のメリットは「ツールの中には『サポートを受けられる』という特典付きのツールがある」ことです。
ツールによって異なりますが、中にはコミュニティ運営に関するアドバイスやサポートを受けられるという特典付きのツールがあります。コミュニティ運営に関する経験や知識を備えた人材から適切な助言を得ることにより、コミュニティ運営に関する経験が少ない方でも適切な運営に近づけます。
どのようなサポート・アドバイスを受けられるかは、ツールにより異なりますが、有料ツールの場合には必要なサポートを受けられるかどうかを確認するために、問い合わせなどでツールの使い勝手とサポートの品質を確かめることをおすすめします。
他のコミュニティとの連携ができる
5つ目のメリットは「他のコミュニティとの連携がしやすくなる」ことです。
コミュニティ運営ツールは、基本的に複数のコミュニティを同じツールで管理することができます。企業は、商品やブランドごとに異なるコミュニティを運営する必要性がある場合もあり、これらを一元管理できることによってコミュニティ運営の効率化を図ることができます。
それだけでなく、同じ運営者がコミュニティを一元管理しやすくなることにより、異なる自社コミュニティ同士でコラボレーションしやすくなります。こうした取り組みはコミュニティの熱量を高める場合も多く、コミュニティが企業にもたらす利益が多くなることも期待できます。
最新情報の把握
6つ目のメリットは「最新情報を把握できる」ことです。
ツールを利用する場合、ツールの提供会社からさまざまな情報を得ることができます。コミュニティ運営は、その手法や適切なツールなどの情報が常に更新されており、そうした情報を一元的に得られることで効率よく最新情報を得ることができます。
また、同じツール導入企業の成功事例や、失敗事例、その他様々な運営に関する情報共有もできるので、運営から最新情報を得るだけでなく、同じツール導入企業からも、情報が得られます。

コミュニティ運営ツールを使用するデメリット
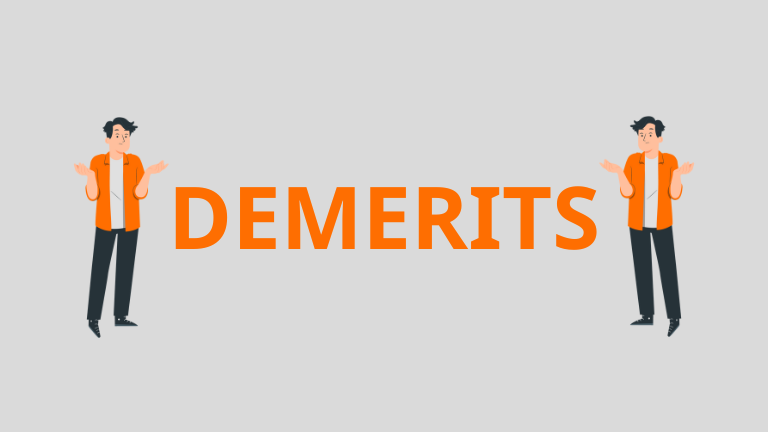
ツールを使えばコミュニティ運営に必要な様々な工程を効率化できますが、すぐに思うような効果が得られるわけではありません。
ここでは、コミュニティ運営ツールを企業が利用する際のデメリットを解説します。
長期的な取り組みが必要になる
ユーザーコミュニティはどれほど適した運営ツールを使っても、企業側が意図する効果を発揮できるようになるまでは時間がかかります。役立つユーザーコミュニティを構築するには、長期的な取り組みが必要と考えて計画することが大切です。
新たなユーザーコミュニティを立ち上げるには、まずコミュニティへ参加するユーザーを増やす必要があります。そして、ユーザー同士が活発にコミュニケーションできるよう環境を整備したり、コンテンツやイベントを提供したりする必要もあるでしょう。
並行してコンテンツも拡充し、成果が出るまで根気よく継続することが重要です。
管理運営のためにリソースを割く必要がある
ユーザーコミュニティは構築よりも、適切に運用していくことが重要です。
そのためには、イベントの企画や情報提供のためのコンテンツの提供・更新のほか、不適切な態度をとっているメンバーへの対処など、運営する企業側のリソースが必要となります。
立ち上がって間もないコミュニティや規模の大きなコミュニティは慣れない運営に時間がかかったり、対処すべき事案が多かったりと企業にとって大きな負担になりがちです。
企業はコミュニティの規模や性質によって、運営する人員の確保や適切な役割分担といった工夫が求められます。
コミュニティツールの主な機能

コミュニティ運営ツールに求められる機能は、コミュニティサイトの構築と運営、そしてサイトおよびユーザーの管理・分析にあるといえます。
ここでは、構築とその後の運用に分けて主な機能をみていきましょう。
コミュニティサイトの構築
コミュニティサイトの構築は、コミュニティ運営ツールに求められる基本的な機能です。通常ならプログラミングやサーバーに関する専門知識を必要としますが、ツールを利用すれば専門知識がなくても、管理画面を操作すれば簡単にサイトを構築できます。
使える機能はツールによって異なりますが、代表的なのは次のような機能です。
- グループの作成
- テキスト・画像・動画などのコンテンツの投稿
- 投稿へのコメントやリアクション
- DM
- メンバー登録
- Q&A
機能は名称だけでなく、「実際に何ができるか」を見極めて選ぶ必要があります。自社の目的を前提に、デモンストレーションなどを通じて確かめることが大切です。
ユーザーやコミュニティサイトの管理・分析
コミュニティサイトを構築して運用を始めたら、登録ユーザーの行動や投稿したコンテンツを適切に管理する必要があります。
例えば、不適切な投稿を非表示にする、不適切なユーザーに退会してもらうといった管理業務は、地味ですが怠ると目的を達成できなくなる可能性もある重要なポイントです。
ツールによっては、他のユーザーへの誹謗中傷や個人情報など不適切な投稿を素早く発見し、対応する機能を搭載しています。
また、同じようなファンやユーザーを育成するためにも、コミュニティサイトから得られたさまざまなデータの分析は重要です。
ツールには、次のような機能を搭載していることが多いです。
- レポートの自動生成
- Google Analyticsの埋め込み
- テキストマイニング
- 各種分析機能
- データ連携
- SO連携
もしユーザーの行動分析機能が搭載されていたら、分析結果を利用した個別アプローチも可能になるでしょう。

コミュニティツールを選ぶポイント
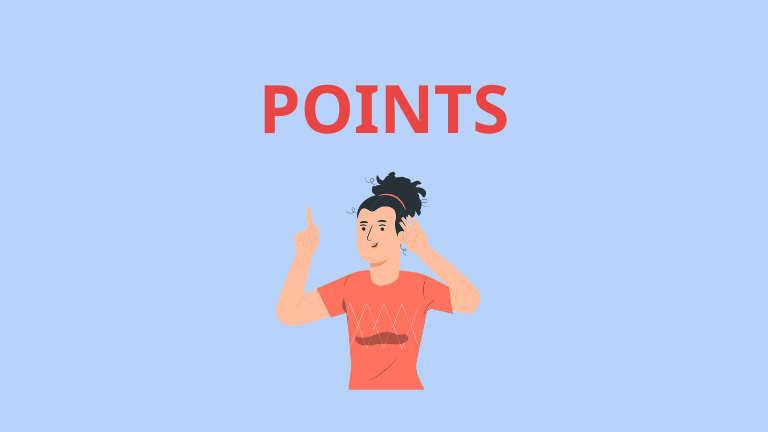
いざコミュニティ運営ツールを導入しようとすると、その種類の多さに戸惑うかもしれません。
ツールはそれぞれ豊富な機能を持っているため、すべてを比較して1つを選び出すのは大変です。選ぶには、自社に適したツールの見極めが必要になります。
ここでは、自社に適したコミュニティツールを選ぶときに、押さえておきたいポイントについて考えてみましょう。
目的に対して適切な機能があるか
コミュニティ運営ツールを導入するときは、まず自社の目的を果たすために必要かつ、適切な機能を持っていることが大切です。ツールの機能は、主にコミュニティの構築と管理、分析に分けられ、それぞれできることやできないことは異なります。
ツールを選ぶときはまず、自社のユーザーコミュニティをどのように活用したいか、そのために必要な機能は何かを明確にすることが大切です。
ユーザーが利用しやすいか
ユーザーコミュニティは、さまざまな属性のユーザーが数多く利用することでより効果を発揮します。コミュニティ運営ツールはユーザーがコミュニティを簡単に利用し、快適かつ使いやすいと感じられるかどうかが重要です。
そのためには、コミュニティに参加するユーザーの年代やカルチャーを想定し、それらのユーザーにとっての利用しやすさを追求する必要があります。
パンフレットなどの資料からだけでなく、自身がユーザーに成り代わったつもりで操作できるデモンストレーションなどを活用し、「実際に利用しやすいかどうか」を確認しましょう。
運営会社のサポート体制が整っているか
導入するコミュニティツールには、運営会社のサポート体制が整っていることも重要です。ここでいうサポートとは、運用中の技術的なトラブルやツールの使い方のレクチャーだけではありません。ツールを使ってユーザーコミュニティを企業の意図に沿って運営するためのアドバイスや情報の提供などが含まれます。
同じコミュニティツールを使っても、方向性が違えば形作られるユーザーコミュニティは変わります。ユーザーコミュニティは企業やブランド、商品の数だけ種類があるといっても過言ではありません。そのため企業は運営にあたり、さまざまなトラブルや課題に突き当たる可能性があります。なかには解決の糸口がつかめず、閉鎖せざるを得なくなるかもしれません。
そのとき、ユーザーコミュニティ運営について豊富な知見を持つ第三者がいれば心強いはずです。運営会社に豊富な実績があるほど頼れる存在になるでしょう。
コミュニティツールを選ぶときは、できることや分析ツールといった機能面だけでなく、コミュニティの運営についてもしっかりサポートしてくれるものを選ぶとよいでしょう。
コミュニティ運営に役立つツール10選

最後に、コニュニティの運営に役立つ6つのツールの特徴やメリットについて解説します。
coorum(コーラム)
1つ目は、コミュニティ機能も搭載したカスタマーサクセスプラットホームの「coorum(コーラム)」です。
このツールの主な特徴は、顧客向けの操作マニュアルや活用Tips・QA等ナレッジを可視化するためのサイトをノーコードで作成できる点。さらには顧客の満足度を正しく分析する事によって、顧客毎に最適な情報を届けることが可能になります。その結果、顧客満足度やLTVの向上、およびカスタマーサポートにかかるコストの削減が可能といった効果が期待できます。

Community Cloud(コミュニティクラウド)
2つ目は、ポータルサイト構築の「Community Cloud(コミュニティクラウド)」です。
セールスフォースが提供するサービスで、コミュニティを構築することができるサービスです。構築されたサイト内では、顧客、パートナー、社員がエキスパートとつながり、情報交換や交流を行うことができます。
Facebook(フェイスブック)※無料利用可能
3つ目は、言わずと知れたSNSの代表的なサービスの1つ「Facebook(フェイスブック)」です。
国内でも数千万人が利用しているとされている大手SNSであり、グループ作成に関するさまざまな機能がアップデートされています。導入のハードルが低いというメリットはありますが、コミュニケーションツールとしては少し使いづらい印象を受けるというデメリットがあります。
LINE@(ラインアット)※無料利用可能
4つ目は、コミュニケーションツールとして多くのユーザーを保有する「LINE」、そのビジネス向けのアカウントである「LINE@」です。
LINE@では、LINEの基本的なコミュニケーション機能だけでなく、「クーポン」や「ショップカード」などのビジネス向けの機能も利用できます。無料でも利用できますが、2つの有料プランも用意されています。
Slack(スラック)※無料利用可能
5つ目は、チームワーク促進ツールとして多くの企業が利用している「Slack(スラック)」です。
もともとはエンジニアやプログラマーといった人が主に利用していたツールなのですが、コミュニティ運営にも役立つツールとして再注目されています。話題に沿ったチャンネルを設定可能であり、スピーディーなコミュニケーションを促進します。ただし、FacebookやLINEと比較すると馴染みのない人が多く、使い方のレクチャーが必要になるケースが多くなります。
Discord(ディスコード)
6つ目は、オンラインゲーム用に開発されたコミュニケーションツール「Discord(ディスコード)」です。
Slackと似たような機能性に加えて「ボイスチャット機能」もあり、快適なコミュニケーションを促進します。ゲーム実況者などには馴染みがありますが、やはりこのサービスを知らないという人が多いのがネックです。
Zendesk(ゼンデスク)
7つ目は、運用や管理にAIを用いたユーザーコミュニティ構築ツール、「Zendesk(ゼンデスク)」です。
フィードバックを集めたり、高い貢献度のあるユーザーを表彰したりすることで、顧客同士または顧客と企業の信頼関係を深め、顧客の知識を活かしてセルフサービス型のサポートが提供できます。
CRAYON(クレヨン)
8つ目は、オンラインで発信することの多いインフルエンサー向けアプリ専用のコミュニティツール「CRAYON(クレヨン)」です。
このツールの強みは、音楽や動画、アニメ、キャラクターといったエンターテインメント分野のコミュニティ構築にあります。企業や企業ブランドより、芸能人や有名人のファンが利用しやすいツールといえるでしょう。
QON(クオン)
9つ目は、1996年創業の老舗「クオン株式会社」が展開する、クラウド型ファンコミュニティ運営サービス「QON(クオン)」です。
ツールの理念である、「絆のコミュニティ」に共感する多くの企業やブランドが多く活用しています。それぞれ過去の支援実績から得た運用経験をAIに導入し、企業とファンの信頼関係の構築やコミュニティ全体の集合知の形成に役立てているツールです。
commmune(コミューン)
最後は、「企業とユーザーが融け合う社会を実現する」というビジョンの下に提供されている、コミュニティツール「commmune(コミューン)」です。
このツールは、売上アップなど企業の重要な指標の実現をサポートします。コミュニティ構築だけでなくデータ分析やKPIの設計といった運営支援に強みがあるため、カスタマーサクセスを通して、戦略的かつ効果的な施策を展開したい企業に適したツールです。
コミュニティツールならcoorum

近年、多くの企業にさらなる業績アップと、コスト削減にともなうより効率的な改善が求められるようになってきました。そのようなニーズに応えるのが、ユーザーコミュニティを運営・管理するコミュニティツールです。
コミュニティツールによって、これまで大きな労力とコストが必要だったユーザーコミュニティは運営・管理しやすくなりました。ただツールの種類は多く、それぞれに異なる機能を搭載しているため、自社に適した1つを選び出すのは困難です。
そこでおすすめしたいのが、ユーザーコミュニティの運営を通してロイヤル顧客の育成や顧客視点での戦略支援が可能な「coorum(コーラム)」です。
coorumなら、質の高い顧客の声をリアルタイムで収集でき、ファンの育成を通して充実したサポートや新規顧客獲得も期待できます。「より顧客に寄り添ったマーケティングや商品企画が必要」「定期的な調査をコストと手間に見合うよう役立てたい」という企業のファンコミュニティ立ち上げ・運営をしっかりサポートするツールです。
コミュニティ運営ツール選びでは、自社の目的と必要な機能の絞り込みの明確化が重要です。さまざまな外部ツールとの連携や、コミュニティサイトのフルカスタム化も可能なcoorumの導入をぜひご検討ください。