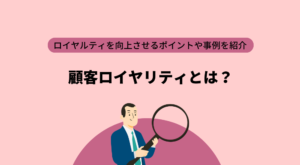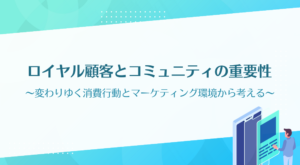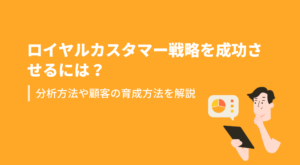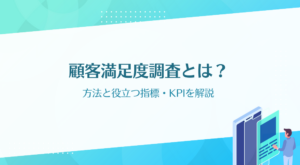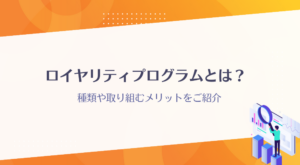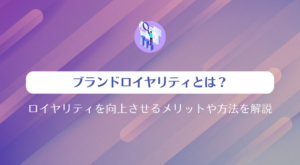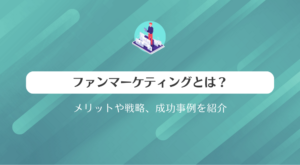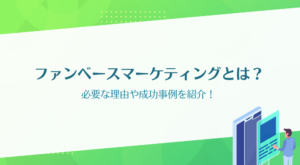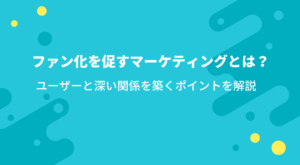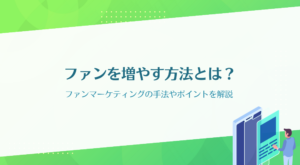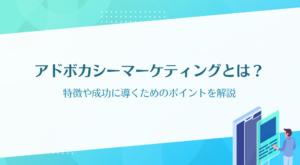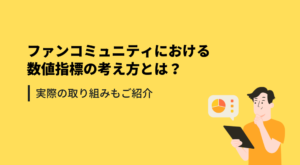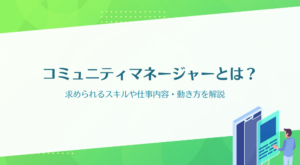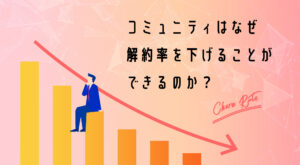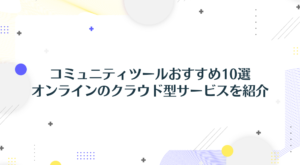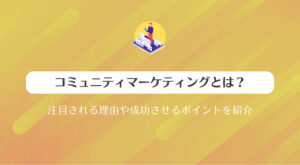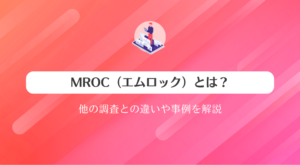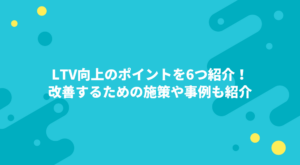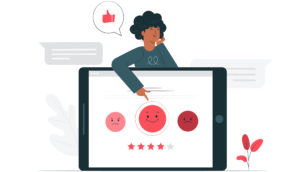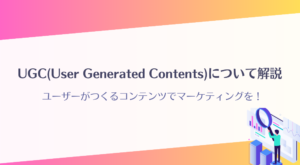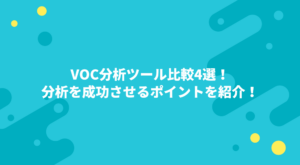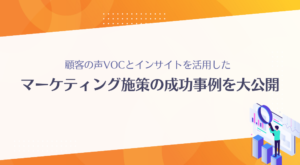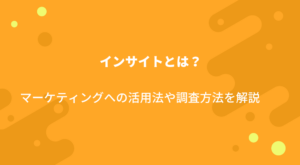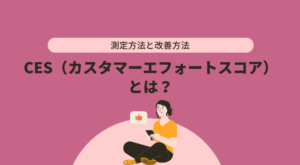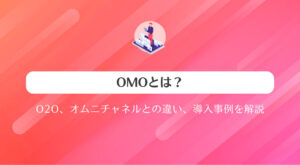
企業が自社のコミュニティを構築し、適切に運営することによってメリットを得られることが知られるようになりました。そんなコミュニティはいくつかのフェーズがあります。まずは立ち上げ期です。この時期はそのコミュニティの目的を定め、メンバー選定をする時期です。その次に、立ち上げ期に定めた目的に沿ったコミュニティを運営していくための運営期です。立ち上げ期段階も重要ですが、継続的に利益を生み続けるためには適切な運営方法を実践することも重要です。
日本では海外ほどコミュニティマネジメントが浸透しておらず、コミュニティの運営方法について悩んでいるという人は少なくありません。そこで、この記事ではコミュニティ運営の秘訣について解説します。
コミュニティ運営の重要性

まず最初に、そもそも「コミュニティ」を運営することが企業にとってどのようなメリットがあるのかについて簡単に解説しておきます。
- 良質なアイデアのフィードバック→既存顧客の売上アップ
- ファンの育成と獲得→ ユーザーの離脱防止
- CS業務のサポート→ ユーザーの離脱防止
コミュニティからユーザーの不満や感想を吸い上げ、これを商品・サービスの開発や改善につなげることで既存顧客のリピート率や継続率の向上になり、売上アップにつながります。
コミュニティの存在は「新規顧客をファン化する」「既存のファンをさらにコアなファンに育成する」という効果があり、これにより売上のアップにつながるだけでなくユーザーの離脱(解約など)防止につながります。
また、コミュニティには「商品・サービスに精通したヘビーユーザー」と「利用経験の浅いユーザー」が混在しています。利用経験の浅いユーザーからの質問をヘビーユーザーが回答することで、ユーザー間でQ&Aが完結され、新規ユーザーの早期離脱を防止するとともに、企業にとってはCS(カスタマーサポート)業務に割くリソースを減らすことができます。
コミュニティは目的に沿った運営が大事
企業はコミュニティから上記のようなメリットを享受できるのですが、そのためには「適切かつ健全にコミュニティを運営する」ことが重要です。
コミュニティは、開設さえすればあとはコミュニティメンバーによって勝手に盛り上がると勘違いしている人も少なくありません。そうしたユーザー主体のコミュニティも確かに存在しますが、ビジネス向けのコミュニティの場合は企業側からのアプローチが欠かせません。
企業側から適切にアプローチをしていないビジネスコミュニティは、次第にユーザー離れを引き起こしてしまいます。良質なユーザーがコミュニティから離れてしまうことでコミュニティは荒れてしまい、コミュニティの本来の目的を達成できなくなってしまいます。
運営のポイントは「活性化」
企業がコミュニティから利益を得続けるためにはコミュニティの運営が欠かせませんが、最も重要なポイントは「コミュニティを活性化する」ことです。
「荒れさえしなければいい」という守りの姿勢は、結局のところコミュニティの監視に留まり、次第に情報は陳腐化・普遍化してしまいます。ユーザーはコミュニティの参加に相応の満足や楽しみを要求しているのですから、つまらないコミュニティはやはりユーザー離れを起こす原因となるのです。
コミュニティは、適切な情報を提供することも重要ですが、何よりもそこに良質なユーザーを集めてコミュニティを形成してもらうことが欠かせません。企業がコミュニティからメリットを得るためには、コミュニティを活性化させるためのアクションを積極的に行う必要があるのです。
企業がコミュニティ運営を行うメリット

企業が、コミュニティ運営を行うメリットはさまざまです。事業にどのような影響がもたらされるのか、一つずつ解説します。
ユーザーのニーズ把握に役立つ
顧客との密接な接点が生まれ、直接商品やサービスに関するお客様の声や情報を収集しやすくなり、ニーズの把握に役立ちます。
さらに企業が見落としていた商品開発の糸口や思わぬ利用方法、課題の発見につながる有益なアドバイスが得られます。コミュニティ内ではユーザー同士の意見の交換が促進され、ディスカッションを通じて、担当者経由では得にくい本音を収集しやすいことが利点です。
顧客との接点増加でコミュニケーションを増やせる
店頭で商品を購入後、店舗との接点が途切れてしまえば、顧客と企業との間でコミュニケーションをもつ機会が失われます。
コミュニティを運営すると継続的な接点が生まれ、ユーザーは商品を使用している時間だけでなく、24時間企業とのつながりを感じとれます。
すると、ユーザー同士や企業とユーザー間のつながりが作られ、愛着や信頼の獲得が可能です。原則レジでのやり取りで店員とのコミュニケーションが完結する小売店のほか、飲食店やパーソナルジムなど、さまざまな形態の店舗で実感できるメリットです。
顧客ロイヤリティの形成に欠かせないコミュニケーション機会を確保するには、コミュニティの構築が有効な方法です。
ユーザーのファン化を促進できる
コミュニティの活動を通じて、製品が提供する価値以外で良質な顧客体験を与えることで、ユーザーのファン化を促進するでしょう。開発秘話をはじめ、興味がある情報を提供できるため、顧客は、知りたいと感じる情報を教えてくれる企業にポジティブな感情を抱くためです。
コミュニティ会員の顧客ロイヤリティ(商品やサービスの愛着)が高まり、サービスの継続率の向上や、クロスセル・アップセルの成功率の上昇などが期待できます。
熱心なファンが増えれば、誰かに何かをいわれたわけでもないのに、ユーザーが自発的に商材に関する肯定的な投稿を寄せるようになります。この口コミやUGCを呼び水となり、新規顧客が増加します。
従業員のエンゲージメント向上につながる
コミュニティ運営では、従業員のモチベーションを高める効果も期待できます。
営業やカスタマーサポートのような日常的に顧客と接する部署ではない場合、ユーザーやお客様の意見に耳を傾ける経験は少ないでしょう。オンラインコミュニティの運営を通じて、メンバー同士の交流や、お客様からのフィードバックやお声、サービス体験談を知ることは、企業に務める社員にとって、刺激的であり、新しい発見や、エンゲージメント向上に繋がります。
利用者の声が耳に入れば、誰のために何のために仕事をしているか明確になり、顧客の期待に応えるために、サービスを改善する活力がはぐくまれます。
カスタマーサポートのリソース削減につながる
コミュニティメンバー同士の交流が盛んになると、古参のユーザーが新規ユーザーのサポート役を担うようになり、結果的にカスタマーサポートの負担が軽減します。
製品の使い方を教えあったり、より良い利用方法に関する情報の提供が活発になったりすれば、企業へ直接問い合わせするユーザーは減るでしょう。
カスタマーサポートには電話やメール、チャットで日々多数の質問や相談が寄せられます。リソースを十分確保できず、問い合わせしてきた顧客を待たせるようなことがあれば、ユーザー離れを引き起こします。コミュニティに疑問解決機能をもたせるのは、効率的な事業運営に不可欠です。

企業がコミュニティ運営を行うデメリット
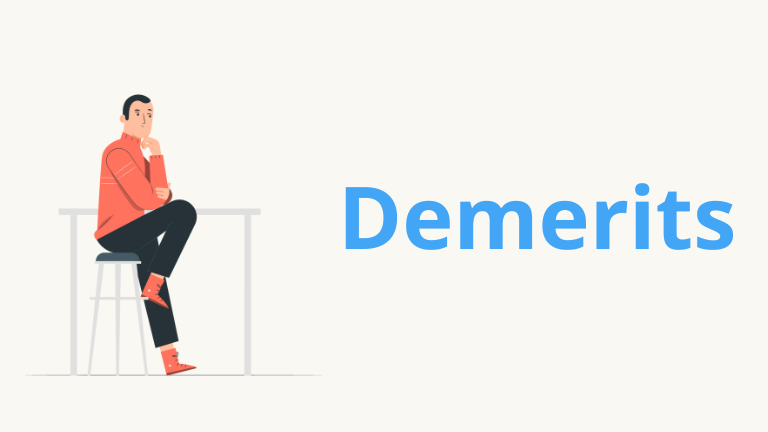
コミュニティ運営の際は、あらかじめデメリットを把握して、失敗を防ぐ心構えをしておきましょう。
コミュニティ内でトラブルが起こる場合がある
コミュニティは性別や年代、職業、価値観が異なるさまざまな人間のが集まっています。商品や企業のファンとはいえ、考え方や感じ方は人それぞれ違うため、ユーザー間やユーザーと企業間でトラブルが巻き起こる場合があります。
例えば、商品のあるべき姿について議論を交わすうち、熱くなって口論に発展するかもしれません。また、コミュニティ運営では決済がうまくいかず、運営とユーザーでトラブルになるケースもあります。
あらかじめルールや規約を策定し、禁止事項や利用時の注意点を明確にしておけば、未然にトラブルを防げるでしょう。
運営するためにはリソースや時間がかかる
コミュニティ運営は成功までに時間がかかる施策で、コンテンツの作成やイベントの企画などに人的リソースを投じる必要があります。はじめのうちは運営だけで手一杯になりがちで、メンバーを増やす仕掛けを講じる余裕がなく、多大なコストが生じるかもしれません。
実際に立ち上げたは良いものの運営にかけるリソースや人員がいなく、短期間でたたんでしまうコミュニティも存在しているでしょう。
コミュニティが拡大するにつれ、確保すべきリソースも比例して増えます。社内の人材だけで対応が難しければ、コミュニティ運営、すなわちコミュニティマネージャー(CSM)業務を他企業に委託したり、代理店にお願いする手段もあります。
コミュニティを作る流れ

コミュニティを構築する際の基本的な流れは次の通りです。
- コミュニティの目的やコンセプトを決める
- コミュニティの形式・プラットフォームを決める
- ルールやコンテンツを考案する
- コミュニティの参加者を募集する
- 交流を促進する仕組みを作る
各段階ですべき作業や注意点について解説します。
1.コミュニティの目的やコンセプトを決める
オンラインコミュニティを実現して、成し遂げたい目的や独自の軸となるコンセプトを決めましょう。目的でいえば、例えば、認知拡大やブランディング、売上の増大、顧客ロイヤリティの向上などが挙げられます。
コンセプトとは、コミュニティ独自の「売り」のことです。自社の商材の特徴や対象となるペルソナを踏まえて決めると、企業として一貫性が生まれ、成功しやすくなります。コンテンツの内容や、イベントの企画などの方向性を決めるうえでもコンセプトは有益です。
また、ベンダー側が成し遂げたいこと以外に、コミュニティの運営を通してユーザーに提供できる価値も考えなくてはいけません。その際にもコミュニティの目的やコンセプトは役立つ存在です。
2.コミュニティの形式・プラットフォームを決める
次は、どのツールを使ってコミュニティを運営するか、基盤となるプラットフォームを決めましょう。選択肢はSNS、オンラインコミュニティに特化したプラットフォームの活用、ゼロからのフルカスタマイズサイト制作の3つです。
SNSは気軽に始めやすい反面、デザインや機能面で自由度が低い方法です。公式LINEやオープンチャットなどの手法もありますが、LINEのUIに依存するため、自社のオリジナリティは発揮しにくいのです。
オンラインコミュニティ専用のプラットフォームは、カスタマイズ性が高く、自社で一からサイトを構築する必要がなく、簡単にサービスの世界観を意識した独自性の高いコミュニティが出来上がります。
3.ルール・コンテンツを考案する
コミュニティを安全に運営するためのルールや規約を決め、コンテンツの方向性を決めましょう。利用規約に含まれる一般的な事項は次の通りです。
- 他のユーザーに対する誹謗中傷を禁止する
- 商材の勧誘は行わない
- コミュニティ内で得た情報を外部に流出させない
コンテンツに関しては、テーマや発信頻度、発信形式(音声、動画など)は最低限でも決めたい事柄です。
4.コミュニティの参加者を募集する
コミュニティの土台が固まったら、さっそく参加者を募集してみましょう。いくらリソースを投じてコミュニティサイトを構築しても、作っただけでユーザーが集まるケースは稀です。積極的に働きかけ、宣伝やマーケティングにも注力する必要があります。
告知に活用できるツールは、SNSやコーポレートサイト、Web広告です。運営元の企業に話をもちかけ、プレスリリースを発行する施策も有効です。店舗をお持ちの企業であれば、QRコードをレジにおいておくといったような形で流入を促すことも可能です。
もう一つコミュニティの運営で知っておきたいのは、立ち上げメンバーが非常に重要になることです。運営のルールは初期メンバーの主導で決まるため、コミュニティの色を決める存在だと言っても過言ではありません。したがって通常のファンを招き入れるよりも、企業側の目線に立って話ができる人材を迎えるべきです。
5.交流を促進する仕組みを作る
オンラインコミュニティの成功を分かつ重要なポイントは、交流を促進する仕組みを作れるかどうかです。企業側のコンテンツをただ参加者が受動的に受け入れる構造では、双方向のコミュニケーションは生まれなく、熱量のあるコミュニティにはつながりません。
交流を促進する仕組みの具体例は次の通りです。
- 企業からのアンケート調査や議題提供などで、会話が生まれやすいコンテンツを活用
- ユーザーの発言に対して他者がコメントやリアクションできる機能を実装する
- オフラインイベントを開催する

コミュニティ運営を成功させる5つのヒント
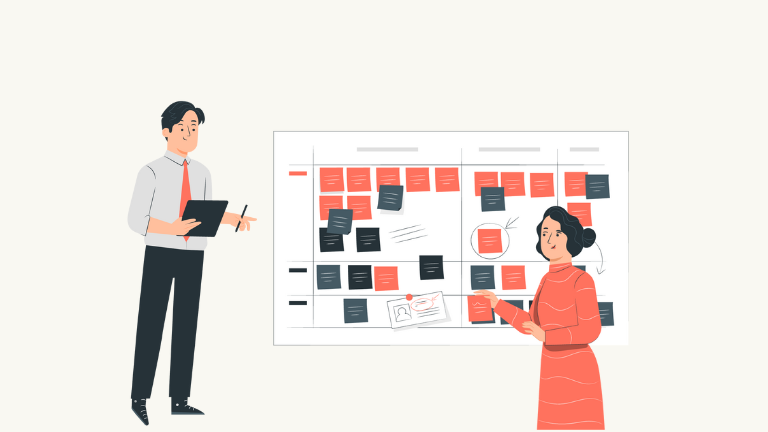
次に、コミュニティ運営を成功させるための5つのポイントについて解説します。
はじめは少人数でスタート
1つ目のポイントは「最初は少人数のメンバーからスタートする」ことです。
コミュニティ活動をスタートする時は、人数よりもそのコミュニティを活性化させることを最優先に考えましょう。
コミュニティの熱量は最終的にコミュニティメンバーの人数にも比例するのですが、最初から人数を集めてもなかなかコミュニティは活性化しません。
例えば、10,000人のメンバーを集めてコミュニティをスタートするとします。メンバーは10,000人という多くの人の集まりの中では、誰と、どのようなコミュニケーションをとればよいのかわかりません。結果、コミュニティは人数に対して十分な熱量のコミュニケーションをとれなくなるのです。
そのため、コミュニティのスタート時期では焚火に火をつけるかのように、少人数で密度の高いコミュニケーションを図り、次第に人数を増やして人数とコミュニケーションの熱量を比例させていくことが良いでしょう。そのため、最初のコミュニティ参加メンバーは可能な限り「熱量の高い人」だけを集めてスタートすることをおすすめします。
コミュニティの目的をはっきりさせる
2つ目のポイントは「コミュニティの目的を明確にする」ことです。
コミュニティには、さまざまな目的があります。企業側からすれば「顧客のニーズを把握したい」「ユーザー間でQ&Aを完結させたい」などの目的があり、ユーザー側からしても「同じ趣味の人で集まりたい」「商品・サービスに関する情報を共有したい」などの目的があります。
コミュニティの目的を明確に設定して「こういう目的でコミュニティを作ります」とアナウンスすることで、その目的に応じてメンバーが集まりやすくなります。コミュニティの目的が明確なほどメンバー間で共感しやすくなり、共感する人同士が集まればコミュニティ内の結束が強まります。結果、コミュニティは熱量を高め、企業はコミュニティから多くのメリットを得られるようになるのです。
参加者に当事者意識を持たせる
3つ目に「参加者にも『当事者』としての意識を持ってもらう」ことです。
コミュニティ活動において、コミュニティの参加者にも何らかの役割を与えることが重要です。そうすることによって、当事者意識を持たせることができれば、継続してコミュニティに参加してくれる可能性が高まるのです。
例えば「メンバーの意見を有機的に反映させる」ための仕組みと、それを公表する仕組みを実践できれば、ユーザーは当事者としてコミュニティ内で活動してくれるようになります。実際にこの点に着目してコミュニティの仕組みを考え、ユーザーを巻き込んだコミュニティ運営に成功している企業も多いです。
参加者同士の交流ができる仕組み作り
4つ目のポイントは「参加者同士で交流できる仕組みを作る」ことです。
特にオンラインコミュニティの運営においては、オンラインの領域だけでなく、オフラインの領域でもコミュニケーションをとれる方法を用意することをおすすめします。いわゆる「オフ会」というものであり、運営側が積極的にイベントを企画することでコミュニティのメンバー同士での交流がより深まります。
コミュニティの参加者同士が気軽にやりとりできる環境を整えることで、企業側がコミュニティを管理しなくても自然にコミュニティは適切な形を維持する力を高めます。もちろん運営側が完全放置することは危険ですが、適切な運営に必要なリソースを少しでも抑え、コミュニティの熱量を高めるためには交流の場を設けることが必要なのです。
新規メンバーを大切にする
5つ目のポイントは「新規メンバーを大切にする」ことです。
コミュニティの中には、開設時から加入しているメンバーもいれば、開設から数年経過して新たにコミュニティに参加するというメンバーもいます。もし、古参メンバーだけで盛り上がっていると、コミュニティは「閉鎖的」な雰囲気になってしまい、新規メンバーの参加率を下げ、離脱率を高めてしまうのです。
長くコミュニティに参加してくれているメンバーを大切にすることはもちろん重要なことですが、新規メンバーに対しても相応の配慮をしなければコミュニティは成長しません。コミュニティに参加しやすく、また、既存のメンバーとの交流もしやすい仕組みや雰囲気を構築することをおすすめします。
コミュニティ運営でよくある4つの失敗

次に、コミュニティの運営でよく見られる失敗パターンを5つ紹介しますので、同じ轍を踏まないように注意しましょう。
入会への敷居が低すぎる
1つ目に「入会への敷居が低すぎる」ことです。
コミュニティ参加の敷居があまりにも低すぎると、コミュニティの目的に合わないメンバーが増えてしまいます。その結果、人数に見合わないほどにコミュニティの熱量が下がる結果となってしまい、コミュニティの管理に割くリソースばかり増大してしまうのです。
コミュニティの中には、特定の条件を満たしたユーザーのみをメンバーとして迎え入れるところもあります。あまりにも敷居が高すぎるとメンバーが十分に集まらず、コミュニティの成長を阻害してしまうリスクがありますが、逆に「来るもの拒まず」の姿勢も避けなければなりません。
良質なユーザーに絞りながらも、潤沢な運営基盤を確保するために、入会のハードルはちょうど良い基準に設定することを心がけてください。
コンテンツ型コミュニティになっている
2つ目は「過度なコンテンツ型のコミュニティになってしまった」というケースです。おもしろい読み物やユーザーの役に立つコンテンツがある一方、ユーザー同士のつながりが希薄で、普通のオウンドメディアのようになってしまったパターンです。
コミュニティには、そのプラットフォームに合わせたさまざまな形があります。特に自社で一からサイトを作り上げる場合などは自由度が高く、さまざまな独自コンテンツを盛り込むことでユーザーの利益となります。
しかし、あまりにもコンテンツ型に傾倒してしまうと、コンテンツの更新など運営者の負担が大きく、その割に失敗しやすいというデメリットがあります。ユーザーが気軽にやりとりできる「交流型コミュニティ」のほうが、失敗のリスクや運営の負担を減らすことができます。
もちろん、何らかのコンテンツを盛り込むことはユーザーの利益となりコミュニティの成長にもつながりますが、あまりにも多くのコンテンツを盛り込むことはおすすめできません。コミュニティの目的に応じて、必要最低限のコンテンツからスタートし、運営側に余裕が出てきたらコンテンツを増やすという流れがおすすめです。
さらにいえば、熱量が高いユーザーが自らコンテンツを投稿するようになれば、願ったり叶ったりです。
短期で結果を得ようとする
4つ目は「短期間で成果を得ようと考える」ことです。コミュニティの立ち上げから利益を生み出すまでには最低でも半年はかかるため、長期的な目線を持たねばなりません。
運営した途端にコミュニティ内のユーザーが次々と商品を購入し始めるケースは極めて稀です。LTVやリピート率の向上や、コミュニティ運営のROASの向上をはじめ、直接利益につながる施策を講じる際には長期的な目線をもちましょう。
前述の通り、企業がコミュニティを構築し運営することは、最終的に企業側にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。しかし、あまりにも利益第一主義が浮き出た運営手法をしてしまうと、ユーザー離れを起こしてしまうリスクが高まるのです。
どんなビジネスモデルであっても、最初から理想通りの利益を生み出すことは稀です。コミュニティがビジネスで役立つまでには、時間がかかって当たり前だということを念頭に置きましょう。
コミュニティ内で稼ごうとする
4つ目は「コミュニティ内でセールスや宣伝ばかりする」ことです。
これもコミュニティによる企業利益の話になるのですが、コミュニティの中には何らかの方法で直接的に稼ごうとする動きもあります。商品販売が最もわかりやすいのですが、あまりにもセールス第一なコミュニティ運営手法は、ユーザーにがっかりされてしまいます。
また、会員特典として新商品の先行販売を行い、早々と利益を確保しようとする行為にも注意が必要です。
もちろん、役立つ商品や限定商品などを販売することは少なからずユーザーの利益にもつながりますが、コミュニティはあくまでも「企業のファンを増やすもの」として考えてください。
コミュニティのメンバーが増えて活発にコミュニケーションが行われ、企業のファンが増えた先にこそ、コミュニティマネジメントにより得られる本当の利益が待っています。

コミュニティ運営に役立つサービス

次に、コミュニティの運営に役立つツールについて紹介したいと思います。
コミュニティ運営に専用ツールを使えば、運営の手間が省けるというメリットがあります。有名どころでは「Facebook」「Twitter」などのSNSや、「LINE」「Slack」「Discord」などのコミュニケーションツールがおすすめです。
ツールの使用にあたっては、ツール毎の機能だけでなく「料金・費用」の特徴にも注目したいところです。一部のツールは基本利用だけなら無料で利用できるというケースもあります。コミュニティの運営にかかるコストを抑えるためには無料ツールを利用するのもおすすめですが、効率よくコミュニティを運営するためには、必要な機能を備えた有料ツール・有料プランを選択することも考慮してください。
コミュニティ運営の成功事例

最後に、コミュニティの運営に成功した3つの企業について解説します。
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社は、エビスファンが集い自由に語り合える場としてcoorumで「ヱビスビアタウン」をローンチしました。半年で7万人のユーザー数に達するほど急成長を遂げています。
この要因は自由度が高い環境作りに励み、エビスビール以外の話もできるコミュニティだからこそ自由な発話が生まれ、お客様の生の声を多く収集することができています。。企業としても調査やアンケートでは得られない顧客のリアルな声を吸い上げられていると実感されていて、うまく機能していると満足の声を寄せています。
導入事例インタビューはこちら▼
ファンが集い語らう街「ヱビスビアタウン」で本音が聞ける理由と運用のポイント
株式会社SUBARU
株式会社SUBARUは、行動ログだけでは読み取れない顧客の心理を把握する場としてコミュニティサイトの構築を決意しました。
既存の会員サイトもあるなか新しいサービスを作ろうとしている理由は、今のコミュニティが一部の先鋭的なユーザーのみの閉鎖的な場所になっていると感じたためです。
新たに参加するライトなファンを招きいれ、より交流しやすくするため、また企業とユーザー間の双方向のやり取りを活発にするため、コミュニティの刷新を決意します。
新規サービスでは普段顧客の声を聞く機会が少ない技術者も参加させて、技術サイドからのこだわりを発信したいという構想を掲げています。
導入事例インタビューはこちら▼
データ統合が進むSUBARUの「効果が見えるファンコミュニティ」。お客様と技術者のつながる場を目指して
株式会社コメダ
喫茶店を全国に展開する株式会社コメダは、coorumを用いてファンコミュニティ『さんかく屋根の下』を立ち上げています。
コミュニティ立ち上げのきっかけは、店舗ごとに常連のお客さんがついている状態から脱却し、コメダ珈琲として常連客同士がつながればおもしろいのではと感じたためです。
オンラインコミュニティを開始する前は、ヘビーユーザーが月に一度店舗に集まって、試作品の試食会や、理想のルノワールを企画するイベントを実施していました。顧客の声を聞く場はあるものの、立地面での制約で参加できるお客様の数は限られます。
上記の問題点を考慮し、ネット上でのイベントならば幅広い人が参加しやすいだろうと考え、オンラインコミュニティの構築もを決断されたのです。
トークテーマの提供やフォトコンテストの開催などさまざまなコンテンツを実行した結果、ユーザー数が1万人を超える規模にまで成長しました。(※2023年2月時点)
今後はコミュニティを通して、アクティブに活動する会員の割合を増やすとともに、データの分析によってLTVとの相関関係を見出し、より熱量が高い運営を目指す構想を立てているそうです。
導入事例インタビューはこちら▼
「より多くのお客様が交流ができる」コミュニティを。株式会社コメダが運営する「さんかく屋根の下」がcoorumを選んだ理由。
株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社すかいらーくホールディングスは、厳選したロイヤル顧客だけが参加できるユーザーコミュニティ「おやさい学校 しゃぶしゃ部」をスタートさせました。
コミュニティ運営を決意したきっかけは、SNSの発信ではコミュニケーションのとり方が一方通行で、ユーザーのインサイトの把握には役立っていないと感じたためです。
コロナによる客離れに悩まされるなか、従来の自社が作りたいモノを作るスタンスから、ニーズを出発点にするモノ作りへとスタイルの変更を余儀なくされたそうです。
このような方針の変化に伴い、顧客の生の意見を吸い上げるためにコミュニティ内のユーザー調査に取り組んでいます。
導入事例インタビューはこちら▼
しゃぶ葉に熱い想いを持ったユーザーに限定したコミュニティ「おやさい学校 しゃぶしゃ部」が目指す、ユーザー全員にとって価値のある施策立案とは?
オンラインコミュニティにおすすめなプラットフォームを詳しく知りたい方はこちらをご参考にしてみてください。
coorumの活用でコミュニティ運営を成功へ導こう

コミュニティを成功させるには作った後の運営を大切にして、中長期的な観点で取り組むことがポイントです。
イベントの企画や継続的なコンテンツの配信をはじめ、コミュニティの熱量を高く保ち続けるには精力的な活動が求められます。
リソースを割いて運営に注力する必要があるため、プラットフォームの選択では、コミュニティの運営に役立つ機能がふんだんに備わった専用ツールの利用を推奨します。
オンラインコミュニティ構築プラットフォーム「coorum(コーラム)」はノーコードで構築が容易ながら、ブランドの世界観を反映した自由度が高いサイトを構築できるサービスです。
数々のコミュニティを立ち上げ、サポートしてきたメンバーによる、充実したコンサルティングや伴走支援が受けられることも特徴です。気になる方は、ぜひご相談ください。

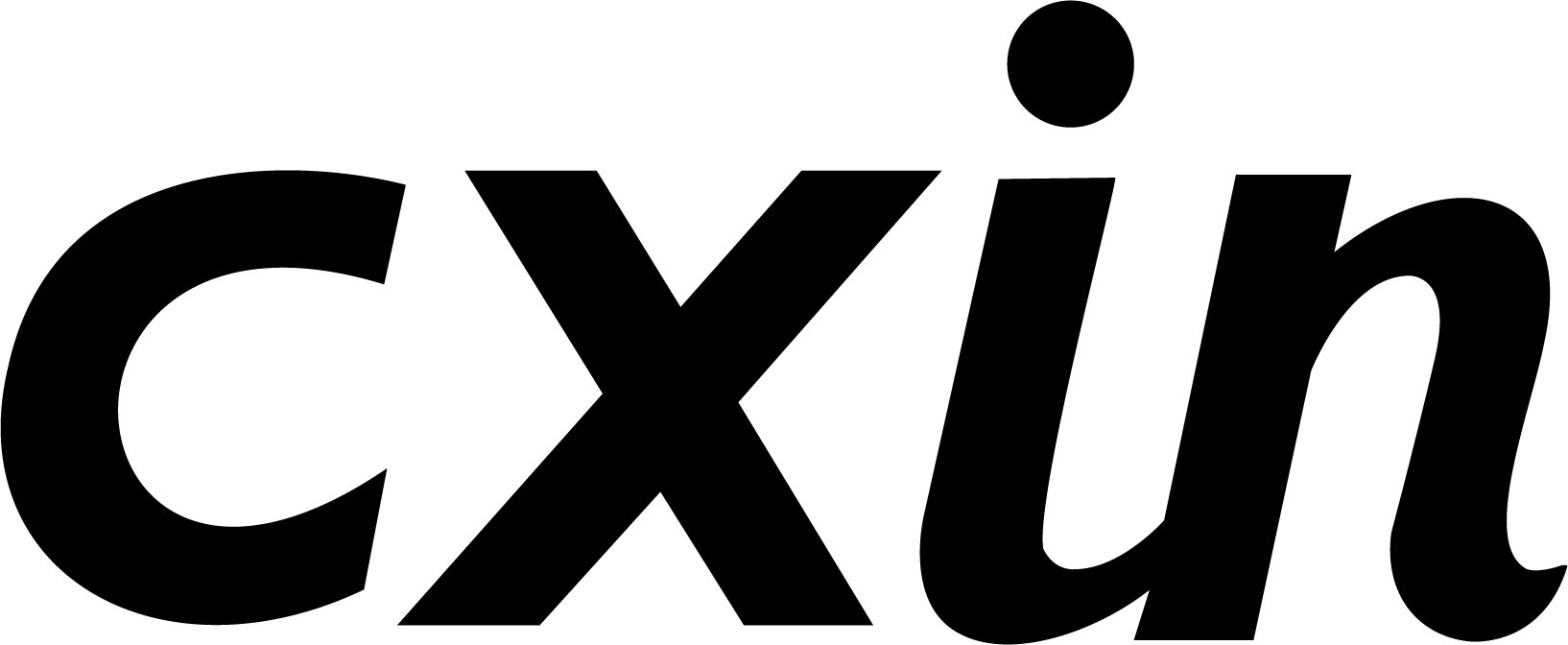




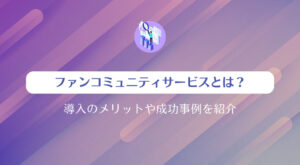
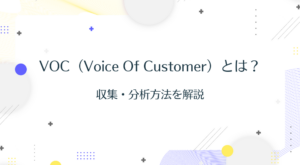
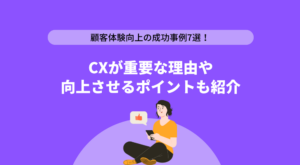
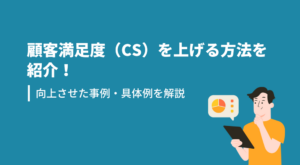
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)