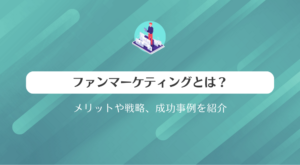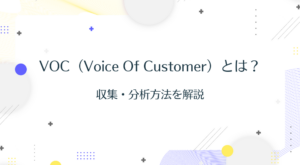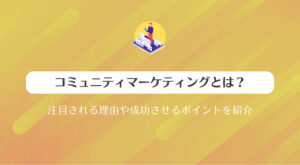市場の競争が激化している中で注目されているのが、ファンマーケティングです。商品・サービスや企業の熱心なファンを増やすことで、継続的な収益が見込めます。
今回はファンマーケティングに取り組む企業の事例や、成功させる施策などを解説します。
ファンマーケティングとはについて知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
ファンマーケティングの成功事例
ファンマーケティングに取り組む企業は増えており、成功事例も見られます。各社の取り組みはさまざまで、顧客をアンバサダーに起用した株式会社ワークマンやSNSを駆使したマーケティングが高い成果を上げている丸亀製麺の事例が代表的です。
ここでは、ファンマーケティングの成功事例をご紹介します。ぜひ、自社で施策を実施する際の参考にしてください。
株式会社ワークマン
作業着やアウトドアウェアなどを製造・販売する株式会社ワークマンは、「アンバサダー・マーケティング」によりファンマーケティングの施策を成功させています。SNSやYouTubeでワークマンの愛用を投稿している熱心なファンに声をかけ、「製品開発アンバサダー」になってもらうという施策です。無償で新商品の発信や商品開発の協力を仰いでいます。
アンバサダーから「このように改良した方がいい」「こういうアイテムが欲しい」といった提案を受けて商品開発を行い、数多くのアイテムを共同開発しているのが特徴です。
共同開発したアイテムは「ネット評価連携ショップ」で販売しています。店内でQRコード付きのPOPからアンバサダーの製品情報サイトに誘導し、セルフ販売店舗で製品説明の一部をアンバサダーが肩代わりするという仕組みです。
アンバサダーと開発したコラボ製品のみの「ファッションショー」を企画するなどのマーケティングを積極的に展開しており、さらに熱心なファンに働きかけながら製品開発アンバサダーを増やしています。
ほかの販促に頼らず、アンバサダー・マーケティングだけで製品を売り抜ける体制を作る方針です。協力の見返りには製品情報の優先開示などでアンバサダーの露出を増やし、ページビューやフォロアーの増加に協力しています。
丸亀製麺
うどん専門飲食店を経営する丸亀製麺は、TwitterやInstagramなど6つのSNSを運用して商品の情報を発信するファンマーケティングを行っています。Twitterのフォロワーは100万人以上にのぼり、商品に関する情報のみを発信していながらも高いエンゲージメントを獲得しているのが特徴です。
Instagramでは視覚的な魅力を追求し、キャプションで商品の楽しみ方を紹介するなどの工夫をして、ユーザーに「美味しそう!」と思わせる投稿作りを行っています。また、ストーリーでユーザーの投稿を紹介するなどユーザーが発信する機会を増やし、ユーザーと企業の距離を縮めて企業への好感度を高める運用をしています。
同社では既存顧客の熱狂度を高め、ロイヤルカスタマーを作る取り組みをするとともに、新規ターゲットとして若年層を取り込む最新施策を実施しています。
「チームタルトリアン」という若者向けのポップなタイトルをつけ、10代から支持を集めるインフルエンサー3組を起用した施策です。SNSを活用しながら、若年層に向けた情報発信が展開されています。
チロルチョコ株式会社
ロングセラーとなっているチョコレート「チロルチョコ」を販売するチロルチョコ株式会社は、熱心なファンが多い企業です。
「チロルチョコ」は50年以上にわたるロングセラー商品で、生き残ってきた背景には独自のマーケティング手法があります。同社ではTwitterなど4つのSNSを利用し、ユニークな情報発信を行ってファンを増やしてきました。
同社ではZOOMを使ってファンが交流するオンラインミーティングを開催し、大盛況をおさめています。参加者からは多くの感謝の声が寄せられ、「また参加したい!」という感想が集まりました。その後も継続して開催され、多くの参加者を集めています。
2022年にはオフラインイベントを開催し、話題を呼びました。来場したチロルチョコファンの総人数は100名以上で、チロルチョコ専用箱のワークショップや新商品プレゼント大会、オリジナルグッズの販売などさまざまなコンテンツを用意し、ファンとの楽しい時間を共有しました。
ヤマダイ株式会社
食品メーカーのヤマダイ株式会社は、顧客との双方向のコミュニケーションを実現する場としてコミュニティサイトを運営しています。導入のきっかけはコロナ禍の影響により、スーパーでの試食販売ができなくなったことです。
同社は試食販売など、直接顧客の声を聞くコミュニケーションを重視してきました。しかし、コロナ禍では試食販売ができず、顧客との接点はSNSだけです。そのため、接点を増やすためにファンコミュニティを検討することになりました。
同社ではコロナが拡大する以前から自社製品のファンクラブを作りたいという検討をしており、リソースの問題で実現できずにいました。
しかし、熱量が高いファンと一緒にブランドづくりをしたいという想いがあり、ファンコミュニティの立ち上げを決めたという経緯があります。コミュニティでは「企業対ユーザー」ではなく、「企業の中の人対ユーザー」という、人と人のつながりを目指しました。
コミュニティの運営でリアルな顧客の声が集まることは、開発者や社員のモチベーションにもつながっています。
導入事例インタビューはこちら▼
本物の「凄麺」好きが集うヤマダイ株式会社のコミュニティ「すごめんち」。その熱さの秘訣とは
株式会社コメダ
喫茶店チェーン・珈琲所コメダ珈琲店などを展開している株式会社コメダは、約1万人の会員登録を誇る「さんかく屋根の下」というファンコミュニティを運営しています。
珈琲所コメダ珈琲店は95%がフランチャイズであり、店舗ごとにロイヤル顧客がいる状況です。これら常連顧客が「コメダ」としてひとつにつながることを目的に立ち上げたという経緯があります。
また、同社では顧客の声に耳を傾ける時間として、常連顧客が店舗に集まるイベントを月に1回開催していますが、立地や時間の都合で参加できる顧客は限られるという事情がありました。ファンコミュニティは、そのような顧客でも参加しやすい場所として機能しています。
今後はアクティブに活動してもらえる会員を増やし、ファンとしての熱量が上がるような運営を目指すとしています。
導入事例インタビューはこちら▼
「より多くのお客様が交流ができる」コミュニティを。株式会社コメダが運営する「さんかく屋根の下」がcoorumを選んだ理由。
株式会社エポスカード
さまざまなアニメや、ゲーム・キャラクターのコンテンツとコラボしたクレジットカードを発行している株式会社エポスカードは、「すみっコぐらしエポスクラブ」というコミュニティサイトを運営しています。
立ち上げのきっかけは、コロナ禍の影響で顧客との接点が減ったためです。顧客との接点が減ったことでオンライン上で顧客とコミュニケーションがとれる場の必要性を感じ、コミュニティサイトの立ち上げを決意しました。
コミュニティでは、ランク制度が好評です。投稿に対するいいね!やログイン回数などによってポイントが付与されていくため、ログイン率やページビュー数の増加につながりました。
すみっコぐらしエポスクラブは、コミュニティを通じて楽しんで利用してもらえるような雰囲気づくり・情報提供を意識しています。顧客の行動を見える化し、施策を改善して顧客体験や顧客満足度をさらに向上させることが当面の目標です。
導入事例インタビューはこちら▼
ユーザー視点での最適なUI/UXがcoorum導入の決め手に。更なる顧客満足度の向上を目指して、コミュニティ施策に力を入れ、オンライン上での顧客接点の強化を実施。
株式会社スープストックトーキョー
食べるスープの専門店、「Soup Stock Tokyo」などの飲食店を運営する株式会社スープストックトーキョーは、社内外オンラインコミュニティ「Smash」を運営しています。
以前は紙媒体でコミュニティを運営しており、各店舗のスタッフ紹介や顧客からの声を掲載していましたが、コミュニティをより強化していく機運が高まり、オンラインに移行しました。
オンライン移行後もコミュニティに方針は変わっていないため、「日めくりカレンダー」というコーナーを作り、パートナーを含めた店舗スタッフを毎日紹介しています。
コミュニティでは「バーチャル社員」という取り組みも行っており、バーチャル社員は現役スタッフと同様の社員割引が受けられたり、商品開発の試食会に参加したりすることが可能です。
今後はバーチャル社員の登録数を増やしつつ、「現役スタッフとバーチャル社員がコミュニケーションを通してつながり続けられるような設計にしていきたい」としています。
導入事例インタビューはこちら▼
「世の中の体温をあげる」ためのスープストックトーキョー社内コミュニティ
株式会社カインズ
ホームセンターチェーンの経営を主力事業に掲げる株式会社カインズは、DIYを楽しむ人々同士がつながるコミュニティ「CAINZ DIY Square」を運営しています。
立ち上げのきっかけは、DIYを楽しむ人々をオフラインとオンラインの両方からサポートしたいという思いがあったためです。カインズに来店しているときもしていないときも、顧客の生活とつながりたいと感じ、立ち上げを決意しました。
コミュニティがあることで、困ったときに助け合える仲間や、DIYの楽しさを伝えサポートするDIYキャプテンがいるという安心感を提供でき、初心者の方でもDIYを続けやすい仕組みが出来上がりつつあります。
ユーザーが増え、コミュニティが盛り上がってきたことで、社内のバイヤーたちからも注目されるようになってきました。ゆくゆくは、コミュニケーションを使った商品開発を目指しています。
導入事例インタビューはこちら▼
DIYをライフスタイル(生活文化)に!カインズが取り組む「コミュニティ」の導入背景と展望とは
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社が運営するオンラインコミュニティ「ヱビスビアタウン」は、オープンから半年ほどで会員数が7万人以上になりました。
会員数を伸ばせた要因は、構想時から自由な場を目指してきたためです。ヱビスビールの話しかできないわけではなく、ビールを飲んでいない瞬間も含めて、気軽に投稿して会話ができるコミュニティであることが、会員数増加という成果につながりました。
SNSだけではコミュニケーションの一方通行感は否めないと感じ、よりオープンで仲間同士のコミュニケーションが発生しやすい場を立ち上げたいと感じたことが、コミュニティ設立のきっかけです。
今後の展望としては、飲食店とのつながりを強め情報を蓄積することで、「お店探しができたり、飲食店側の方が活用できたりするようなコミュニティにしたい」としています。
導入事例インタビューはこちら▼
ファンが集い語らう街「ヱビスビアタウン」で本音が聞ける理由と運用のポイント
京セラ株式会社
京セラ株式会社が運営している「TORQUE STYLE」は、「TORQUEの仲間に出会える」をコンセプトにしています。TORQUEの愛用者が集い、いっしょに語り合うことでTORQUEをより好きなってもらう場にしたいと考えたためです。
コミュニティ設立前は、アンケートで収集した意見や改善要望をアップデート内容に盛り込む以外の活用方法がありませんでした。そのため、乱立していた既存メディアとともに集約し、効果的に運営できるコミュニティを作りたいと感じたことが設立のきっかけです。
顧客同士のコミュニティの場「TORQUEチャット」では、1つの投稿に20~30ほどの返信がつくこともあり、活発な交流がなされています。顧客の要望に応えて実施した、「壁紙倉庫」という企画も好評でした。
素早い情報発信を継続し着実に会員数を増やしていきながら、顧客の声に耳を傾け会員が心地よく楽しく過ごせるようなコミュニティを目指すことを、今後の目標として掲げています。
導入事例インタビューはこちら▼
コミュニティにメディアを集約してお客様との交流に注力。仲間に出会える「TORQUE STYLE」

ファンマーケティングが重要視される理由
ファンマーケティングが重要視される理由としては、以下の3つが考えられます。
- 少子高齢化により新規顧客の獲得が難しさを増した
- 個人による発信が容易になった
- 他マーケティング手法の難易度が増加している
それぞれの理由について詳しくみていきましょう。
少子高齢化により新規顧客の獲得が難しさを増した
日本は、少子高齢化が進んでいます。その結果、消費にアクティブな若年層が減少し、市場が縮小していることが新規顧客の獲得が難しくなった要因です。
新規顧客の獲得が難しくなったことで、既存顧客にファンになってもらうファンマーケティングの重要性が増しています。
一人でも多くの既存顧客をファンにできれば、リピート購入で売上を増やしたり、UGC(口コミをはじめとするユーザーからの発信)で宣伝してもらえたりするためです。
個人による発信が容易になった
SNSの普及により、個人による情報発信が容易になったことも、ファンマーケティングが重要視される要因といえるでしょう。
SNSはさまざまな年代、属性の方が利用しており、その影響力は計りしれません。実際に、製品やサービスを購入したファンからの好意的な発信は、売上にプラスの影響を及ぼしています。
ファンマーケティングで確実にファンを増やし、ファンに企業の商品・サービスを積極的に発信してもらうことが、これからのマーケティングでは重要となるでしょう。
他マーケティング手法の難易度が増加している
インターネットが普及したことで、企業のマーケティング手法はWebマーケティングが中心となりました。その結果、Webマーケティングを行う企業も増加し、消費者の注目を集めるための競争も激化しています。
その最たる例が、リスティング広告です。参入企業が増えたことで効果的な広告展開が難しくなったため、クリック単価の上昇を引き起こしています。
以上のことから、企業はこれまでのWebマーケティングとは異なる独自のコンテンツを持つ必要があり、SNSを活用したファンマーケティングの注目度が高まってきているのです。
ファンマーケティングを行うメリット
ファンマーケティングを行うメリットは以下の3つです。
- 収益の安定化につながる
- ユーザーのリアルな意見を集めやすい
- 新規顧客の獲得にもつながる
それぞれ詳しく解説します。
収益の安定化につながる
ファンは既存顧客よりも、商品・サービスのリピート率が高いです。競合他社の商品・サービスに乗り換える「ブランドスイッチ」が起こる可能性も低いため、収益の安定化につながります。
ファンを大切にすることの優位性は、「パレートの法則」からも明らかです。「全体の数値の80%は全体を構成するうちの20%の要素によって生み出されている」という法則で、この法則に倣うと2割のファンが8割の売上を生み出していることになります。
ファンマーケティングによってファンを増やせば、強固な売上基盤を構築できるでしょう。
ユーザーのリアルな意見を集めやすい
ファンマーケティングの施策としてファンと直接交流できる場を用意すれば、ファンのリアルな意見を集めやすくなります。ファンから得た意見を反映させれば、より良い商品・サービスを生み出せる可能性が高まるでしょう。
仮に否定的な意見が多かったとしても、真摯に対応すればファンとの関係をより強固にできます。顧客とのニーズのズレを修正できれば、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
新規顧客の獲得にもつながる
SNSやインターネットが普及した現在の日本では、商品・サービスを購入する前に口コミを参考にする消費者が増えてきています。実際に使用した人の口コミには信頼性があるため、より目的に合った商品・サービスを購入できると考えているためです。
そのため、口コミを発信するような熱心なファンを獲得できれば、その口コミがユーザーの目に留まり、新規顧客の獲得につながります。

ファンマーケティングを成功させる3つのポイント
ファンマーケティングを成功させるには、押さえたいポイントがあります。
- ファンのニーズを把握する
- ファンが集まるコミュニティを作る
- ファン限定のイベント・キャンペーンを開催する
まず、現状のファン層とニーズを把握し、それに沿った適切なアプローチを考えます。ファン同士が交流できる場を作り、商品・サービスの理解度を深める施策も必要です。
ファンマーケティングを成功させるポイントをみていきましょう。
ファンのニーズを的確に把握する
ファンマーケティングの施策では、まずファンを見つけることから始めます。方法は、主に以下の3つがあげられます。
- 顧客リストの中から購入回数・購入金額の大きいユーザーをリストアップする
- 一般消費者の口コミ・投稿をチェックする
- ソーシャルリスニングを行う
自社の商品・サービスのリピーターは、熱心なファンの可能性が高いでしょう。一般消費者によるSNSへの投稿やECサイトの商品レビュー、口コミサイトなどを調査するのもファンを見つけるのに効果的です。
ソーシャルリスニングとは、SNSやブログなどで交わされるユーザーの自然な会話を収集・分析し、ビジネスに反映させることです。
次に、ファンのニーズを把握しましょう。ファンであっても熱量は異なるため、熱量に応じてファンのリストを作成し、それぞれのニーズはなにか考えます。熱狂的なファンには、満足度を高めてもらうための企画、まだ熱量がそれほど高くないファンにはファン化を促進する企画を検討しましょう。ニーズを知る方法としては、アンケートの実施があげられます。SNSを活用して集めるのもよいでしょう。
ファンが集まるコミュニティを作る
顧客との信頼関係を作るために、接点を増やすことも大切です。インターネットの普及で気軽に接触できる機会は多く、SNSなどを活用して積極的に顧客との接触を図りましょう。
SNSで自社に関する投稿には「いいね!」をつけたり、コメントを入れたりする接触も効果的です。定期的にライブ配信を行い、視聴者とコミュニケーションをとるという方法もあります。
ファンとの接触で特に効果的なのが、コミュニティの運営です。コミュニティではファンとの交流が深まり、効果的なファンマーケティングができます。
コミュニティが活性化することでファン同士の情報交換を促し、商品やサービスの理解度を深められるのもメリットです。ファンがファンを呼ぶ効果や、交流を通じてライトユーザーがコアなファンになることも期待できます。
また、コミュニティを作れば、顧客に対しリサーチをかけ、商品・サービスについての意見や改良ポイントを知ることもできます。外部の業者にリサーチを依頼する必要がなく、コストもかかりません。
企業とファン、あるいはファン同士が交流することでファンの愛着や信頼緯度も上がり、ロイヤリティを醸成します。
ただ購入している商品・サービスの性能や価格に価値を感じている優良顧客の場合、それ以上に魅力的な商品・サービスが他社から提供されたときにはそちらへ流れてしまう可能性があります。
しかし、ロイヤリティの高いファンであれば、企業やブランドそれ自体に価値を感じているため、競合他社に移行する可能性は低くなるでしょう。コミュニティの運営は、このような企業やブランドへの愛着や信頼を育むために効果的です。
ファン限定のイベント・キャンペーンを開催する
ファンとのつながりを強めるには、飽きさせない工夫も必要になります。ファンが離れないための戦略として有効なのが、ファン限定のイベントやキャンペーンの開催です。
定期的にイベントを開催することで、ファンの熱量をより高めることができます。熱心なファンは積極的に情報を発信する傾向があり、魅力的なイベントの開催は情報の拡散も期待できるでしょう。
ファンと直接コミュニケーションすることでファンの生の声を聞く良い機会になり、参加者にとっては特別な体験になります。ファンとしての意識を高め、熱量の高いファンへと変わることが期待できるでしょう。
リアルなイベントの場合はその場で商品を手に取り、試食やサービスの体験など物理的な体験を提供できます。オンラインでは伝えきれない商品・サービスの良さを実感してもらえるのがメリットです。来場者と直接顔を合わせてアピールできるのも、高い訴求効果があるでしょう。
ファンマーケティングの注意点
ファンマーケティングの実施では、いくつか注意したい点があります。ファンの育成はすぐに効果が得られるものではなく、労力や時間がかかるという点です。中・長期的な計画でのぞまなければなりません。また、ファンとの距離感を誤ると炎上などのリスクがあります。
ここでは、ファンマーケティングの実施で注意したいポイントをご紹介します。
ファンの育成には時間がかかる
ファンマーケティングを実施しても、すぐに効果が出るわけではありません。顧客が企業や自社の商品・サービスに愛着や信頼を持つのには時間が必要です。始めてすぐに成果を得られるものではないことを理解し、長期的な視野で取り組まなければなりません。
成果を急ぐあまり十分な計画を行わずに実施しても、顧客との関係性を深めることはできないでしょう。長期的な計画と目標を設定し、地道に顧客との信頼関係を築区ことが大切です。
距離感を誤らないこと
顧客との接触では、企業と顧客との距離感を忘れないようにしましょう。信頼関係を築くにはより親しみを込めて接触することも必要かもしれません。しかし、早く関係性を築こうとして距離感を誤ると、炎上につながる恐れがあります。
イベントやSNSなどで顧客と直接交流する際、距離を縮めるためにあえてカジュアルな話し方をしたり率直な意見を述べたりすることがあるかもしれません。
それを快く受け取る人ばかりとは限らず、企業としてふさわしくないと感じる場合もあるでしょう。反感を買ってトラブルになるケースもあります。SNSでトラブルの内容を発信・拡散されれば、企業イメージを損なう結果になるでしょう。
企業として、顧客とのコミュニケーションには十分な注意が必要です。
ファンマーケティングは長期的視点で取り組むことが大事
ファンマーケティングは企業のファンを増やす施策で、安定した収益を上げるなど多くのメリットがあります。ファンの口コミによる宣伝効果で、広告費を削減することもできるでしょう。
ファンマーケティングで多くのファンを獲得している成功事例も少なくありません。ファンマーケティングの成功には、ファンのニーズを把握し、接点を増やすなどの施策が必要です。
コミュニティの運営など効果的な施策を行うことで、着実にファンを増やしていけるでしょう。ただし、ファンの育成には時間が必要です。手間と時間をかけ、ゆっくり信頼関係を築く施策であることを把握しておきましょう。

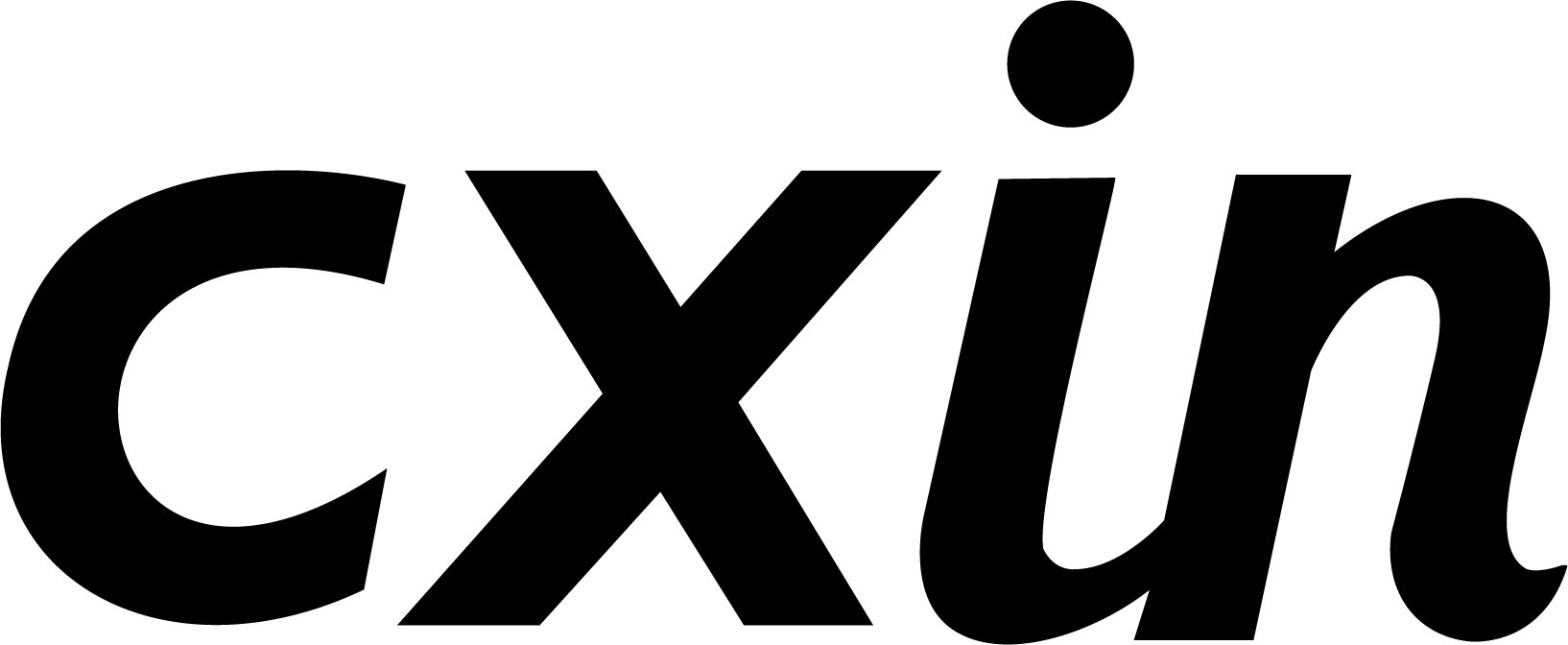


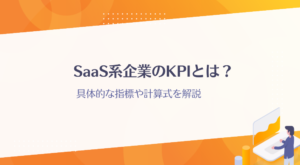

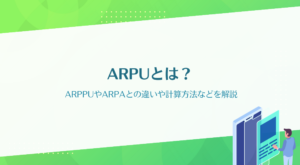



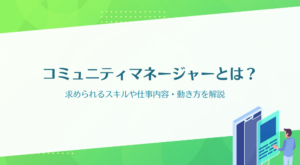


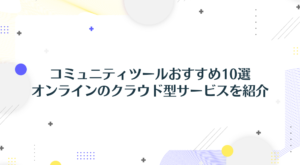




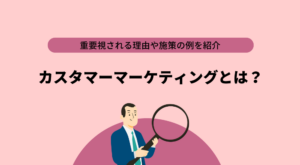



![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)