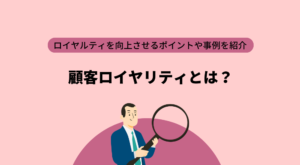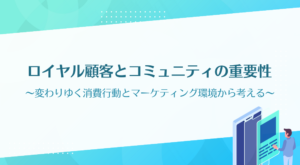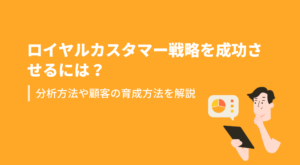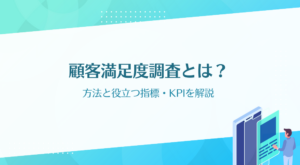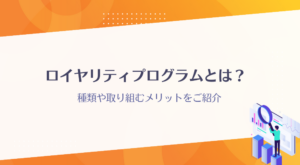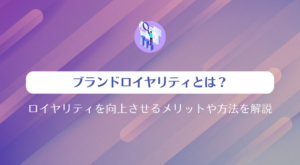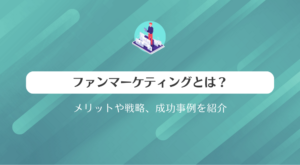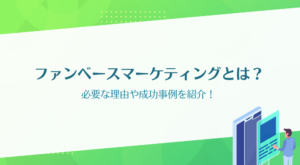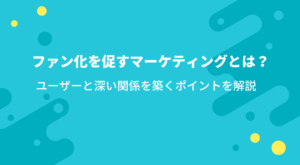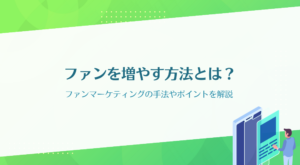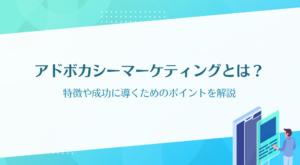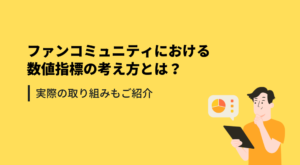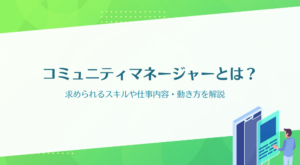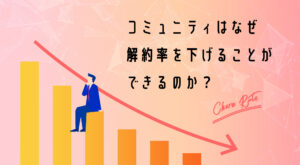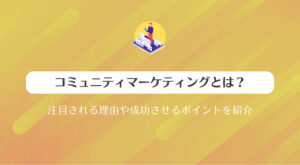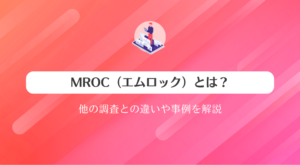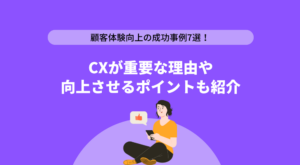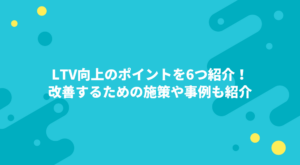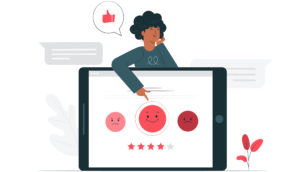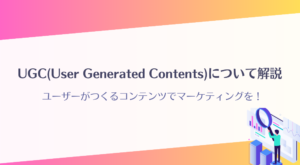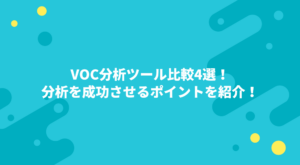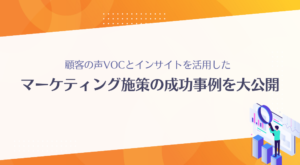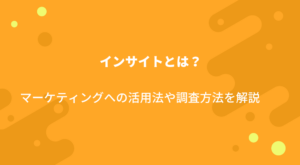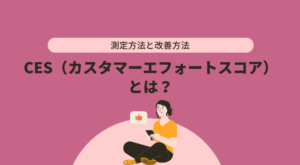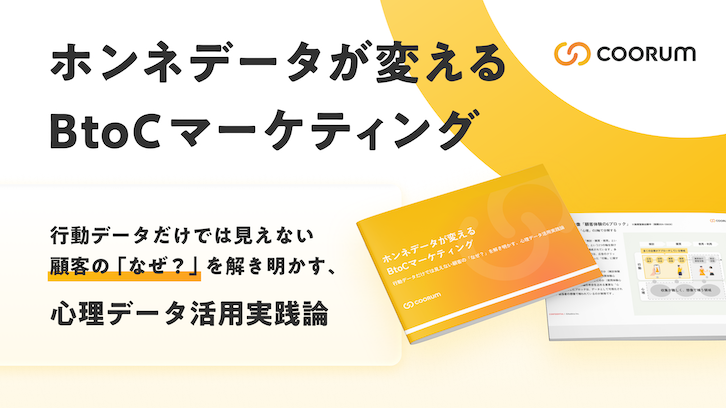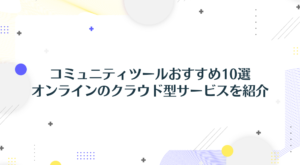
ビジネスにおける「顧客接点」は、ますます重要になりつつあります。顧客接点を強化することで、顧客のニーズの把握や顧客対応の改善ができ、顧客満足度の向上にもつながります。
この記事では顧客接点の概要や種類、強化するための方法や成功事例を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
顧客接点(タッチポイント)とは?
まずは、顧客接点(タッチポイント)の概要とビジネスにおいて重要性を増している理由を押さえておきましょう。
顧客接点の概要
顧客接点とは、企業と、顧客が接する機会・場所・媒体などのことです。「タッチポイント」や「コンタクトポイント」と呼ばれることもあります。
企業と顧客にはさまざまな関わり方があり、「宣伝する」「アフターフォローをする」「苦情や改善要望を受け付ける」などがあります。いずれの場合も、企業と顧客の接点がなければ成立しません。
また、企業からすると、顧客接点は商品やサービスを直接的に提供する場所だけではなく、企業やブランドのファンを育成に繋げることが可能です。
顧客接点が重要な理由
もともと顧客接点として、店舗などのオフライン(リアル空間)がありました。加えて昨今はECサイトやSNSなどが普及し、顧客接点のオンライン化が進行しています。
顧客の購買プロセスやサービスへのアプローチも大きく変化しているため、顧客接点を活用してニーズを常に把握する必要があります。実店舗やDM(手紙)など「オフライン」の顧客接点や、ECサイトなど「オンライン」の顧客接点など、それぞれを強化していくことが必要です。
さまざまな顧客接点においてアプローチを強化すると、認知やブランドイメージの向上、売上の拡大も期待できます。
顧客接点は4種類ある
顧客接点は主に、4種類に分けられます。この章では、4種類の顧客接点の具体的な内容を見ていきましょう。
1.オフライン
オフラインの顧客接点とは、対面でのコミュニケーションを通じて顧客とつながる場を指します。具体的には、実店舗、DM(手紙)、展示会、イベントなどが挙げられます。
顧客は商品やサービスを直接体験でき、クオリティを具体的に実感できるのがメリットです。企業側としては、顧客の反応を直接確認できるのがメリットで、顧客との信頼関係の構築にもつながります。
ただし、オフラインの顧客接点は、時間と場所に限りがあるのがデメリットです。
2.オンライン
オンラインの顧客接点とは、インターネット経由の接点のことです。具体的には企業のWebサイト、モバイルアプリ、SNS、オンラインコミュニティなどが該当します。
オンラインの顧客接点の場合、顧客は都合のよいときに情報の入手や商品の購入ができるため、利便性が高い点がメリットです。オンラインではアクセス履歴や閲覧履歴などが記録されるため、企業側はデータの収集・分析がしやすく、顧客の行動パターンや嗜好を考慮したコンテンツも提供できます。
一方、商品・サービスを実際に試せないため、購入意欲を高められないケースもあります。
3.O2O(Online to Offline)
O2O(Online to Offline)とは、オンライン・オフラインの両方の顧客接点を活用する方法です。主にオンラインで顧客を獲得し、実店舗などのオフラインで商品を販売する方法が主流となっています。
たとえば、モバイルアプリでクーポンを配信し、実店舗で利用するように促す方法があります。オンラインならではの利便性、オフラインの直接的な体験を組み合わせることで、サービスの向上につなげることが可能です。
4.OMO(Online Merges with Offline)
OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインの接点とオフラインの接点の垣根を超えた、新たな顧客接点です。
OMOの具体例として「クリック・アンド・コレクト」があります。実店舗に掲示されたQRコードを読み込むことでオンライン上の商品情報を閲覧できたり、オンラインで購入した商品を実店舗で受け取ったりできるサービスです。
オンラインとオフラインの垣根を超え、ハイブリッドな体験を提供します。O2Oとの違いなど、OMOに関してさらに詳細を知りたい場合は、下記記事をご覧ください。
顧客接点を強化するメリット
事業を成長させるためには、顧客接点の強化が欠かせません。ここではその理由として、4つのメリットについて見ていきましょう。
顧客対応の改善ができる
顧客接点を強化すると、商品やサービスに対する顧客からのフィードバックを得られやすくなります。顧客の意見をもとに顧客対応の見直しや改善につなげることが可能です。
顧客対応を改善することで、企業の商品・サービスの魅力が高まり、より自社を支持してもらえるようになります。
さらに、顧客の意見から新たな商品・サービスの開発につながる可能性もあります。
顧客ニーズを把握できる
顧客ニーズがない商品・サービスを販売しても、なかなか売上につながりません。顧客がどのようなものを求めているのかを知るには、まず顧客と接触する機会が必要です。
たとえば、オンラインコミュニティを活用して商品やサービスに関するアンケートを実施することで、顧客の率直な意見を収集できます。「coorum(コーラム)」では顧客の本音について収集から分析までワンストップで実施でき、顧客起点のマーケティング実施に活かせます。
また、自社のサイトやECサイトにレビュー欄を設置することも、顧客の意見を収集する方法の1つです。
顧客満足度の向上を図れる
それぞれの顧客接点において個々の顧客に適した対応を取ることで、顧客満足度を向上させることが可能です。顧客接点を強化することで、顧客一人ひとりの情報を収集し、パーソナライズした対応が取れます。
顧客満足度を向上させると、リピーターとなる顧客が増えるのもメリットです。リピーターが多くなると、商品・サービスを繰り返し購入してもらえるため、事業の安定化につながります。
集客の改善ができる
顧客接点を増やすことで、次第に認知度が向上します。より多くの人に自社の商品やサービスを認知してもらうことで、新規の集客につながる可能性があるのもメリットです。
WebサイトやSNSなどオンラインの顧客接点を強化すると、これまでオフラインで関われなかった顧客へもアプローチできます。オンラインなら時間や場所に関係なく接点を持てるため、集客の改善が期待できるでしょう。

顧客接点を強化する方法
この章では、顧客接点を強化する具体的な方法として以下6つを解説します。
- ブランドイメージを明確に設定する
- ペルソナを設定する
- カスタマージャーニーマップを描く
- O2OやOMOを取り入れる
- ファーストパーティデータを分析する
- ゼロパーティデータを分析する
ブランドイメージを明確に設定する
個々の顧客接点の見直しを図る前に、まずどのような自社のブランドイメージを作りたいかを決めます。ブランドイメージとは、企業が実現したい未来の姿や顧客に持ってもらいたいイメージのことです。
ブランドイメージは独自性を訴求するものでもあり、他社との差別化ができる要素です。顧客接点を通じて、最終的にどのようなイメージを持ってもらいたいかを決定しましょう。
ペルソナを設定する
ペルソナとは、商品やサービスを利用するもっとも象徴的・重要なユーザー像のことです。一般的な「ターゲット」よりも詳細なユーザー像であり、職業・趣味・ライフスタイルなどを実在する人物のように設定します。
ペルソナを設定し、自社サービスと接するタイミングや方法、経路などを考えます。この結果、どの顧客接点を優先的に強化すべきか、どの顧客接点がより重要性が高いのかを把握可能です。
カスタマージャーニーマップを描く
カスタマージャーニーマップは、顧客が商品・サービスを発見・認知し、検討してから購入に至るまでの道のりをモデル化したものです。認知から購入までのプロセスごとに、どの接点を通じて、どのような行動をしているかを図に表していきます。
カスタマージャーニーマップを描くことで、具体的な顧客接点を抽出でき、どのように接点を改善していけばいいかを整理できます。
O2OやOMOを取り入れる
顧客接点の強化において、オンラインとオフラインの双方をいかに活用するかも重要です。O2OやOMOの手法を取り入れることで、オンラインとオフラインの顧客接点を一体化し、シームレスな顧客体験の提供を目指します。
また、オンラインとオフラインのデータを統合すると、顧客をより詳細に分析し、パーソナライズしたマーケティング活動もできるようになります。
ファーストパーティデータを分析する
ファーストパーティデータとは、企業が直接顧客から収集したデータのことです。顧客の行動・購買履歴や嗜好などが含まれ、分析・活用によりパーソナライズされたマーケティングやサービスの提供につながります。
たとえば、ECサイトの閲覧履歴や購入データを分析することで、顧客の興味関心を分析し、顧客に合った商品を推奨として画面に表示させることが可能です。
ゼロパーティデータを分析する
ゼロパーティデータとは、顧客が積極的に企業と共有するデータのことです。個人情報・購入意向・嗜好など、顧客が自らの意思で共有したデータです。
ファーストパーティデータとともに、顧客の求めるものを把握し、パーソナライズされたマーケティング活動をするのに役立ちます。顧客側にとっては自分のニーズに合った商品が推奨されるようになるため、接点を持つなかで顧客満足度の向上が期待できます。
顧客接点の強化に成功した事例
ここからは、顧客接点を強化してマーケティングに活用している企業の事例を3つ紹介します。
サッポロビール:ヱビスファンと社員がつながるコミュニティ
「ヱビスビアタウン」はヱビスビールが運用する顧客接点であり、ファンが自由に語り合えるオンラインコミュニティです。顧客プラットフォームサービスの「coorum(コーラム)」を活用して設立し、開始から半年で7万人ものファンが集うようになりました。
ファンとの共同開発施策として行われている、「ヱビスものづくりプロジェクト」も人気です。最終的にはファンと一緒にビールを作る構想があり、その前段階として東京の工芸品とのコラボレーションを実施しました。
特注の工芸品を作る企画であり、単価が1万円を超える商品ですが、多くのファンが参加し盛り上がりました。
導入事例インタビューはこちら▼
「ファンが集い語らう街「ヱビスビアタウン」で本音が聞ける理由と運用のポイント」
江崎グリコ:ポッキーを愛するファンのためのコミュニティ
江崎グリコは、ポッキーを愛するファンのためのコミュニティ「ポキトモ」を運営しています。
「ポッキーを愛してくださっているファンの方に恩返しがしたい」との思いから、「coorum(コーラム)」を活用して、ファンの方と深く交流するツールとして立ち上げました。
顧客接点としてポキトモを運用することで、顧客のリアルな声が聞けるようになったことが大きな収穫となりました。今後は顧客起点のマーケティングを実行する場としても活用するとしています。
導入事例インタビューはこちら▼
ポッキーを愛するファンのためのコミュニティ「ポキトモ」。江崎グリコ株式会社がシェアする体験とは?
無印良品:アプリで顧客接点を創出
無印良品は自社のスマホアプリ「MUJI passport」を活用して、購入前の顧客接点の創出に成功しました。アプリにチェックインするだけでポイントがもらえるようにすることで、来店しなくても無印良品を想起してもらえます。
顧客接点を日ごろから持つことが重要と考えたことから生まれた施策で、「無印良品週間」などのキャンペーン期間にも、多くの方が店頭でアプリを提示するようになりました。
参考|広告アサヒ「320万人が使う「MUJI passport」 顧客と「C to B」の関係築く」
顧客接点を強化するならcoorum
顧客接点(タッチポイント)とは、企業と顧客が接触する機会・場所のことです。顧客の嗜好が多様化しているため、顧客接点において常に顧客のニーズを把握する必要があります。
顧客接点にはオフライン・オンラインがあり、それぞれメリットやデメリットがあります。OMOなど、双方をシームレスに連携させる手法も重要です。
これから顧客接点を創出したい方には、「coorum(コーラム)」がおすすめです。オンラインで顧客と継続的な接点を持ち、顧客の声を商品開発に活用できます。また、顧客育成や、LTVの最大化のためのプラットフォームとしても活用可能です。
「coorum(コーラム)」では顧客の声や商品の使用実態をスピーディーに収集し、インサイトの把握に役立てることができます。アイデアがほしいとき、気になっていることを聞きたいときに、すぐ顧客にアプローチが可能です。
アンケート、目安箱のように顧客の声を収集できる「アイデアBOX」、インタビュー調整など、顧客起点のマーケティング施策をサポートする機能も備えています。顧客接点を活用して、顧客のニーズを活用したマーケティングを実践したい方は、ぜひ「coorum(コーラム)」をご利用ください。

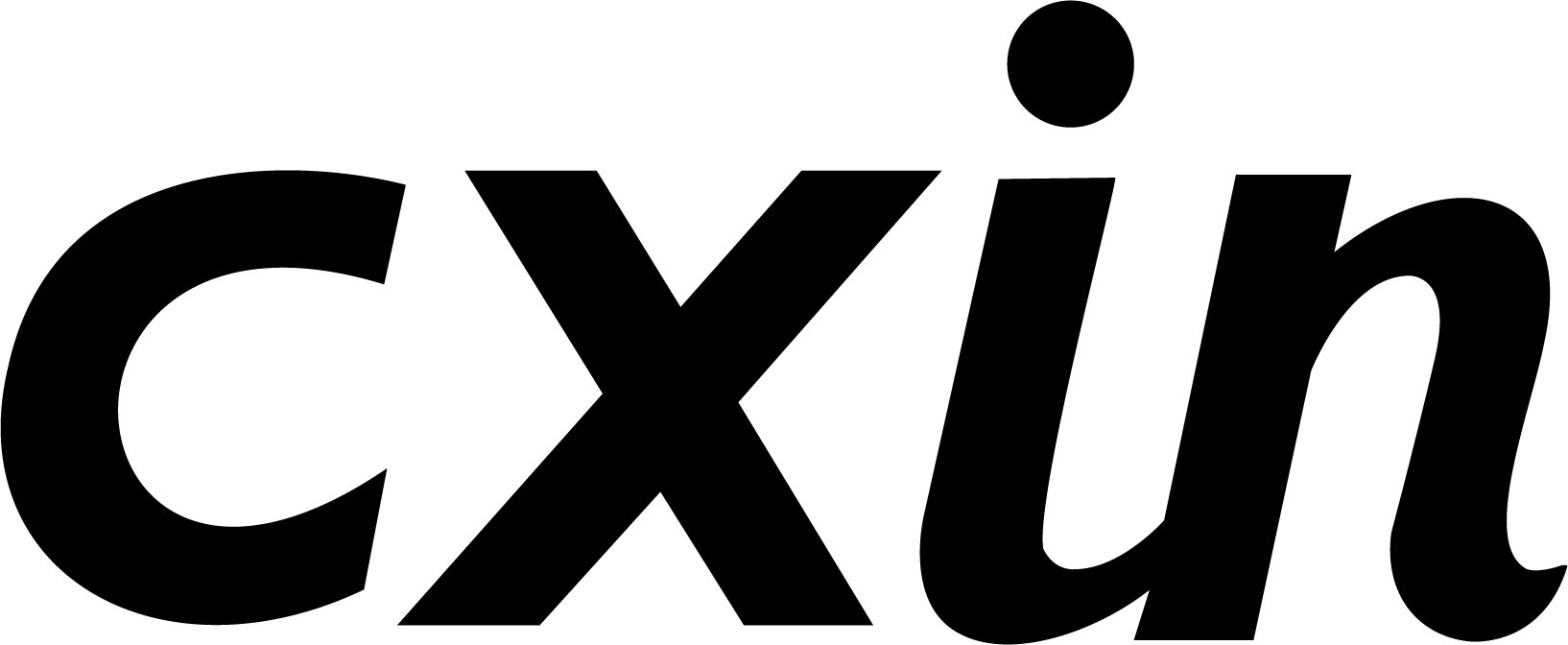

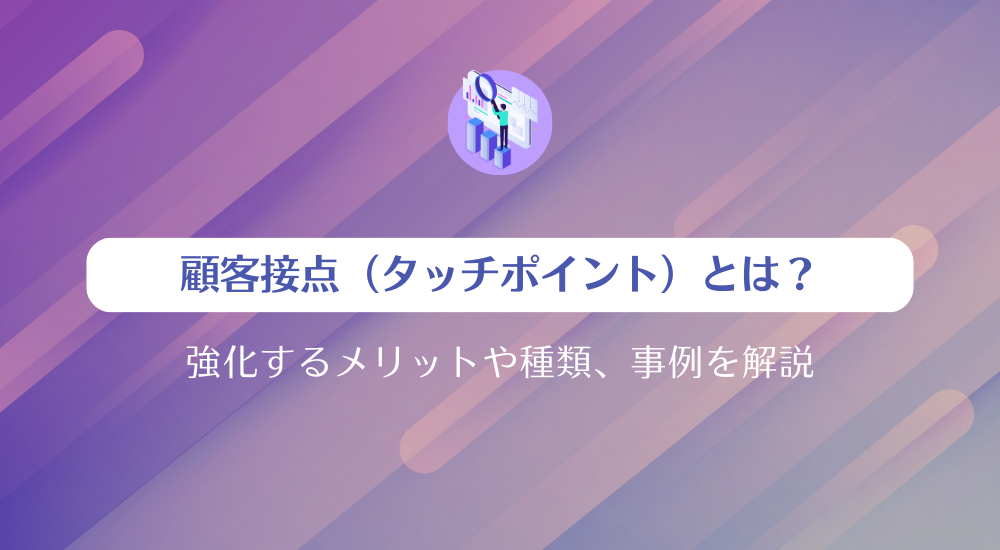
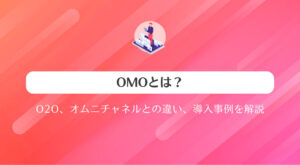


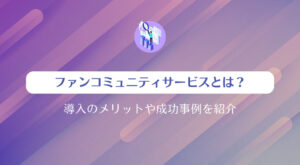
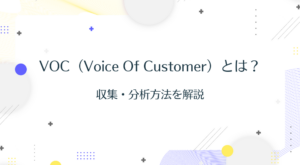
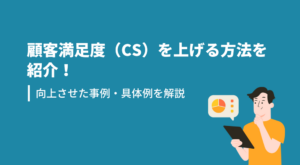
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)