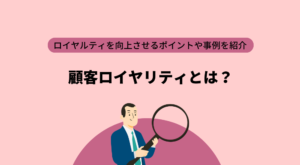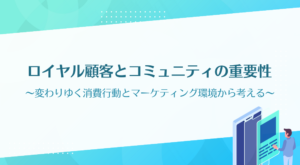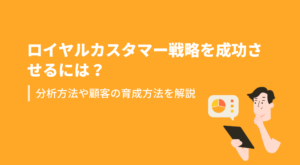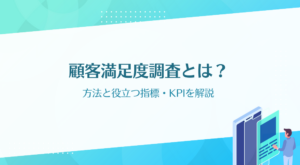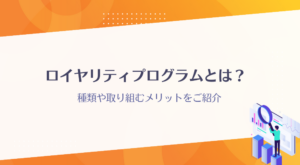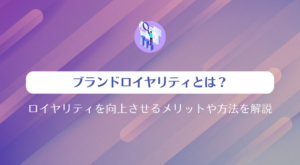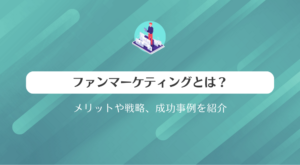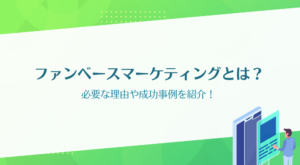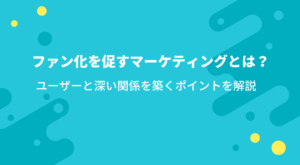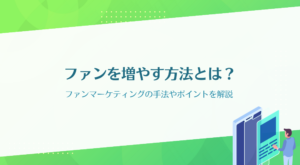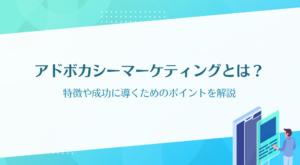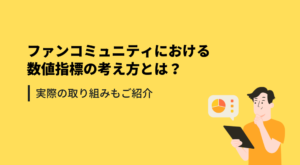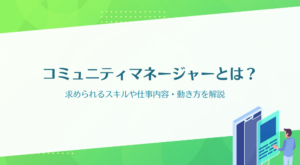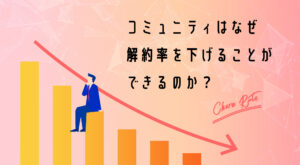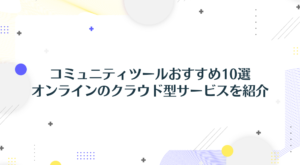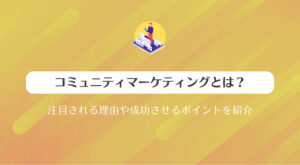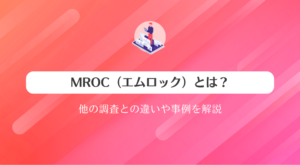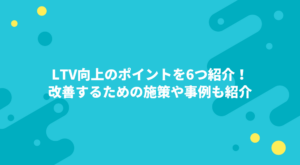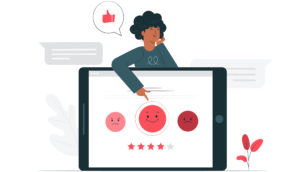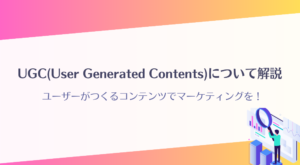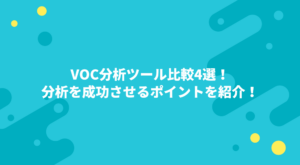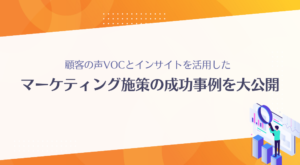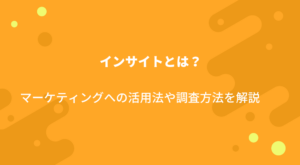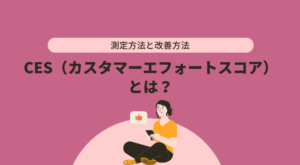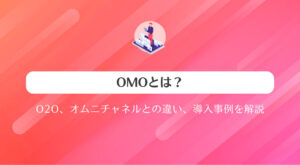
近年注目されるLTVについて話をよく聞くものの、重要性までわからない方もいるでしょう。本記事では、LTVの概要をはじめLTVを向上するためのポイントを解説します。マーケティング活動や教育の際に参考にしてください。
LTV(ライフタイムバリュー)とは
LTVとは「顧客生涯価値(ライフタイムバリュー/Life Time Value)」の略称で、1人の顧客が自社の商品・サービスの利用を始めてから終了するまでの期間に、自社にもたらした総利益を表す指標のことです。
新規顧客の流入ではなく、既存顧客の継続購入や満足度・ロイヤルティに重点が置かれます。LTVを把握することで、マーケティング戦略や顧客分析、商品・サービスの改善などにつながります。
顧客のロイヤルティが高いほど購入頻度が高くなり、LTVも高くなります。LTVは商品そのものや価格、流入媒体、顧客の購入頻度など、さまざまな要素から構成され、向上させるには多角的な施策が必要です。
LTV向上は既存顧客に向けた施策になるため、顧客満足度の向上や長期的な関係の構築に効果的です。
LTVがマーケティングで重要視される理由
LTVはマーケティングにおいて、以下の理由で重要視されています。
- 新規顧客獲得の難易度が年々高くなっているため
- One to Oneマーケティングが重要視されているため
- サブスクリプション型サービスが増えてきたため
- 顧客ロイヤルティの重要性が高まっているため
- Cookie規制で新規獲得が難しくなる見込みがあるため
ここからは、それぞれの理由について詳しく解説します。
新規顧客獲得の難易度が年々高くなっているため
競争の激化や少子高齢化といった社会の変化により、新規顧客の獲得は年々難しくなっています。そのため、既存顧客との信頼関係やロイヤルティを可視化できるLTVが重要視されるようになりました。
信頼関係を継続することで、既存顧客が家族や知人に自社商品・サービスを紹介し、新規顧客の獲得につながる可能性もあります。
LTVを高めることで、長期的に得られるメリットが大きいといえます。
One to Oneマーケティングが重要視されているため
顧客との丁寧なコミュニケーションをベースとした「One to Oneマーケティング」が重要視されている点も、LTVが注目されるようになった理由の1つです。One to Oneマーケティングは顧客をある程度絞り、個々のニーズに沿ったアプローチを行います。
たとえば、顧客の誕生日に特別なクーポンを配信したり、購入履歴をもとにおすすめの商品を提案したりするなどの手法です。
顧客データをもとに個々に寄り添ったマーケティングにより、顧客単価の向上が期待できます。また、顧客との継続的な関係の構築やロイヤリティの向上につながり、効果的に商品・サービスの利用を促進できます。
顧客との信頼関係の構築が重要とされるOne to Oneマーケティングは、LTVの数値と関連づけられます。LTVの数値を分析することで、マーケティング活動の効果を可視化できます。
サブスクリプション型サービスが増えてきたため
サブスクリプション型サービスが浸透したことも、LTVが重要視される背景に大きく影響しているといえるでしょう。
以前は動画配信サイトやデジタルツールなどのWebコンテンツが多かったものの、近年はファッションや家具のレンタル、カーシェアリングなど、さまざまな業界に普及しています。
企業にとっては安定した収益や顧客の維持につながるため、今後も展開していくことが考えられます。
サブスクリプションサービスは、顧客が継続利用することで収益が発生するビジネスモデルで、LTVの高さや解約率が収益にも直結しています。単なる売上の向上や新規顧客の獲得に向けた施策では、既存顧客が離れ、売上が低下することも考えられます。
サブスクリプション型サービスにおいて、LTVは売上に関連していたり、サービスを改善したりするために大いに役立つ指標です。サブスクリプション型サービスが拡大していく現代において、LTVの重要性は高まり続けるといえます。
顧客ロイヤルティの重要性が高まっているため
自社商品やサービスへの愛着・信頼の度合いを表す、「顧客ロイヤルティ」の重要性が高まっていることが、LTVの注目につながっています。
ロイヤルティが高い顧客は継続的な利用だけでなく、周囲に自社ブランドを薦めるなど「宣伝役」になることもあるでしょう。
SNSが普及し情報発信・収集がしやすくなった現代では、UGCや口コミが重要視されています。また、顧客ロイヤルティが高まることで顧客が競合他社へ流れにくくなり、競争力を高められるでしょう。
顧客ロイヤルティが注目される中、LTVはロイヤルティを見極める指標の1つです。単に自社商品・サービスに満足していても、スタッフの対応や購入プロセスなどに不満があると、購入や成約に至らないこともあります。
仮に購入につながったとしても、一度きりになることもあるでしょう。顧客ロイヤルティが高いほどLTVも向上し、効果を発揮していることがわかります。
Cookie規制で新規獲得が難しくなる見込みがある
「3rd Party Cookie(Webサイトやアプリから発行される顧客情報)」の規制により、Webマーケティングでの新規顧客獲得が困難になることが予想されています。
たとえば、一度ネット上で検索した商品やサービスの広告が繰り返し表示される「リターゲティング広告」は、Cookieの規制により使えなくなることが懸念点の1つです。そのため、1st Party Cookieを利用して、リピート顧客を増やしLTVを向上させる施策が注目されています。
1st Party Cookieとは、ユーザーが訪問しているWebサイトのドメインから直接発行されているCookieで、Webサイトの運営者が提供する機能などをコントロールできます。例えば、自社サイトにアクセスした人の、過去の訪問履歴や行動履歴を確認・管理が可能です。
ログを顧客データとして収集・活用し、顧客一人ひとりに向けたパーソナライズされたサービスや、顧客ニーズを分析し、マーケティング施策や商品開発などに活かすことが期待されています。
1st Party Cookieを活用したマーケティングには、顧客との長期的な関係性が重要です。そのため、施策の効果を測るためには、LTVの分析が必要不可欠となるでしょう。
LTV(顧客生涯価値)の計算方法
LTVの数値は、定期的に測ることで顧客満足度の可視化や適切な施策を行いやすくなります。LTVは、さまざまな計算方法で求められますが、ビジネスモデルによって適切な計算方法が変わる場合もあります。
自社のビジネスモデルに合った、活用しやすい方法でLTVを算出しましょう。以下では、LTV(顧客生涯価値)の計算方法を解説します。
LTVの計算式
以下は、LTVの代表的な計算式です。
- LTV = 平均購入単価 × 粗利率 × 平均購入頻度(回/年)× 平均継続期間(年)
LTVを求める数値も、それぞれ算出が必要になります。以下は、算出に求める数値の詳細です。
| 平均購入単価 | 1年間あたりに顧客が自社商品・サービスを購入した際の1回の購入単価 |
| 粗利率 | 売上額に対する粗利額(売上-売上原価)の割合「粗利÷売上=粗利率」 |
| 平均購入頻度 | 1年間あたりに顧客が自社商品・サービスを平均して何回購入したか |
| 平均継続期間 | 顧客が契約してから解約するまでの継続期間の平均。チャーンレート(解約率)の逆数から算出が可能。「1÷チャーンレート」 |
他にも、新規顧客獲得にかけた広告費や営業活動などの「顧客の獲得・維持コスト」や、「収益率」を用いた計算式もあります。
LTVの計算例
月額1,000円(粗利率50%)の動画配信サービスを、2年間利用した顧客のLTVを計算式に当てはめると、以下の金額になります。
- LTV = 平均購入単価 × 粗利率 × 平均購入頻度(回/年)× 平均継続期間(年)
- LTV=1,000円×50%×12回×2年=12,000円
この場合、LTVは12,000円です。ここから1人あたりの顧客獲得・維持コストを差し引くと、マーケティングや営業活動の費用対効果も測定できます。
次に、1回100万円のセミナー(粗利率50%)を1年に1回、3年間利用した例で計算してみましょう。ここでは、顧客獲得・維持コストとして広告費や人件費が60万円かかったこととします。LTVは以下のように求めます。
- LTV = 平均購入単価 × 粗利率 × 平均購入頻度(回/年)× 平均継続期間(年)ー顧客獲得・維持コスト
- LTV=100万円×50%×1回×5年-60万円=190万円
セミナーを利用した企業のLTVは190万円です。
LTVに関連する指標
LTVに関連する指標には以下のものがあります。LTVとあわせて利用することで新たな課題を発見したり、改善策を立てたりできます。
| ARPA・ARPU | ARPA=1つのアカウントの平均売上額ARPU=1人のユーザーあたりの平均売上額 |
| CAC | 1人の顧客を獲得するために必要なコスト |
| MQL・SQL | MQL=マーケティング活動で獲得した見込み客SQL=営業活動で獲得した見込み客 |
| チャーンレート | サービスの解約率 |
| ユニットエコノミクス | ビジネスの採算性や健全性を可視化 |
以下では、それぞれの指標について詳しく解説します。
ARPA・ARPU
サブスクリプションサービスや定額課金モデルのビジネスで用いられる指標に、「ARPA(Average Revenue Per Account)」と「ARPU(Average Revenue Per User)」があります。
ARPAは、1アカウントあたりの平均売上金額を示す指標です。以下の計算式で算出されます。
- ARPA=売上 ÷ アカウント数
アカウントごとの売上であるため、1人のユーザーが複数のアカウントを持っている場合や、複数のユーザーが1つのアカウントを利用している場合もあります。アカウント数で課金することの多い企業では、実態に近い数値を把握できることでARPAを用いることが多いです。
一方、ARPUは1ユーザーあたりの平均売上金額です。以下の計算式で算出できます。
- 売上÷ユーザー数
ユーザーごとに一定期間の累積額を把握できるため、企業の業績を評価するために活用されています。
自社のビジネスモデルにより、ARPA・ARPのどちらが適しているかは異なります。それぞれの定義を理解した上で活用することで、LTVの解像度を高められるでしょう。
CAC
「CAC(Customer Acquisition Cost)」は、1人の顧客を獲得するために生じたコストを示す指標です。広告やイベント出店、営業活動などにかかったすべての費用が含まれます。CACは以下の計算式で算出します。
- 獲得に要したコスト(営業・マーケティング・広告費 など)÷ 新規顧客獲得数
CACがLTVを上回る場合、顧客が企業にもたらす利益以上に、新規顧客の獲得にコストが発生していることを意味します。
そのため、顧客を獲得するたびに損失が発生し、長期的な視点で考えると、新規顧客を獲得しても赤字の状態になるでしょう。そのような状態を防ぐためにも、LTVとあわせてCACを把握しておくことが必要不可欠です。
MQL・SQL
自社の見込み客として「MQL(Marketing Qualified Lead)」と、「SQL(Sales Qualified Lead)」があります。
MQLは、メルマガやイベントなどのマーケティング活動で獲得した見込み客の中でも、確度の高いリード(見込み客)です。MQLはそれぞれの顧客の反応によってスコア付けをしていくことで、顧客ごとの行動を可視化し効果の高いアプローチにつなげられます。
SQLは、営業活動によって得られた見込み客で、顧客からの問い合わせや要望から生まれることが多いです。また、MQLの中でより自社商品・サービスへの関心度が高いとされる見込み顧客がSQLとして分類され、営業担当者によりアプローチを行うこともあります。
それぞれの顧客に最適な提案がしやすくなるMQL・SQLを利用することで、マーケティング活動や営業活動の精度を高め顧客との関係性構築やLTVの向上につながるでしょう。顧客の中でMQLやSQLの選出は、過去の実績から基準を設けておくことでスムーズな分類が可能です。
チャーンレート
チャーンレートは、サービスの解約や離反・離脱の割合を示す指標(解約率)です。解約だけではなく、有料会員だったユーザーが無料会員になるなど、ダウングレードする場合も含まれます。以下の計算式で算出が可能です。
- 一定期間中に失った(ダウングレードした)顧客数÷当初の顧客数
企業にとってはマイナスな指標ですが、チャーンレートを正しく把握して現状の問題点を洗い出すことで、LTVの向上につながることが期待できます。
とくに、契約の継続が必要なサブスクリプションサービスにおいては、顧客ニーズや改善点を分析するためチャーンレートの把握が欠かせません。
チャーンレートには顧客数ベースの「カスタマーチャーンレート」と、収益ベースの「レベニューチャーンレート」があります。双方活用することで、解約率を多角的に分析しLTVを向上するための適切な策を講じられるでしょう。
また、チャーンレートは月次と年次など、指定する期間によっても数値が大きく変動するのが特徴です。自社の測定したい期間にあわせて、最適な方法で算出する必要があります。
ユニットエコノミクス
ユニットエコノミクスとは、「顧客獲得のために生じたコスト」と「獲得した顧客から得られる利益」のバランスを示す指標です。
ビジネスの採算性や健全性を可視化し、「顧客の獲得を目指すか」「収益の改善をするべきか」などという経営判断につながります。主に、サブスクリプション型サービスで活用されています。以下の計算式で、ユニットエコノミクスを求められます。
- ユニットエコノミクス=LTV ÷ CAC
ユニットエコノミクスの目安は3以上です。数値はかけたコストに対するリターンを意味しており、3の場合は3倍のリターンを得たことになります。ユニットエコノミクスが3以下の場合は採算性が低く、なんらかの見直しをしなければいけません。
一方、数値が3を大幅に上回っている場合にも、機会損失の可能性があり注意が必要です。例えば、ニーズがあるにもかかわらず新規顧客の獲得にコストをかけないことで、顧客を取りこぼしている可能性があります。
このように、ユニットエコノミクスは採算性のバランスを可視化し、企業の課題を明確にできます。赤字化や機会損失を防ぎ、企業の将来的な成長性も予測しやすくなるでしょう。

LTV向上に役立つツール
LTVは以下のツールで向上に役立てられます。
- MA
- CRM
- チャットボット
- コミュニティ
LTVを向上させるためには、顧客データの収集や計算、分析などが必要不可欠です。ツールを使用することで、効率的かつ正確なLTVの分析ができます。人手不足などの課題がある場合にも便利です。ここからは、それぞれのツールについて詳しく解説します。
MA
MA(マーケティングオートメーション)は、マーケティング活動の自動化や効果測定ができるツールです。見込み顧客情報の一元管理やメール配信、顧客行動の分析などの機能で、マーケティング活動を大幅に効率化できます。
顧客の興味や関心度にあわせて適切なアプローチができるため、良好な関係が構築しやすく、LTVの向上にもつなげやすいです。
また、過去に行ったマーケティング施策を分析し、改善につなげられます。精度の高い施策を実施できる点でも、LTVの向上が期待できるでしょう。
CRM
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理し分析できるツールです。氏名や所属企業、部署などの個人情報をはじめ、行動特性やニーズなどあらゆる情報を蓄積し、顧客への適切なアクションをとるための基盤づくりができます。
カスタマーサポートやカスタマーサクセス機能があるものでは、顧客の対応履歴や過去の問い合わせ内容を参照し、柔軟な対応がしやすくなります。
同じトラブルの発生や、重複対応を防げるため、従業員の対応力強化にもつながるでしょう。結果的に、顧客満足度の向上が期待できます。
個々のニーズを細かく把握したアプローチにより、長期的な関係性を築くことで、LTVを向上させることが可能です。
チャットボット
チャットボットとは、人間に代わってロボットがテキストや音声を通して、自動で会話するコミュニケーションツールのことです。
AIに学習させることで、Webサイト上などでユーザーが質問した内容に対し、的確な返答ができます。
例えば、自社のWebサイトやECサイトなどにチャットボットを導入すると、顧客からの質問に自動で応答してくれます。顧客側は電話やメールで問い合わせする手間が省け、気軽に質問できるでしょう。
また、スピーディに対応できるため、属人的なカスタマーサポートの対応より、素早く問題解決ができて顧客満足度が向上します。結果的に、解約率の改善、LTVの向上につながります。人手不足を補いながら、業務の質を高められます。
オンラインコミュニティ
オンラインコミュニティは、企業とユーザー、またはユーザー同士など、共通の目的・利益を持つ人同士がインターネット上で交流できる場です。ファンコミュニティとも同義です。
コミュニティは独自のサイトを一から構築するほか、SNSやプラットフォーム、サービスを利用するなどという方法があります。コミュニティ内でのコミュニケーションはもちろん、顧客の意見収集やLTVの分析までできるなど、さまざまなメリットがあります。
コミュニティ運営を効果的に行うことで、ユーザーが企業やサービスに対する愛着が湧きやすく、顧客ロイヤルティを高められます。コミュニティ内で顧客の率直な意見を集められるため、自社商品・サービスの改善がしやすく、高い品質を保ちやすくなります。結果的にLTVの向上につながるでしょう。
LTV(顧客生涯価値)を高めるためのポイント
LTVを高めるためには、以下のようなポイントに留意する必要があります。
- アップセルやクロスセルを促し購入単価を上げる
- 顧客との接点を増やすことで購入頻度を高める
- 顧客維持・顧客獲得のコストを減らす
- 顧客ロイヤリティを向上させ解約率を下げる
LTVにはさまざまな要素が絡んでくるため、課題となる部分の強化が大切です。ここからは、LTVを高めるためのポイントについて詳しく解説します。
アップセルやクロスセルを促し購入単価を上げる
LTVを向上するためには、顧客単価を高める取り組みの「アップセル」や、購入予定の商品とあわせて別のものを提案する「クロスセル」を利用することが効果的です。LTVは顧客の購入金額と直結しており、金額が上がることでLTVの向上につながります。
アップセル・クロスセルは、顧客視点での提案内容やタイミングが重要です。購入を検討している段階でグレードが高い商品やサービスを薦めると、無理矢理買わされるように感じる方もいるでしょう。
購入を決定した際にあわせて使用すると便利な商品や、顧客にメリットがある内容など、自然なタイミングで提案する必要があります。
顧客との接点を増やすことで購入頻度を高める
顧客との接点を増やし、購入頻度を高めることもLTVの向上につながります。顧客との接点は、商談や接客などの対面だけでなく、メールマガジンやファンコミュニティなどのツールを使うことも効果的です。ツールを活用して自社製品やサービスを顧客にリマインドすれば、購入のきっかけになることもあります。
また、顧客との接点を増やしていくことで自社へのロイヤルティが高まり、継続した購入も期待できるでしょう。購入頻度が高まれば自然と顧客単価も向上し、結果的にLTVの改善につながります。
顧客維持・顧客獲得のコストを減らす
LTV向上のためには顧客へのアプローチだけでなく、現在の顧客維持や顧客獲得にかかるコストを見直し、抑制することも重要です。
しかし、コストを削減したがためにサービス品質が下がり、顧客が不満を抱く結果にならないよう注意が必要です。顧客視点を維持しつつ、無駄な業務にかかるコストなどの洗い出しを行い費用対効果の高い施策を実施しましょう。
顧客ロイヤルティを向上させ解約率を下げる
解約率を下げ、顧客の長期的な利用を促進することも、LTV向上には必要不可欠です。そのためには、顧客ロイヤルティを高める施策が必要になります。商品・サービスの品質を高めることはもちろん、顧客との信頼関係を構築することが必要不可欠です。
顧客ロイヤルティを高めるためには、スタッフの対応やサポート体制、購入プロセスの簡単さなど、顧客体験一つひとつを改善していくことが求められます。
SNSやオンラインコミュニティを活用し、顧客のニーズを探すことや、企業・ユーザーと交流して自社への愛着を深めることも効果的です。
LTVの向上にはcoorumがおすすめ
年々注目度を増すLTVは顧客ニーズを多角的に分析し、既存顧客と長期的な信頼関係を構築するために重要な指標です。企業の競争が激化し、新規顧客の獲得が困難になる中、顧客ロイヤルティの向上にもつながるLTVのための施策が必要不可欠です。
LTVを向上させるためには、顧客満足度の改善や、購入単価を上げるアップセル・クロスセルや、解約率を下げる取り組みを実施するなど、さまざまな方法があります。また、CRMやMAなどのツールやオンラインコミュニティを活用することも効果的です。
「coorum」(コーラム)は、顧客の声の収集やロイヤル顧客の育成ができるオンラインコミュニティで、顧客単位で行動分析・心理データの分析ができます。
顧客参加型のイベントや販促プロモーションとの融合、マーケティング施策や商品企画への幅広い活用方法があるため、LTV向上に向けた施策にも柔軟な対応が可能です。LTVの分析・向上につながるツールを検討している場合は、ぜひご利用ください。
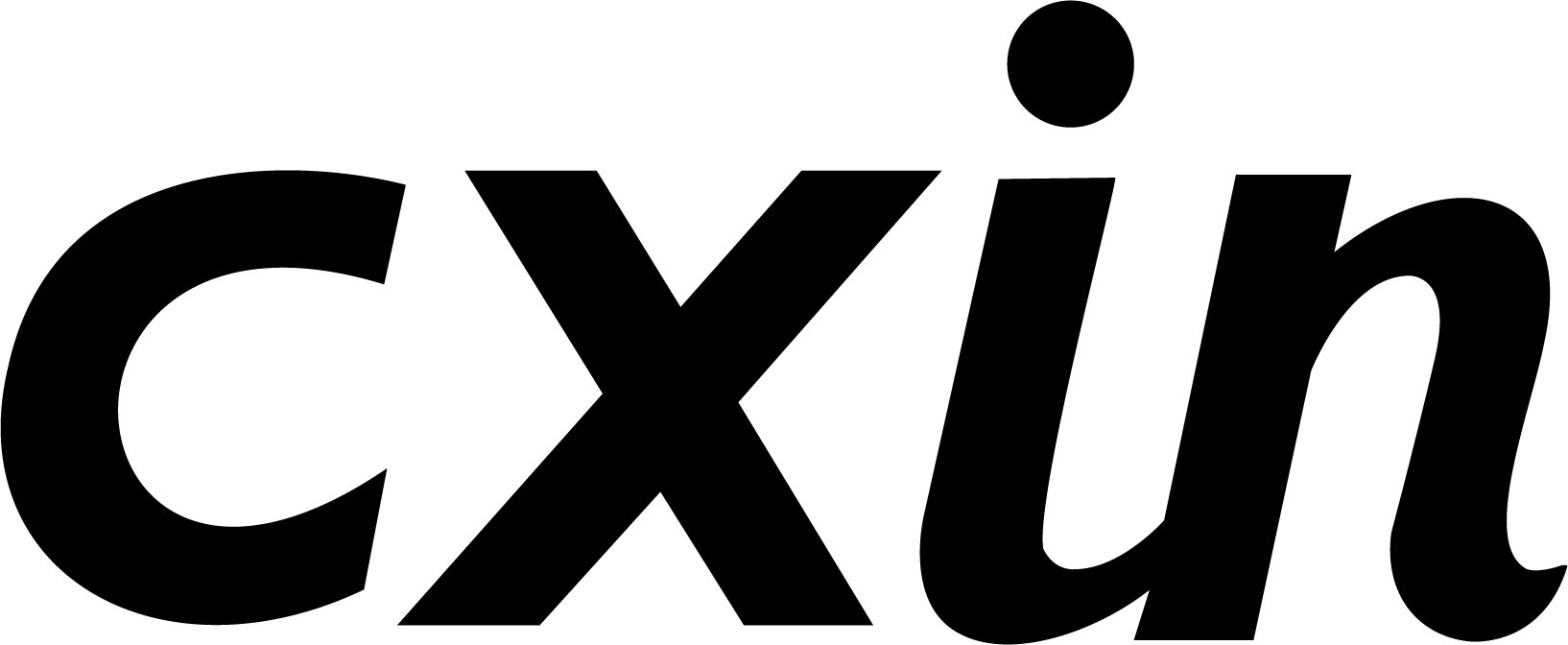

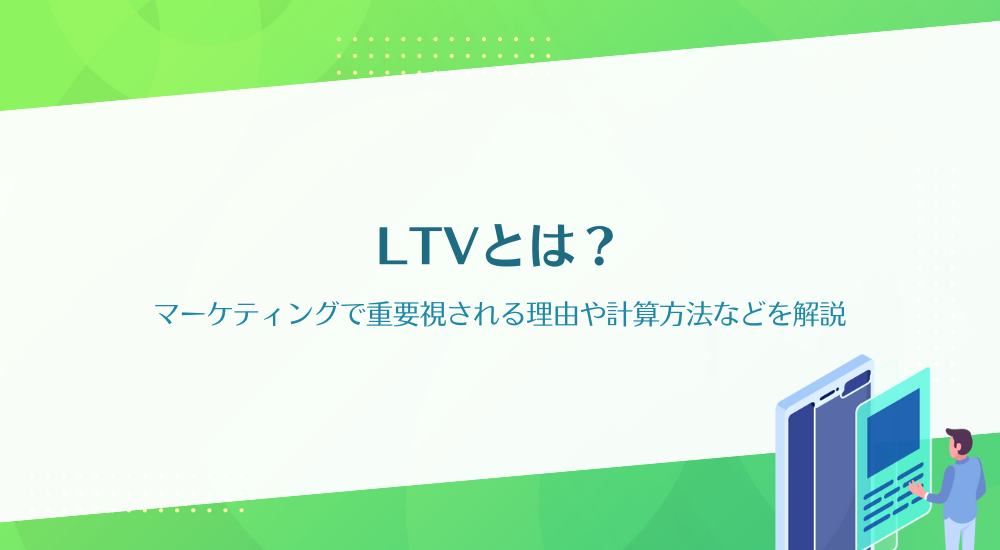


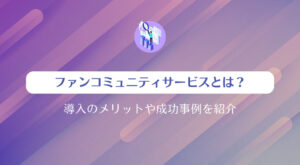
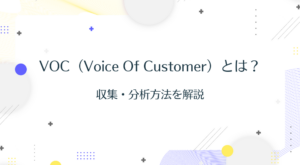
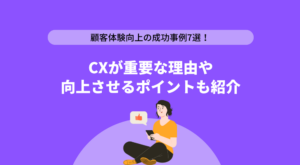
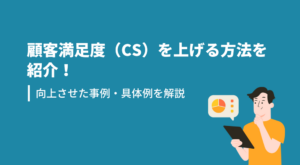
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)