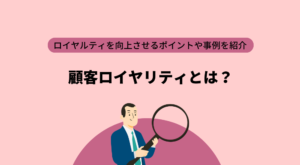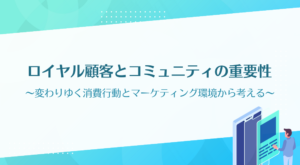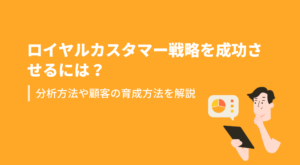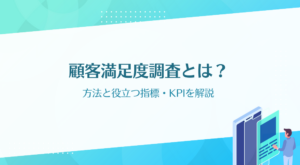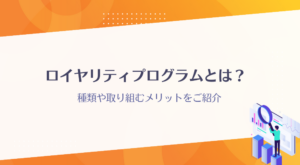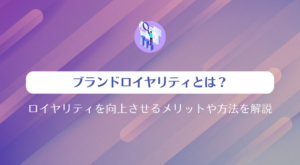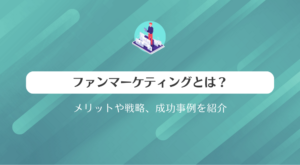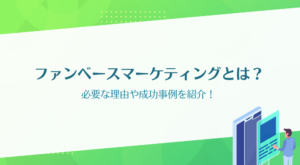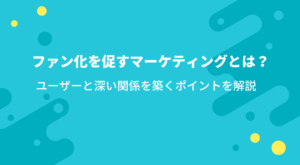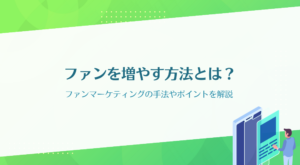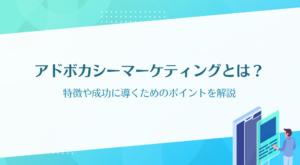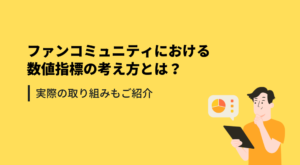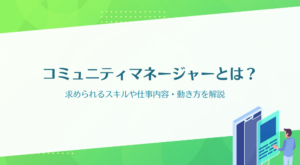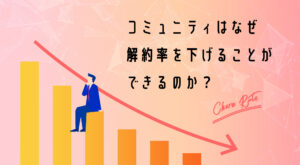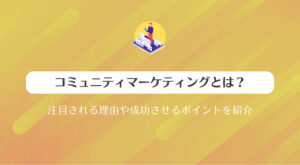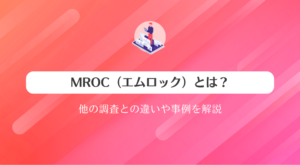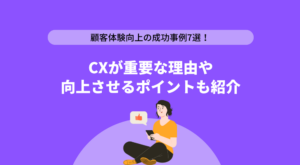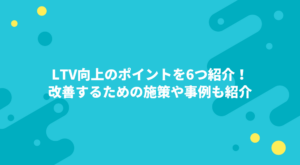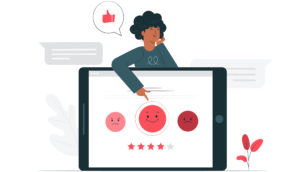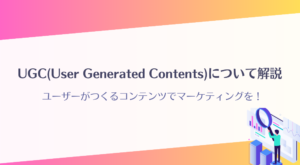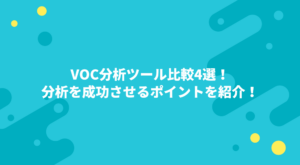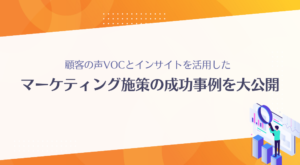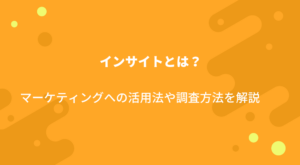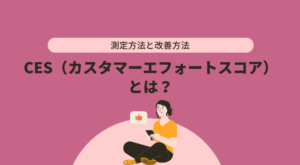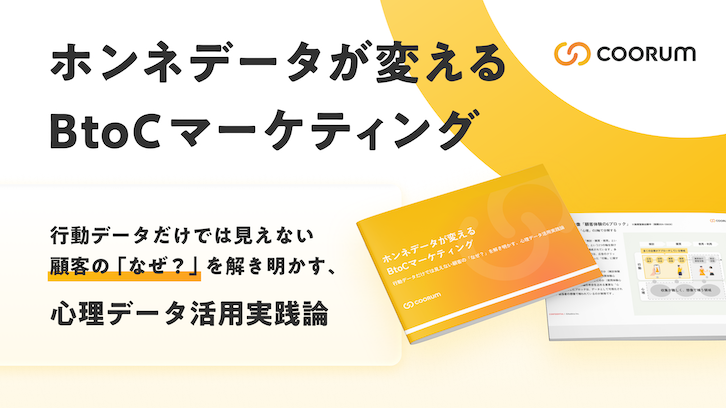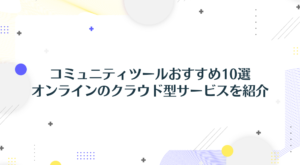
共創マーケティングとは、顧客など社外の人と協力して新たな商品やサービスを生み出すマーケティング手法です。差別化が難しく、変化が激しい現在のマーケティングにおいて、注目されています。
この記事では、共創マーケティングの概要やメリット、成功させるポイント、成功した事例を紹介しますのでぜひ参考にしてください。
共創マーケティングとは?
まずは共創マーケティングの概要と近年マーケティングで重要視されている理由を解説します。
共創マーケティングの概要
共創マーケティングとは、社外のパートナーとともに商品・サービスの開発を行うことです。主なパートナーは顧客と外部企業で、開発の初期段階から最終的な製品化まで関わります。
企業と顧客が協力しながら開発するため、早い段階から顧客ニーズを取り入れやすいのがメリットです。また、両者が協力することでより良好な関係性を構築し、商品やサービスの質を高められます。
共創マーケティングが重要な理由
昨今、共創マーケティングが重要になってきている背景として、従来型マーケティングの限界があげられます。商品のコモディティ化が進み、他社との差別化がしづらく、顧客ニーズも多様化・細分化し、対応が難しくなっています。
従来と同じ商品開発手法では、顧客が真に求める商品・サービスを提供することは困難です。また、ビジネスの環境変化が激しくなっているため、これまでのやり方に固執すると競争環境で脱落するおそれもあります。
厳しいビジネス環境で生き残るには、顧客の声を聞いて本質的な価値を追求しなくてはなりません。このような必要性から、共創マーケティングが有効な手法として注目されています。
企業が共創マーケティングを実践するメリット
共創マーケティングには、主に以下3つのメリットがあります。
- 発売前から一定数の顧客を確保できる
- 顧客満足度向上につながる
- 新たなアイデアが生まれる可能性がある
発売前から一定の数の顧客を確保できる
共創マーケティングにおいて、顧客は製品開発の初期段階から最終段階まで関わることになります。自分が深く関わった商品やサービスに対しては、自然に愛着がわくようになる可能性が高いでしょう。
実際に製品化し、販売した際にも購入する可能性が高いため、発売前からある程度の顧客を確保できます。
熱心なファンになると、発売後にSNSなどで情報を発信してくれるかもしれません。共創マーケティングは関係者間だけでなく、外部へと効果が波及する可能性もあります。
顧客満足度向上につながる
共創マーケティングでは、顧客の声を取り入れながら商品・サービスを設計します。そのため、従来の方法に比べて、企業として届けようとしている価値と顧客として求めている価値のズレが少なくなるのも大きなメリットです。
企業・顧客それぞれが持つ価値のズレを埋め、顧客のニーズに応えることにより、長期的な関係性の構築が可能になります。商品やサービスの品質が向上し、顧客満足度の向上につながります。
新たなアイデアが生まれる可能性がある
他社との差別化をはかるためには、これまでにない新たなアイデアも重要です。しかし、自社の従業員だけではこれまでの経験や慣習などに縛られてしまい、柔軟な考えができなかったり、新たな発想ができなかったりする可能性があります。
共創マーケティングの実践により、企業は従来の固定観念にとらわれず、顧客の客観的な視点や革新的なアイデアを採り入れることが可能です。その結果、これまで自社にはなかった強みを持つ商品・サービスを開発し、市場における競争力を高められます。
共創マーケティングの実践方法
共創マーケティングを実践するステップとして、以下を紹介します。
- 共創マーケティングの目的や意義を考える
- 誰と何を共創するかを決める
- 顧客が参加するメリットを定める
- 顧客の声を収集して生かす仕組み・土台を作る
共創マーケティングの目的や意義を考える
まずは共創マーケティングを行う目的は何か、顧客が価値を感じられる商品・サービスとは何かを、改めて考える必要があります。共創マーケティングは外部の協力が必須であり、多くの方の協力を集めるには、説得力のある目的が必要です。
自社の製品が顧客にとってどのような価値を与えているか、どのような役割を果たしているかを再認識することにより、顧客が共感しやすい価値を見つけられます。
誰と何を共創するかを決める
共創マーケティングの目的や意義を設定したら、次は自社のマーケティングプロセス全体を見直しましょう。プロセスにおいて、共創の可能性がある部分や顧客の関与が重要となるポイントを探ることが大切です。
たとえば、自社の食品がさまざまな料理に使えることをPRしたい場合、メニューや献立に関する情報発信が手段として考えられます。その際に顧客からレシピなどのアイデアを募ると、効率的に情報を集められるでしょう。
また、ともに取り組むパートナーについて、ターゲットを設定する必要もあります。共創の目的に相応しいパートナー像を定義しましょう。
顧客が参加するメリットを定める
自分にとってメリットが感じられない活動に参加しようとする方は少ないため、顧客が取り組みに参加するメリットを明確に決めましょう。たとえば、新たなフレーバーの調味料を開発する場合、製品化した後のサンプルがもらえるなどの特典が考えられます。
顧客側が取り組みに参加する価値を感じられるか、参加者の目線で再度チェックし、興味関心や期待感が持てる内容にしましょう。
顧客の声を収集して生かす仕組み・土台を作る
顧客の意見を単に収集するだけでは、マーケティングの実施につながりません。収集した声を、実際に商品開発などに活用する仕組みを準備しておく必要があります。
仕組み・土台としておすすめなのが「coorum(コーラム)」です。「coorum(コーラム)」を活用することで、顧客の声の収集から分析まで一貫して対応できます。
「coorum(コーラム)」を通じて顧客と継続的につながることでインサイトを発見し、商品企画・開発に活かすことが可能です。

共創マーケティングを成功させるポイント
共創マーケティングを成功に導くために重要な以下の3つのポイントを解説します。
- 顧客にとって魅力的な企画にする
- ロイヤリティの高い顧客の声を活かす
- 商品・サービスを定期的に改善する
顧客にとって魅力的な企画にする
共創マーケティングでは、顧客の積極的な協力が必要不可欠です。そのため、顧客にとって「楽しそう」「おもしろそう」「好奇心がくすぐられる」など、魅力を感じられる企画でなくてはなりません。
同時に、企業にとっても新たな発見やアイデアにつながるような企画にする必要があります。調査におけるアンケート項目などは、どのような意見があれば商品開発に活用できるかを考えて、事前に準備することが重要です。
ロイヤリティの高い顧客の声を活かす
ロイヤリティの高いユーザーを集めることも、共創マーケティングを成功に導くための大切なポイントです。その商品やサービスを愛用しているロイヤルユーザーであれば、商品開発などに積極的に関わってもらえる可能性が高いでしょう。
また、商品やサービスを熟知しているロイヤルユーザーからは、重要で核心をついたインサイトを得られる可能性もあります。
「coorum community」は顧客の育成・蓄積による、顧客起点のマーケティングを支援します。顧客単位でロイヤリティの推移を確認できるため、どの方のロイヤリティが上がっているかも把握可能です。
商品・サービスを定期的に改善する
共創マーケティングは、一度製品が完成すればそれで終わりではありません。顧客から商品やサービスに関するフィードバックを継続的に得ることで、さらなる改善や成長をはかることも重要です。
共創マーケティングに参加した顧客から継続的に意見やフィードバックをもらう機会をつくり、ニーズを反映した改善を行うことで、エンゲージメントを高めることも可能です。
共創マーケティングに成功した事例
ここからは、共創マーケティングの成功事例として以下の4つの事例を紹介します。
- クラシエホームプロダクツ:mä & më time
- しゃぶ葉:おやさい学校 しゃぶしゃ
- ニップン:アマニコミュニティ
- タマチャンショップ:タマリバ
クラシエホームプロダクツ:mä & më time
クラシエホームプロダクツの「mä & më time(マーアンドミー)」は、「mä & më」シリーズのファンが集まるオンラインコミュニティです。mä & mëは「おとなと子どもが一緒に使える」をコンセプトに、シャンプー・リンス・ボディソープなどの商品を展開しています。
「mä & më time」は顧客の声(VOC)を直接聞くこと、「mä & më」シリーズの認知を向上させることなどを目的とし、顧客の声を収集・分析するプラットフォームである「coorum(コーラム)」を活用して設立されました。
初期メンバーであるコアファンがコミュニティから離脱せず、継続的に活動しているのが特徴です。
mä & mëは2022年にスキンケアシリーズを発売しましたが、主力のシャンプーとは売り場が違うことなどから、認知向上が課題となっています。スキンケア商品の魅力をさらに伝えていくことを目的に、共創マーケティングの一環としてアンバサダー企画を進行中です。
具体的には、商品サンプルをアンバサダーの方にお渡しして、周囲に紹介してもらうという内容です。企画に対する反響は大きく、10名の募集に対し60名以上の応募が集まりました。
導入事例インタビューはこちら▼
親子のヘアケア&スキンケアブランド「mä&më(マーアンドミー)」がファンとの共創を目指すコミュニティを始めた理由
しゃぶ葉:おやさい学校 しゃぶしゃ部
しゃぶ葉の「おやさい学校 しゃぶしゃぶ部」は、すかいらーくホールディングスが運営しているオンラインコミュニティです。
ユーザーと濃密なコミュニケーションができる場をつくること、やり取りで得たインサイトをユーザー全体の価値へ転換することといった効果が期待されています。
すかいらーくホールディングスは長年「プロダクトアウト」の開発スタイルでしたが、コロナ禍をきっかけに「マーケットイン」でのメニュー開発・プロダクト開発を目指す方向に変わってきました。
「おやさい学校 しゃぶしゃぶ部」は「coorum(コーラム)」を活用し、顧客のインサイトを調査するために導入されました。
コミュニティでは入部審査を実施してメンバーを厳選し、熱い想いを持ったロイヤルカスタマーが交流できる場をつくり、新たな「おだし」の共同開発などの共創マーケティングをすすめています。
おだしの共同開発では、コミュニティ内だけで取り組みの価値をはかるのではなく、コミュニティから発生した価値をコミュニティ外の顧客に提供する方針です。
顧客全体へどのように効果が波及したかを確認することで、ファンコミュニティでの活動をより意義の高い取り組みにできると考えています。
導入事例インタビューはこちら▼
しゃぶ葉に熱い想いを持ったユーザーに限定したコミュニティ「おやさい学校 しゃぶしゃ部」が目指す、ユーザー全員にとって価値のある施策立案とは?
ニップン:アマニコミュニティ
ニップンは、創業120年以上の歴史がある総合食品メーカーです。冷凍食品、小麦の加工食品、健康食品など多岐にわたる事業を展開しています。
共創マーケティングに取り組んでいるのは健康食品の「アマニ」で、亜麻という植物の種子を使った胡麻のような食品です。DHAやEPAの仲間である「α-リノレン酸」を含んでおり、世界保健機関(WHO)や厚生労働省が摂取を推奨しています。
アマニはまだ日本では、認知が低い食品です。コアなファンとつながり、顧客インサイトの発見や情報配信などを目的として、「coorum(コーラム)」を活用してオンラインコミュニティを立ち上げました。
ニップンは顧客の声を反映した、フレンチ風クリーミードレッシングを発売しました。当初、こってりとしたドレッシングは健康志向の人は求めていないと考えていましたが、実際に声を聞いてみると、こってり系でも買うという意見が寄せられたためです。
また、商品リニューアルにおいて、商品につけるPOPの文言をコミュニティで検討しました。ニップンでは「α-リノレン酸が60%以上である」ことを重視していましたが、それよりも効能面を訴求するキャッチコピーが人気を誇る結果となりました。
現在、コミュニティの意見で採用されたPOPを実際に商品につけて販売しています。
導入事例インタビューはこちら▼
「ニップン アマニコミュニティ」で見つけた新たな顧客像と、毎日のアマニ習慣が広がる秘訣とは?
タマチャンショップ:タマリバ
タマチャンショップは、有限会社九南サービスが運営する自然食品のショップです。ナッツ・雑穀・ドライフルーツといった食品を販売しています。
愛用者のレビューを募り、さらに自社を好きになってもらうための場として「coorum(コーラム)」を活用したオンラインコミュニティを立ち上げました。
コミュニティで集めた声を商品開発やプロモーションに活用する、共創マーケティングにも着手しています。
12月はタマチャンショップからお客様へお礼をするタイミングと位置づけており、商品の購入者にカレンダーを同梱します。そこに掲載されたレシピの多数は、コミュニティに投稿されたものです。
「鍋キット」の新発売にあたっては、ロイヤルユーザーのレビューをLPに採用しました。レビューの収集はファンの熱狂度を上げることが目的でしたが、プロモーションにも活かせています。
さらに、コミュニティ内だけでなく、SNSで外部へと自発的に発信してくれるユーザーも現れるようになりました。このようなUGC(ユーザーが自発的に生成したコンテンツ)を増やすためにも、さらにファンとともに盛り上げたいとしています。
導入事例インタビューはこちら▼
ユーザー投稿のレシピ・食へのこだわりが溢れるタマチャンショップのコミュニティ「タマリバ」。ロイヤル顧客を育てる仕掛けとは?
共創マーケティングを実践するならcoorum
商品のコモディティ化により差別化が難しくなっている現在、共創マーケティングは新たなマーケティング手法として注目されています。
共創マーケティングには、発売前から一定数の顧客を確保できる、顧客満足度向上につながるといったメリットがあります。顧客にとって魅力的な企画をつくることや顧客の声を収集することが成功のポイントです。
共創マーケティングを実践する場としておすすめなのが、顧客の声を収集・分析するプラットフォームである「coorum(コーラム)」です。「coorum(コーラム)」を活用することで、ユーザーと交流し、アイデアを募りながら共創マーケティングを実践できます。
顧客との継続的な接点を持ち、コミュニケーションを図ることで、良好な関係性を構築することが可能です。「coorum(コーラム)」を通じて得た幅広い顧客の声やインサイトを活用し、顧客起点の商品開発を実現できます。
共創マーケティングに取り組みたい方はぜひ「coorum(コーラム)」をご活用ください。

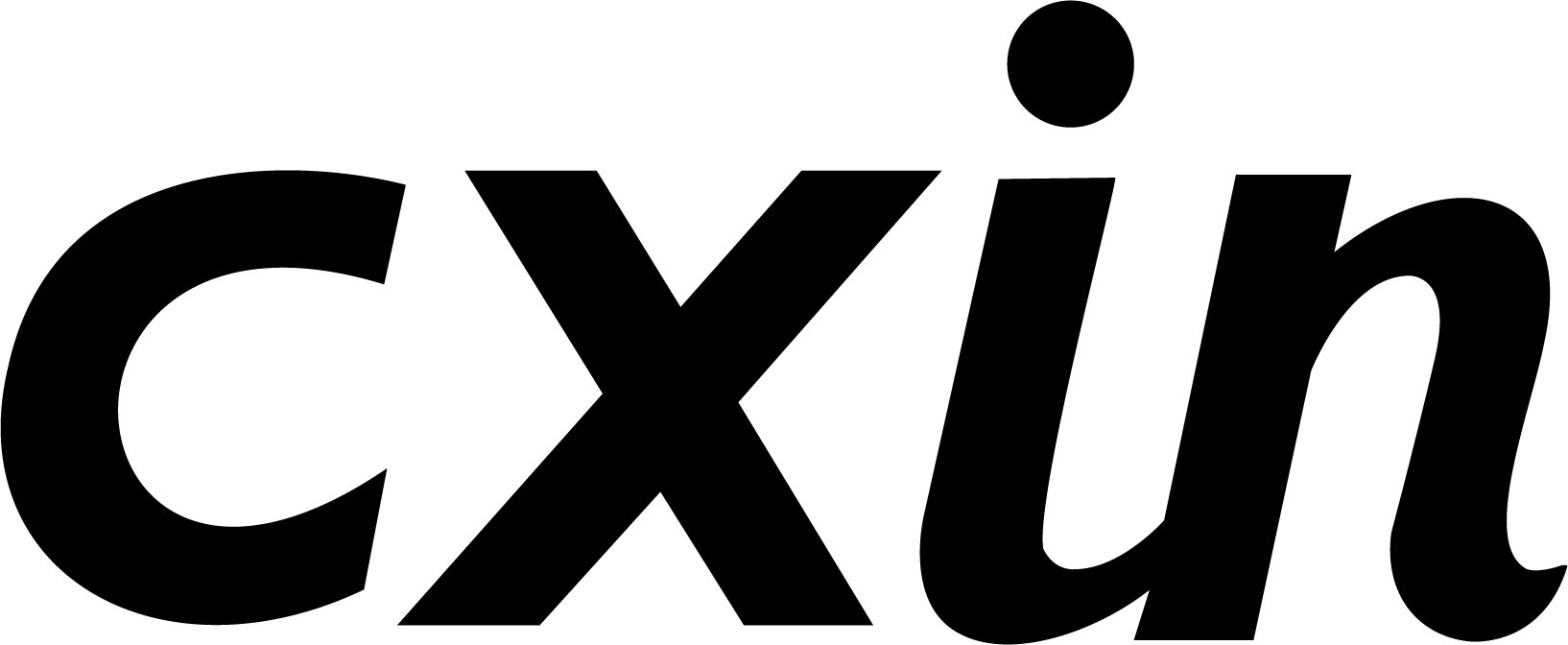

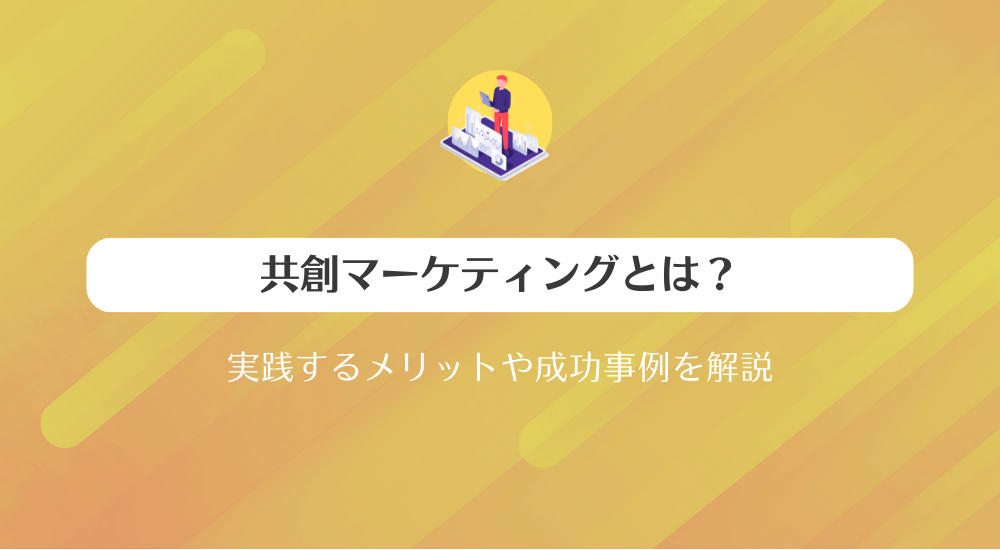
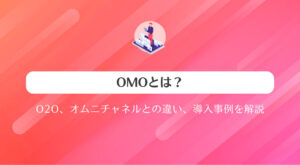


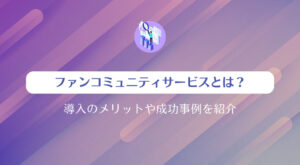
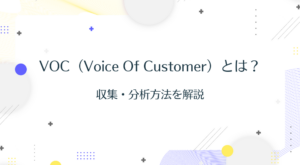
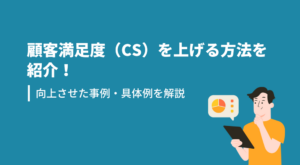
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)