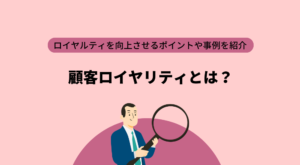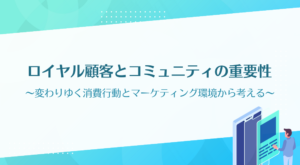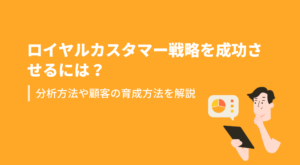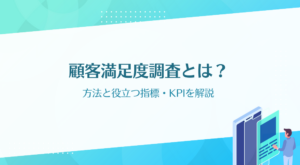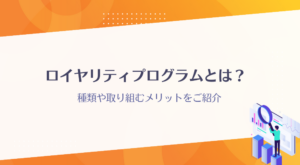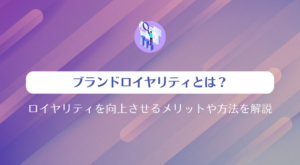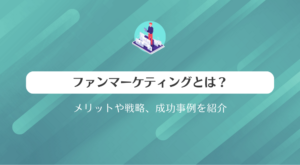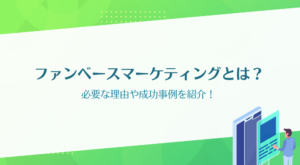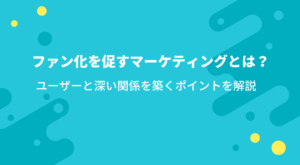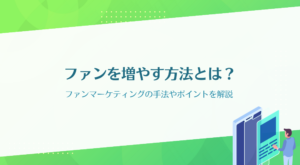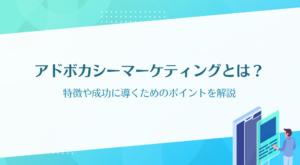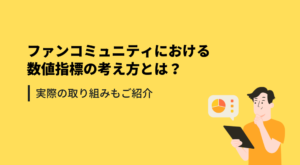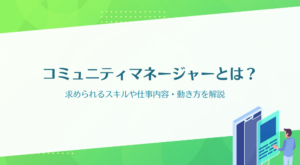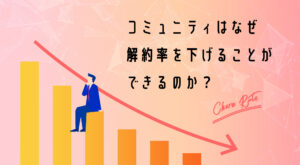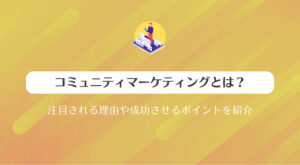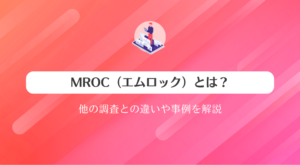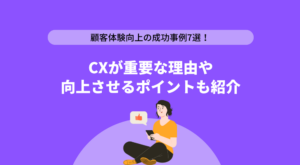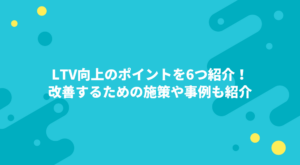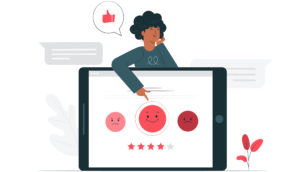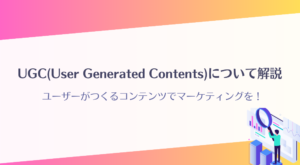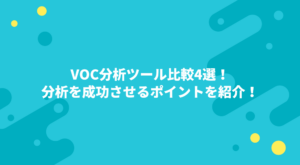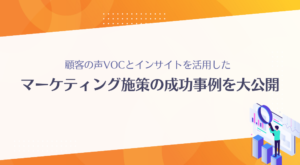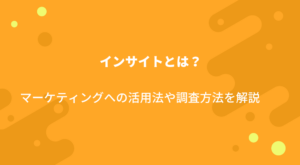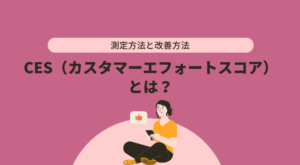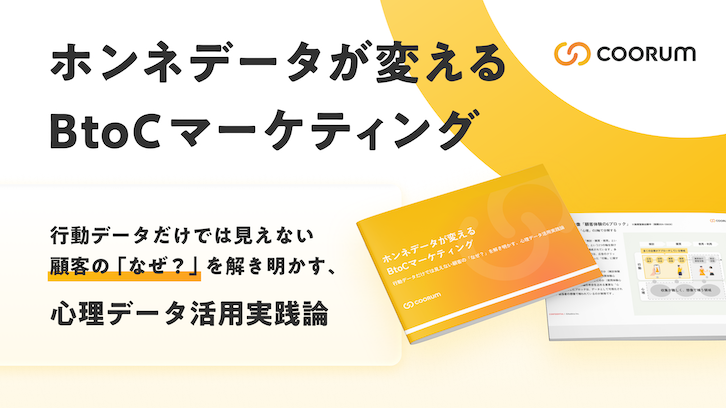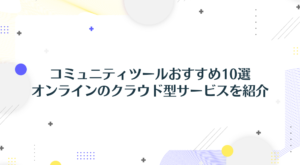
ブランドエクイティとは、ブランドが社会全体に対して持つ価値のことです。目には見えない無形資産であり、価値を高めることで他社との差別化や長期的な売上の向上につながります。
本記事では、ブランドエクイティの構成要素や高めるメリット、成功事例などを解説します。
ブランドエクイティとは?
ブランドエクイティとは、ブランドが持つ資産価値を指す言葉です。ブランド名やブランドが掲げるシンボルなどと結びついた価値の集合体であり、消費者の購買行動に影響を与えます。
ブランドは目に見えない無形資産ですが、建物や生産設備などの有形資産と同じく投資や施策などにより価値が高まります。
ブランドエクイティは、1980年代のアメリカで提唱された概念です。企業の合併や買収(M&A)が広まっていた当時のアメリカでは、それまで単なる製品名や記号と捉えられていたブランドが、競合他社より優位性を保つ資産価値があるものと考えられるようになりました。
その中でブランドを会計上の無形資産として計上するという考え方が現れ、「エクイティ」という表現が生まれます。
エクイティには「資本」という意味がありますが、ブランドエクイティは利益を生むプラスの面だけでなく、負債も含めて表現されることが一般的です。つまり、ブランドの持つプラスの面だけでなく、マイナスイメージなど負債部分も含めた総合的な価値を表します。
目に見えないブランドを資産として捉え、ブランドエクイティを高めることが他社との差別化とリピーターの獲得、安定的な売上の向上につながると考えられています。
ブランドエクイティの構成要素
ブランドエクイティを構成する要素は、提唱者であるデイヴィット・アーカー氏による「アーカーモデル」と、アーカーモデルよりも顧客視点を重視する「ケラーモデル」に分けられます。
アーカーモデルは抽象的なブランドエクイティを具体的に理解できるモデルであり、次の5つの要素で構成されています。
- ブランド認知
- ブランド連想
- 知覚品質
- ブランドロイヤリティ
- その他のブランド資産
ここでは、アーカーモデルにおけるブランドエクイティの5つの構成要素を紹介します。
ブランド認知
ブランド認知とは、そのブランドがどれほど顧客に認知されているかを表すものです。
消費者は同じような製品・サービスがある場合、知っているブランドを優先する傾向にあります。ブランド認知が上がるほど消費者の信頼度や安心度が上がり、選ばれる可能性が高まるでしょう。
車や家電製品、食品などそれぞれのカテゴリーにおいて一番に想起されるブランドは、高いブランドエクイティがあるといえます。
ただし、ブランド認知は、単なる「知名度」とは異なります。知名度は企業や製品、サービスなど表面的な「名前」が知られていることで、それだけでは消費者がブランドを選ぶ決め手にはなりません。
ブランド認知は、ブランドの歴史や製品・サービスへの想いなど、より深い部分への理解を得ていることを指します。
ブランド連想
ブランド連想とは、消費者がそのブランド名を聞いて連想するすべてのものを指します。たとえば、「Apple」であればシンプルでスタイリッシュなデザイン、直感的な操作性などがあげられます。「トヨタ」であれば、国際的な車、技術力が高いなどがブランドイメージになるでしょう。
ブランド連想を形成する要因は、広告や他者の評判、実際に利用した体験などさまざまです。そのため、ブランドエクイティが高い企業ほど、多様なイメージが形成されています。
ポジティブな内容で、多くの連想ができるほどブランドエクイティが高い状態といえるでしょう。
知覚品質
知覚品質とは、同じ機能や目的の製品・サービスと比べたとき、知覚できる品質や優位性を指します。性能など企業が認識している事実としての品質ではなく、消費者がそのブランドに抱く品質への評価のことです。
知覚品質は、さまざまな要素で形成されます。製品・サービスの基本的な性能やオプション機能だけでなく、「不良品・欠陥品がない」「アフターサービスが充実している」といった信頼度、広告へのイメージなどがあげられるでしょう。
さらには、製品・サービスを利用して楽しめる・安心できるなど、感情で判断する要素も含まれます。
ブランドロイヤリティ
ブランドロイヤリティとは、ブランドへの忠誠心や愛着度、信頼度を指します。5つの要素の中でも、特に重要な要素とされています。
ブランドロイヤリティのある顧客は他の製品・サービスに乗り替える可能性が低くなり、ブランドロイヤリティが高いほど継続的に購入する傾向にあります。そのため、ブランドロイヤリティが高い顧客が増えることでリピート率が高まり、安定した収益確保につながるでしょう。
ブランドロイヤリティの獲得は、ブランドエクイティの最高段階です。ロイヤリティのある顧客は、周囲に製品・サービスを積極的にすすめる行動も期待できます。新規顧客の獲得にもつながり、ブランドにとって重要な存在になるでしょう。
その他のブランド資産
4要素以外の無形資産全般も、ブランドエクイティの構成要素です。主に、次の無形資産があげられます。
- 商標
- 特許
- 著作権
- 取引先との信頼関係
- 独自の技術・ノウハウ
これらの要素はいずれも、ブランド・エクイティに重要な役割を果たします。たとえば、商標権があれば、競合他社は似たブランド名やロゴなどを使用できません。
また、特許取得により、自社独自の技術を守れます。自社ブランドを守るこれらの無形資産も、競合優位性を獲得する力となります。

ブランドエクイティを高めるメリット
ブランドエクイティを高めることで、次のようなメリットがあります。
- ファンが増加する
- 他社と差別化できる
- プレミアム価格の設定ができる
詳しくみていきましょう。
ファンが増加する
ブランドエクイティを高めると、ファンの増加が期待できる点がメリットです。「このブランドだから購入する」「新作が出たら必ず購入する」という顧客が増え、安定した売上につながります。
ファンとなった顧客はSNSなどで積極的に自社の製品・サービスについて口コミを発信することが多く、マーケティングコストを抑えながら新規顧客の獲得が期待できるでしょう。
他社と差別化ができる
技術の進化により機能面での差別化が難しくなっている現代において、ブランドエクイティの向上は、類似の製品・サービスを提供する他社との差別化に有効です。
消費者は、似たような製品・サービスがある場合、より認知度・好感度の高いブランドを優先的に選ぶ傾向にあります。そのため、ブランドエクイティの向上をさせることは、既存顧客の維持だけでなく、新規顧客の獲得にもつながります。
プレミアム価格の設定ができる
ブランドエクイティの向上により、プレミアム価格の設定ができることもメリットです。消費者はブランドエクイティの高い企業の製品・サービスに対し信頼や安心感を抱いておりブランドとしての価値を認識しています。
そのため、他社の製品・サービスよりも価格が高くても、消費者はその価値を理解し、納得して購入してくれるでしょう。その結果、価格競争から脱却し、プレミアム価格の設定が可能になります。
ブランドエクイティを高める戦略
ブランドエクイティを高めるためには、効果的な戦略の策定が重要です。ここでは、ブランドエクイティを高める戦略を解説します。
一貫したメッセージを発信する
ブランドエクイティの向上には、一貫性のあるメッセージの発信が必要です。すべてのコミュニケーションチャネルで、同一のメッセージを繰り返し発信します。
一貫して発信されるメッセージは消費者の記憶に残りやすく、ブランドの認知度の向上につながります。ブランドメッセージが一貫していることで、ブランドに対する信頼感も高まるでしょう。
一貫したメッセージを発信するためには、ブランドが提供する価値を明確にした上でインナーブランディングを強化することが重要です。
インナーブランディングとは、企業理念やブランド価値を社員に浸透させる活動を指します。ブランドの顔として顧客と接する社員が自社ブランドを正しく理解できていなければ、一貫したメッセージの発信はできません。
自社の価値を正しく理解している社員は、自ら製品やサービスの魅力についても一貫した内容で発信できるでしょう。
インナーブランディングを強化することで顧客へのメッセージを統一でき、ブランドエクイティ向上が期待できます。
製品やサービスの質を高める
製品やサービスの質を高めることも、ブランドエクイティの向上に欠かせません。品質が高いほど消費者の満足度が向上し、ブランドへの信頼が高まります。品質が高いという認知はブランドエクイティに反映され、消費者の購入意欲を高めるでしょう。
消費者は同業他社よりも自社の製品・サービスを優先的に購入しようと考えるようになり、差別化を図れます。
製品・サービスの品質を高めるためには、利用した顧客の声を詳細にリサーチし、改善を重ねることが大切です。
顧客体験を向上させる
顧客体験(CX・カスタマーエクスペリエンス)の向上も、ブランドエクイティに影響を与えます。
顧客体験とは、顧客が製品・サービスに興味を持ち、購入してからアフターフォローを受けつつ利用し続けるまでの接点における一連の体験のことです。あらゆる接点で高品質な顧客体験を提供することで、ブランドに対する好感度が高まります。
たとえば、店員の丁寧な接客や配慮が行き届いたカスタマーサービス、購入後の使い心地の良さ、充実したアフターサポートの提供などがあげられます。一貫した質の高い顧客体験により、顧客ロイヤリティの向上が期待できるでしょう。

ブランドエクイティの測定方法
ブランドエクイティの施策を実施する際は、自社のブランドエクイティがどの程度であるか測定することが必要です。
無形資産であるブランドエクイティは数値化しにくいのが実情ですが、次のような測定方法が用いられます。
- NPSを活用する
- 財務情報をもとに測定する
- ブランドリプレイス費用から計測する
ここでは、それぞれの内容を解説します。
NPSを活用する
NPS(ネットプロモータースコア)とは、顧客ロイヤリティを測る指標です。顧客にアンケートをとり、自社製品やサービスを周りにどの程度すすめたいか、0から10までの11段階で評価してもらいます。
0~6を付けた顧客は「批判者」、7・8を付けた顧客は「中立者」、9・10を付けた顧客を「推奨者」として振り分け、「推奨者」の割合から「批判者」の割合を差し引く方法です。
シンプルな方法で数値を算出でき、数値が高ければ高いほどブランドエクイティも高いと判断できます。
アンケートにより数値を算出できるだけでなく、顧客の具体的な声を拾えるというメリットもあります。
ただし、NPSは商品・サービスの推奨度を聞く基本的な質問に絞るため、一度に収集できる情報は多くありません。精度の高い結果を得るには多くの回答数が必要という点がデメリットです。
一人ひとりの顧客からより多くの情報を収集して分析したい場合には、NPS単独では十分でない可能性があります。
NPSよりも顧客のリアルな反応を継続的に収集でき、ブランドエクイティの測定におすすめなのが、「coorum(コーラム)」です。
「coorum(コーラム)」は、顧客との継続的な接点を作り、顧客自らが能動的に発信した顧客の声を蓄積・分析ができるツールです。顧客の心理・使用実態の収集とデータ分析により、より精度の高いブランドエクイティの測定を実現します。
財務情報をもとに測定する
ブランドエクイティは、企業の財務情報から測定することも可能です。財務情報で判断されるブランドエクイティは、「超過収益力」もしくは「のれん」で表されます。
超過収益力とは、経営の継続で蓄積した目には見えない潜在的な企業価値のことです。ブランドエクイティのほか、独自性の高い技術力やノウハウ、人材などが該当します。
企業買収(M&A)の際、買収価格は純資産(企業価値)に超過収益力を加えて決定します。たとえば、純資産10億円の企業が15億円で買収された場合、5億円が超過収益力(のれん)ということです。
そのため、財務指標上の企業価値が低くても、ブランドエクイティなど超過収益力が高い場合は高額で会社を売却できる可能性があります。
財務情報をもとにした計算方法は、企業の規模、業種によって変わり、主に次の3つの方法で算出されます。
- コスト・アプローチ:企業の貸借対照表の純資産価値に着目する
- インカム・アプローチ:今後見込まれる収益の価値から査定する
- マーケット・アプローチ:対象となる企業と類似した企業・取引事例から査定する
超過収益力は、ブランド力をどの程度重視しているか、どの計算方法を使うかによっても変動します。そのため、財務情報をもとにしたブランドエクイティの計測を行う際は、複数の専門家の意見を確認することも必要になるでしょう。
ブランドリプレイス費用から計測する
ブランドリプレイス費用とは、ブランドが知られていない場所で新たに事業を展開した際に、現状と同じブランド力を獲得するためにかかる費用のことです。
ブランドリプレイス費用の内容は、次の3つに分けられます。
- アイデンティティを確立するための費用
- 認知獲得の費用
- 顧客維持の費用
アイデンティティの確立にかかる費用とは、キャッチコピーの宣伝やロゴ制作、Webサイトの構築などにかかる費用があげられます。
認知獲得の費用はユーザーに認知されるための広告費で、テレビCMや雑誌・ネットなどの広告にかかる費用のことです。
顧客維持の費用とは、主にCRM(顧客関係管理)ツールにかかる費用や、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)にかかる費用が該当します。
ブランドエクイティ戦略に成功した事例
ブランドエクイティ戦略に成功すれば、企業の飛躍的な成長が可能です。ここでは、ブランドエクイティの確立に成功した企業の事例をいくつか紹介します。
Appleの成功例
Apple社は、他社と差別化する戦略として、シンプルかつスタイリッシュなデザインを採用しました。背面のリンゴマークとシンプルなデザインを見ただけで、多くの人は「Appleの製品」だと認知できます。また、使いやすさと直感的な操作性により、優れた顧客体験を提供しているのもAppleのブランドエクイティを高めている要素です。
さらにApple社は、2030年までに製品の生産を通じて排出される二酸化炭素(CO2)を実質ゼロに抑える「カーボンニュートラル」を打ち出しています。これは、国連が掲げる2050年という目標時期よりも20年前倒しにする取り組みです。
地球温暖化の解決に向けて2050年までにカーボンニュートラルを達成するには社会変革が必要であり、Apple社の取り組みはその先駆けになるものといえます。
Apple社は取り組みの一環として、すべての製品ラインでレザーの使用を廃止し、新しいApple Watchのラインナップ向けに作ったApple初の100%繊維ベースのパッケージを発表しています。さらに、iPhoneでの再生素材の使用も継続的に拡大しました。
このような環境問題への積極的な取り組みも、Apple社のブランドイメージの強化につながっています。ブランドエクイティの一環と見ることができるでしょう。
参考|Apple「Apple、2030年までに サプライチェーンの 100% カーボンニュートラル達成を約束」
参考|Apple「Apple、初のカーボンニュートラルな製品を発表」
無印良品の成功例
無印良品は、衣服や家具、雑貨、食料品など、暮らしに関わる商品を幅広く提供している会社です。
商品カテゴリを絞らず、「シンプル・ナチュラル」というコンセプトで商品展開をしています。すべての商品には必ず「シンプル・ナチュラル」を感じさせる要素があり、ブランド連想によりブランドエクイティの向上に寄与しています。
1980年に登場した無印良品の簡素でピュアな製品群は、それまで市場で主流を占める商品が演出過剰ぎみだったのとは対照的で、世界に大きなインパクトと共感を与えました。
以来、無印良品は「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」という3つの原則を守り、生産プロセスを徹底して合理化することで、シンプルかつ低価格の商品を生み出しています。
スターバックスの成功例
世界規模のコーヒーチェーンであるスターバックスは日本でもすべての都道府県に店舗を構えており、ブランドエクイティの確立に成功した代表事例のひとつです。
スターバックスは日本上陸以来、「サードプレイス」という企業コンセプトを掲げています。サードプレイスとは、家庭や職場とは異なる、居心地の良い「第3の場所」を指しています。
居心地が良くリラックスできる店舗設計と店員のフレンドリーな接客、コーヒーを自分好みにカスタマイズできるサービスが特徴です。
すべての店舗が直営店であるスターバックスではインナーブランディングを確立しており、従業員全員が一貫したブランドイメージを共有しています。「サードプレイス」というコンセプトの浸透にも成功し、一般的なコーヒーショップという枠を超え、顧客にとって特別な価値のある場所となりました。
ただコーヒーを飲むだけの場所ではなく、居心地の良い第3の場所として特別な顧客体験を提供しており、差別化に成功しています。
ブランドエクイティの構築に役立つcoorum
「coorum(コーラム)」は、ブランドエクイティの構築に役立つツールです。「coorum(コーラム)」では、顧客との継続的な接点の構築と顧客分析機能で、効果的なマーケティングを実現します。
ここでは、「coorum(コーラム)」がどのようにブランドエクイティ向上に役立つのかを解説します。
UGCを自発的に投稿するユーザーを増やす
ブランドエクイティは一貫性のあるメッセージの発信が大切ですが、「coorum(コーラム)」では質の高いUGC(User Generated Content)の醸成により、ブランドエクイティの向上をサポートします。
UGCとは、一般のユーザーが自発的に作るコンテンツのことで、SNSの投稿やブログ、レビューなどが該当します。
「coorum(コーラム)」では顧客との継続的な接点により、製品やブランドに関する投稿を積極的に行うユーザーを増やすことが可能です。自社への理解を深めたユーザーにより質の高いUGCが発信されることで、ブランドイメージの周知に役立ちます。
サービス・ブランドを推奨するUGCの発信でブランドエクイティを高める
「coorum(コーラム)」でユーザーとの継続的な接点を構築することで、企業とユーザーとのコミュニケーションが深まります。
自社を推奨してくれるユーザーが増え、サービス・ブランドを推奨するようなポジティブなUGCの発信が期待できます。その結果、ブランドの認知度が上がり、ブランドエクイティの向上につながるでしょう。
ユーザーのロイヤリティが向上することで、UGCよりも影響度が高いFGC(Fan Generated Contents)の醸成も可能です。FGCを発信するユーザーはブランドへの愛着心・信頼度が高く、作成されるコンテンツからも製品やサービスの本質が伝わります。
日常的に配信するなど、継続的なコンテンツ配信も期待できるでしょう。
質の高いユーザー調査で顧客満足度向上
「coorum(コーラム)」では、ユーザーへのリサーチ機能もあります。ゲーミフィケーション型アンケート等によるリサーチで、顧客の心理・使用実態などのデータを収集できます。
いつでも好きなタイミングで、質の高い調査が可能です。調査会社に依頼するアンケートな日数やコストがかかりますが、「coorum(コーラム)」のユーザーリサーチであれば短期間で実施でき、都度料金もかかりません。
調査結果をもとに、製品・サービスの質を高めるというブランドエクイティの戦略を推進でき、顧客満足度の向上を図れます。
coorumでブランドエクイティを高めよう
ブランドエクイティの向上により自社製品・サービスを競合他社と差別化でき、市場競争を勝ち抜くことが可能です。プレミアム価格を設定し、価格競争からも脱却できるでしょう。
ブランドエクイティを高める戦略には、一貫したメッセージの発信や質の高い顧客体験の提供などがあげられます。
「coorum(コーラム)」を活用すれば、蓄積した顧客データの分析からブランドエクイティを測ることが可能です。顧客との継続的な接点によりUGCの醸成・発信もでき、リサーチ機能で商品・サービスの改善と顧客満足度の向上も図れます。
ブランドエクイティ向上に役立つツールとして、ぜひご活用ください。

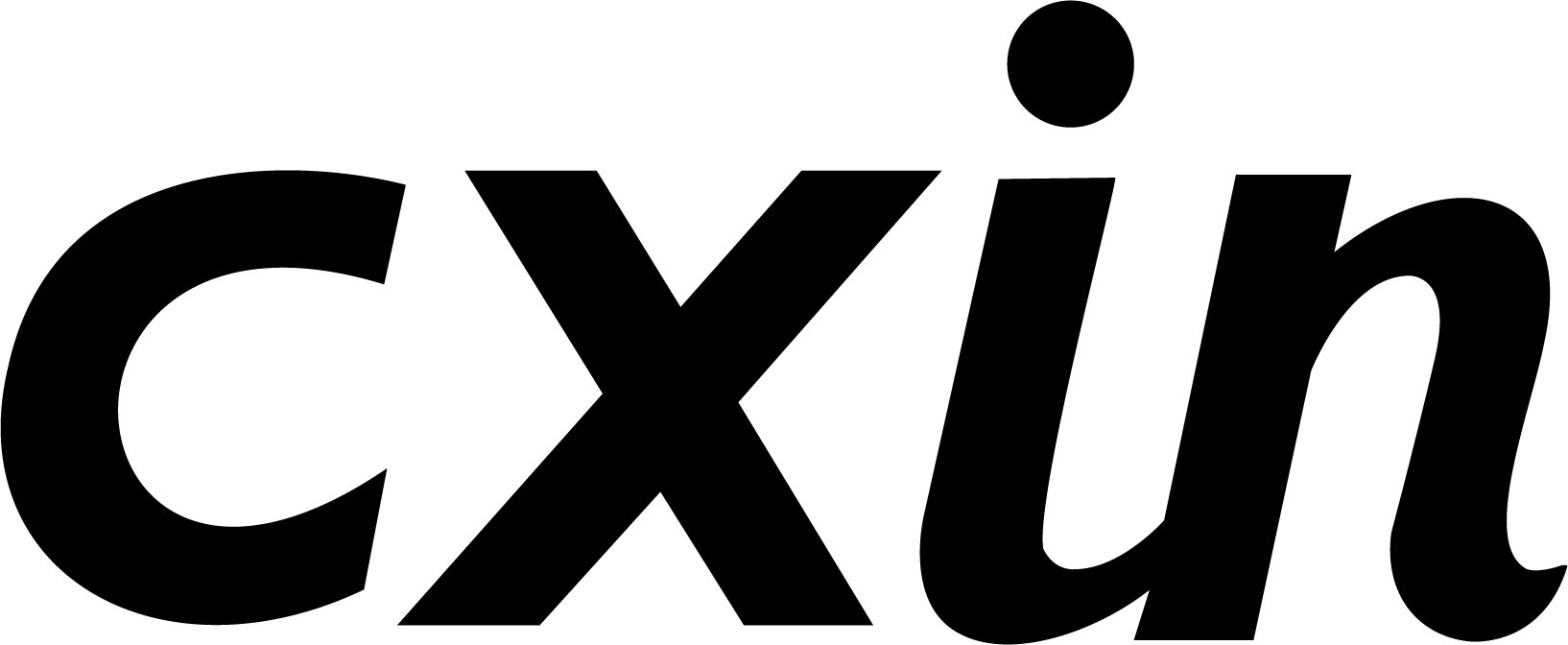

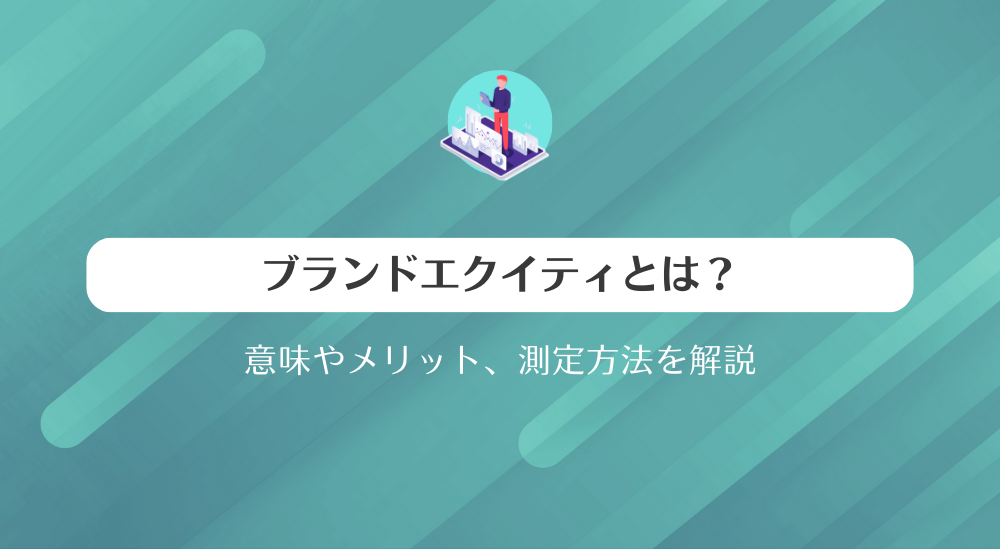
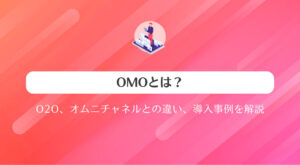


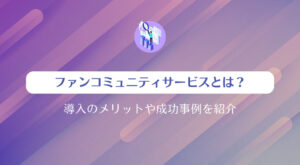
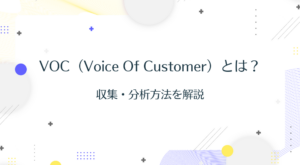
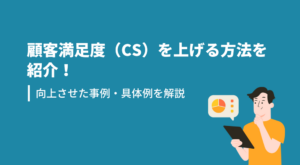
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)