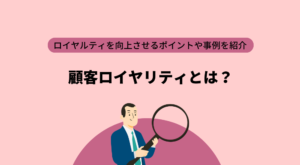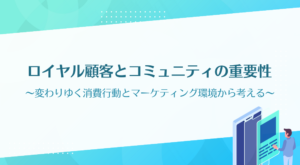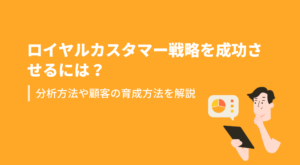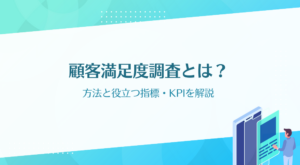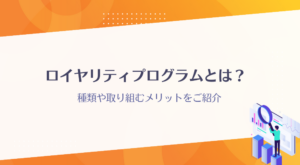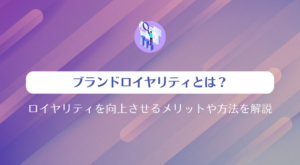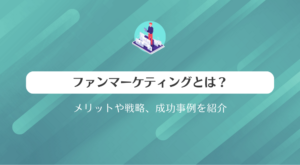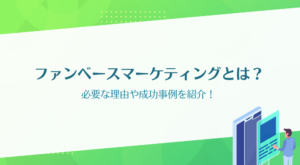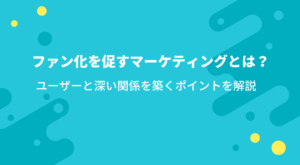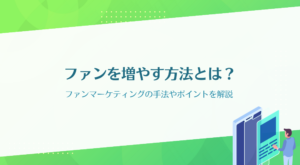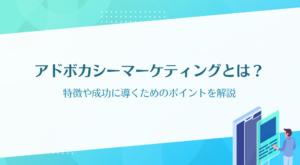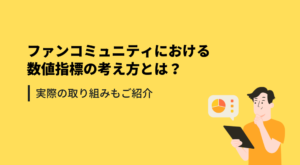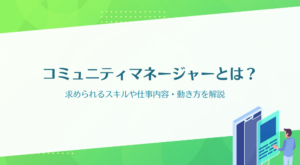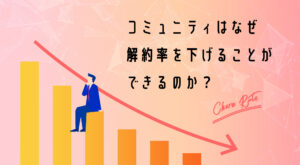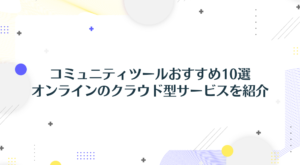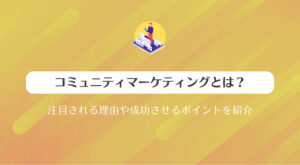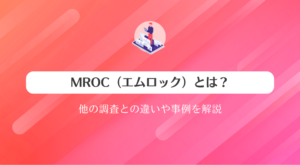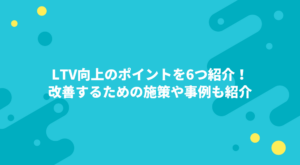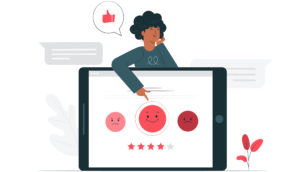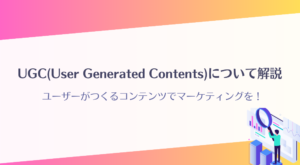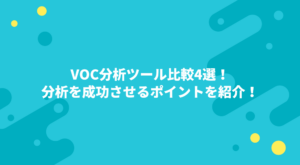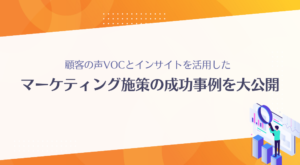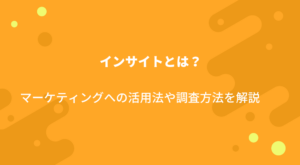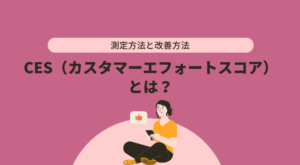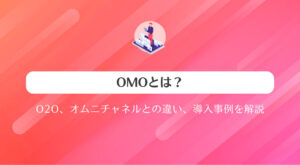
ビジネスパーソンとして「NPS」という言葉は知っておきたいところです。企業において業績に直結する要素の1つでもあります。そこで、NPSの基本的な知識から、調査後の分析方法まで幅広く解説します。
NPSとは

まず最初に、NPSとは何かという基本的なことについて解説します。
NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは、「企業やブランドに対してどの程度の愛着や信頼を感じているか」についての指標です。一般的に顧客ロイヤリティや、顧客の継続利用の意向を知るための指標として用いられ、企業の業績に直結するものとされています。
NPSの基本的なモデルは「○○(商品やサービス、ブランド名など)を家族や友人におすすめしますか?」という質問を数値化することで評価します。その特性上、NPSは「顧客推奨度」とも表現されます。
NPSと顧客満足度の違い
NPSは、しばしば「顧客満足度」と混同されます。
顧客満足度とは、商品やサービス、ブランドに対して顧客がどの程度の満足を感じているかを数値化したものです。顧客が満足しているかどうかは基本的に顧客の主観・感性に委ねられるものではありますが、「顧客の期待を超えること」を顧客満足として定義することも多くみられます。
これだけを見ると「顧客が満足している:顧客満足度」と「顧客が推奨したいと思っている:NPS」は似たような概念であると感じるかもしれませんが、両者には大きな違いがあります。それは「業績への直結度合い」です。
顧客満足度の高さは、必ずしも商品のリピートやアップセルなど、売上アップになる行動につながらないことがわかったのです。ある調査においては、サービスを解約した顧客の8割が、直前に行われた顧客満足度調査において「満足している」と回答していることがわかっています。
つまり、顧客満足度が高いからといってリピーターになるわけではなく、業績との相関関係が薄いことがわかります。一方でNPSは業績との相関関係が強いことがわかっており、多くの企業が業績アップにつながるNPSに注目するに至ったのです。
NPSの計算方法
NPSの計算は、データさえそろっていれば簡単に計算することができます。
まず、以下のようなアンケートを実施してください。
| あなたはこの企業(製品・サービス・ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか? | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 全く思わない ⇔ 非常にそう思う | ||||||||||
「あなたはこの企業(製品・サービス・ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」という質問を行い、回答者は0~10までの11段階(数字が大きいほど、薦める可能性が高い)で評価します。
| あなたはこの企業(製品・サービス・ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか? | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 批判者 | 中立者 | 推奨者 | ||||||||
0~6までの回答を「批判者」、7と8の回答者を「中立者」、9と10の回答者を「推奨者」として区分します。NPSの計算を行うにあたっては、回答者全体のうち推奨者と批判者がどれくらい存在するかによって計算されます。
例えば、回答者が全体で100人いるとして、「批判者:50人」「推奨者:30人」という結果が得られたとします。NPSの計算は「推奨者の割合-批判者の割合」で計算しますので、このケースの場合は、
30(推奨者の割合[%])-50(批判者の割合[%])=−20
ということで、NPSは「マイナス20」となります。
この計算方法においては、NPSの最低値はマイナス100、最高値はプラス100となり、どれだけ数値が大きいかによってNPSの高さが評価されます。一般的に批判者の方が割合として多いため、多くの企業でNPSの計算結果はマイナスになります。
日本におけるNPS調査
「NTTコム オンライン」が実施した調査によると、日本企業におけるNPS調査は以下のような内容になっています
| 業界 | 業界トップ企業(最もNPSが高い) | NPS | 業界平均NPS |
|---|---|---|---|
| 大手携帯キャリア | NTTドコモ | -55.4 | -56.7 |
| 対面証券 | 大和証券 | -56.1 | -56.7 |
| 不動産管理会社(マンション | 三井不動産レジデンシャルサービス | -38.4 | -52.8 |
| 通販化粧品 | FANCL(ファンケル) | -11.2 | -21.6 |
| セキュリティソフト | ESET | -8.6 | -23.6 |
| 航空会社 | ANA | -6.6 | -17.1 |
| 動画配信サービス | Netflix | 3.3 | -24.7 |
※https://www.nttcoms.com/service/nps/report/ より抜粋
一部を除き、業界トップ企業でもNPSはマイナスになっています。そのため、NPSについて評価するにあたっては単純な数値の大小ではなく「その業界の平均NPSと比較してどのくらい差があるのか?」を重視する必要があります。
NPSが注目される理由

次に、なぜNPSという評価方法が注目されるようになったのか、その理由について解説します。
業績との相関が高い
NPSが注目されるようになった最大の理由は「企業の業績との高い相関関係が確認されている」ことが挙げられます。
NPSが高く評価されることは、そのまま企業の売上高成長率に深く関係しているのです。NPSが高いということは、それだけ多くのユーザーがその企業を知り合いにおすすめしたいと思っている、ということです。
そうなれば、本人が継続的に使用してくれるだけでなく、ユーザーではない知り合いに商品やサービスをおすすめしてくれることによって、その対象者が新規顧客になる可能性を高めるのです。
実際に行われた調査によると、NPSは企業の売上高成長率との相関が強いことが明らかだとされています。特に「航空業界」において、NPSと5年間の売上高成長率では相関係数(2種類のデータの関係性を示す指標)が「0.89」と、強い相関関係が見られています(相関係数が0.7~1の間だと「強い正の相関」とされている)。
NPSの高さは、「既存ユーザーの継続率やアップセル・クロスセル率の高さ」や「新規ユーザーの獲得可能性の高さ」に直結します。企業にとって売上や利益を増やすことは企業活動において必要不可欠な要素であるため、NPSが注目されているのです。
支持されている点を調査し、ブランドの「強み」として強化
NPSが注目されるのは「推奨者の多さを測る」だけでなく、同時に「批判者についての分析」にもつながることが理由として挙げられます。
批判者からネガティブなイメージを持たれている点の調査・分析を行い、できる限りスピーディーに改善を実行することにより、批判者を中立者または推奨者に変えることができる可能性があります。改善がユーザー全体にとって利益になることであれば、既存の中立者や推奨者の評価を高めることにもつながります。
NPSを分析するにあたっては、推奨者の多さだけでなく、調査方法によっては推奨者が何をもってして企業を支持しているのかも判明します。推奨者の推奨理由は「ブランドの強み」でもあります。ネガティブな部分を改善すると同時にブランドの強みの部分を強化することによって、企業は売上の成長につなげることができるのです。
NPSを測るメリット/デメリット

次に、NPSを測ることによって得られるメリットおよびデメリットについて解説します。
シンプルな項目で可視化しやすい
1つ目のメリットは「シンプルである」ことです。
NPSの計算方法=推奨者の割合[%]-批判者の割合[%]
質問内容が11段階の評価によるものであり、計算方法も割合を計算して引き算するだけというシンプルな方法です。誰にとってもわかりやすく、可視化できることで情報や認識を共有しやすいのです。
スタッフのモチベーション向上
2つ目のメリットは「モチベーションの向上につながる」ことです。
例えばNPSがマイナス25からマイナス20になったとします。プラス5ポイントの改善になったということは、何かしらの対策が奏功したという成果の表れに他なりません。
実行した改善点が評価されることによって、立案者や実行者のモチベーションアップにつながるのです。また、有効な改善点が明確になることでスタッフ1人1人が「自分にできることは何か?」ということがわかりやすくなります。
競合サービスと比較しやすい
3つ目のメリットは「競合サービスとの比較がしやすい」ことです。
NPSの評価方法は、どの企業においても基本的に共通しています。先ほどもNPS業界トップ企業と業界平均NPSの比較について触れていますが、自社のNPSを測ることによって業界の平均値との乖離を知ることができます。
業界平均NPSよりも高く評価されているのか、あるいは低く評価されているのか、単純な数値による比較ができるのでこれも可視化しやすいのです。もし、業界平均NPSよりも大幅に低い評価をされているとわかれば、すぐにでも改善が必要であるということがわかります。
必ずしも売上と結びつく訳ではない
NPSのデメリットの1つ目は「必ずしも売上アップにつながるわけではない」ことです。
例えば「〇〇社の商品はおすすめ!」と情報が拡散されるとします。しかし、品質重視で価格を度外視した高額な商品をおすすめされたとしても、それを購入できる消費者層は限られてしまいます。
また、NPSの高さは継続率の向上や新規顧客の獲得率などにも影響しますが、業界の特性上、アップセル・クロスセルや新規顧客の獲得が難しい場合だと、NPSが高くても売上アップには直結しません。
このように、企業や商品・サービスの性質上、NPSが売上との相関関係が弱いケースもあることを理解しなければなりません。
アクションプランを組み立てる必要がある
2つ目のデメリットは「アクションプランの組み立てが必要である」ことです。
NPSの分析は比較的シンプルでフィードバックもしやすいと思われるかもしれませんが、必ずしもそうであるとは限りません。例えば「NPSを分析したところ、業界平均よりもNPSが低い=批判者が多い」ことが判明したとします。批判者を減らして推奨者を増やすことが基本方針であることは明白ですが、では、批判者は何をもってして低い評価を下しているのかは、NPSの数値を調べるだけではわかりません。
NPSを企業の成長につなげるためには、NPSの調査と同時に具体的な改善案を知るための調査も必要です。NPS調査はいわゆる「成績表」であって、成績を改善するための具体的な方針を決めるための調査や人材の確保、および改善の実施が必要不可欠であることは理解しておく必要があります。
NPS向上につながる質問作成手法

次に、NPSの評価を改善するために役立つ質問の作成手順について解説します。
カスタマージャーニーマップを作る
まず最初に「カスタマージャーニーマップ」を作成するところからスタートします。カスタマージャーニーマップとは、商品・サービスの認知や購入、批評という顧客の行動や感情などの一連の流れを時系列で捉え、図示化したものです。
顧客体験を整理する
次に「顧客体験」を整理する段階となります。
細かく定義した顧客のペルソナになりきって、どのように商品やサービスに接する機会があるのかを把握し、認知段階から購入後まで顧客とどのような接点があるかを具体的にイメージします。
質問に落とし込む
次に「判明したデータを質問内容に落とし込む」段階です。
整理した顧客体験のうち、どの体験がNPSに対して影響を与えているかを明確にします。同じ業界でも企業ごとに顧客体験がNPSに与える影響は異なりますので、他社と異なることよりも自社にとってNPSに深く関わっていることを重視することが重要です。
どの顧客セグメントがどのように感じているのかを明確にする
さらに「顧客セグメントの分析」についても明確にしておく必要があります。
顧客には、さまざまな年齢や性別、地域などの属性があります。特定のセグメントにおいてNPSへの影響が顕著であれば、そこがNPSの向上につながる大きな要因となる可能性があるのです。
NPSは全体の平均値も重要ですが、改善にあたってはセグメントごとの分析も必要不可欠です。調査セグメントを細かく設定するほどコストはかかりますが、より細かいデータを収集することでNPS改善の糸口を明確にしやすくなります。

課題発見のためのNPS分析

最後に、課題発見のためのNPS分析について解説します。
NPSの計算方法
もう一度、NPSの基本的な計算方法について解説しておきます。
NPS=推奨者の割合[%]-批判者の割合[%]
例えば、回答者全体のうち、推奨者の割合が20%、批判者の割合が50%であれば、20-50=−30がその企業(商品・サービス)のNPSとなります。
NPSの分析方法
NPSの分析においては、NPSを「目的変数」とし、顧客体験を「従属変数」とした「重回帰分析」という統計分析を活用した手法が望ましいと言われています。
重回帰分析とは、「1つの従属変数を複数の独立変数から予測・説明する」と仮定した際に用いる統計手法です。具体的な計算方法は省略しますが、基本的に面倒な計算方法なのでツールを用いて計算するのが一般的です。
ただし、この手法が難しいという場合には、NPSに対して何が最もマイナスもしくはプラスに影響しているか、各体験の平均点を比較するのも一つの手段です。

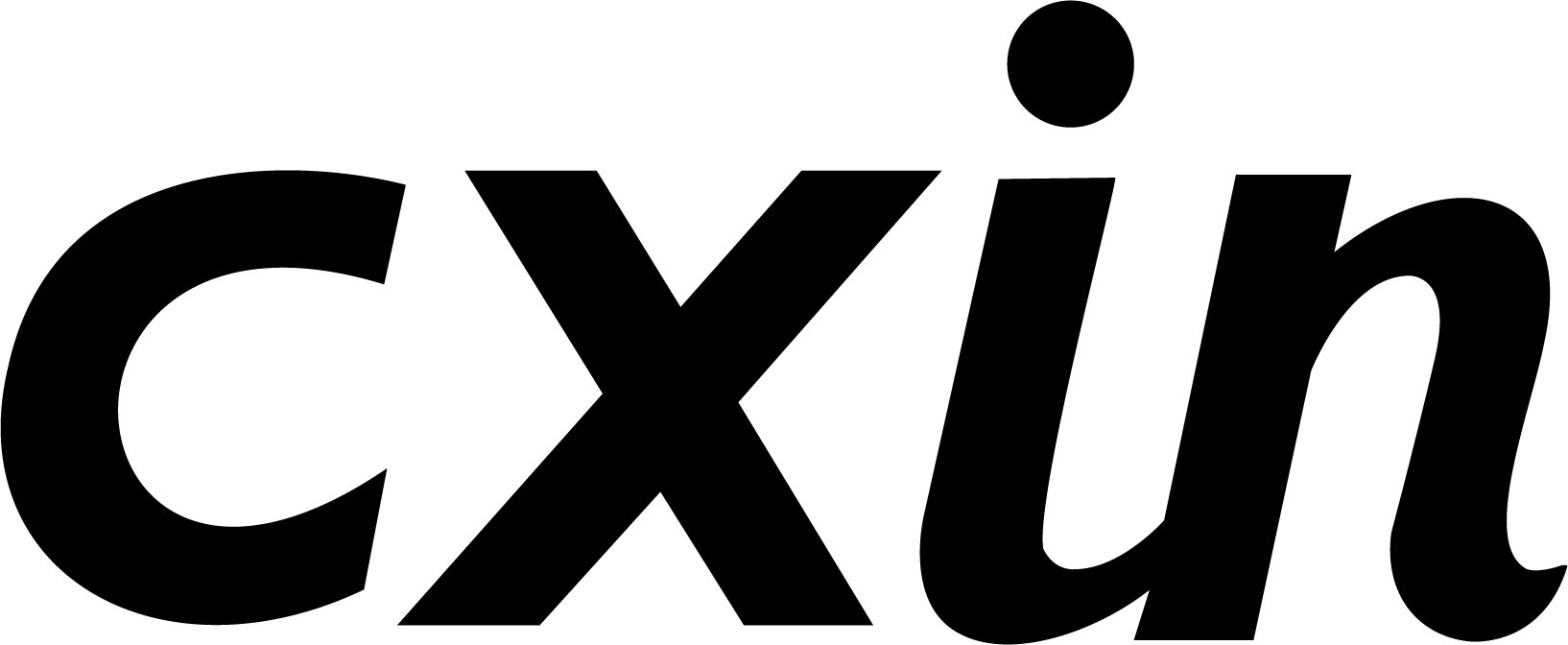




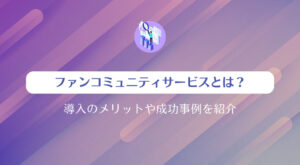
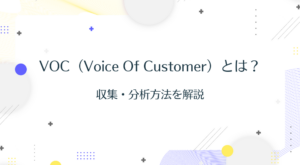
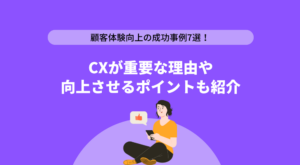
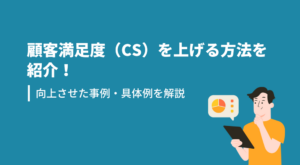
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)