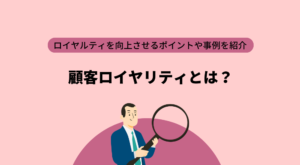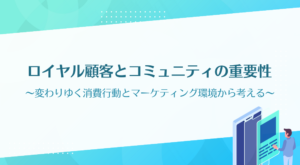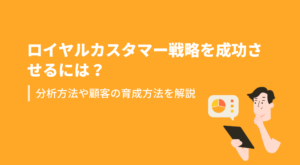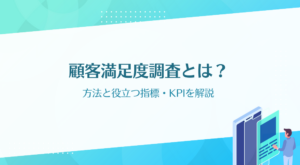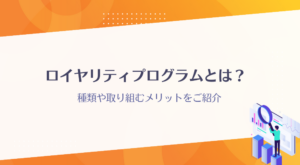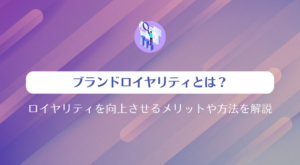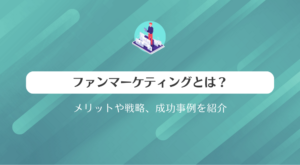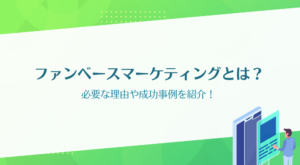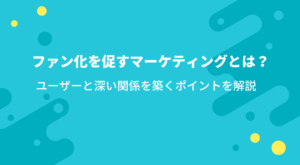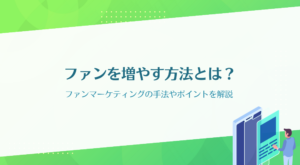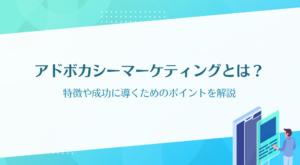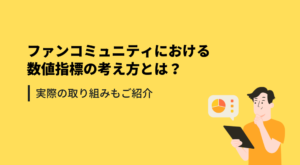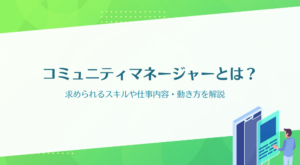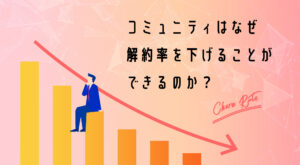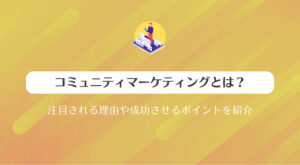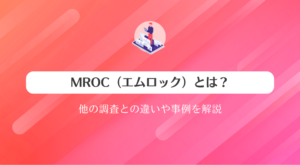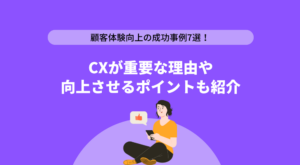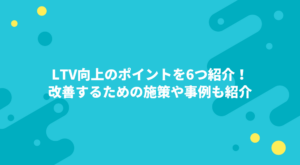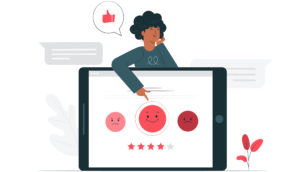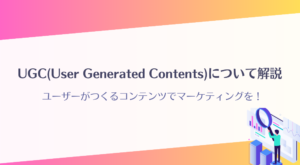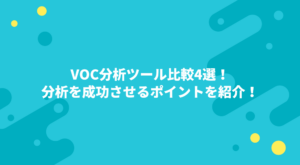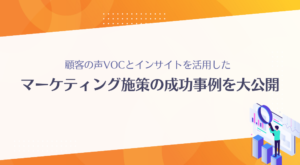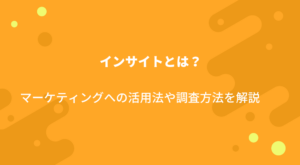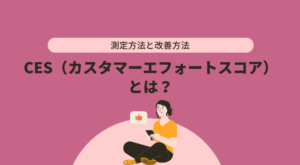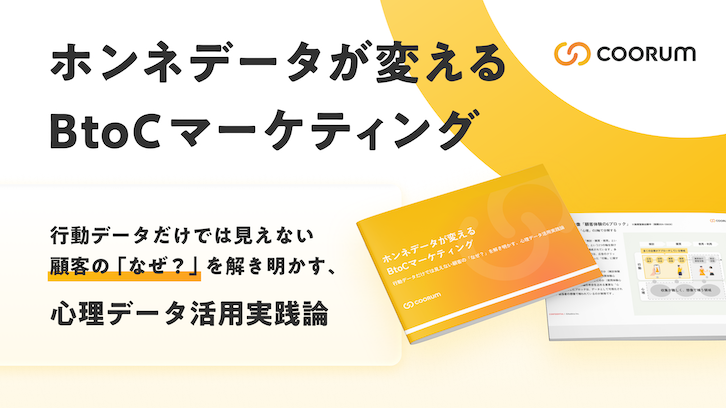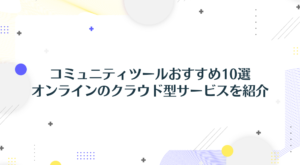
パーセプションとは、商品やサービスに関する顧客の認識のことです。パーセプションを効果的に変化させることで、顧客の購買行動を促せます。
本記事では、パーセプションの概要や、活用するモデル、パーセプションを変える方法を解説します。マーケティング施策に活用した事例も解説しますので、参考にしてください。
パーセプションとは
パーセプションとはどのような意味の言葉なのか、マーケティングでどう使われるのかを解説します。
似たような言葉に「ブランドイメージ」がありますが、パーセプションとは異なります。両者がどのように違うのかも、あわせて把握しておきましょう。
パーセプションの意味
パーセプションとは、「認識」を意味する言葉です。名前を知っている状態を超え、どのような価値があるか、どのような存在であるかを知っている状態を指します。
たとえば「駄菓子は子ども向け」「あのブランドの洗剤は汚れが良く落ちる」といった例が挙げられます。
マーケティングにおいて、パーセプションは顧客の購買行動を左右する重要な要素の1つです。パーセプションは、顧客が商品やサービスと日常的に触れ合う中で作られます。そのため、企業は広告や広報・PRなどのマーケティングコミュニケーションを通じて、顧客のパーセプションを形成することができます。
また、すでに作られたパーセプションを変容させることで、新たな購買行動を促すことも可能です。
パーセプションとブランドイメージの違い
パーセプションとは、商品やサービスそのものの価値や存在意義に関する認識のことです。一方でブランドイメージは、ブランドに対して生活者が抱いているイメージを指します。
パーセプションは事実に基づいた認識であるため、すぐ変容することはありません。ブランドイメージは広告やPRなどによって、より良い印象を持ってもらえるよう変えていくことが可能です。
パーセプションフロー・モデルとは
パーセプションをマーケティング施策で有効活用できる方法が、「パーセプションフロー・モデル」です。顧客の意識の変化を重視しており、顧客目線で考えられたモデルといえます。
パーセプションフロー・モデルは、顧客の購買行動を設計するモデルである「カスタマージャーニー」に似ていると言われることもありますが、実際は両者は異なります。
この章では、パーセプションフロー・モデルの概要とカスタマージャーニーとの違いを解説します。
パーセプションフロー・モデルの概要
パーセプションフロー・モデルとは、顧客の購買行動を「認識( パーセプション)」の変化に沿って設計し、それをもとにマーケティング施策を立てるためのフレームワークです。
顧客の行動を、以下のように8つの段階に分け、各々に対する施策を検討します。
- 現状
- 認知
- 興味・関心
- 購買
- 使用
- 満足
- リピート購入
- 口コミ
8つの段階において、以下5つの要素を把握します。
- 行動・態度
- パーセプション
- 知覚刺激
- KPI
- メディア・媒体
| 行動・態度 | パーセプション | 知覚刺激 | KPI | メディア・媒体 | |
| 現状 | |||||
| 認知 | |||||
| 興味・関心 | |||||
| 購買 | |||||
| 使用 | |||||
| 満足 | |||||
| リピート購入 | |||||
| 口コミ |
参考:Cotra「パーセプションフロー・モデルとは?メリットや作り方をくわしく解説」
上の図はフォーマットで、各項目を埋めていきます。認知から興味・関心へと顧客のステータスが変わる際に起こる変化が、構成要素の「行動」や「パーセプション」です。企業は「知覚刺激」により、顧客へコミュニケーションで伝えます。
知覚刺激の内容が決まると、目標や効果測定のためのKPIやマ―ケティング施策として利用するメディア・媒体も決まります。
カスタマージャーニーとの違い
パーセプションフロー・モデルを見て、カスタマージャーニーと似ていると感じた方もいるでしょう。両者の大きな違いは、認識をもとにしているか、行動をもとにしているかです。
カスタマージャーニーは、企業と顧客との接点ごとに、「顧客がどのように行動するか」を中心に購買行動を設計するモデルです。たとえば商品の比較検討の段階では、資料のダウンロードや説明を受けるなどの行動が考えられ、そのタッチポイントは自社ホームページやセミナーです。
一方、パーセプションフロー・モデルは、「顧客はどのように認識するか」の変化を捉えることで、消費行動を図式化するモデルとなっています。興味関心のある段階のパーセプションは「この商品を使うのが良いのかも」であり、商品を今すぐ購入する機会を提供することが打ち手となります。
パーセプションフロー・モデルは、購買行動をもとにするカスタマージャニーでは捉えられない部分を補うために提唱されたものです。

パーセプションフロー・モデルを活用するメリット
パーセプションフロー・モデルを活用することには、以下4つのメリットがあります。
- 顧客心理の変化を把握できる
- 顧客視点でのマーケティング施策を建てられる
- マーケティングの一元管理ができる
- 社内のコミュニケーションが円滑になる
顧客心理の変化を把握できる
パーセプションフロー・モデルは、顧客の認識の変化をもとに、マーケティング全体を設計する方法です。パーセプションがどう変化するかを想定し、知覚刺激をどう与えたら変化をもたらせるのか、どのように行動するかを設定していきます。
パーセプションフロー・モデルにより、顧客心理の変化をより現実的に、正確に把握することが可能です。
顧客視点でのマーケティング施策を立てられる
顧客のパーセプションの変化が、どのような知覚刺激によってもたらされるかを図式化できると、どのような広告やPRなどが有効かも明らかになります。顧客目線で設計図を作成できるため、顧客へ理想的な購買行動を促すことが可能です。
顧客の8つの段階ごとに、最適な施策を立てられることもメリットです。顧客視点で、よりきめ細かいマーケティングができます。
マーケティング全体を一元管理できる
パーセプションフロー・モデルは、マーケティングの設計図のようなものです。ターゲットである顧客について明確に捉えるのに加え、施策の立案・実行、効果測定まで定めるため、全体を一元管理できます。
また、パーセプションフロー・モデルは価格戦略や流通戦略、販売促進などマーケティング全体を可視化します。このため、営業部門や商品開発部門など、マーケティング以外の関連部門も全体で共有して利用可能です。
社内のコミュニケーションが円滑になる
マーケティングに関わる組織が複数ある場合、組織同士で使用する言葉や前提条件が違うと、コミュニケーションが難しくなることがあります。
パーセプションフロー・モデルでは、どの工程をどのような名称で呼ぶのかを明確に定められます。使用する用語をマニュアル化するため、言葉の食い違いを防ぎやすく、コミュニケーションの円滑化が可能です。
さらに、マーケティング全体を可視化することにより、誰がどの工程を担当するかも把握しやすいため、業務の推進もスムーズになります。
既存の認知を変えるパーセプションチェンジも必要
パーセプションフロー・モデルとともに押さえておきたいのが、「パーセプションチェンジ」です。この章では、パーセプションチェンジの概要、必要とされる背景、実際に行う方法を解説します。
パーセプションチェンジとは
パーセプションチェンジとは、商品やサービスに関する顧客の認識を変化させるという意味です。認識を変えることで態度や行動も変容させ、商品・サービスの購買につなげることを目指します。
パーセプションチェンジでは、商品・サービスの価値を再定義することが必要です。たとえば、子ども向けのお菓子と認識されていた森永製菓のラムネが、実は二日酔いに効果的という情報がSNSなどで拡大し、科学的根拠も存在しました。
そこで森永製菓は、「大人向け」としてサイズを大きくしたラムネを販売し、大ヒットしました。
参考:日経クロストレンド「森永ラムネが大ヒット ブランドへの認識のギャップが成功の鍵」
パーセプションチェンジが重要な理由
パーセプションチェンジが現在のマーケティングで大切な理由は、日本の市場はすでにモノが飽和しているからです。この状態で、全く新しい商品を市場に投入して売上を伸ばすのは簡単ではないため、既存の商品に工夫を加えて売上を伸ばすことが重要です。
パーセプションチェンジによってカテゴリーやブランド自体の認識を変化させることにより、新たな顧客に接触するアプローチが取れます。
パーセプションチェンジを行う方法
パーセプションチェンジは、以下5つのSTEPで実践します。
1.商品カテゴリーのパーセプションを理解する
2.ブランドのパーセプションの確認(自社ブランド・競合ブランド)
3.自社ブランドが想起されるシーンや目的の理解
4.熱狂的なファンが価値を感じているポイントの把握
5.自社が新たに取るべきパーセプションを決める
現在のパーセプションがどうなのかを理解し、想起シーンや目的を理解することが重要です。ファンが価値を感じているポイントも把握したうえで、新たに設定するべきパーセプションを決めます。
パーセプションをマーケティングに活用した事例
パーセプションをマーケティング施策に活用し、成功した事例を紹介します。
新たな訴求軸を発見したDAISOの学習ドリル
大手100円ショップのDAISOは、顧客心理や使用実態を収集・分析な可能なプラットフォームである「coorum」(コーラム)によって、新たな訴求軸を発見しました。
DAISOが販売している子ども用の学習ドリルに関して、コミュニティで「ドリルが薄いことで1冊をサクサク終わらせられる点がメリット」という声が寄せられました。同社にとって予想外のパーセプションであり、ドリルの新たな訴求ポイントを発見できた事例です。
参考:「買ってよかった」を実現するCX(顧客体験)戦略の作り方。実践企業の事例を交え紹介
ターゲットを増やした男性用化粧品
日本では長年、化粧品(コスメ)は女性向けだというイメージが強く根付いていました。この既成概念を打ち破り、化粧品メーカーは男性の顧客を取り込むことに成功しました。
肌をきれいに保ちたい男性は多いものの、女性用の商品には抵抗を示す方も多いです。そこで男性用の商品を販売することで、潜在的なニーズに応えられました。
近年では化粧水や乳液といった基礎化粧品だけでなく、男性用のメイク商品も販売されています。市場調査会社のインテージによると、男性用メイクアップ商品と日焼け止めの合計で、2023年に433億円の市場に成長しました。
参考:産経新聞「20代は抵抗なく…「化粧する男性」急増のナゾ メンズコスメ市場も500億円規模に拡大」
「手間抜き」にチェンジした冷凍食品
冷凍食品は忙しいときにも簡単に食事が取れて便利ですが、以前はどことなく「手抜き」のイメージがありました。そこで大手食品メーカーは、冷凍食品を「手間抜き」と定義し直しました。
調理時間を短縮することで、他のことに時間を有効活用できるメリットの強調です。カテゴリーのマイナスイメージを、パーセプションチェンジによって変えた事例といえます。
富士経済によると、2024年の冷凍食品の市場規模は1兆2,909億円と、2022年比で5%増加する見通しです。コロナ禍の巣ごもり需要が落ち着いた後も、個食タイプの商品などの付加価値が支持され、市場は成長しています。
参考:富士経済「冷凍食品、農畜水産加工品など加工食品の国内市場を調査」
名刺を財産と位置付けた名刺管理サービス
現在は多くのビジネスパーソンも積極的に利用する名刺管理サービスですが、以前は名刺をデータとして活用するという認識はあまりなく、机や名刺入れにしまったままというケースがほとんどでした。
名刺管理サービスを手掛けるSansanは、名刺を「企業の財産」と再定義し、名刺をデジタル管理する必要性を打ち出しました。名刺のビジネス上の意義や利点を掘り起こし、新たな認識・需要の形成に成功した事例です。
参考:日経X TREND「シェア8割超 Sansan成功の意外な戦略「名刺という言葉を封印」」
パーセプションを把握して事業成長に活かせるcoorum
パーセプションは、顧客の購買行動に影響する重要な要素の1つです。企業はマーケティングにおけるコミュニケーションを通じて、適切なパーセプションを形成する必要があります。
パーセプションをマーケティング施策に取り入れるなら、「coorum」(コーラム)を活用するのがおすすめです。「coorum」(コーラム)は、商品・サービスに関する顧客の声の収集やデータ分析ができるプラットフォームです。
「coorum」(コーラム)は顧客自らのアクションで、収集した各顧客セグメントごとの顧客心理(パーセプション)を把握できます。顧客の現在のパーセプションを把握し、パーセプションチェンジなどを実現でき、ブランドや事業の成長につなげることが可能です。
パーセプション以外にも、顧客目線の効果的なマーケティング施策の実行が可能です。顧客と長期的に良好な関係を構築し、事業の成長に活用できます。
パーセプションを活用して商品やサービスの売上を伸ばしたい方は、ぜひ「coorum」(コーラム)を活用しましょう。

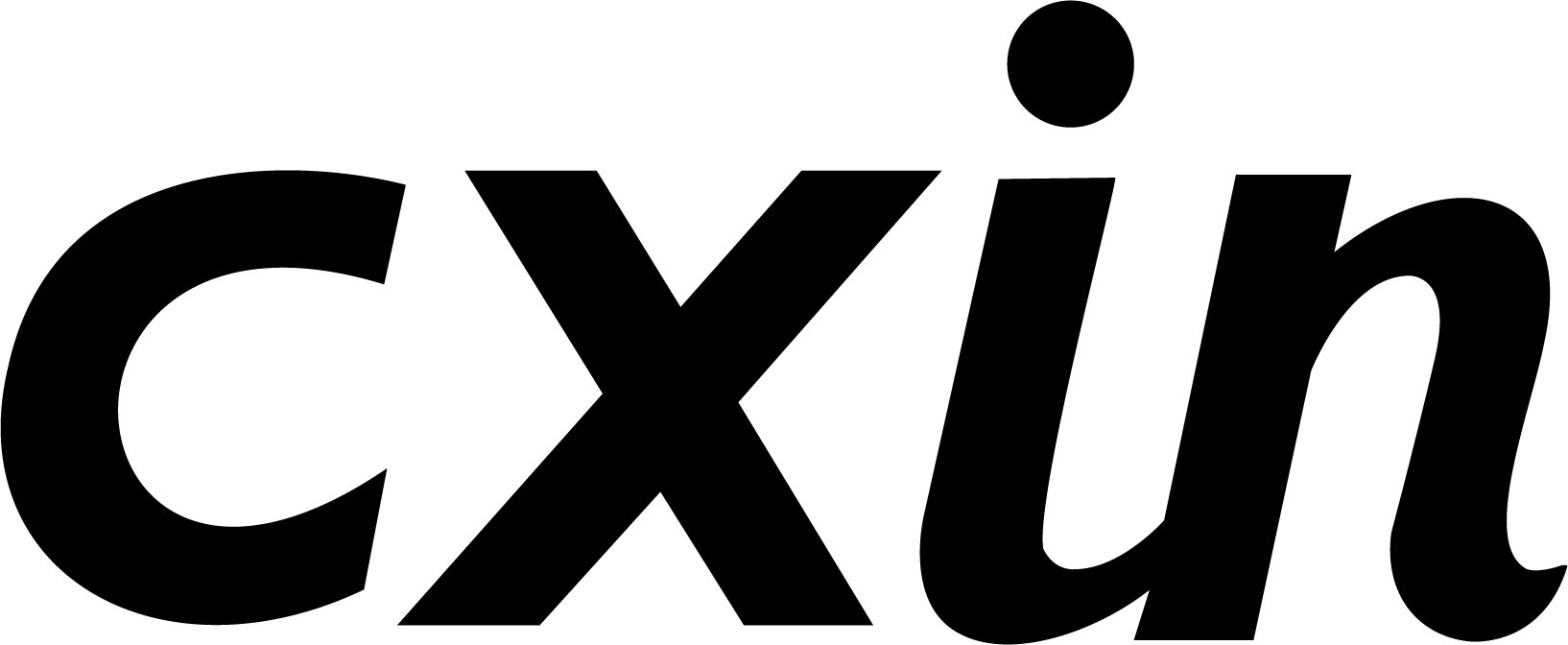

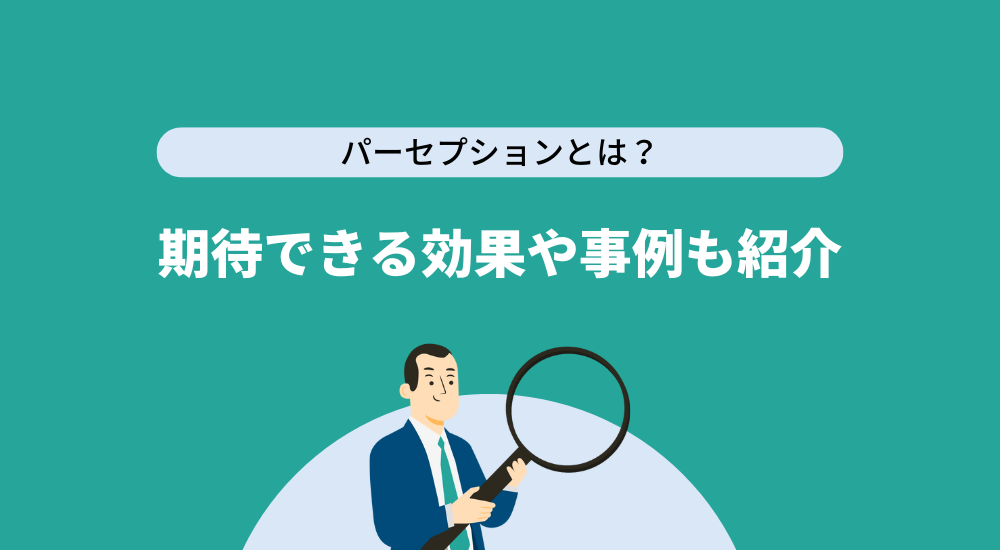
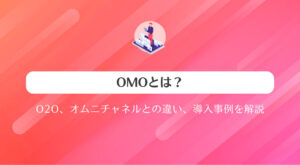


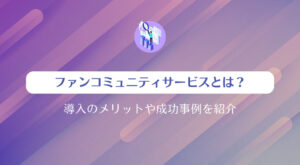
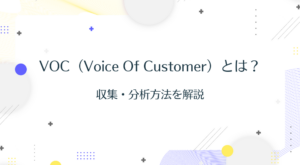
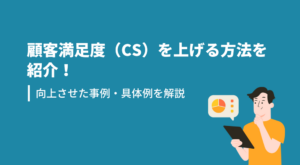
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)