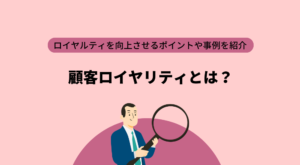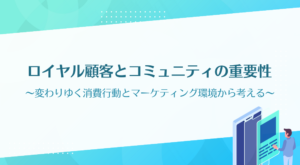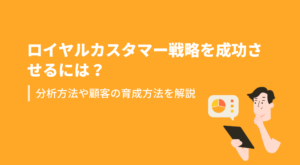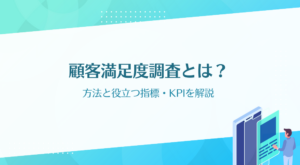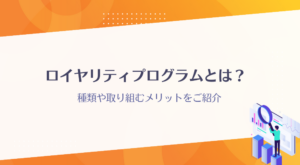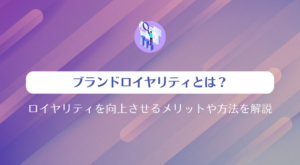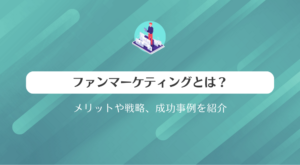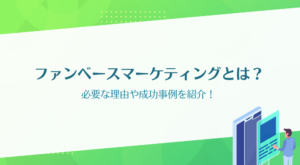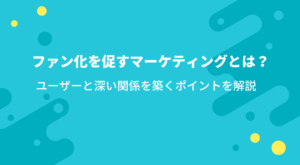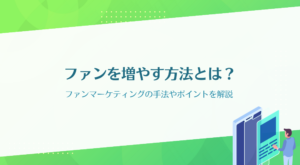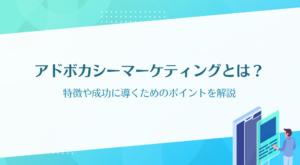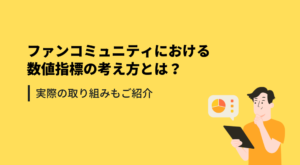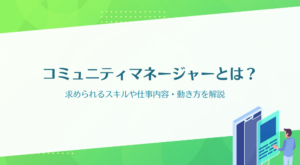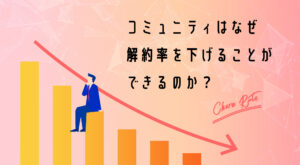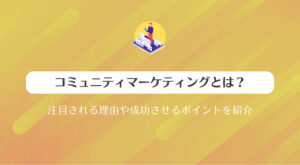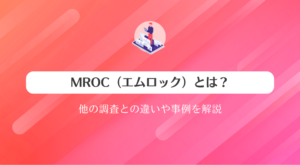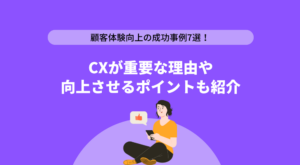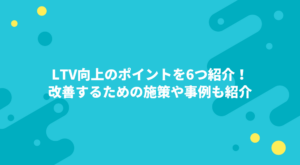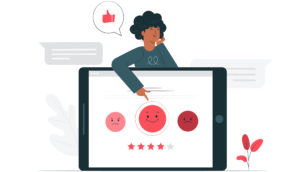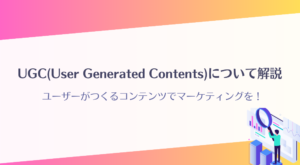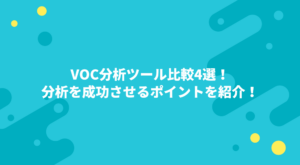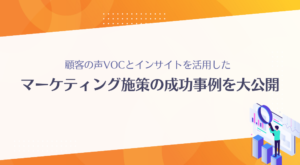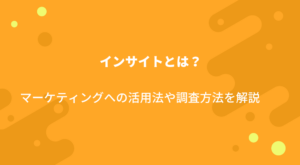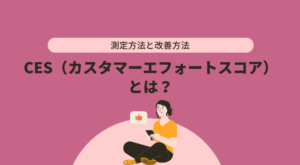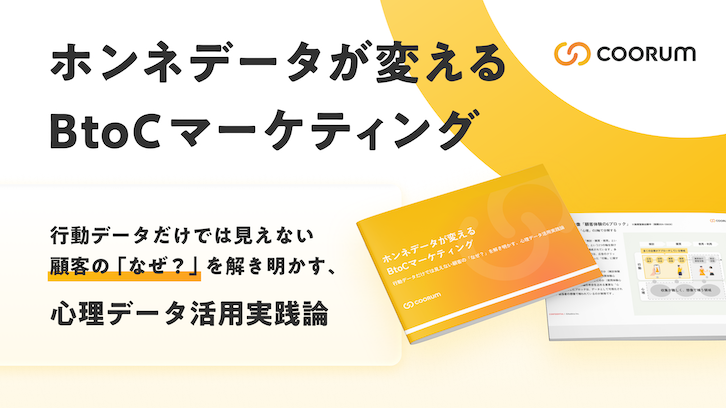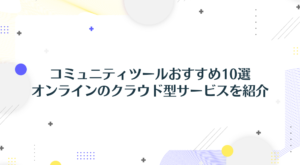
新しく商品を開発しようとする際に、どうやってアイデアを考えればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。アイデアを生み出すには、いくつかポイントや方法があるため、ポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。
この記事では、商品開発アイデアを生み出す方法やアイデアを生むためのポイント、商品開発におけるアイデア例について解説します。商品開発担当者は、最後までぜひチェックしてください。
商品開発アイデアを生むためのポイント
商品開発アイデアを生むためのポイントを紹介します。押さえておきたいポイントは、次の8つです。
- 「不」の解消を意識する
- 顧客の声からインサイトを探る
- アイデアを分類・図式化して整理する
- 質より量を重視する
- 既存の要素を掛け合わせる
- 固定観念を捨てる
- 環境を変えて考えてみる
- 他社事例を参考にする
それぞれのポイントについて詳しくみていきましょう。
「不」の解消を意識する
商品開発のアイデアを探る場合に注目したいのが、「不」のつく状態です。「不」のつく状態とは、商品や社会に対する「不」の感情を意味します。
たとえば、商品に対しての「”不”安」や「”不”満」のほか、使用して感じる「”不”便さ」など、頭に「不」という文字がついたマイナスの感情のことを指します。
人は製品や社会に対して、自身が抱く「不」が解消されることを望むため、世の中にある「不」の感情を探し出すことが顧客ニーズの発見にもつながります。
「不」の解消に役立つ方法として、「7つの不」を定義し、その解決策を検討するフレームワークがあります。詳細はページ内のこちらをご覧ください。
顧客の声からインサイトを探る
顧客の声からインサイトを探ることでも、新たな商品開発のアイデアが生まれる可能性があります。インサイトとは、顧客の隠れた本音や購買動機のことです。
顧客がなぜその商品を購入したのか、どのような理由や気持ちがあったのか、購買の裏に隠れた本音を把握することで、商品開発のアイデアを生むヒントになります。顧客の声を知るうえでは、顧客アンケートやインタビュー調査、コミュニティの活用などが有効です。
顧客のインサイトの把握には、「coorum(コーラム)」の活用がおすすめです。「coorum(コーラム)」では、顧客の心理や製品の使用実態などの顧客データを収集し、顧客単位で分析が行えます。
インサイトを踏まえた商品開発に、「coorum(コーラム)」をぜひご活用ください。
アイデアを分類・図式化して整理する
新たなアイデアを見つけたり、顧客ニーズに気づいたりするには、アイデア同士の関係性について理解することが求められます。そのためには、アイデアを分類・図式化してアイデア同士を紐づけて考えることが重要です。
アイデアを視覚化するとそれぞれの関連性が見えてくるため、アイデアに膨らみが出てきます。また、言葉ではうまく伝えられないアイデアを絵にすることで、他人と共有しやすくなります。
質より量を重視する
アイデアの質より量を重視して、多くのアイデアを出し合うようにしましょう。そもそも、アイデアを検討する場合には、次の2つのプロセスを経ることが一般的です。
1.アイデアの量を重視する段階
2.アイデアの質を吟味する段階
1の段階では、とにかくアイデアを多く出すことが重要です。その際は、アイデアの質にこだわる必要はありません。また、多角的な視点を持つうえではアイデアの粒度も気にせずどんどんアイデアを蓄積していきましょう。
1の段階から商品の生産にかかるコストや一般論にとらわれると、自由な発想を阻害する原因になりかねません。まずは、思考の枠を取り外してできるだけ多くのアイデアを出し合うようにしましょう。
既存の要素を掛け合わせる
新たなアイデアを生み出す際には、既存の異なる要素を組み合わせることも効果的です。
たとえば、世の中にすでにある市場や技術、顧客などの中から、これまで組み合わされていない要素同士を組み合わせることで、新たな商品アイデアが生まれるかもしれません。
その際、要素が多いほどバリエーションも広がりを持つため、未知なるアイデアが生まれる可能性が高まります。
掛け合わせる際のヒントは、次のようなものです。
- 異なる習慣や文化、分野を掛け合わせる
- 既存要素の目的を変えてみる
- 既存の要素を別のものに置き換えてみる など
固定観念を捨てる
新しいアイデアを生み出すためには、常識にとらわれない自由な発想が必要です。そのためにも、固定観念を捨てるようにしましょう。
自身の凝り固まった思考を解きほぐすには、視点を強制的にずらすことが必要です。視点をずらすおすすめの方法としては、次のような方法があります。
- 現状を否定する:例)アイスは夏に食べるものだが、冬に食べるとしたら?
- 条件を取っ払う:例)アルコールの入っていないお酒があったらみんなが飲めるようになる?
- 逆転の発想で考える:例)炭酸は振ってはいけないけど、振って飲む炭酸があってもいいのでは?
上記の例を参考に、固定観念を取り除いてみましょう。
環境を変えて考えてみる
環境を変えることで、新しいアイデアが生まれる可能性があります。新しいアイデアは、思いもしないようなタイミングで生まれるものです。
たとえば、普段使わない商品を手に取ったときや、誰かのふとした発言に触発されたときなど、さまざまな状況でアイデアは生まれる可能性を秘めています。
また、内在的な環境を変えることも有効です。たとえば、アイデアを考える時間を制限してみたり、今日中に○個アイデアを出すといったように自分にノルマを課したりします。
アイデアを検討する際の前提条件が変わると、普段と異なる角度から物事を捉えられるようになるでしょう。
他社事例を参考にする
すでに結果が出ている他社の事例を参考にすることも、新しいアイデアが生み出されるきっかけのひとつです。他社が成功した要因を分析したうえで、他社が抱えている課題を解消できれば、二番煎じにとどまらないアイデアを生み出せるようになります。

商品開発アイデアを生む方法
続いて、商品開発アイデアを生む方法の概要や手順について紹介します。代表的な方法は、次の8つです。
- ブレインストーミング
- ブレインライティング
- マインドマップ
- マンダラート
- オズボーンのチェックリスト
- セブンテクニック法
- シックスハット法
- 7つの不
それぞれの特徴を把握して、自社にあった方法を選びましょう。
ブレインストーミング
ブレインストーミングとは、集団でアイデアを生み出すフレームワークのことです。複数のメンバーが集まり、一定のルールに従って思いつくままにアイデアを出し合います。
その後、アイデアを分類・整理して俯瞰することで、より独創的なアイデアに成長させていくのが特徴です。
なお、ブレインストーミングを行う際には、自由にアイデアを出し合えるように、次のようなルールを設定します。
- 立場はみな平等である
- 参加者の発言を否定しない
- 冗談もOK
- 発言のハードルを上げたり、プレッシャーを与えたりしない
ブレインライティング
ブレインライティングとは、前の人が出したアイデアに対して回覧板を回すように、次々とアイデアを引き継ぎながら広げていく方法です。
リレー形式で、アイデアを同じ紙に書き出していくため、発言が消極的な人や苦手な人からでも意見を引き出せます。
ブレインライティングの手順は、次のとおりです。1人3個ずつアイデアを出して各自のシートに記入し、その下に次の人がアイデアを書き込んでいきます。
1.意見を書き込むマスを用意した用紙を準備する
2.用紙の上部にテーマを書く
3.記入する順番と制限時間を決める
4.最初の人が1行目にアイデアを3個書く
5.次の人は前の人のアイデアを参考にして、自分のアイデアを各マスの下に書く
6.最後の人までこの流れを繰り返す
7.書き終わったら、書いた意図をそれぞれ発表する
8.アイデアの中から、評価の高いアイデアを選別する
マインドマップ
マインドマップは、頭の中にあるアイデアや思考を視覚的に記載して外面化する方法です。マインドマップを作成することで。一見脈絡がないように見えるアイデアでも関連性が可視化されるため、全体像を把握しやすく、アイデアを自由に伸ばせる点が魅力といえます。
マインドマップを作成する手順は、次のとおりです。
1.A4より大きい白い紙を用意する
2.真ん中にテーマを記載する(開発したい商品など。例:「コーヒー」)
3.テーマに付随するサブテーマ(「にがみ」「豆」「デザイン」「香り」など)を派生的に追加していき、詳細を深掘りする
上記のように、連想される言葉を記載していくことで、思いつかなかったアイデアにたどり着ける可能性が高まります。
マンダラート
マンダラートとは、日本のデザイナー今泉浩晃氏が1987年に考案した思考法です。9つのマス(マンダラ)を埋めていく技法(アート)から、マンダラートという名が付けられました。
マンダラートでは、9マス(3×3)の中心にテーマを記入し、その周りのマスにテーマから連想できる言葉を書き出していく方法です。視覚的にアイデアの広がりがわかるほか、アイデア同士の関係性も把握しやすくなっています。
マンダラートを行う手順は、次のとおりです。
1.9マス(3×3)の正方形のマス目を作る
2.マスの中心にテーマを書き込む
3.テーマの周りの8つのマス目に連想される言葉や文章を書き込む
4.8つのマス目に記載された言葉を、新しい9つのマスの中心に転記する
5.新しい中心の言葉をもとに、同じように進めていく
6.合計81個のアイデアの要素が出たら完了
すべてのアイデア要素が出終わったら、それぞれの要素を組み合わせてアイデアを深めていきましょう。
オズボーンのチェックリスト
オズボーンのチェックリストとは、ブレインストーミングの考案者であるオズボーン氏が考えたフレームワークです。
あらかじめ用意された、9つのチェックリスト項目を参考にしながらアイデアを作り出していくため、発想をより多角的に膨らませられます。問い形式で深掘りできるため、アイデア出しを1人で行うときにも有効です。
オズボーンのチェックリストで活用する項目は、次のとおりです。
| チェック項目 | 概要 |
| 転用 | 別の使い方や別の領域へ適用できないか検討する |
| 応用 | 既存商品や過去商品から類似商品を探し、応用/真似できる点がないか検討する |
| 変更・修正 | 色、形、匂い、味、原料、意味などの要素を変えてみる |
| 拡大・追加 | 大きさや高さ、長さなどを拡大・追加できないか検討する |
| 縮小・省略 | 大きさや高さ、長さなどを縮小・省略できないか検討する |
| 代用 | 素材や材料、製法など代用できる方法がないか検討する |
| アレンジ | 製品の順序やパターン、レイアウト、要素、などの組み合わせを変えてみる |
| 逆 | 前後や裏表、上下、左右、因果、役割などを入れ替えてみる |
| 組み合わせ | 目的やアイデア、他の要素などを組み合わせてみる |
セブンテクニック法
セブンテクニック法とは、既存商品やアイデアに対して、7つのテーマでアプローチし新たなアイデアを生み出す方法です。
セブンテクニック法で用いる7つのテーマは、次のとおりです。
- テクニックB(壊す/Break):既存商品やアイデアのルールや当たり前を壊してみる
- テクニックD(夢/Dream):もしも既存商品やアイデアが○○だったら夢のよう
- テクニックF(欠点/Fault):既存商品やアイデアの欠点を補うとしたら?
- テクニックO(誇張/Overstatement):既存商品やアイデアを拡大、縮小してみると?
- テクニックR(逆転/Reverse):既存商品やアイデアの反対のものは?
- テクニックJ(連結/Joint):既存商品やアイデアを他のものと組み合わせたら?
- テクニックA(選択肢の追加/Adding Option):既存商品やアイデアに選択肢を加えるとしたら何を加える?
シックスハット法
シックスハット法は、6つの視点でアイデアを出し、新たなアイデアを見つける方法です。事前に6つの役割を各自に割り振り、それぞれの視点からアイデアを強制的に出していくため、通常期待できないようなアイデアが出る可能性があります。
シックスハット法では、参加者が下記のような役割になりきり、1つのテーマに対して議論します。
<役割>
- 中立的な視点
- 否定的な視点
- 俯瞰的な視点
- 想像的な視点
- 直感的な視点
- 積極的な視点
7つの不
7つの不では、顧客が感じている不の要素7つをもとに、解決・改善できる方法を見つけていきます。7つの不の感情を探ることで、より求められているニーズを発見しやすくなる点が特徴です。
7つの不を探る際に基準となる要素が次のとおりです。
- 不安:日頃の不安(健康、金銭、人付き合いなど)を解消する方法は?
- 不便:商品に対する不満を解消する方法は?
- 不精:面倒に感じていることを改善する方法は?
- 不純:行動を起こす理由となる感情(稼ぎたい、楽したいなど)を満たすには?
- 不人気:多くの人が嫌がる物事や仕事を改善し快適にする方法は?
- 不労:働かなくても収入を得られる仕組みはどうやったら作れる?
- 不変:変わらないものはないという視点で考えると見えてくるものは?
顧客の「不」を把握するためには、顧客の声に耳を傾けることが大切です。「coorum(コーラム)」では、顧客の心理や製品の使用実態などの顧客データを収集し、顧客単位で分析が行えます。
「coorum(コーラム)」を活用すれば、アイデアを生み出す際に欠かせない顧客の「不」を正確に把握することが可能です。

商品開発におけるアイデア例
商品開発における具体的なアイデア例を紹介します。各社の取り組みを参考に、自社でも取り組めるアイデア例がないかチェックしましょう。
すかいらーくホールディングス
すかいらーくホールディングスでは、「coorum(コーラム)」を活用してユーザーインサイトの獲得、ならびに新規施策への反映を行っています。
なかでも、手軽にしゃぶしゃぶを楽しめるお店「しゃぶ葉」において、「coorum(コーラム)」で収集した顧客の声をもとに『新だしの共同開発』を行いました。
しゃぶ葉をよく利用する顧客を対象にアンケートを実施することでリアルな声に耳を傾け、顧客とともにしゃぶ葉を良くしていく施策の現れの一環です。
しゃぶ葉では、「coorum(コーラム)」を活用することで顧客との接点を増やし、初来店にとどまることなく2回目、3回目と来店回数を追うごとに新しい楽しみ方を見つけ出せる施策作りなどにも挑戦しています。
導入事例インタビューはこちら▼
しゃぶ葉に熱い想いを持ったユーザーに限定したコミュニティ「おやさい学校 しゃぶしゃ部」が目指す、ユーザー全員にとって価値のある施策立案とは?
キユーピー
キユーピー株式会社ではマヨネーズの需要拡大を図るべく、炒め物に使う専用マヨネーズの開発に取り組みました。
炒め物用マヨネーズの開発に至った経緯は、『マヨネーズを使って炒めるとコクが出る』『ボリューム感のある野菜炒めに仕上がる』といった開発担当者自身の経験や現場の声です。
それらの意見をもとにマヨネーズの需要を分析したところ、炒め物専用ソースにニーズがあるのではないかという結論に達します。
食べ盛りの子どもを持つ主婦(30~40代)をターゲットとして、炒め物用のマヨネーズを開発したところ、簡単にマヨネーズ味の炒め物ができると高評価を受け、今では基幹商品へと成長しています。
参考|独立行政法人中小企業基盤整備機構「あの人気商品はこうして開発された 食品編 キユーピー3分クッキングマヨ風味炒め用ソース “あったらいいな”が出発点」
Anker
Ankerでは、顧客の『モバイルバッテリーを使いたい』『USB急速充電器を使いたい』というそれぞれ別のニーズを1台で可能にする商品を生み出しています。
それまで、モバイルバッテリーといえば、スマートフォンを充電するためのものでした。しかし、いざ充電しようとした際に『モバイルバッテリーの充電ができていない……』という自体が起き、顧客からもそれについてなんとなかならないかという問い合わせも来ていたそうです。
そこでAnkerが世に送り出したのが、モバイルバッテリー本体を充電しながらさまざまな機器の充電も同時にできる「PowerCore Fusionシリーズ」です。
2017年の登場後、Ankerで1、2を争う人気製品となり、2020年には満を持して第二弾製品が出るなど、不動の地位を確立しています。
参考|Anker「Fusionシリーズはなぜ生まれた?充電器とモバイルバッテリーの一体型モデルの魅力を解説」
商品開発アイデアを実らせるうえでの注意点
商品開発アイデアを実らせるうえでの注意点は、次の5つです。
- 常にアイデアの種を探して記録しておく
- 会社視点になりすぎない
- アイデアで顧客(ユーザー)のニーズを満たせるか考える
- アイデアに競合優位性はあるか考える
- アイデアに実現可能性はあるか考える
注意点を理解して、アイデアの実現性を高めましょう。
常にアイデアの種を探して記録しておく
常にアイデアの種を探して、記録しておくようにしましょう。アイデアの種は、いつどこで思いつくかわかりません。思いついたときにすぐに記録することで、アイデアを忘れてしまうことを防げます。
また、アイデアを記録しておけば、あとでアイデアを振り返る際にも役立ちます。記録する際は、そのとき思いついた内容をできるだけ詳細にメモするようにしましょう。
会社視点になりすぎない
アイデアは、会社視点になりすぎないことが大切です。会社の独りよがりなニーズを満たしたアイデアと、実際の顧客ニーズは異なります。実際の市場における顧客の反応を活かした商品開発をすることが重要です。
そのためにも、アイデア出しを行う際には制約や条件を設けず、多角的に考えるようにしましょう。また、実際の顧客の声を参考にアイデアを形にしていく方法も有効です。
「coorum(コーラム)」では、顧客の心理・購買行動などのデータを安定的に取得できます。顧客の実際の需要を知れるほか、アイデアの種がほしいときにも役立ちます。
アイデアで顧客のニーズを満たせるか考える
顧客に刺さる商品を開発するには、アイデアが顧客のニーズにマッチしていることが重要です。商品開発担当者が作りたいと思った商品を開発しても、顧客のニーズにマッチしなければ購入されません。
顧客のニーズを満たすには、顧客の声に耳を傾けることが重要です。また、日頃から顧客の声を蓄積し、それらを分析することでよりニーズに合致した商品を開発できるようになります。
顧客の声や顧客心理などのデータを安定的に取得したいのであれば、「coorum(コーラム)」の活用が有効です。顧客の実際の需要を知れるため、よりニーズに合致した商品開発に役立ちます。
アイデアに競合優位性はあるか考える
思いついたアイデアに、競合優位性があるかどうかも検討しましょう。競合優位性とは、他社の商品よりも自社の商品が優位なポジションを獲得できる領域のことです。とくに、市場において後発で参入するのであれば、競合優位性が重要になります。
アイデアに実現可能性はあるか考える
浮かんだアイデアが自社リソースで実現可能なものであるかどうかも、あらかじめ確認しておきましょう。自社の保有するリソースとしては、ヒト・モノ・カネ・情報の4つが挙げられます。
既存リソースで実現できるのか、新たな人材の確保や設備投資などが必要にならないか、必要な場合は他社と連携することで実現可能なのかなど、総合的な視点で判断するようにしましょう。
「coorum(コーラム)」でユーザーの声を集めよう
商品開発のアイデアを生むためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。「不」の解消を意識したり、顧客の声からインサイトを探ったり、他社事例を参考にしたりするなどです。
また、商品開発アイデアを生む方法としては、ブレインストーミングやマインドマップ、セブンテクニック法、7つの不といった方法があります。それぞれ方法が異なるため、自社にあった方法を選択できるように、しっかりと内容を理解しておきましょう。
商品開発アイデアを実らせるためには、アイデアの種を記録しておくこと、会社視点になりすぎず顧客視点に基づいたアイデアにすることが重要です。そのためには、顧客のリアルな声に耳を傾ける必要があります。
「coorum(コーラム)」を活用すれば、開発する商品のターゲットとなる顧客の心理や、既存商品の使用実態をを収集・分析できるため、新しい商品のアイデア捻出や商品開発に役立ちます。
「coorum(コーラム)」を活用して、顧客のニーズにあった商品開発アイデアを立案しましょう。

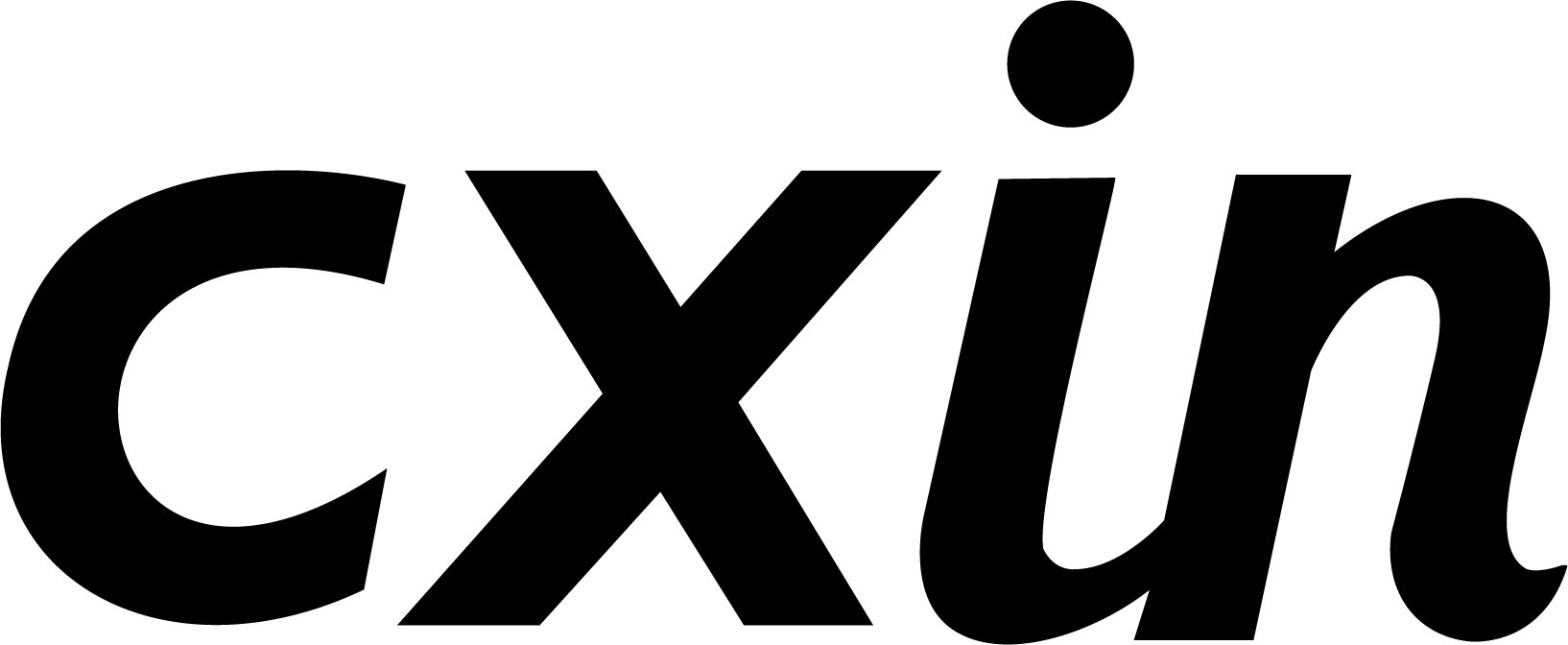

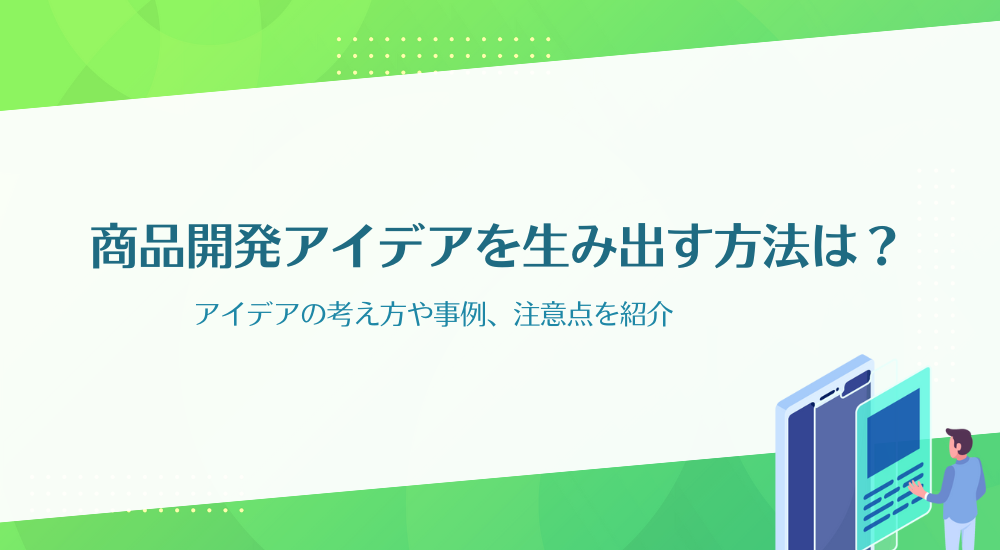
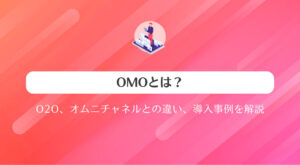


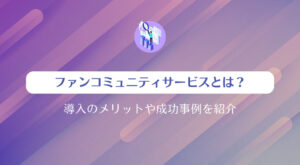
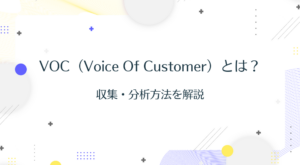
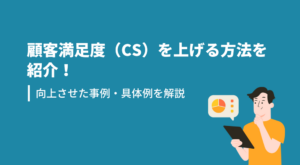
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)