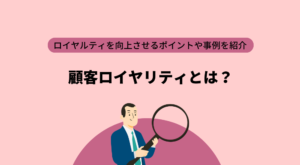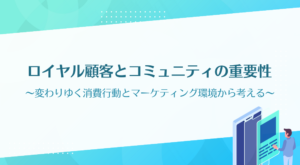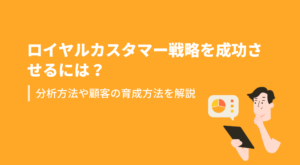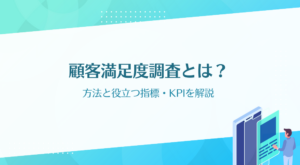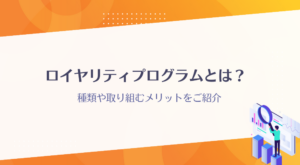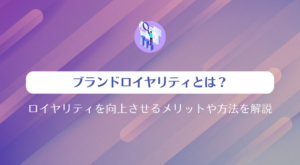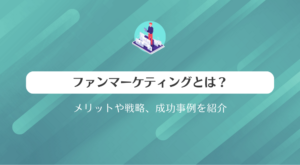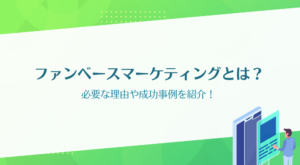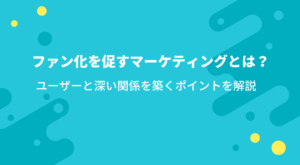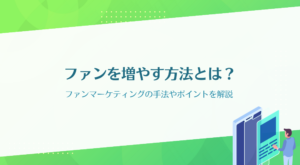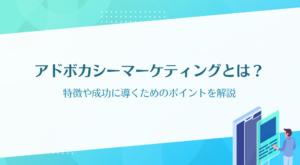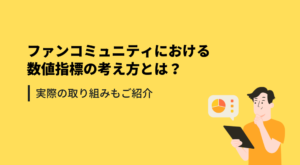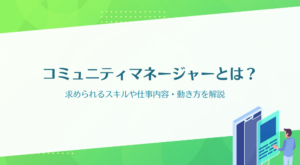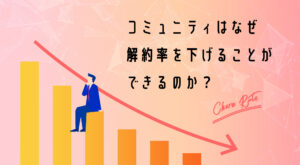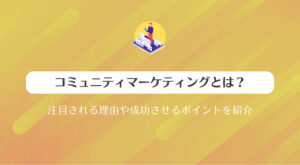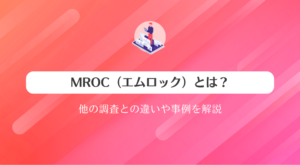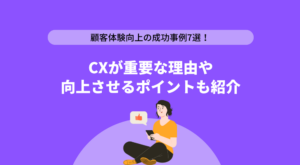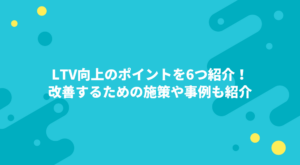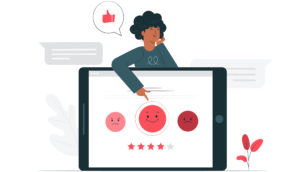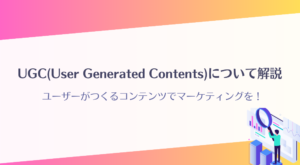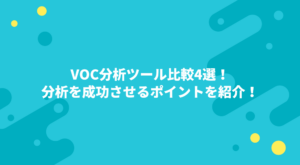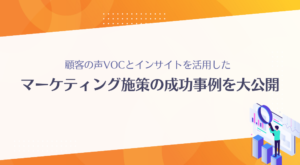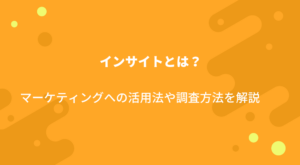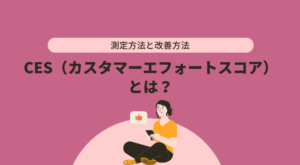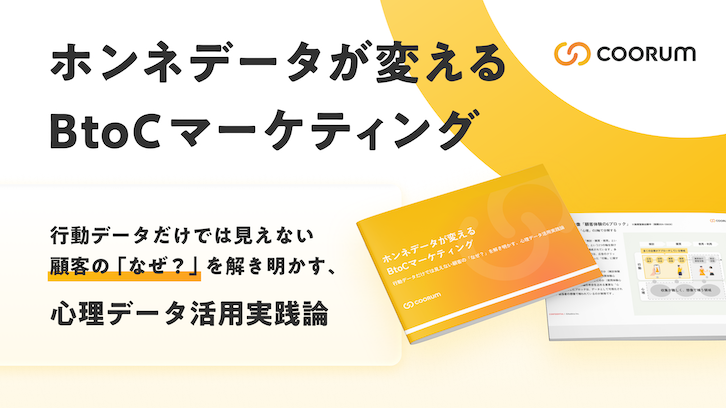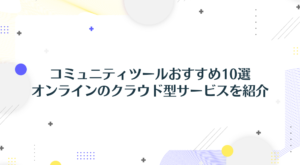
ポジショニング戦略とは、市場における自社商品のポジションを定めるためのマーケティング戦略です。競合商品があふれる中で、お客様に自社商品を選んでいただくための手法として活用されています。
この記事では、ポジショニング戦略の重要性や進め方、気を付けるべきポイントや成功事例などを解説します。
ポジショニング戦略とは?
ポジショニング戦略とは、市場における自社商品(製品・サービスなど)の立ち位置(ポジション)を定めるための、マーケティング戦略です。
別の言い方だと、「お客様にとってナンバーワン・オンリーワンの存在になるために、市場での自社商品のポジションをどのように確立させるか検討すること」ともいえます。
マーケティングに限定することなく「他社と比較した自社の立ち位置を検討する」という意味合いであれば、商品自体の見直しを検討するケースもあるでしょう。
一方、マーケティング観点でのポジショニング戦略においては、商品名やパッケージなどを見直すことはあっても、商品自体には手を加えません。基本的には、すでにお客様の頭の中にあるイメージを変えることで、自社商品に結びつける手法がとられます。
ポジショニング戦略がマーケティングで重要な理由
ポジショニング戦略は、マーケティングを考えるうえで議論に挙がりやすい手法の1つです。市場にあふれる商品の中で他社商品との差別化を図り、特定の価値やメリットをアピールし、お客様に自社商品を選んでもらうための手法として用いられています。
ポジショニング戦略によって、お客様が自社商品を他社商品と区別しやすくなることで、価格競争を避けたり顧客に選ばれやすくなったりするメリットが期待できます。競合他社が少ない市場を確保することで、競争が激しい市場で独自の地位を確立しやすくなるでしょう。
ポジショニング戦略の中でターゲットとなるお客様の特性を深く理解することは、戦術・施策を生み出しやすくするだけでなく、お客様からの好評価につながる価値提供にも役立ちます。
ポジショニング戦略に限らず、「戦略(資源配分の最適化)」においては、以下3つの要素が重視されます。
1.認知
2.配荷
3.プレファレンス
ポジショニング戦略は、この中の「プレファレンス(好意度)」を高めるために必要となる手段の1つです。
STP分析とポジショニング戦略の関係
ポジショニングは、STP分析の構成要素です。
STP分析とは、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングという、3種類の英単語の頭文字から名付けられたマーケティング手法です。顧客ニーズの把握や、他社との差別化のための分析方法として活用されています。
STP分析では、以下の流れで分析を進めます。
1.セグメンテーション(Segmentation):市場を細分化する
2.ターゲティング(Targeting):狙うべき市場を選択する
3.ポジショニング(Positioning):自社の立ち位置を決定する
ポジショニングは「STP分析」の「P」にあたり、最後に行われるプロセスです。セグメンテーション・ターゲティングを経て、ターゲットを明確にしてからポジショニングを検討する必要があります。
ポジショニング戦略の進め方
ポジショニング戦略の進め方の流れは、以下のとおりです。
1.セグメンテーションを行いターゲットを決める
2.ポジショニングマップの軸を決める
3.ポジショニングマップに競合や自社を配置する
4.差別化するための施策を検討する
順番にみていきましょう。
1.セグメンテーションを行いターゲットを決める
ポジショニングの前段階として、まずはSTP分析のセグメンテーションとターゲティングを実施する必要があります。
セグメンテーションとは、お客様の属性やニーズに基づき、市場をいくつかのグループに分類することを指します。BtoC商品の場合、「若者・ファミリー・シニア」など「人」に焦点をあてることが一般的です。BtoBでは「企業規模・決裁権の有無・事業内容」などが対象となります。
市場を細かくセグメント化し、グループごとのニーズや特性を把握できたら、市場規模や成長性、競争状況などの観点から各セグメントの魅力度を評価します。評価結果をふまえて、自社にとって最も有望で利益を上げやすい、ターゲットとなる市場を選定しましょう。
2.ポジショニングマップの軸を決める
自社が狙うべきターゲット市場を定めたら、ポジショニングマップを作成します。
ポジショニングマップとは、縦軸と横軸にターゲットの購入動機となる異なる評価ポイントをそれぞれ設定し、自社と他社の状況を配置した図のことです。ターゲット市場における自社商品のポジションの可視化や、競合との差別化に役立ちます。
縦軸と横軸の例は、以下のとおりです。
- 「スピード」と「品質」
- 「機能性」と「デザイン」
軸は、複数設定することも可能ですが、2つの軸まで落とし込むことで、社内展開などする際に、比較的シンプルに自社の立ち位置を理解してもらうことができるでしょう。
3.ポジショニングマップに競合や自社を配置する
前ステップで定めた軸に従い、ポジショニングマップ内に自社商品と競合商品を配置します。マップ上の競合位置を確認したうえで、自社商品をどの位置にポジショニングすべきかを検討しましょう。
たとえば、競合が密集しているエリアに自社が位置している場合、競争の激化が予想されます。他社と比べて大きく有利になり得る強みがない限り、「競合が少ないエリアへのポジショニング」「ポジショニングマップの軸の再考」といった検討が必要でしょう。
一方、マップ上の空白エリアや競合の少ないエリアは、競合他社が進出していないニーズと読みとれます。これらの位置に自社をポジショニングできれば、他社との差別化を実現しやすくなります。
4.差別化するための施策を検討する
自社の強みを活かし、他社商品と差別化するための施策を考えます。
施策の一例は、以下のとおりです。
- 価格を見直す
- 製品の機能を拡張する
- プロモーションに注力する
ポジショニングマップや自社の特徴をふまえ、「自社を配置したエリアのニーズを捉えるために必要な施策」を検討しましょう。

ポジショニング戦略を行う際のポイント・注意点
ポジショニング戦略を行う際は、以下のポイントに注意しましょう。
- ターゲットとなる市場の規模を確認する
- 顧客のニーズをふまえて軸を設定する
- 軸を設定する際は相関性の低いものにする
- 自社の理念や戦略に合致しているか確認する
- 競合分析やPDCAを継続して行う
- 自社の強みを理解したうえで行う
- 市場以外にも景気や社会の状態など外的要因も考慮する
各ポイントについて解説します。
ターゲットとなる市場の規模を確認する
ターゲットとなる市場規模は、しっかり確認しましょう。
たとえば、ポジショニングマップ上の空白エリアへの位置づけは、他社との差別化に有利です。
一方、「市場が小さく事業が成り立たない」という理由から空白エリアになっている可能性も考えられます。その場合、空白エリア内のポジションを狙っても、十分な成果は得にくいでしょう。
自社の利益につながるユーザーニーズがあるかどうか、市場規模をきちんと確認しておくことが大切です。
顧客のニーズをふまえて軸を設定する
ポジショニングマップの軸は、自社が差別化できそうな要素よりも「顧客ニーズに沿った要素」を重視して選ぶことがポイントです。
他社との差別化を図ることは、非常に重要です。しかし、他社との差別化を重視して顧客ニーズから外れた軸でポジショニングした場合、施策がお客様に響かず、十分な成果を期待できません。
一方、お客様が自社商品に価値を感じて共感できるような魅力あるポジションを選べば、感情的なつながりが生まれ、ブランドに対するロイヤリティや信頼の向上につながります。
顧客ニーズを判断するためには、自社商品を利用してくれているお客様の情報やお客様アンケートをふまえた調査が役立ちます。
「coorum(コーラム)」は、「顧客の本音」データを収集し、顧客起点のマーケティングを実現するツールです。お客様とのコミュニケーションはもちろん、お客様情報の分析や顧客が能動的に答えてくれる顧客調査の実施も可能です。顧客ニーズの的確な把握に、ぜひお役立てください。
軸を設定する際は相関性の低いものにする
ポジショニングマップで軸を設定する際は、相関性が低く、互いに影響を与えにくい要素を選びましょう。
たとえば「価格」と「品質」という2つの軸は、互いの相関性が高めです。価格が高いほど高い品質を実現しやすいため、結果として1つの軸によるポジショニングとほぼ変わらず、狙うべきポジションがわかりにくくなるでしょう。
競合のポジションを正確に把握し、効果的に自社をポジショニングするために、相関性が低い軸同士を設定することをおすすめします。
自社の理念や戦略に合致しているか確認する
自社の理念や戦略に合致した、ポジショニング戦略を練ることが大切です。自社が大切にする理念とポジショニング戦略に整合性がない場合、ブランドイメージに悪影響を与える可能性があるためです。
たとえば、「高価格かつ高品質な商品でお客様からの高い期待に応える」ことをポリシーとしていた企業が、低価格帯のポジションを選んだとします。
これまでのブランドイメージとかけ離れたポジショニング戦略は、お客様の混乱を招き、ブランドに対する信頼を失う恐れがあるでしょう。
ポジショニングマップで見つけた魅力的なポジションが、自社が譲れないポリシーや維持したいイメージに反しないかどうか、見極める必要があります。
競合分析やPDCAを継続して行う
競合分析やPDCAは、継続して行いましょう。市場や競合他社の動向は常に変化します。定期的に競合分析を実施し、必要に応じてポジショニング戦略を調整することが重要です。
また、練りに練ったポジショニング戦略であっても、初めからうまくいくとは限りません。期待していた成果が得られなかった場合は、原因を分析して改善し、PDCAサイクルをまわしましょう。
ポジションを変更することで、成果が伸びる可能性もあります。現状のポジションに固執しすぎず、状況にあわせてリポジショニングを行うこともポイントです。
自社の強みを理解したうえで行う
自社の強みをふまえたポジショニング戦略を行いましょう。たとえポジショニングマップ内で競合他社がいない空白エリアに顧客ニーズが存在したとしても、自社の強みを活かせなければ十分な成果につながらない可能性が高いためです。
自社の強みを活かしつつ、競合他社と差別化できる戦略を検討しましょう。
たとえば、自社が保有しているお客様の情報やお客様アンケートなどによる顧客の声や使用実態を把握する調査結果は、自社の強みの把握に役立ちます。
「coorum(コーラム)」は、お客様との定期的なコミュニケーションを図る多くの機能を備えており、顧客の声や使用実態を継続的に収集可能です。自社の強みを客観的に把握し、効果的なポジショニング戦略を策定するために、ぜひご活用ください。
市場以外にも景気や社会の状態など外的要因も考慮する
ポジショニング戦略では、市場だけでなく景気や社会の状態といった「外的要因」も考慮することがポイントです。
景気や世論、技術革新といった外部環境が自社に及ぼす影響をふまえ、自社だけでなく他社も含めてどのような対策を講じ、どのようにポジショニング戦略に活かすべきかを検討しましょう。
自社の強みや市場を理解したうえで戦略を策定するためには、以下のフレームワークが役立ちます。
| 5フォース | 競合や業界全体の状況や収益構造を以下5つの競争要因に分類して明らかにし、自社の収益性をアップに向けて分析する手法 ・業界内での競争 ・業界への新規参入者 ・代替品の存在買い手(顧客)の交渉力 ・売り手(サプライヤー)の交渉力 |
| SWOT 分析 | 自社の内部環境と外部環境を以下の観点から洗い出し、分析する手法 ・強み(Strength) ・弱み(Weakness) ・機会(Opportunity) ・脅威(Threat) |
| PEST 分析 | 自社を取り巻く以下の外部環境が、現在もしくは将来的与える影響を把握・予測する手法 ・政治(Politics) ・経済(Economy) ・社会(Society) ・技術(Technology) |

ポジショニング戦略の成功事例
ポジショニング戦略をスムーズに進めるために、実際の成功事例をチェックしておきましょう。
ここでは、「シーブリーズ」、「Salesforce」、「レッドブル」の事例をピックアップして紹介します。
シーブリーズの事例
資生堂によるボディケアブランド「シーブリーズ」は、リポジショニングによる成功事例の1つです。
1980年代、シーブリーズは20代~30代の若い男性をターゲットにしており、海で使える日焼けケア商品がヒットしていました。しかし、時代とともに海に行く人は減り、日焼けに対する抵抗感も強まった結果、ブランドが衰退してしまいます。
そこで資生堂が実践したのが、ポジショニングの変更です。ターゲットを女子高生へ、また学校や街など日常シーンで手軽に汗をケアできる商品としてプロモーション戦略を行った結果、低迷期の約8倍もの売上を実現しました。
参考|PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)「実例から学ぶマーケティング概論(第3回)」
Salesforce の事例
他社との差別化を図るポジショニング戦略の成功事例が、Salesforce(セールスフォース)です。
Salesforceは、クラウドベースのCRM(顧客関係管理)を中心としたソフトウェアを提供しています。
1990年代の業務向けソフトウェアは、CD-ROMをインストールして使用する買い切り型が主流でした。そのような中、Salesforceはインターネットを介するSaaS型の業務向けソフトウェアを提供し、他社との差別化に成功しました。
また、多くのアプリケーションと連携可能なセールスフォースは、企業ニーズにあわせてカスタマイズできる点も魅力です。「高機能・高柔軟性」というポジションを確立したことで、現在でも多くの企業に選ばれています。
参考|株式会社ROUTE06 (ルートシックス)「SaaSの誕生とSalesforce、マーク・ベニオフの革新的なマーケティング戦略」
レッドブルの事例
オーストリアのレッドブル社が販売するエナジードリンク「レッドブル」は、従来の栄養ドリンクとは異なる独自のポジショニング戦略を展開し、成功をおさめました。
従来の「ひどく疲れた中高年が疲労回復のために飲むもの」という栄養ドリンクに対する世間のイメージに対し、レッドブルは「飲むと強くなる」「力を発揮する」というイメージでプロモーション活動を実施しました。
また、レッドブルを「エキサイティングな体験」「スリルや冒険そのもの」と定義し、創業当時に若者が熱狂していたエクストリーム・スポーツのスポンサーに名乗りを上げます。
その結果、コアターゲットとなる若者へのアピールに成功し、「疲労時に限らず、元気を出したいときにも適したエナジードリンク」として、市場における新たなポジションを確立しました。
参考|BizDrive(ビズドライブ)「レッドブルが差別化と優位性を実現したマーケ戦略」
ポジショニング戦略の推進にはcoorumがおすすめ
競合商品が市場にあふれる中で、お客様に自社商品を選んでいただくためには、適切なポジショニング戦略が欠かせません。
一方、市場規模や顧客ニーズに沿わないポジショニング戦略を進めた場合、思うような成果を得られないだけでなく、既存顧客からの信頼を失ってしまう恐れもあるため注意が必要です。
単純に競合が少ないポジションを選ぶのではなく、市場規模や顧客ニーズ、自社の強みなどもふまえたうえで検討する必要があります。
そのためには、客観的な視点での分析や調査が必要不可欠です。効率的かつ的確に情報収集・分析を進めるためには、ツールの活用を検討しましょう。
「coorum(コーラム)」は、お客様の声の収集から顧客ニーズ・自社の強みの把握まで幅広くカバーできるお役立ちツールです。
たとえば、「coorum resarch」にてゲーミフィケーション型の顧客調査を実施し、お客様の心理や商品の使用実態を収集すれば、日々変化する顧客ニーズも的確・簡単に把握できます。また、自社を継続的に選んでいる顧客との定期的な接点を「coorum community」で構築することで、自社の強みなどを把握することも可能です。
顧客の目線をふまえた客観的な情報を取り入れることで、企業視点では気づけないような、自社に最適なポジションを把握することができます。スムーズかつ効果的にポジショニング戦略を推進したい場合、ぜひ「coorum(コーラム)」の導入をご検討ください。

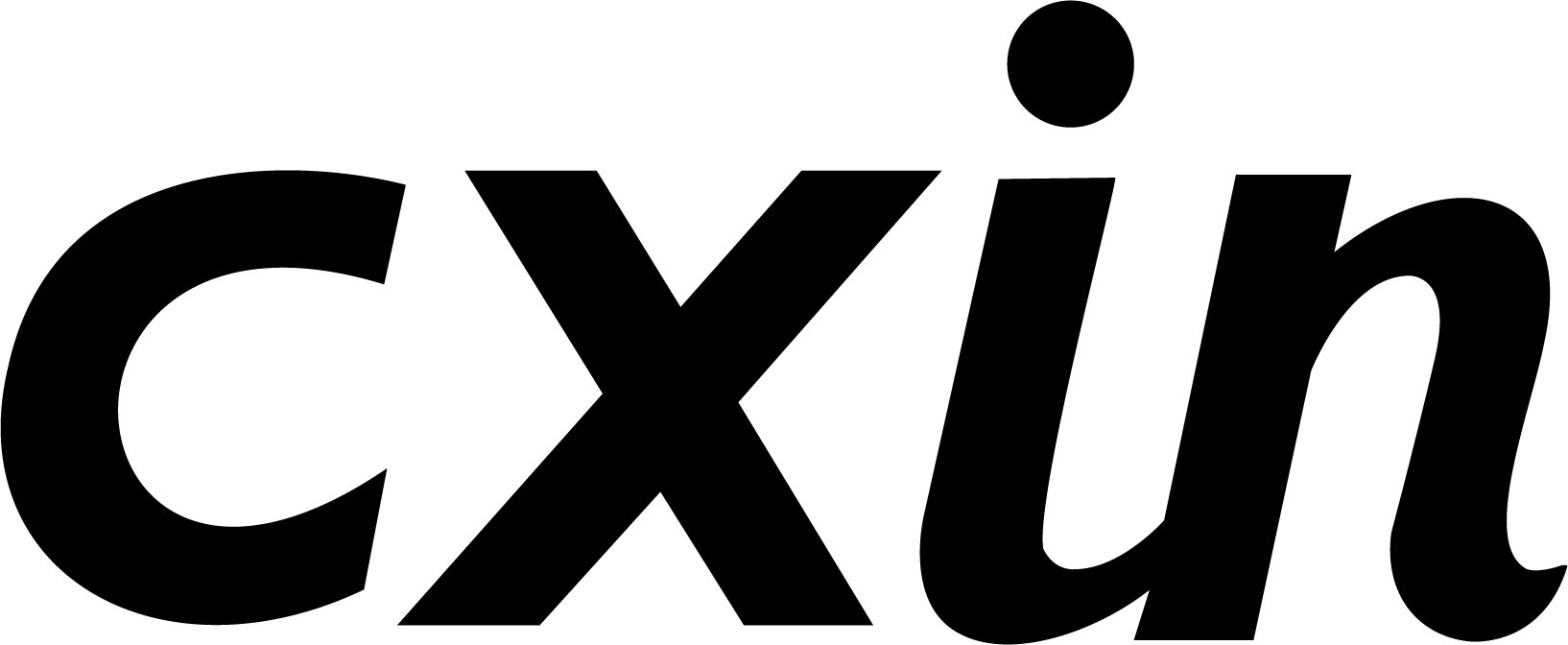

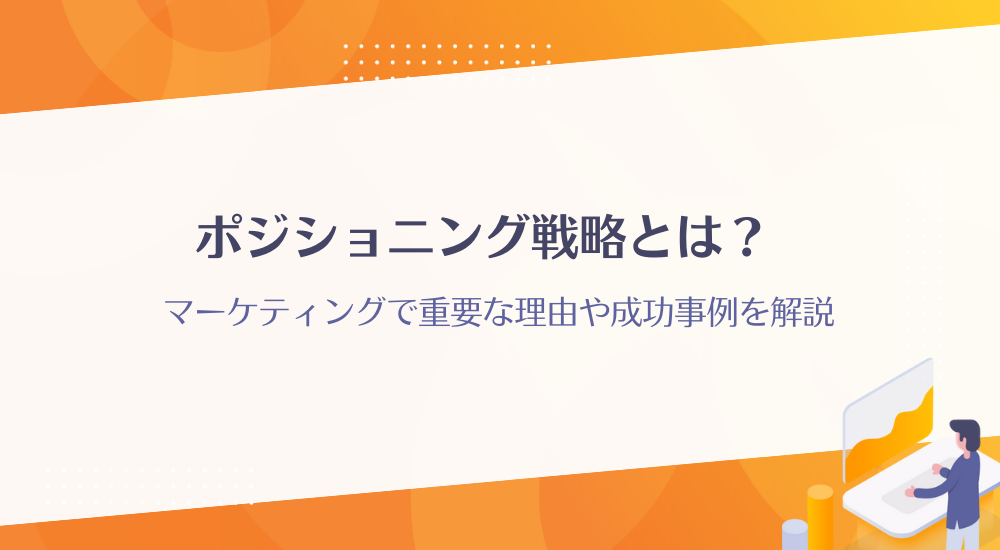
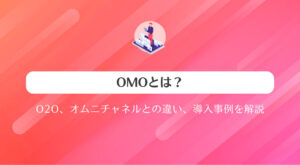


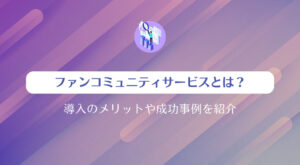
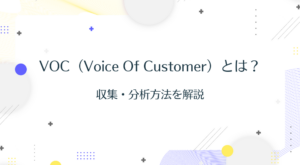
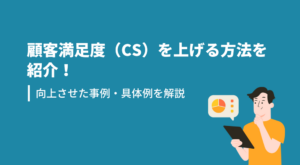
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)