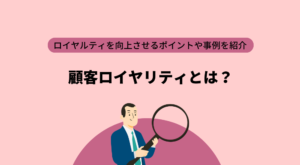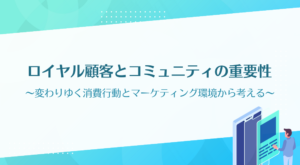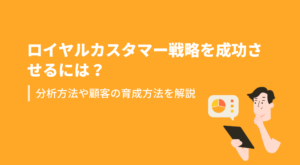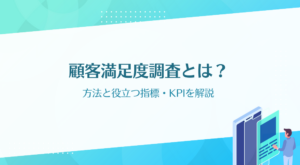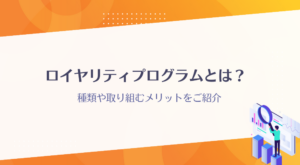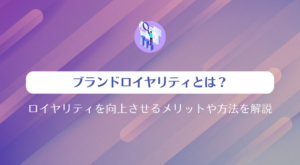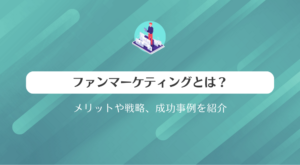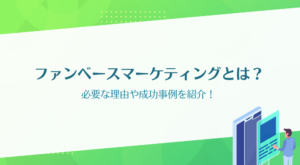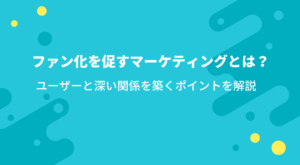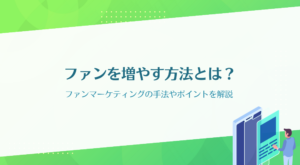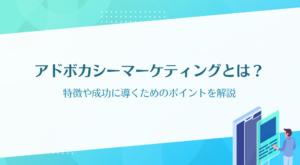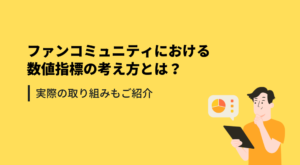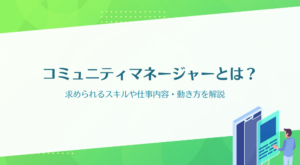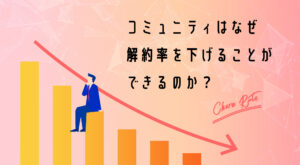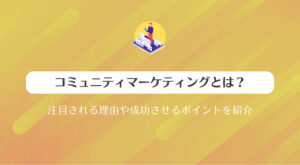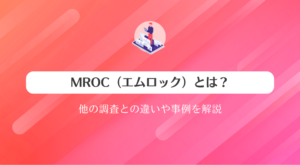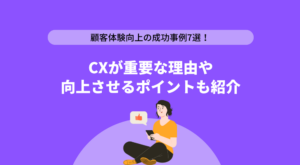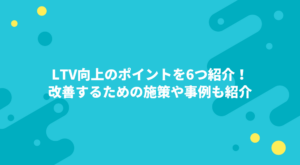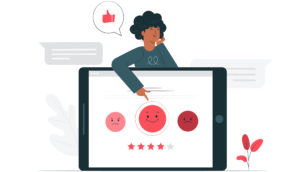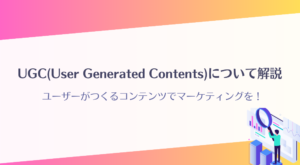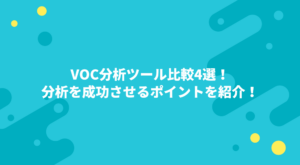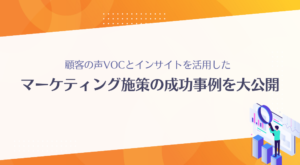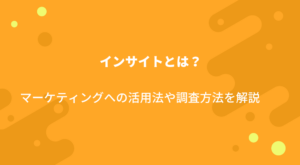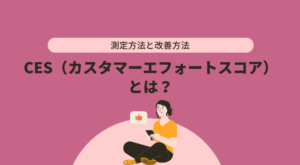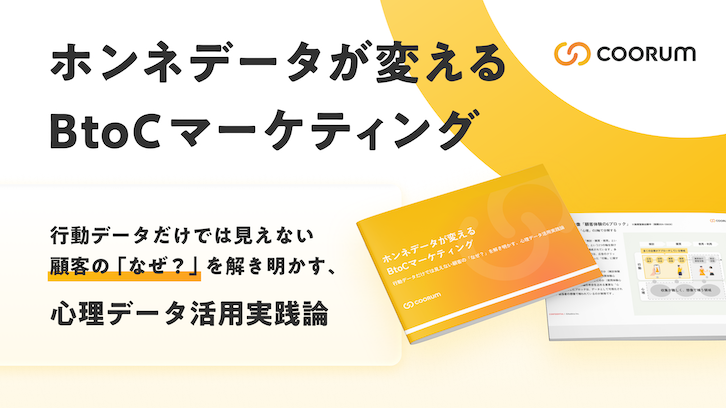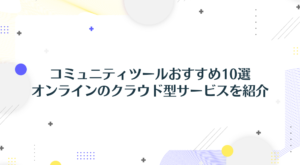
マーケティングや営業活動を成功させるためには、顧客ニーズに沿った施策を取ることが必要不可欠です。顧客ニーズを把握するためには、自社でできるものや調査会社に依頼するものなどさまざまな方法があります。
本記事では、顧客ニーズの重要性から把握する方法、満たすポイントまでを詳しく解説します。
顧客ニーズとは
顧客ニーズとは、商品やサービスに対する顧客の要求や期待のことです。必要性や要求、需要などを意味する英単語の「need(s)」が語源で、問題解決や目標の達成、満たしたい欲求など、顧客が理想の状態とのギャップを抱えることから発生しています。
マーケティング活動において、顧客への価値提供につながる顧客ニーズの理解は必要不可欠です。ここからは、顧客ニーズと「ウォンツ」との違いや、顧客ニーズの中で大別される「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の違いを解説します。
ウォンツと顧客ニーズの違い
顧客ニーズと似た用語として、「ウォンツ」があります。顧客ニーズが「目的」であるとすれば、ウォンツはそれを達成するための「手段」や「解決方法」です。ニーズを満たすために、特定の商品やサービスを必要とする状態といえます。
たとえば、「仕事の効率を上げたい」というニーズがある場合、「高性能のパソコンが買いたい」「デジタルツールを導入したい」というウォンツが発生するでしょう。
ウォンツは、上記のような手段としての「基本ウォンツ」をはじめ、「条件ウォンツ」「期待ウォンツ」があります。
条件ウォンツは、基本ウォンツに具体的な条件を加えた要求で、「デジタルツールを導入したい」という基本ウォンツに、さらに「画面操作が簡単なデジタルツールを導入したい」という条件が加わります。
期待ウォンツは、満たされることが当然のものとして期待される要求を意味します。たとえば、デジタルツールであれば「エラーがなくスムーズに作動する」ことは、誰もが当然のように期待することであり、期待ウォンツといえるでしょう。
ウォンツもニーズと同じように、顧客の購買行動のモチベーションとなる重要な要素です。
顕在ニーズと潜在ニーズの違い
顧客ニーズは、顧客自身がニーズとして自覚している「顕在ニーズ」と、自覚していない状態の「潜在ニーズ」に大別できます。たとえば、管理職が職場で人的な作業に時間がかかることから、「業務の効率を上げたい」と考えるのは顕在ニーズです。
しかし、この管理職が業務効率を上げたい本心には、「顧客と向き合う時間を増やしたい」という思いがあるかもしれません。その場合、顧客ごとにマーケティングを最大化できるMAや、顧客と交流できるオンラインコミュニティも有効でしょう。
このような無意識に隠された不満や、理想とのギャップが潜在ニーズです。潜在ニーズを掴み、効果的な提案やアプローチを行うことで、顧客の購買意欲をより高められます。
顧客ニーズを把握する重要性
顧客ニーズを把握することで、購買意欲を喚起する施策に活かして受注につなげることができます。また、購入後の適切なアプローチにより顧客満足度やLTVを向上させることができるでしょう。
以下では、顧客ニーズを把握する重要性について詳しく解説します。
顧客の購買意欲を喚起し受注につなげられる
顧客ニーズを把握することで顧客に対して適切な施策を実施できるため、購買意欲を喚起し、受注につなげられます。
顧客ニーズを理解したアプローチは、接客や商談など直接的な営業活動をはじめ、広告やブランディングといったマーケティング活動からも購買行動を後押しできます。
顧客ニーズを把握するためには、顧客がどのような理想を持っており、理想の実現にあたり何が課題となっているかを調査・分析することが必要です。
顧客満足度やLTVの向上につなげられる
顧客ニーズを正しく理解した商品・サービスは、顧客満足度やLTVの向上につながります。
購入後も顧客ニーズに寄り添った継続的なアプローチや、契約後のアフターフォローなど価値提供を続けることで、顧客が自分のことを「理解してもらえた」と感じ、長期的な利用になりやすいでしょう。
また、より高価なものに移行するアップセルや、関連商品も組み合わせて購入するクロスセルなどの向上も期待できます。契約後や購入後も、トレンドや顧客ニーズの変化を的確に捉えて効果的なアプローチを行うことが大切です。

自社でできる顧客ニーズを把握する5つの方法
顧客ニーズを把握する方法には、以下のような取り組みや分析方法があります。
- ペルソナ作成
- カスタマージャーニーマップ
- RFM分析
- CTB分析
- 競合分析
これらをもとに顧客ニーズを正しく理解することで、戦略的なマーケティング活動や、購買意欲につながる営業活動に活かせるでしょう。
自社で取り組めるため、コストが抑えて実行できる点がメリットです。一方、手間がかかったり、精度の高い結果が得られなかったりするリスクもあります。
それぞれの方法のメリット・デメリットを解説します。
1.ペルソナ作成
ペルソナとは、商品・サービスの具体的なユーザー像であり、顧客ニーズを把握する上で効果的な方法です。ペルソナ作成では、性別や年代、職業などに加え、年収、家族構成、現在の悩みなど具体的な一人の人物として詳細に設定します。
ユーザーの解像度を高めることで、いつ・どのような場面で課題を感じ、課題を解決するためにどのような行動や意思決定を行い、商品・サービスの利用につながるかをイメージしやすくなります。
以下では、ペルソナ作成のメリットとデメリットについて解説します。
ペルソナ作成のメリット
ペルソナを作成すると、顧客ニーズや行動パターンを深く理解できるため、マーケティング施策の成功率を高められるメリットがあります。ペルソナの目線に立つことで、顧客ニーズを正確に把握しやすくなり、実際の消費者にマッチした施策を立てられるためです。
また、作成したペルソナは商品・サービスに関わる社員間で共有することで、共通認識を持ち、スムーズに連携が取れます。それぞれが一貫した顧客ニーズの把握に努めることで、消費者に響く商品・サービスの開発につながるでしょう。
ペルソナ作成のデメリット
ペルソナ作成し、人物像が絞り込まれることで、新しい視点が生まれにくかったり、変化する顧客ニーズを想像しづらくなったりするデメリットがあります。新しいアイデアや大胆な発想が求められる場合は、ペルソナを使った手法が適さない場合があるかもしれません。
また、効果的なペルソナを作成するためには、市場調査やインタビューなどで情報収集を行うことが大切です。情報収集には時間やコストがかかるため、ペルソナを作成する目的を明らかにした上で慎重に取り組む必要があるでしょう。
自社の商品・サービスを利用してくれる適切なペルソナを作成するためには、顧客との継続的な接点を構築し、顧客心理や使用実態を収集する仕組みを構築することも必要です。
「coorum」(コーラム)は、顧客との継続的な接点を構築し、顧客分析ができるサービスです。coorumで自社が把握しきれていない顧客の実態を把握することで、適切なペルソナを作成することができます。
2.カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップとは、顧客が自社の商品やサービスの存在を発見してから、購入に至るまでのプロセスを、時系列に沿って図式化したものです。
カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客目線での購買プロセスを可視化できるため、顧客の抱える課題や悩みを発見しやすくなります。以下では、カスタマージャーニーマップのメリットとデメリットについて解説します。
カスタマージャーニーマップのメリット
カスタマージャーニーマップを作成することで、フェーズごとの顧客ニーズに応じたアプローチがしやすくなるメリットがあります。認知から購入に至るまでのプロセスごとに、自社と顧客がどのように関わるのか認識し、顧客ニーズを整理できるためです。
また、カスタマージャーニーマップを活用することで、それぞれのプロセスにおける問題点や課題を客観的に捉えられます。優先度の高い課題が明らかになることで、新たな施策や改善策などをスピーディに実行でき、顧客ニーズを満たすことにつながるでしょう。
カスタマージャーニーマップのデメリット
カスタマージャーニーマップは、顧客のネガティブな反応を想定しにくいという懸念点があります。作成する側は、理想的な顧客行動を想定することで問題点が明確化できず、課題解決につながらないことも考えられます。
カスタマージャーニーマップを活用するためには、購入に至らない場合のパターンまで考え、顧客が言語化できない潜在ニーズまで深く掘り下げる必要があるでしょう。
3.RFM分析
RFM分析は、「Recency (直近の購入日)」「Frequency (購入頻度)」「Monetary (購入金額)」の3指標で顧客をグループ分けする手法です。
購入実績のある顧客の中でもそれぞれの傾向を把握し、顧客ニーズに応じた的確なアプローチができます。以下では、RFM分析のメリットとデメリットについて解説します。
RFM分析のメリット
RFM分析は、それぞれの顧客層へのアプローチ方法にメリハリをつけられるメリットがあります。
たとえば、グループ分けした中で購入頻度が高くても購入金額が低い顧客は、購買力が不足していると考えられるでしょう。その場合、低価格帯の商品への誘導や、サービスの提案をするなどのアクションができます。
離反顧客に費やしていた費用を優良顧客や見込み顧客に充てるなど、経営の見直しも可能です。マーケティング施策の費用対効果を高め、収益の最大化につながるでしょう。
RFM分析のデメリット
RFM分析は購買行動をもとに分析するため、顧客の背景までは想像しにくく、ライフステージの変化までは把握できないデメリットがあります。学校の卒業や就職、結婚などにより、施策の効果が充分に発揮されないこともあるでしょう。
複数の分析方法と併用したり、別の角度から顧客を分析したりなど、表面的な結果にとらわれないことが大切です。
4.CTB分析
CTB分析とは、「Category(カテゴリ)」「Taste(テイスト)」「Brand(ブランド)」の3指標で顧客を分類・分析し、購買行動を予測する手法です。
顧客の趣味嗜好への理解を深めて各施策に活用したり、潜在顧客を発見してアプローチにつなげたりできます。以下では、CTB分析のメリットとデメリットについて解説します。
CTB分析のメリット
CTB分析は、顧客行動や嗜好、ニーズを深く理解することで、特定のグループの顧客に響きやすいマーケティング施策を考えやすくなるメリットがあります。既存顧客のリピート率を高めるだけでなく、同じ属性の新規顧客の獲得も期待できるでしょう。
また、時系列にデータを分析することで、トレンドや顧客ニーズの変化をタイムリーに把握し、施策の見直しなど柔軟に対応できます。
CTB分析のデメリット
CTB分析は、単一の商品・サービスでは充分な効果を得られないデメリットがあります。顧客と行動や好みなどを結び付けるためには。複数の商品・サービスを横断した分析が必要です。
広いカテゴリを分析することで、把握できる顧客ニーズの精度も高まるため、なるべく多くの商品・サービスに対しする実施が求められます。その分、時間と手間もかかるでしょう。
5.競合分析
競合分析は、自社と似た顧客ニーズを満たす商品・サービスを取り扱う競合他社を調査し、分析する手法です。
競合他社の商品・サービスの特性をはじめ、企業戦略、強み・弱みなどを評価し、自社と比較します。他社の施策やその効果を分析することで、自社の課題の把握にもつながるでしょう。以下では、競合分析のメリットとデメリットについて解説します。
競合分析のメリット
競合分析は、市場のトレンドや顧客ニーズを踏まえながら、客観的に自社の現状や強み・弱みを理解できるメリットがあります。自社の競争優位性や課題を把握して、効果的な戦略の立案や商品・サービスの改善に役立てることが可能です。
また、競合分析を通して競合他社の動きや市場の変化に素早く気づくことで、顧客が他社に流動するなどのリスクを抑え、柔軟に施策の見直しができます。
競合分析のデメリット
競合分析のデメリットは、分析前に必要な競合調査に手間がかかることです。とくに、競合他社
が多い場合には調査の対象が増えるため、膨大な時間が必要となるでしょう。
また、顧客ニーズの把握に活かすためには、競合他社の顧客がどのような課題を抱え、どのような点に魅力を感じて利用に至ったかまで細かく調査する必要があります。

顧客の声から顧客ニーズを把握する5つの方法
顧客の声から顧客ニーズを把握するためには、以下の方法が有効です。
- インタビュー
- アンケート調査
- ソーシャルリスニング
- NPS調査
- 行動観察調査
目的や課題、ビジネス形態によって、適切な方法は異なります。精度を高めるために、複数の調査方法の併用や、調査会社に依頼するなど、自社に合った適切な方法を取ることが大切です。
調査会社に依頼する場合、自社にかかる手間を省ける一方、自社にデータを蓄積できなかったり、頻繁に実施できなかったりする懸念があります。
それぞれの方法のメリット・デメリットを紹介します。
1.インタビュー
インタビューは、自社の商品やサービスを利用中の顧客と直接対話し、具体的な意見や感情、情報などを詳しく聞き取る方法です。
対面でヒアリングすることで、ニーズが探れます。また、顧客の話を深掘りしたり、別の角度から質問をしたりなど、柔軟に顧客の声を聞き出すことも可能です。
インタビューには、座談会形式で複数の対象者に話を聞くグループインタビュー、1対1のデプスインタビュー、Web会議サービス使って実施するオンラインインタビューがあり、調査の目的や必要な情報の種類に応じて使い分けをします。
以下では、インタビューのメリットとデメリットについて解説します。
インタビューのメリット
インタビューは、顧客の感じた価値体験や心情の変化などの定性的な情報を収集できるため、的確にニーズを取り入れた施策を講じやすくなるメリットがあります。
顧客が何を求め、商品・サービスにどのような魅力を感じて購入に至ったかなど理解が深まり、潜在ニーズを引き出すことにもつながるでしょう。
定量的な調査とは違い、数字では表せない顧客の声を拾うことにつながるため、アンケート調査などを併用して顧客ニーズの解像度が高まります。また、調査結果をもとにした商品・サービスの改善による、リピーターの獲得も期待できます。
インタビューのデメリット
インタビューのデメリットは、対象者の選出やインタビューの実施、データの比較や分析などに時間や手間がかかることです。とくに、デプスインタビューの場合は、一人あたりの時間が長くなります。
また、インタビュアーの技量によって調査結果が変動することも懸念点です。自社でのインタビュアーの育成や調査会社への依頼など、実施方法を慎重に決める必要があります。
インタビューの対象者の選出や実施についてもコミュニティが活用できます。コミュニティを運営し、顧客の声を聞く基盤を作っておくことで、インタビューも円滑に実施できるでしょう。
「coorum」(コーラム)では、顧客自らが心理や使用実態を発信する仕組みを備えているため、質の高い顧客の声を拾えます。顧客のニーズの変化をスピーディに把握し、施策へ反映できます。
2.アンケート調査
アンケート調査は、商品・サービスに関するフィードバックを、顧客から直接収集する方法です。Webアンケートや紙での調査など、さまざまな形式で実施できます。
多くの回答を手軽に集められるため、一般的な顧客の意見や傾向を把握する定量調査として便利な方法です。以下では、アンケート調査のメリットとデメリットについて解説します。
アンケート調査のメリット
アンケート調査のメリットは、自社商品・サービスに対する率直な意見や感想を把握できることです。自社が求める情報に合わせてアンケートを設計でき、ポイントを押さえた意見収集を行い、商品・サービスの改善に活かせます。
また、定期的にアンケートを実施することで、顧客ニーズの傾向や変化の把握も可能です。タイムリーに顧客ニーズへ対応し、効果的な施策を立てることにつながるでしょう。
アンケート調査のデメリット
アンケート調査は、簡単に回答できるものもあることから、表面的な回答が紛れ込んでいる可能性もあり、内容の見極めが必要となります。
また、アンケートの設計をはじめ、集計や分析には手間がかかるという懸念もあります。Webアンケートや郵送のアンケートなさまざまな種類があるため、自社に適した方法を選択しましょう。
3.ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングは、SNSやブログなどのソーシャルメディア上で、消費者の投稿や発信内容から意見を収集・分析する方法です。
市場トレンドやマスメディアの反響などから、顧客ニーズを汲み取り、今後のマーケティング活動にも役立てられます。以下では、ソーシャルリスニングのメリットとデメリットについて解説します。
ソーシャルリスニングのメリット
ソーシャルリスニングのメリットは、リアルタイムに顧客の本音を集められる点です。ソーシャルメディア上では顧客目線の発信がしやすく、表面化する前の顧客の不満の声を拾い、商品・サービスの改善につなげられます。
また、顧客の声だけではなく、現在のトレンドや市場調査などにより、消費者の潜在ニーズを発掘しやすくなるでしょう。既存顧客だけでなく、新規顧客獲得のヒントも得られるでしょう。
ソーシャルリスニングのデメリット
ソーシャルリスニングは、膨大な量の投稿の中からの情報を精査することが難しいというデメリットがあります。
また、性別・年齢などの属性が不明瞭であるため、ユーザー層の特定も困難です。匿名性の高いSNSでは、プロフィールが正しい情報ではない可能性もあるため、効果的に活用するためには信頼できる情報であるか見極める必要があります。
4.NPS調査
NPS調査は、商品やサービスに対する信頼・愛着などを示す「顧客ロイヤルティ」を測る、NPS(Net Promotor Score/ネット・プロモーター・スコア)を調査する方法です。
顧客が特定の企業や製品について他の人にどれだけ強くすすめるかを尋ね、その回答をもとに値を算出します。以下では、NPS調査のメリットとデメリットについて解説します。
NPS調査のメリット
NPS調査は、顧客満足度を可視化できるため、顧客ニーズが的確に把握できているか否かを客観的に測れるメリットがあります。明確な数値を算出できるため、専門知識がなくても理解がしやすい指標です。
また、世界共通の測定方法が整備されているNPSは、業界や企業に関係なく同じ測定方法が用いられるため、競合他社との比較もしやすいのが特徴です。NPS調査の結果を分析・活用することで自社の商品・サービスを客観的に評価し、商品・サービスの改善に役立てられます。
NPS調査のデメリット
NPS調査は、一般的な顧客満足度調査などと比較して得られる情報が少ないというデメリットがあります。自社の商品・サービスの推奨度を軸に質問が構成されるため、シンプルで顧客の回答が得られやすいものの、多角的な分析が難しい点が課題です。
また、定量調査であるNPS調査において、正確に顧客ニーズを測るためには、多くの回答が必要となります。
5.エスノグラフィー(行動観察調査)
エスノグラフィー(行動観察調査)は、調査員が消費者や既存顧客の日常生活に身を置き、行動を観察して分析する方法です。
商品・サービスの利用状況や何気ない行動・言動から潜在ニーズを調べることで、商品やサービスの開発や改善、マーケティング施策に活かせます。以下では、エスノグラフィーのメリットとデメリットについて解説します。
エスノグラフィーのメリット
エスノグラフィーは、消費者の潜在ニーズを引き出し、適切な施策のために結果を活用しやすいメリットがあります。顧客が自覚していない課題や言語化できない悩みは、インタビューやアンケートなどのヒアリングでは把握しにくいでしょう。
時間をかけて顧客を観察することで、顧客の心の深層にあるニーズを浮き彫りにできます。リアルな消費者の生活環境に触れることで、商品の課題や強み、顧客の本質的なニーズの再確認が可能です。
エスノグラフィーのデメリット
エスノグラフィーは顧客を一定期間観察し続けたり、行動を共にしたりする必要があるため、調査の難易度が高いことがデメリットです。調査員の確保や必要機材の調達など、さまざまな準備が必要であり、コストもかかります。
また、対象者のプライバシーに関する問題が発生する可能性もあります。調査目的や方法などを充分に説明して同意を得た上で、調査員は必要な配慮を怠ることなく調査を実施しなければいけません。
顧客ニーズを満たすポイント
顧客ニーズを満たすポイントとして、以下のような取り組みが挙げられます。
- 顧客一人ひとりに合わせた対応を行う
- 購入後もフォローアップやコミュニケーションを行う
- トラブル発生時は迅速かつ丁寧に対応を行う
顧客ニーズを満たすためには、戦略的なマーケティング施策はもちろん、デジタルツールを有効活用した現状の把握や、顧客視点に寄り添った業務改善なども大切です。ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
顧客一人ひとりに合わせた対応を行う
顧客一人ひとりに合わせた対応を行うことで、顧客ニーズを満たすだけでなく、特別感にもつながります。「自分のことを理解してもらえている」と感じることで、自社への愛着も高まるでしょう。
たとえば、提案メール一つでも前回購入した商品に関連するものが表示されることで、自分に合った提案を受けていると感じ、次回の購入にもつながりやすくなります。
購入後もフォローアップやコミュニケーションを行う
購入後もフォローアップやコミュニケーションを行うことで、顧客との長期的な信頼関係を築けるため、顧客ロイヤリティやLTVの向上につながります。
たとえば、購入後に電話やメールで顧客にアプローチして、利用状況や不便な点はないかといった内容を伺う方法があります。顧客の意見から商品・サービス内容を改善し、理想の実現に寄り添うことで、顧客の価値体験も向上するでしょう。
顧客と継続的に関わりをもつことは、顧客のニーズの把握に役立つだけでなく、顧客ロイヤリティの向上のためにも大切なポイントです。
トラブル発生時は迅速かつ丁寧に対応を行う
顧客ニーズを満たすためには、トラブル発生時の対応も重要です。顧客が問題に直面した際の企業の対応によって、顧客が企業に抱く印象も大きく変わります。顧客からの意見や不満の問い合わせがあった場合は、すぐに謝罪して解決策を提示したり、社員へ周知して改善策を講じたりする必要があります。
とくに、カスタマーサービスの品質を高めることで、顧客の体験価値が向上し、顧客ニーズを満たすことにつながるでしょう。顧客が不満を抱えた状態でも、迅速な対応や丁寧なサポートができれば、顧客の信頼獲得につながります。
coorumで顧客ニーズを把握しよう
顧客ニーズとは、商品やサービスに対する顧客の要求や期待のことです。顧客の購買行動につながるマーケティング施策や営業活動を実施するためには、顧客ニーズの把握が必要不可欠です。また、購入後も継続して顧客ニーズを満たすことで、顧客ロイヤリティの向上も期待できます。
顧客ニーズは、NPS調査やインタビューなどをはじめとした、さまざまな方法で調査できます。顧客ニーズに沿った施策を実施するためには、自社に合った方法を効果的に用いることが大切です。しかし、人員や機材の手配、調査のための下準備で、時間もコストもかかるという懸念もあります。
効率的な顧客ニーズの把握には、coorum(コーラム)を活用することが有効です。coorumは、顧客自らが顧客心理や使用実態を発信することを促す仕組みと、それを収集・分析可能なプラットフォームです。
また、coorumでは既存顧客の関連データとID連携できるため、解像度の高い顧客分析を行い、質の高いデータの蓄積が可能です。顧客の声やインサイトを活用した、顧客起点の商品開発により、新規顧客の獲得だけでなくLTVの最大化も期待できます。
単発的な顧客ニーズの把握ではなく、顧客との接点を継続的に持ち、顧客自らの発信で効率的かつ質の高い顧客の声で顧客ニーズを把握したい方は、coorum(コーラム)をぜひご活用ください。

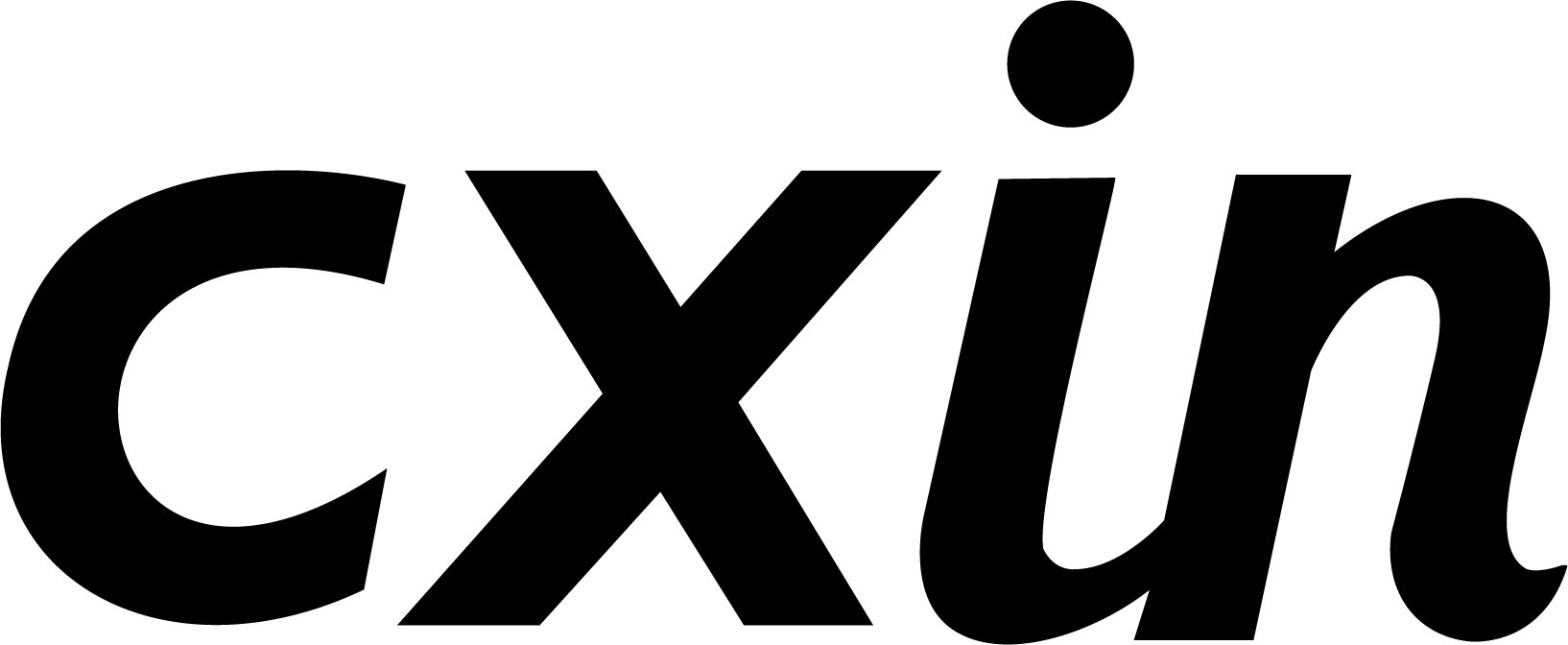

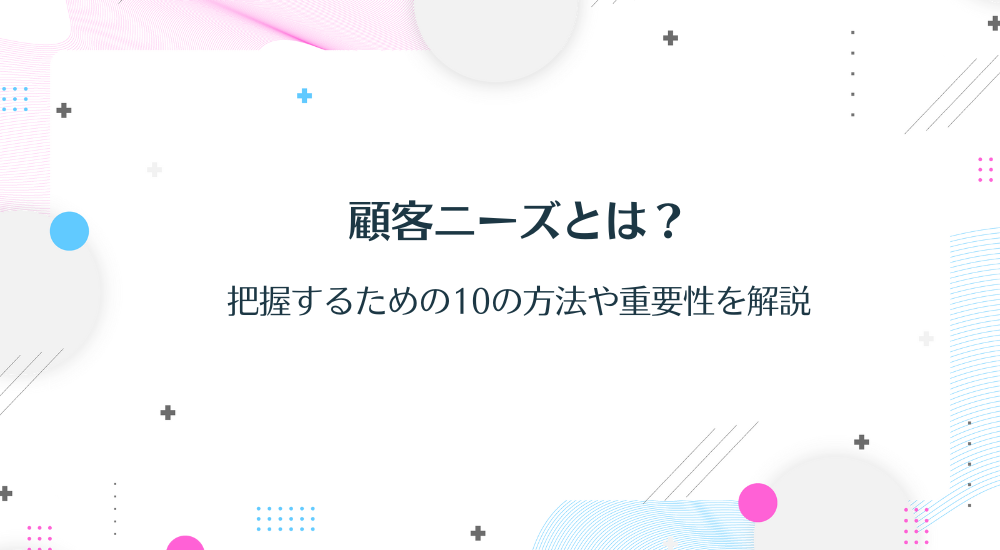
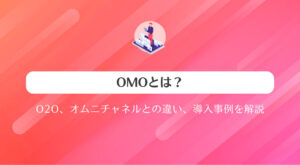


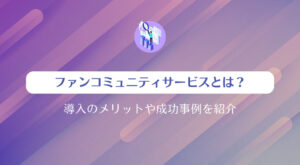
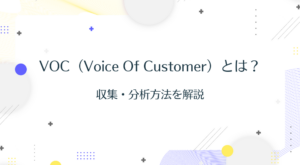
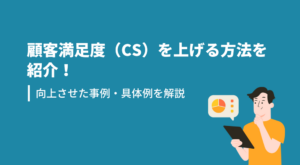
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)