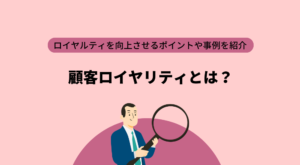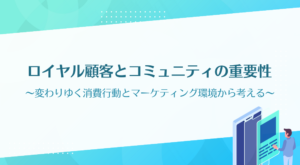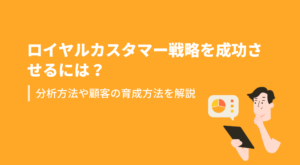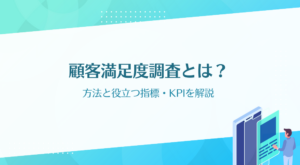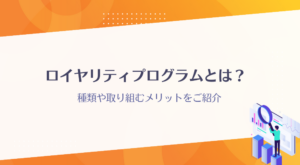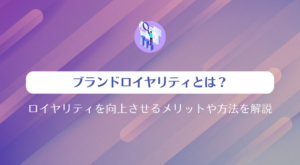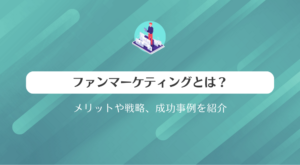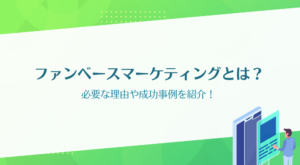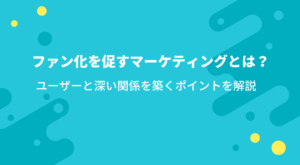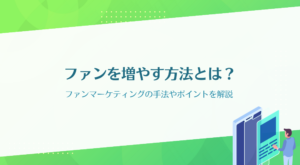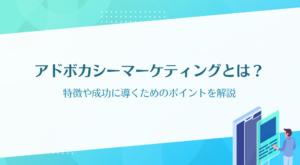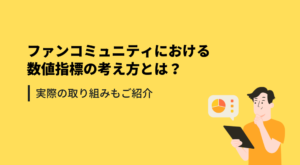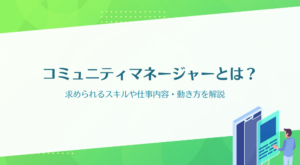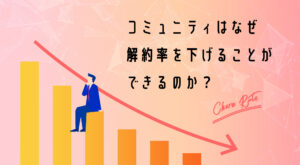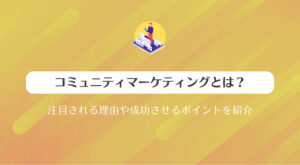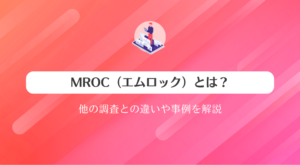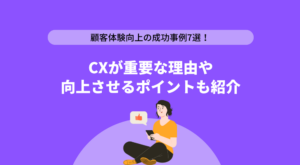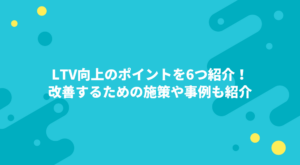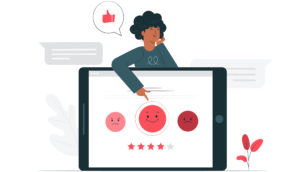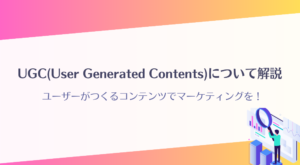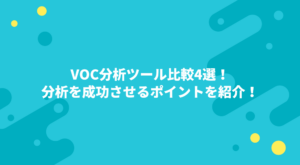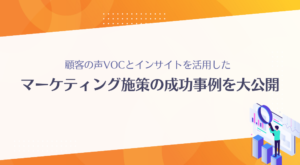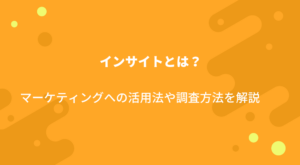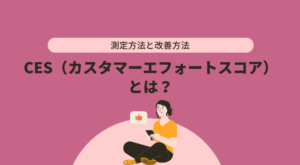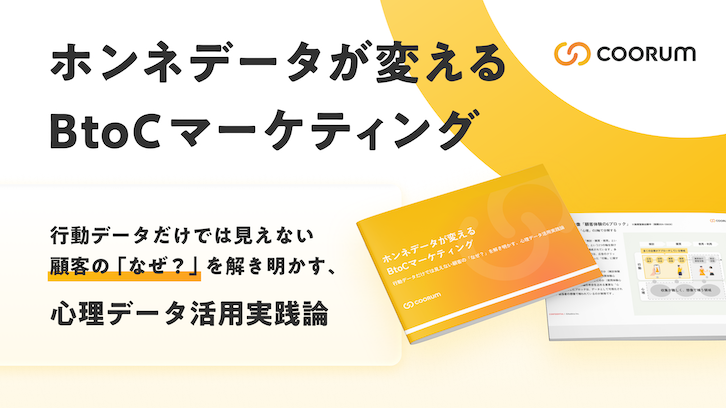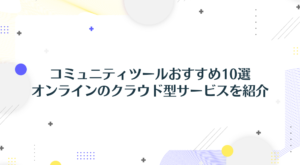
マーケティングリサーチとは、企業が抱えている課題を解決するために、様々なデータを調査することです。調査したデータを収集・分析すれば、自社商品・サービスの改善に役立てられるでしょう。
本記事では、マーケティングリサーチの概要や調査方法、実施する際の流れを解説します。マーケティングリサーチの成功事例もあわせて紹介するため、リサーチを実施する際の参考にしてください。
マーケティングリサーチとは
マーケティングリサーチとは、企業が抱えている課題の解決を目的として、調査を通して消費者のデータを収集・分析することを指します。
収集したデータを分析すれば、顧客ニーズを正確に把握することが可能です。顧客ニーズに合致した商品・サービスを提供できれば、市場での競争力を大きく高められます。
市場が成熟している現在の日本では、商品・サービスが優れているというだけでは、競合他社との競争に打ち勝つことは困難です。お客様の悩みやニーズを把握し、それを解決するための商品・サービスを展開することが、売上の最大化を図るうえで重要となるでしょう。
市場調査とマーケティングリサーチの違い
マーケティングリサーチと混同しやすい言葉に、「市場調査」があります。市場調査とマーケティングリサーチには、どのような違いがあるのでしょうか。
市場調査は、特定の市場や業界を対象にした調査のことです。過去のデータを活用し、現在の市場の規模や成長率、競争状況などを把握することを目的としています。
一方、マーケティングリサーチは市場調査のような現状の分析だけでなく、将来の市場動向や需要の予測なども目的に含まれています。そのため、マーケティングリサーチは市場調査を内包した、より広義のものといえるでしょう。
マーケティングリサーチが重要視される理由
マーケティングリサーチが重要視される理由としては、以下の3つが考えられます。
- 顧客ニーズの把握や分析につながる
- リサーチの結果を施策や商品開発に活かせる
- 他の部門や役員などの関係者の説得に活用できる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
顧客ニーズの把握や分析につながる
マーケティングリサーチを実施し、お客様の声を深く理解したうえで多角的に分析すれば、顧客ニーズを的確に把握することが可能です。顧客ニーズを把握すれば、お客様がどのような商品・サービスを求めているのかが明らかになります。
これにより、どのような商品・サービスを市場投入するべきかが明確になるため、顧客ニーズは、新規商品・サービスを開発する際の大きな判断材料となるでしょう。競合他社との競争に打ち勝つためにも、顧客ニーズを満たす商品・サービスを追求することが大切です。
リサーチの結果を施策や商品開発に活かせる
マーケティングリサーチの結果は、施策やセールス、商品開発に活かすことが可能です。リサーチで得られたお客様の声やデータを活用すれば、売上向上が期待できる企業の施策へとつなげられます。
調査で得られるお客様の声やデータからは、自社商品・サービスの現状の課題や改善点を発見することも可能です。リサーチ結果を踏まえて商品・サービスの質を改善・向上させ、売上が伸びれば企業経営の安定化にも大きく貢献するでしょう。
他の部門や役員などの関係者の説得に活用できる
マーケティングリサーチの結果は、他の部門や役員などの関係者の説得に活用することも可能です。リサーチによって客観的なデータを得ることで、関係者の説得やマーケティングの意思決定につながります。
マーケティング施策を実行するには、他の部門や役員などの関係者の合意が必要な場合も多いです。そのため、リサーチによって客観的なデータを得られる点は、施策を進めるうえで大きなメリットになり得ます。

マーケティングリサーチの具体的なやり方
次に、マーケティングリサーチの具体的なやり方について見ていきましょう。マーケティングリサーチの手法は、「定量調査」と「定性調査」の2種類に大別されます。
これらの調査は収集・分析するデータの種類が異なるため、リサーチの目的に適した手法を選択するとよいでしょう。
定量調査
定量調査は、数値化できるデータを収集・分析する調査です。結果が数字で表れるため誰でもわかりやすく、結果に説得力が出やすいというメリットがあります。
数値で表せるものの調査に向いており、実態調査や仮説検証などが目的である場合に適した調査になります。
定量調査にはアンケート調査や郵送調査などさまざまな手法があるため、それぞれの手法について詳しく解説します。
アンケート調査
アンケート調査とは、メールやSNSなどを通して調査対象者にアンケートを実施する手法です。「はい」「いいえ」による回答や5段階評価による回答など、数値化できる回答を収集します。
短時間で多くの回答を収集でき、実施が簡単でコストがかからない点がメリットです。また、アンケートツールを活用すれば、回答データの自動集計やグラフ・チャートの生成も可能になります。
質問項目を作成する際は、難しい言葉を極力使用しない、視覚的にわかりやすい画像や図を提示するといった配慮が大切です。これらの配慮により、調査対象者にかかる負荷が軽減されます。
郵送調査
郵送調査とは、調査対象者に調査票を郵送し、回答記入後に返送してもらう手法を指します。インターネットに慣れていない年齢層や、メールアドレスがわからない方を対象にする場合に有効です。
後述する訪問調査や会場調査と比較すると、低コストで実施できる点もメリットといえるでしょう。
ただし、郵送調査には回収率が低くなりやすいというデメリットがあります。調査対象者が調査票の存在自体を忘れてしまったり、返送が面倒になったりしてしまうケースがあるためです。
回収率を高めるには、調査票のレイアウトの工夫やインセンティブの提供など、調査対象者が回答しやすくなるような工夫が必要となるでしょう。
訪問調査
訪問調査とは、調査員が調査対象者の自宅を訪問してアンケートやインタビューを行う手法です。調査対象者の表情や生活環境を直接観察できる点は、アンケート調査や郵送調査にはないメリットといえます。対面で調査を行うため、高い回答率が期待できる点も大きな特徴です。
一方、交通費や宿泊費など他の調査方法よりもコストがかかる点や、調査員のスキルによって結果にばらつきが生じる可能性がある点はデメリットといえます。
訪問調査を成功させるには、入念な事前準備や調査員のトレーニングが必要となるでしょう。
会場調査(CLT)
会場調査とは、調査対象者を特定の会場に集めてアンケートやインタビューを行う手法です。調査対象者は同じ環境で調査を受けるため、外部要因の影響を最小限に抑えられます。そのため、精度の高いデータを得られやすい点がメリットです。
一方デメリットとしては、会場の確保に手間やコストがかかる点や、地理的な制約が生じやすい点が挙げられます。調査の目的に応じて、適切な会場や環境を選定することが重要となるでしょう。
ホームユーステスト(HUT)
ホームユーステストとは、試用品を調査対象者の自宅に送付し、その使用感や効果を回答してもらう手法であり、実際に商品を使用した方からの、リアルな回答を得られます。スキンケア用品やヘアケア用品など、一定期間の使用が前提となる商品でも、使用感を評価してもらうことが可能です。
ただし、商品の発送・回収にある程度のコストがかかる点や、調査対象者が途中離脱する可能性がある点はデメリットといえます。途中離脱をなるべく回避できるよう、試用品を送付する際は、詳細でわかりやすい案内書を同封するとよいでしょう。
定性調査
定性調査は、数値化できないデータを収集・分析する調査です。「なぜその商品を選んだのか?」といった、数字では把握が難しいお客様の心理や価値観を、掘り下げて把握できるというメリットがあります。
感想や意見など数値で表せないものの調査に向いており、消費者理解や改善点の発見、仮説の構築などが目的であればこちらを用いるとよいでしょう。
定性調査には、デプスインタビューやグループインタビューなどいくつかの手法があるため、それぞれの手法について詳しく解説します。
デプスインタビュー
デプスインタビューは、調査担当者と調査対象者が1対1の面談式で質問項目についてインタビューする手法です。
1対1でじっくりと意見を聞き取るため、お客様の心理や二ーズに深く迫れます。商品・サービスのコンセプト評価や、周りに人がいる状況では聞きづらい内容を聞き取りたい場合に有効です。
ただし、1対1でインタビューを行うことから、多くの回答を得るには相応の時間・コストが必要になります。また、デプスインタビューの回答はあくまでも調査対象者個人の考えのため、大多数の考えとは違う偏った意見になることもあります。
グループインタビュー・座談会
グループインタビューは、調査対象者を1つの会場に集め、座談会形式でインタビューする手法です。調査対象者は複数のグループに分けられ、それぞれのグループで司会者が調査内容に沿って進行していきます。
参加者同士で会話を交わすため、相互作用によって多様な意見や新しい視点を得られやすい点がメリットです。参加者がリラックスして発言できるような、環境を整えるとよいでしょう。
ただし、強い意見を持つ参加者がいた場合、他の参加者がその意見に影響され、参加者の意見が偏ってしまう場合があります。そのような場合は司会者が場をコントロールし、参加者全員が安心して発言できるような環境を作ることが大切です。
覆面調査
覆面調査とは、調査員がお客様を装って店舗やサービスを利用し、接客態度や営業スキルなどを評価する手法です。顧客視点でのフィードバックを得られるだけでなく、従業員のパフォーマンスをリアルタイムで評価できるため、具体的な改善案を立てやすくなります。
一方、評価が調査員の主観に依存してしまう点はデメリットです。覆面調査の存在自体が、従業員に心理的なストレスを与えてしまう場合もあるでしょう。

マーケティングリサーチを実施する流れ
課題解決が期待できるマーケティングリサーチを行うには、適切なリサーチとなるよう、実施する際の流れを把握しておくことが大切です。
ここからは、マーケティングリサーチを実施する際の流れを詳しく解説します。
1.リサーチを実施する目的を明確にする
マーケティングリサーチを実施する際は、あらかじめリサーチを実施する目的を明確にしておきましょう。目的によって、調査対象や手法などが異なるためです。
また、目的を明確にすればその後の方向性もしっかりと定まります。具体的には、「現状の課題は何なのか」「どのような調査結果が必要なのか」などを明確にすることが大切です。
スムーズに調査を行えるかどうかは、目的が明確か否かに左右されるため、マーケティングリサーチの手順の中でも特に重要な箇所といえるでしょう。
2.調査計画を作成する
リサーチの目的を明確にした後は、調査計画を作成しましょう。明確にした目的を達成できるよう、調査対象や調査手法、調査項目などを決めることが大切です。
調査対象については、見込み顧客と既存顧客どちらをターゲットにするかを決める必要があります。調査手法は、課題解決に役立つ回答が得られる手法を選びましょう。調査項目は、調査対象者が回答しやすいような項目となるよう作成してください。
3.リサーチを実施する
調査計画を作成できたら、調査計画に沿って実際にリサーチを行います。アンケートやインタビュー、商品の試用(商品を実際に試してもらい、感想や評価を回答してもらう)など、データを収集する方法は調査手法によってさまざまです。
リサーチを実施する際の注意点として、アンケート調査や郵送調査など、調査終了まで時間がかかる手法を実施する際は、調査の進捗を定期的に確認するようにしましょう。また、会場調査やグループインタビューなど、調査対象者を会場に集める必要がある場合は、予期せぬトラブルに対応できるようさまざまな状況を想定しておくことが大切です。
4.得られたデータを分析する
調査が終了したら、収集したデータを整理・分析しましょう。集めたデータをさまざまな切り口で分析することで、次の行動や施策に活かせます。
定量データの主な分析手法には、質問ごとに回答を集計・分析する「単純集計」や、2つ以上の質問項目を掛け合わせて分析する「クロス集計」などがあります。
また、定性データを分析する際の分析手法としては、インタビューの発言を端的な言葉に言い換える「コーディング」や、データを紙に書き込んでグルーピングする「KJ法」などが適しています。
5.分析したデータをもとに次の行動を決める
最後に、データ分析の結果を踏まえて、次の施策を打ち始めるか、リサーチを再度行うかを決定しましょう。
リサーチの目的を達成できそうにない場合は、再度リサーチを行います。分析結果が不十分なまま施策を進めても、想定通りの効果は得られない可能性が高いでしょう。
また、リサーチを再度行う際は、調査対象や調査項目が適切かどうかを見直すことをおすすめします。
マーケティングリサーチの成功事例
最後に、マーケティングリサーチの成功事例を紹介します。実際にどのようなリサーチを行ったのか、参考にしてみてください。
ニップンの事例
総合食品メーカーのニップンは、マーケティングリサーチや情報発信などを目的としてオンラインコミュニティを立ち上げました。
コミュニティから収集したお客様の声は、ドレッシングの開発に役立てられています。実際のお客様の声を商品開発の起点にすることで、自信を持って商品開発・提案できるようになったとのことです。
また、POPの文言を検討する際もお客様の声が活用されており、コミュニティ内で人気の高かったキャッチコピーは、そのまま商品のPOPに採用されています。
お客様の生の声が、商品開発やプロモーションの後押しにつながった好例といえるでしょう。
導入事例インタビューはこちら▼
「ニップン アマニコミュニティ」で見つけた新たな顧客像と、毎日のアマニ習慣が広がる秘訣とは?
セブンイレブンの事例
コンビニ大手のセブンイレブンは、価格訴求ではなく価値訴求に重きを置いたブランド「セブンゴールドシリーズ」を展開しています。その中でも人気の高い「金の食パン」は、マーケティングリサーチやテスト販売などを行ったうえで販売し、ヒット商品となりました。
セブンイレブンが価格訴求から価値訴求へと方向転換できたのは、「多少値段が高かったとしても品質のいいものが欲しい」という消費者が増えてきていることを、リサーチを通して確認できたためです。
消費者のニーズを知るためにマーケティングリサーチをきちんと行い、その結果に基づいた商品開発に取り組んだことが、高い成果につながっていると考えられるでしょう。
参考|PRESIDENT Online「PB商品「金の食パン」が高くても売れる理由」
アサヒビールの事例
大手ビールメーカーのアサヒビールは、当初「ダブルゼロ」というノンアルコール飲料を発売しましたが、売上は芳しくありませんでした。しかし、マーケティングリサーチを行ったうえで発売した「ドライゼロ」では、ターゲット層を変えることで売上改善につながっています。
リサーチによって、消費者が競合ブランドにどのようなイメージを持っているのか把握できたこと、シンプルなコンセプトほど多くの消費者に受け入れられる事実に気づけたことが、売上改善の大きな要因です。
十分なリサーチを行い調査データを徹底的に分析したことで、シンプルながら明快なコンセプトを打ち出せたと考えられます。
参考|ITmediaビジネスONLINE「「ドライゼロ」のヒットを導いた王道マーケティングリサーチ」
coorumでマーケティングリサーチを推進しよう
マーケティングリサーチとは、企業が抱えている課題の解決を目的として、調査を通して消費者のデータを収集・分析することです。調査によって顧客ニーズを把握できれば、商品・サービスの改善に役立てられます。
マーケティングリサーチの手法は定量調査と定性調査に大別され、収集するデータの種類はそれぞれ異なります。調査目的によって適切な手法は異なるため、実際にリサーチを行う際は実施する目的を明確にし、調査計画を作成したうえで実施するようにしましょう。
マーケティングリサーチを実施する際は、「coorum(コーラム)」の導入をおすすめします。「coorum(コーラム)」は、ロイヤル顧客やリピート顧客など、顧客セグメントごとにお客様の心理・使用実態を収集・把握できるツールです。
「coorum community」を活用すれば質の高いロイヤル顧客の声の収集が、「coorum resarch」を活用すれば、WEBサイトやアプリ上などでゲーミフィケーション型アンケートによるお客様の声の収集が可能になります。また、「coorum insight」を活用すれば、収集した顧客データの分析・可視化も可能です。
これらのサービスが内包された「coorum(コーラム)」を導入すれば、お客様とコミュニケーションをとりつつマーケティングリサーチを行って、効率よく企業の業績につなげられるでしょう。

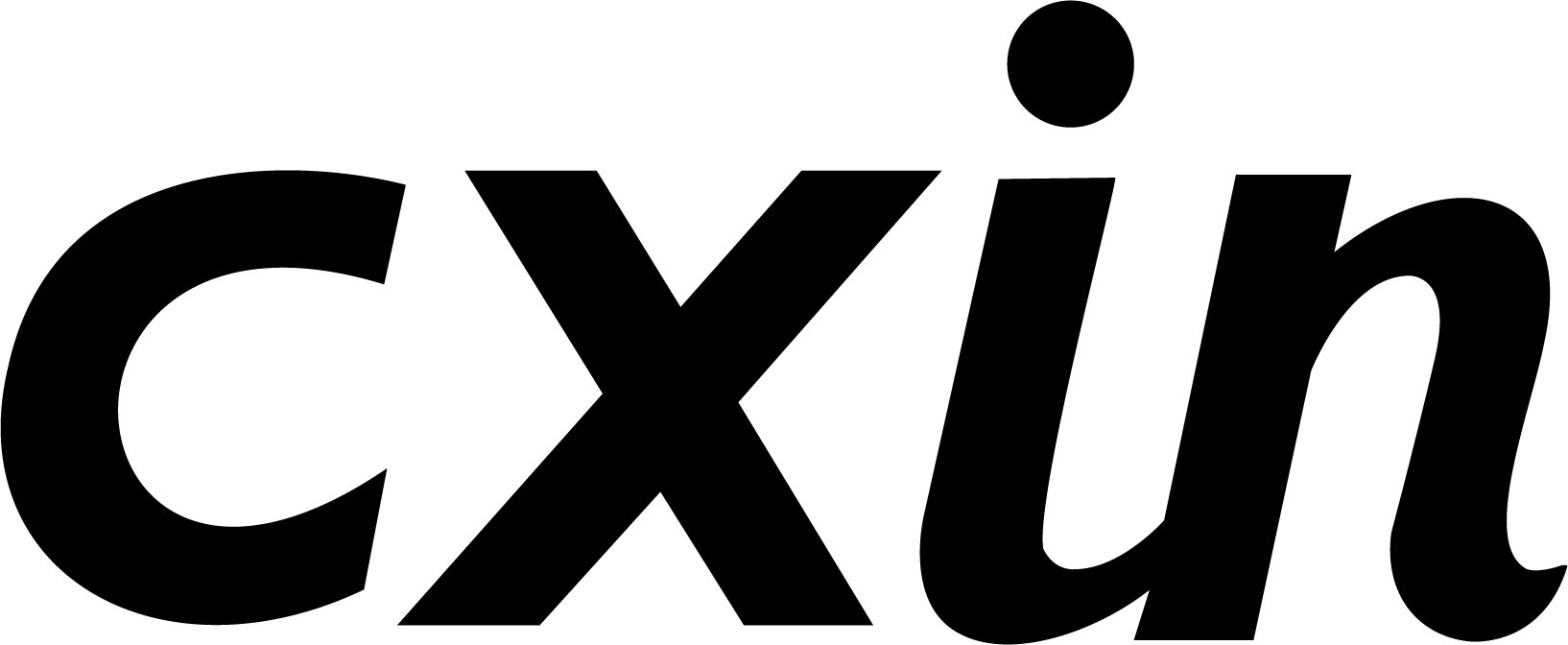

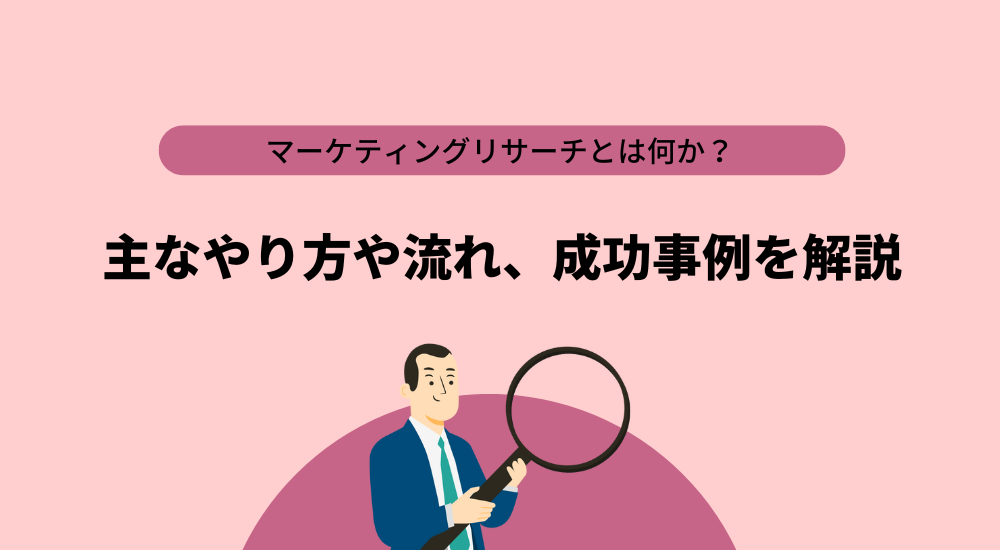
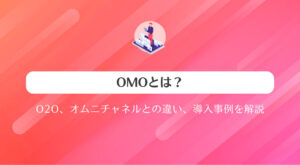


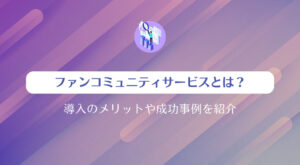
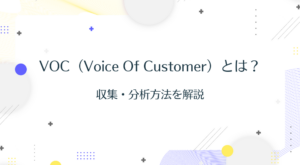
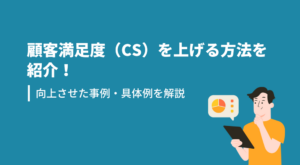
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)