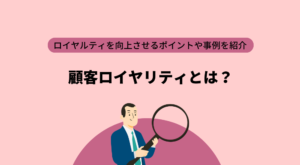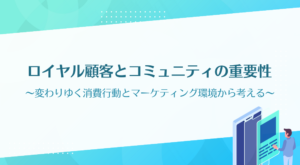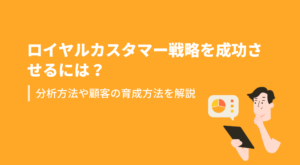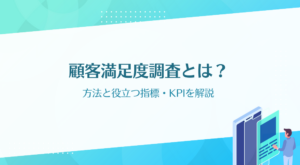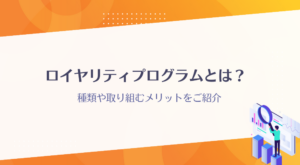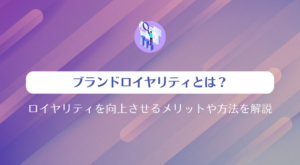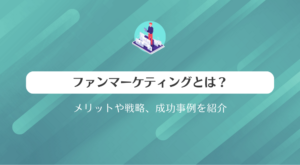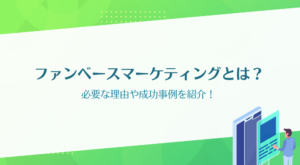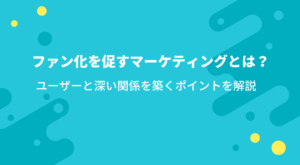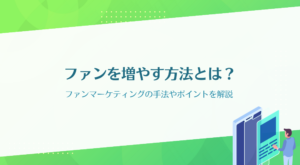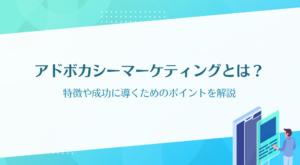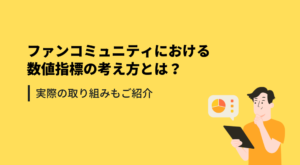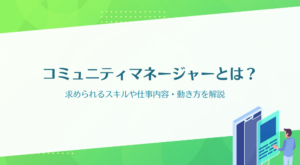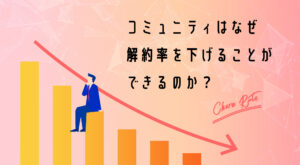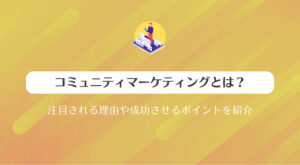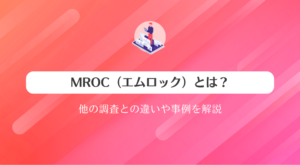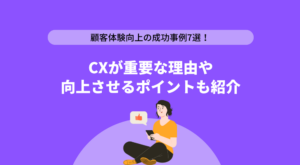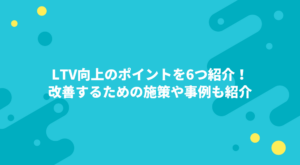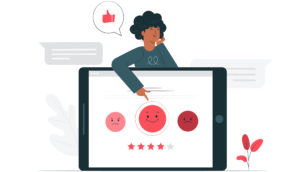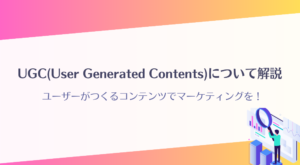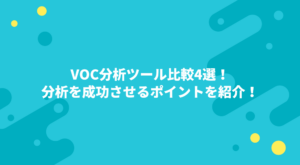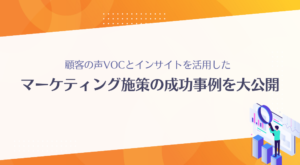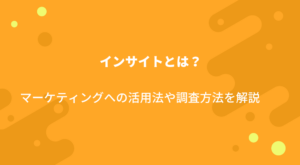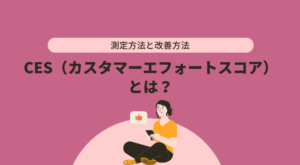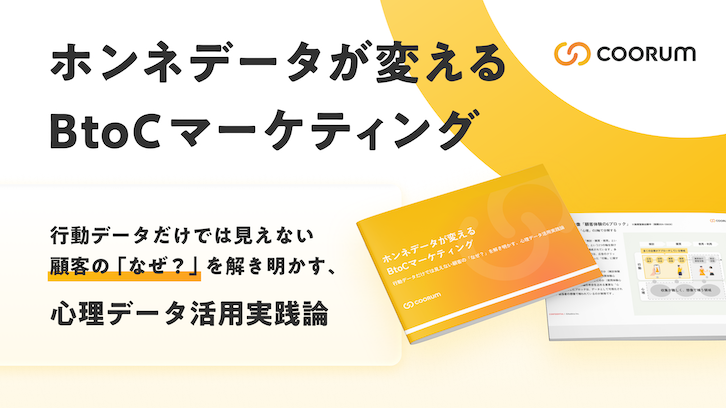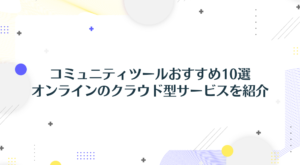
自社の商品やサービスについて、ユーザーの意見を聞く有効な方法に悩んでいませんか。ユーザーの心理や行動の理由など、より深い情報を得たい場合は、定性調査が有効です。
本記事では、定性調査の概要とメリット・デメリット、具体的な調査方法を解説します。定量調査との違いや調査時の注意点も押さえることで、より有益な定性調査ができます。定性調査への理解を深めて、ユーザーとのよりよい関係を築きましょう。
定性調査とは
定性調査とは、数値化できないものについて言葉で回答を得る調査です。対象者の感情や行動、その理由や経緯などについて詳細な情報を得られる可能性があります。
定性調査の方法の多くは、対象者とのコミュニケーションを伴うものです。ただ質問に対する回答を得るだけでなく「そう答えたのはなぜ?」「過去にどのような経緯があってそうなった?」という風に回答をさらに掘り下げた質問ができます。
こうした質問に対する回答から、企業側は対象者の深層心理や隠れたニーズを見抜ける可能性があります。
定性調査と定量調査の違い
定性調査と定量調査では、得られる回答の種類が異なります。
定性調査では、主に言葉で回答が得られます。そのため、対象者の感情や行動の理由を細かく把握できます。こうした回答は、「どうすればさらによくなるか?」についての仮説を立てるのにも有効です。
一方で、定量調査の回答は数値で集計されます。定量調査の方法は選択肢から選んで回答するアンケートが一般的であり、集計することで「人数」「回答数」「割合」などが把握できます。
「実際に〇〇と感じている人は何人いるか?」「何割の人が満足しているか?」という風に、現状や傾向を把握するのに有効です。
定性調査のメリット
定性調査には、定量調査にはない以下のメリットがあります。
- 商品へのイメージや購入の理由を把握できる
- ユーザーの心理を深掘りして聞ける
- 生の声をもとに仮説を立てられる
- 新たな商品・サービスの開発に役立つ
それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。
商品へのイメージや購入の理由を把握できる
定性調査では、対象者が商品やサービスに対する思いやその背景について質問できます。具体的には、商品・サービスのイメージや購入の理由などが挙げられます。
| 商品・サービスのイメージ例 | ・好き/嫌い・新しい ・意外/よくある ・何かと似ている ・かわいい/かっこいい/洗練されている/ほっとする など |
| 購入の理由例 | ・デザインがいいから ・使い心地 ・使い勝手がいいから ・別のものと比べて優れていると思うから ・ほかにいいと思うものがないから ・ずっと使っているから ・たまたま目についたから ・友人にすすめられたから など |
定量調査でも、上記のような選択肢を設定することでイメージや購入理由についての情報を集められます。しかし、選択肢以外の回答は得にくいでしょう。
定性調査では、以下のような感情や行動の変化を聞き取ることも可能です。
- 使う前はそれほど魅力を感じていなかったが、実際に使ってみると使い心地のよさに驚いた
- 使用感は好きだが、デザインに関しては今のものよりも前の方が好きだった
このように、対象者の感情や行動の変化について詳細な情報を得られるのは、定性調査ならではの強みといえます。
消費者の心理を深掘りして聞ける
定性調査では、対象者から得た回答に質問を重ねることで、深層にある心理を深掘りできます。
定性調査の方法は、企業側と消費者が双方向的にコミュニケーションを取れるものが一般的です。回答を得る中で「さらに知りたい」という事項について、その場でさらに質問できます。
たとえば、「好き」というイメージについて、「どれくらい好きなのか」「どのようなところが好きなのか」とさらに質問をすることで、対象者の心理をより詳細に理解できます。
「なぜそう思うのか?」という問いを繰り返すことで、対象者本人も気づいていなかったニーズや深層心理を把握できる可能性があります。
「使い心地は好きだけど、パッケージのデザインは正直あまり好みではない」「満足しているけど、すぐ使い終わるから増量版も作ってほしい」といった「好き」以外のイメージや考えを聞けることもあるでしょう。
こうした率直な声を収集する方法の1つに「coorum research」があります。coorum researchは、「coorum(コーラム)」の機能の1つであり、ユーザーに記録してもらうことで定性的な情報を集められるツールです。ユーザーが楽しみながら、手軽に記録できる仕組みを搭載しています。
「coorum research」を既存のアプリや会員基盤に実装することで、手軽にデータ収集や分析が可能です。ユーザーの心理をより深く理解したい方は、ぜひ詳細をご確認ください。
生の声をもとに仮説を立てられる
定性調査は言葉で回答を得られるため、対象者のリアルな声を把握できます。
対象者の声は、企業側が想定しているものとは異なる場合もあります。生の声を知ることで、よりニーズに合致した仮説を立てられるでしょう。
「ここを改善するとよいのではないか」「この点はあまり重視されていないのではないか」という仮説を立てた上で、実際に商品やサービスに変更を加えて検証することが大切です。
新たな商品・サービスの開発に役立つ
定性調査で得た回答は、新商品や新サービスを作るためにも役立ちます。
既存の商品やサービスについて調査をする中で「このような商品もあるといいのに」「このような悩みが気になる」という意見を得られることもあります。
こうした声を活かすことで、既存の商品やサービスを改善するだけでなく、新たな商品やサービスを開発することも可能です。

定性調査のデメリット
定性調査には多くのメリットがあるものの、以下のデメリットもあります。
- 網羅的な結果は得られない
- 結果がモデレーターの技量に左右されやすい
それぞれのデメリットを詳しくみていきましょう。
網羅的な結果は得られない
定性調査は時間やコストがかかり、対象者の負担も大きくなるため、定量調査に比べると網羅性に欠けるといえます。
定性調査では、対象者の話を聞いたり行動を観察したりする方法が一般的です。一方、定量調査ではオンラインで一斉にアンケートを取るといった方法が可能です。
いずれも対象者全員からの回答を得られるわけではありませんが、定量調査よりも定性調査の方がハードルが高く、広く回答を得ることは難しい傾向にあります。
また、定性調査では、対象者一人ひとりの感情や考えを深く聞き取ることができる反面、対象者の主観的な要素が強い回答となるため、定性調査の結果をもって対象者全体の声とすることは難しいでしょう。
言葉で回答してもらう定性調査は、選択肢から選ぶことで回答できる定量調査と比べると対象者に負担がかかります。面倒に感じて答えてもらえない可能性があることも、デメリットです。
すべての対象者の声は得られなくても、思いや行動の理由とともに対象者自身の情報を得られれば、対象者についてより深く理解できるでしょう。
「coorum(コーラム)」の機能の1つである「coorum community」を利用してコミュニティを運営することで、ユーザーはコミュニティ内で心理状態や使用感などについて発言できます。発言内容だけでなく、ヘビーユーザーやリピーター、使い始めて間もないユーザーなど「発言したのはどのような人か」まで把握できます。
すべてのユーザーをカバーできなくても、ユーザーのセグメント別に情報を細かく管理することが可能です。
気軽に発言してもらえる環境を整えることで、定性調査のハードルの高さをカバーしつつ、定性的な情報を集められます。ユーザーからの生の声を広く集めたい方は、「coorum community」を活用したコミュニティの運営を検討してはいかがでしょうか。
結果がモデレーターの技量に左右されやすい
インタビュー形式の定性調査の場合は、司会者として進行するモデレーターの技量によって結果が変わる可能性があります。モデレーターの質問の仕方や、場の雰囲気の作り方によって、意見の出方が変わってくることもあるでしょう。
モデレーターが変わっても、調査結果にブレが生じないようにすることが大切です。モデレーターに対して研修を実施したり、インタビューのマニュアルを整備したりすることで対策を行いましょう。
定性調査の手法と活用例
定性調査には、主に以下の方法があります。
- グループインタビュー
- デプスインタビュー
- 行動観察調査(エスノグラフィ)
- MROC(エムロック)
以下ではそれぞれの手法の特徴と活用例を紹介します。
グループインタビュー
グループインタビューは、複数の対象者を集めて意見を聞き取る方法です。モデレーターの進行のもと、対象者に自由に発言してもらいます。
グループインタビューは、限られた時間の中で複数人の声を聴ける効率的な方法です。発言の内容だけでなく、話の流れや対象者同士の関係性から読み取れる情報もあるでしょう。
対象者をセグメントに分けてグループインタビューを行い、セグメントを比較することも可能です。
- 例:化粧品のユーザーを複数人集めて、使用感や好きな点などについて意見を交わしてもらう。
複数のユーザーの思いや意見を聞く方法として、「coorum research」があります。オンラインでユーザーの声を収集・分析できるため、グループインタビューのように対象者を1か所に集める必要がありません。
企業側・ユーザー側の両方に負担の少ない方法で定性調査をしたい場合は、ぜひ「coorum research」の利用をご検討ください。
デプスインタビュー
デプスインタビューでは、モデレーターと対象者が1対1で話すことで意見を聞き取ります。
- 例:食材の宅配サービスを利用している顧客にインタビューを行い、気に入っている点や改善してほしい点を聞く。数ある類似サービスの中でなぜ自社を選んだのかといった深い内容についても質問を重ねる。
1人の話に集中できるため、深い内容まで聞き取れる方法です。ただし、一度に複数人の意見を聞けるグループインタビューと比較すると、デプスインタビューは時間がかかる点に注意が必要です。
デプスインタビューについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
行動観察調査(エスノグラフィ)
行動観察調査(エスノグラフィ)は、対象者の行動を観察する方法です。具体的には、対象者の買い物に同行する、自宅へ訪問して商品やサービスの使い方を見るなどの方法で行います。
- 例:サイトを改善するために、調査対象者に実際にサイトを使ってもらい、閲覧する順番や時間などを観察する。
行動観察調査には、企業側が想定している使い方をされているか確認できるほか、対象者の無意識な行動の癖を知れるなどのメリットがあります。対象者の行動そのものが調査結果です。その場で気になった行動があれば、すぐに質問できることもメリットといえます。
MROC(エムロック)
MROC(エムロック)は、対象者をインターネット上のコミュニティに所属させて行う調査方法です。コミュニティ内の発言や所属メンバー同士のコミュニケーションから、対象者についての情報を収集します。
- 例:飲食店がオンラインコミュニティを運営し、店舗では拾いきれないお客様の意見をコミュニティ内のユーザーとのやり取りから集める
インタビューや行動観察調査とは異なり、長期的に情報を収集できる点がメリットです。
MROCの実施には「coorum(コーラム)」が活用できます。「coorum(コーラム)」では、機能の1つである「coorum community」を活用したコミュニティの運営を通して、ユーザーの声を広く集められます。
投稿や発言の機会を継続的に設けられるため、単発のリサーチの機会を設ける必要がありません。MROCを実施したいとお考えの方は「coorum(コーラム)」をぜひご活用ください。
また、MROCについてさらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

定性調査を行う際の注意点
定性調査を行う際には、以下の注意点を理解しておきましょう。
- 定量調査と組み合わせて行う
- 対象者を選定する必要がある
- 調査結果は言葉で残す
効果的な調査を行うためのポイントを、それぞれ詳しく解説します。
定量調査と組み合わせて行う
定性調査を行う際は、定量調査を組み合わせることでより有益な調査結果を得られることがあります。
定性調査でも定量調査でも、すべての顧客・見込み顧客に調査を行うことは難しいものです。しかし、2つの調査を組み合わせることで効率的な調査ができます。
たとえば、新たな市場開拓をしたい場合は、まずターゲット層の数名にインタビュー(定性調査)を行うことで、ニーズの仮説を立てられるでしょう。その上で、より多くの人に対してアンケート(定量調査)を取ることで、多くの人が自社に求めることを効率的につかめます。
商品のユーザーに対して、改善してほしい点についてアンケート(定量調査)を取り、多かった意見について数名にデプスインタビュー(定性調査)を行うという方法もあります。
知りたい情報に合わせて、手法を柔軟に選び、組み合わせることが大切です。
対象者を選定する必要がある
定性調査では、調査できる人数が限られているため、対象者を選ぶ必要があります。少ない人数への定性調査で核心をついた回答を得るために、適切な対象者を選定しましょう。
選定のポイントは、自社が聞きたいことについて具体的に答えてもらえるか、自社が想定しているターゲットと合致しているかなどが挙げられます。商品やサービスについてのイメージ・使い方について変化があった人に、その経緯を聞くことも有効です。
調査結果は言葉で残す
定性調査の結果は割合や数値でまとめてしまうのではなく、言葉で残しておきましょう。
対象者からの言葉は大切な情報です。意見が少数だからといって、重要性が低いとは限りません。無理に数値化することで、大切なニーズを見落としてしまうことも考えられます。
あとから振り返っても詳細な内容がわかるよう、調査結果は言葉のままで残しておきましょう。
定性調査にcoorumを役立てよう
定性調査とは、対象者の感情や行動の理由、背景などについて把握できる調査方法です。調査結果は数値ではなく言葉であるため、対象者の心理やニーズについてより深く把握できます。
顧客の生の声は、商品・サービスの改善や開発に役立てられます。具体的な調査方法は、個人や複数の人を対象とするインタビュー・行動観察、ユーザーのコミュニティを活用したMROCなどです。
「coorum(コーラム)」では、手軽に楽しみながら情報を収集できる仕組みを活用し、ユーザーの声を広く集められます。継続的に情報を集められるだけでなく、発言したユーザーとそのセグメントを結び付けて管理することも可能です。
インタビューや行動観察のように手間をかけることなく、ユーザーの背景情報も含めた生の声を集められます。効率的に多くのユーザーの声を集めたい方は、ぜひ「coorum(コーラム)」の利用を検討してみてください。

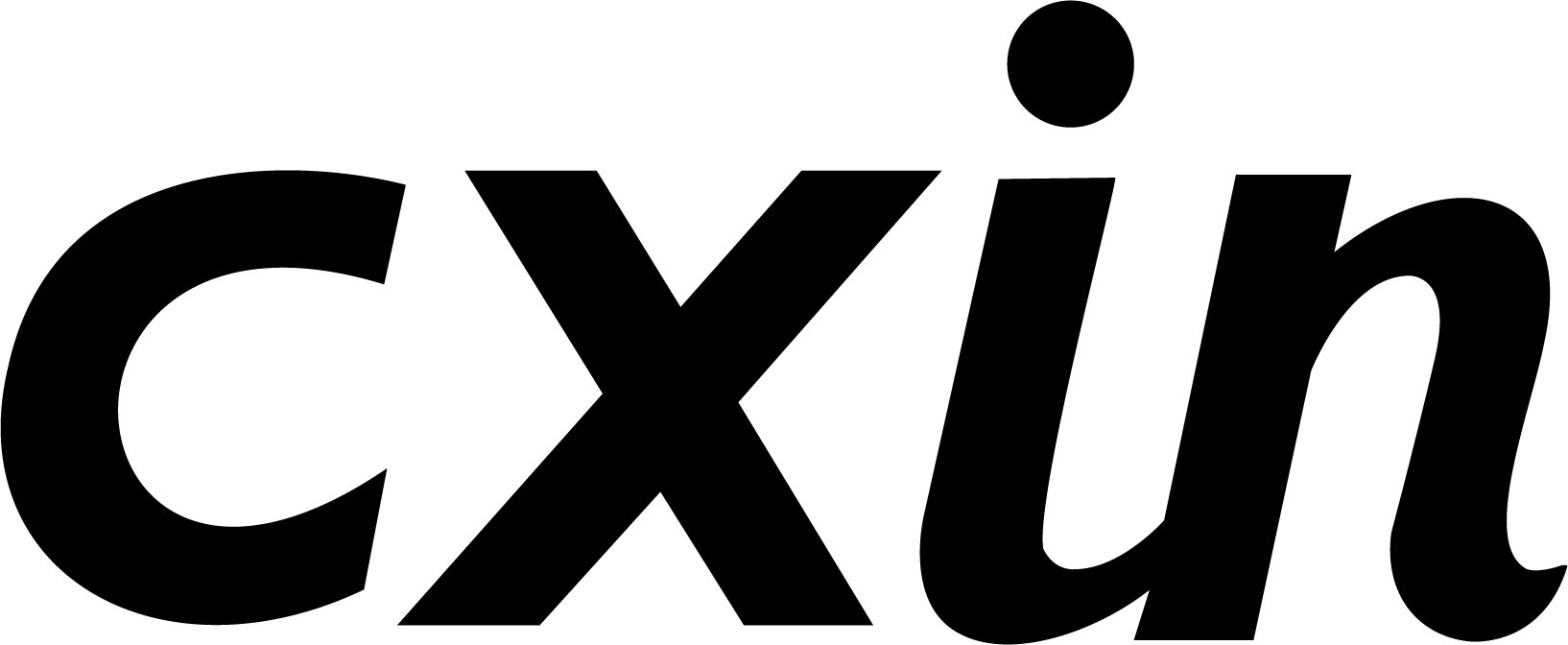

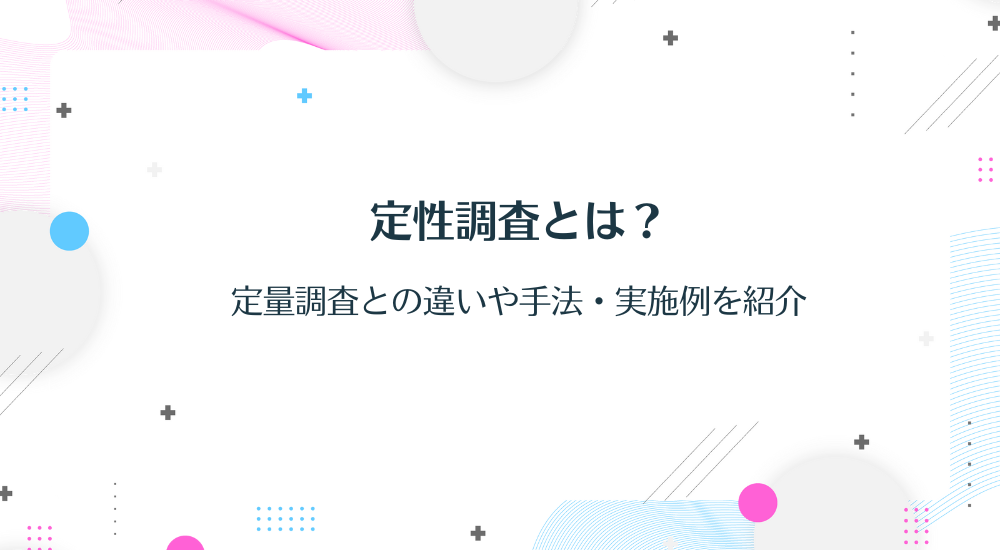
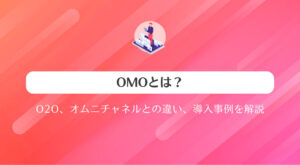


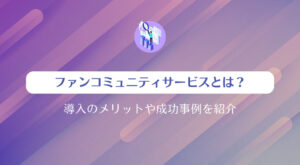
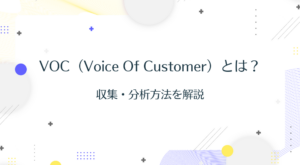
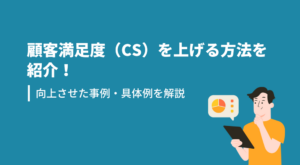
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)