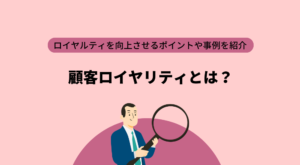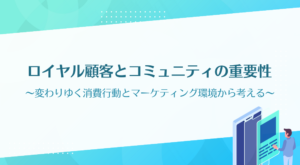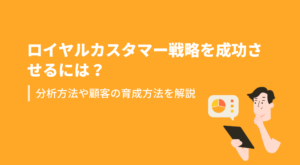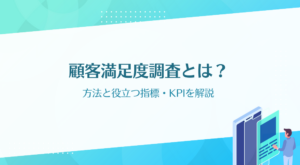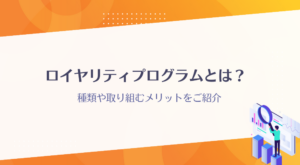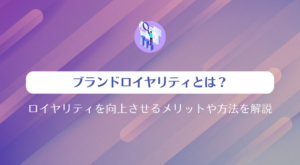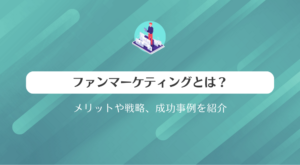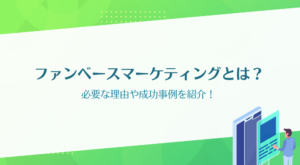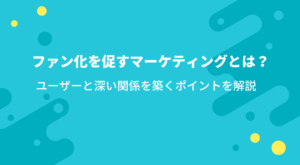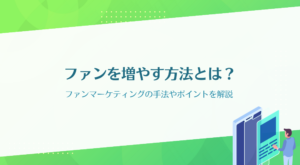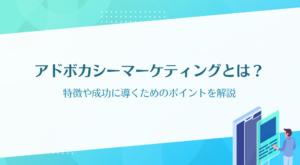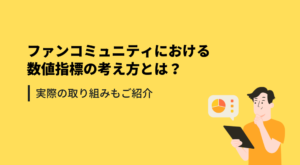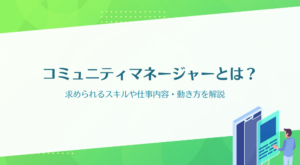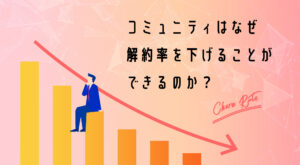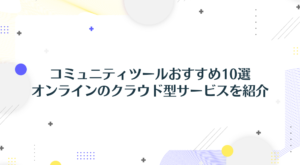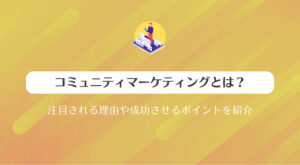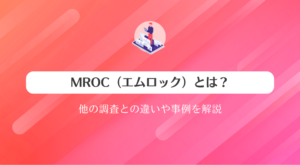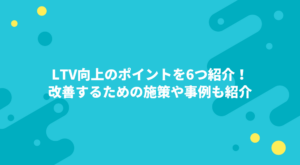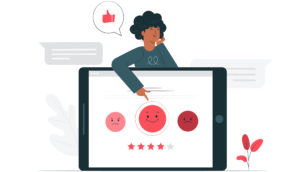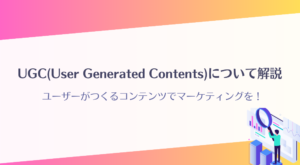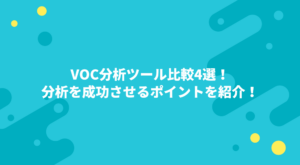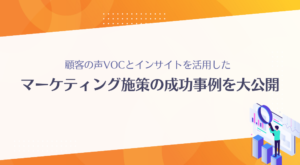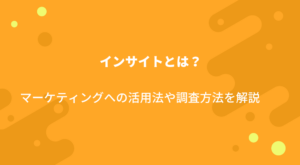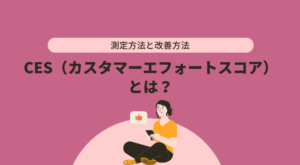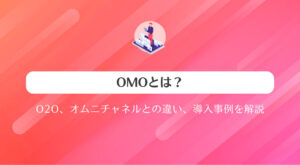
CX(カスタマー・エクスペリエンス)は、商品の購入だけでなく購入前後を含めた商品にまつわる顧客の体験のことをいいます。顧客がどのような感情的価値を抱いているのかに注目し、分析や改善を行うことでCXの向上を図ることができます。今回はCXとUXの違いや、CX向上によるメリット、改善方法や取り組み事例をご紹介します。
CX(カスタマーエクスペリエンス)の意味とは?
CX(カスタマー・エクスペリエンス)は商品やサービスを購入し、使用、購入後に必要なフォローアップまでの過程における体験にフォーカスを当てるマーケティング手法です。良い体験を提供するだけでなく、「商品やブランドに対しどのような感情を抱いているのか」という顧客の感情に注目して施策や改善を行うのが特徴です。
製造技術の発展に伴い、商品そのものの価値だけでは他社との差別化が難しくなっている現状を踏まえ、商品の価値に加えて「感情的な価値」を提供し、差別化を図ろうという狙いがあります。
なお日本語では「顧客経験価値」「顧客体験価値」と表現されます。

UX(ユーザーエクスペリエンス)との違い
UX(ユーザー・エクスペリエンス)は商品やサービスを利用した、そのときに得られる顧客の体験のことを指します。つまりCXが購入からアフタフォローまで含めた体験価値を指すのに対し、商品やサービスを使用する一点に着目するのがUXであるという違いがあるのです。
また、UXでは単一の商品やサービスに着目するため、デザイナーやエンジニアなど商品やサービスそのものに携わっているスタッフと連携することで改善に取り組めますが、CXは関連するフローが多いため、デザイナーやエンジニアはもちろん、販売スタッフやコールセンターのスタッフ、外部のリソースを利用する場合が多い流通に至るまで幅広い視点が求められます。
いち商品の域を超え、経営戦略や顧客戦略にも影響を与えるため、CX対策に取り組む専任のチームを設けたり、外部のコンサルティング会社のサポートを受けたりして、慎重に取り組むべきでしょう。
カスタマージャーニーとの違い
カスタマージャーニーとは、顧客の思考や取るであろう行動を時系列で記載するフレームワークのことです。顧客が商品・サービスを購入する前に何を検討するか、どのようなアクションをするかを全て書き出し、顧客の体験改善や販売に活かします。
なお、カスタマージャーニーを書き出すには、顧客をモデル化した「ペルソナ」を設定することが必要です。ペルソナを具体的に描くことで、カスタマージャーニーも具体的に描けるようになります。
カスタマーサクセスとの違い
カスタマーサクセスとは、顧客の成功をサポートすることを主軸とした営業手法・マーケティング手法のことです。どのような行動が顧客の成功につながるのかを分析し、数値として評価することで、顧客の成功に寄与した度合いを表示します。
カスタマーエクスペリエンスとカスタマーサクセスの違いは、施策の目的にあります。カスタマーエクスペリエンスは顧客の体験を向上させることを目的として実施しますが、カスタマーサクセスは顧客を成功に導くことを目的とした施策です。
顧客満足度との違い
顧客満足度とは、カスタマーエクスペリエンスを評価する指標のことです。顧客が商品・サービスに対してどの程度の満足を感じているか評価し、具体的な数字として表示します。
一方、カスタマーエクスペリエンスは顧客の体験全体を指すため、満足しているかどうかや数字による評価はありません。顧客満足度を調べた結果をもとにカスタマーエクスペリエンスを改善することで、より顧客に満足を与える企業活動を行えるようになります。
デジタルカスタマーエクスペリエンスとの違い
デジタルカスタマーエクスペリエンスとは、Webサイトやチャットボットサービスなどのデジタル技術を用いた顧客体験のことです。顧客にとって利便性が高いデジタルカスタマーエクスペリエンスを提供することで、顧客満足度がさらに向上します。
たとえば、ECサイトの使いやすさもデジタルカスタマーエクスペリエンスの一つです。直感的に操作でき、少ないステップで商品比較や購入を行えるECサイトなら、顧客満足度も高くなり、ロイヤリティ向上にもつながるでしょう。
CXが重要な理由
CX(カスタマーエクスペリエンス)が重要な理由としては、次のポイントが挙げられます。
- 商品・サービスに付加価値を与えられるから
- 競合商品・競合サービスとの差別化が難しくなったから
- 非物質的価値が重視されるようになったから
それぞれの理由について解説します。
商品・サービスに付加価値を与えられるから
発売当初には機能やデザインにおいてオリジナリティが高かった商品・サービスであっても、時間が経過し、市場競争が激化することで、類似する商品・サービスに独自性のある立場を取って代わられる可能性があります。後発の商品・サービスとの差別化が明確ではなくなり、オリジナリティのない一般的な商品・サービスと認知されるようになってしまうかもしれません。
しかし、商品・サービスにオリジナリティがなくなっても、優れたカスタマーエクスペリエンスがあれば、離反する顧客は少ないと考えられます。たとえば、コーヒーショップが増え、似たような味や値段のコーヒーが数多く誕生したとしましょう。
そのような状況でも、「ソファーの座り心地がいい」「カップやケーキがインスタ映えする」など、他のコーヒーショップでは体験できない付加価値があれば、顧客の離反を食い止められます。より良い商品・サービスを提供することも大切ですが、顧客に唯一無二の体験を提供することも大切といえます。
競合商品・競合サービスとの差別化が難しくなったから
モノやサービスが増えたことで、競合商品・競合サービスとの差別化が難しくなっています。何か一つが流行すれば、あっという間に類似する商品・サービスが誕生し、オリジナリティが失われてしまいます。
しかし、商品やサービスは真似ができても、体験そのものを真似することは困難です。損なわれにくいオリジナリティを商品・サービスに付与するためにも、カスタマーエクスペリエンスに注目することが必要です。
非物質的価値が重視されるようになったから
物質ではなく、非物質に価値を置く人も増えてきています。何かを買うよりも、何か特別なことを経験したいと考える人も多く、ますます非物質的価値が重要視されるようになってきています。
たとえば、次のような非物質的価値は、顧客が「次も利用したい」と思う動機付けになることがあるでしょう。
- 店員の接客が丁寧だった
- 店員の笑顔が自然で、心からもてなされていると感じた
- 注文から提供までの時間が短かった
- 清潔で居心地が良かった
カスタマーエクスペリエンスを充実させることで、非物質的価値を重視する顧客の心をつかめるでしょう。顧客がどのような体験を求めているのか、どのような体験に価値を感じるのかを正確に分析し、顧客が求めるカスタマーエクスペリエンスを提供することが大切です。
CX向上に取り組むメリット
CXが向上すると次のようなメリットがあります。

ファンが増え、LTVが向上する
顧客が商品に関連する良い体験をし、CXが向上することで「またこの商品を使いたい」という思いを持つファンを増やすことができます。商品やブランドに愛着を持つファンは、一度商品を購入したあとも、繰り返し購入してくれる傾向にあります。また、気に入った商品を繰り返し購入するだけでなく、アップセルやクロスセルにつながる可能性も高いため、LTV(Life Time Value)が高く、安定した収益の基盤となってくれます。
UGC(クチコミ)により認知が拡大する
良いCXを体験したファンは、その体験を友人や知人に話したり、SNSやレビューサイトに投稿するなど自ら進んでUGC(クチコミやレビュー)の投稿を行ってくれるようになります。ファンが発信するUGCは、顧客個人の感想でありその投稿によって収益を得ることがないため、企業が自ら発する情報に比べ信頼性が高いと感じる顧客が多い傾向にあります。
また信頼性の高いUGCが潜在顧客の目に触れることで、広告費をかけずともプロモーション効果が期待できる点もメリットといえるでしょう。UGCを収集し、顧客の声として紹介したり、商品開発やデザインの参考にすることもできます。
ブランディングできる
CXはECサイトや企業が公開するコンテンツ、店舗での接客、カスタマーサポートの対応など、商品購入のプロセス全般に及ぶため、CX向上を目指した分析や改善に取り組むことで顧客のロイヤリティを高めることができます。
良いCXを追求することはファンを増やし、ファンが発信するUGCは潜在顧客へのプロモーションとなり、新たなファンを生むという好循環につながります。こうしてブランドとしての認知や高感度が高まります。
一方で悪いCXは、その体験をした顧客が離れるだけでなく、悪い評判を生み、利用したことがない顧客にまで悪いイメージが広がってしまう可能性もあります。CXに真摯に向き合うことがブランドの価値向上につながるのです。
顧客離れを軽減できる
CXへの取り組みは顧客離れを防ぎ、安定した収益を挙げ続けるうえで有効です。顧客は感情的・情緒的な価値を感じているため、サービスの質が落ちたとしても、他社へ乗り換えるリスクを抑えられます。
継続して利用を続けてきた商材でも、満足いくサービスを得られなかったと感じたとき、利用をやめる企業は少なくありません。他社への乗り換えは貴重な優良顧客を失うと同時に、競合のシェアを伸ばす行為に他ならず、二重の意味で痛手です。
日頃からCXを意識して顧客と良好な関係を築けていれば、サービスの質を維持できなくなった場合のリスクヘッジが効きます。
競合他社との差別化ができる
CXの向上によって競合他社と差別化でき、自社の商材が選ばれやすくなります。あらゆる領域で産業のレベルが底上げされた昨今、機能や価格で独自の価値を生むのは難しくなりました。
また、インターネットの普及によって、顧客は事前に購入を検討する商品の比較が可能です。アプローチする相手がすでに知識を持っている状態だと、サービスの特徴を押し出しても、心には刺さりにくいでしょう。
CXに邁進し、ノベルティの配布やパーソナライズされたコミュニケーションなどを実践すると、他の企業にはない固有の価値を提供しやすくなります。

CXの分類5つ
CXは、「SENSE(感覚)」「FEEL(情緒)」「THINK(創造や認知)」「ACT(肉体やライフスタイル)」「RELATE(社会)」に分類できます。それぞれの定義や、具体的な活動をみてみましょう。
SENSE(感覚)
SENSEとは感覚的経験価値を表し、単刀直入にいえば五感に与える経験のことです。カフェ一つとっても、オシャレなBGMが流れる快適な空間を提供すれば、来店したお客さんは長時間滞在したいと思うでしょう。飲食店であれば、厨房からの美味しそうな匂いも来店意欲をそそる戦略の一つです。
商品自体の価値にプラスアルファで、居心地のよい場所にする工夫がCXにおけるSENSEです。近年はAR(拡張現実)技術の進展で、味覚や触覚を疑似体験できるITデバイスも登場しています。
FEEL(情緒)
FEELとは情緒的経験価値を意味し、顧客の感情に与える体験や経験のことです。たとえば、丁寧な接客、細やかな気配りによる信頼や熱狂、愛着などが該当します。
商品自体に大きな差はなくても、接客態度やコミュニケーションのとり方に注意を払えば、顧客の気持ちを刺激できます。
リピートを決める際には、機能面の満足度だけでなく、人間的な感情を抱いてのことが少なくありません。ケーキを提供するお菓子屋さんの場合、鮮やかなデコレーションを施して、来店した人に「きれい」「かわいい」と思わせると購買につながります。
THINK(創造や認知)
THINKとは創造的・認知的経験価値を表す言葉で、創造性や知的好奇心を刺激される経験のことです。
利便性以外にも、新たな知見や知恵を与えることでCXは向上します。たとえば、水族館でのシャチへの餌付けや、工場見学での生産ラインの一般公開が該当します。
リピート中の商品が、どうやって生み出されるのか知りたいと感じているファンは少なくありません。情報発信に注力して、新たな利用方法を紹介するのも、THINKを向上に導く一つの方法です。
ACT(肉体やライフスタイル)
ACTとは肉体的経験価値とライフスタイル全般を指す概念で、顧客の日常生活に影響を与える体験のことを意味します。言い換えると、興味がありながらも今まで行けなかった場所・体験できなかった経験の、実現による喜びや満足感のことです。
VRを活用した、観光地の疑似体験が一例に挙げられます。今では当たり前になったスマートフォンも、移動時の利便性を飛躍的に高めたデバイスとして、行動やライフスタイルに著しい変化を生んだ事例です。
RELATE(社会)
RELATEとは準拠集団や文化との関連付けを表し、特定の集団や分化に所属することで得られる経験のことを指します。わかりやすい例でいえば、アーティストやスポーツチームのファンクラブや会員サイトが代表的です。
推しがいる場合、応援したい気持ちや貢献意欲を満たすために私財を投げ出すファンも少なくありません。ファンクラブは入会特典による物質的な価値のほか、好きな選手とつながりを得られる精神的な充足感、コミュニティへの帰属意識など、さまざまな価値を提供します。
CXを向上させる戦略的方法
実際にCXを向上させるためには、次の順に戦略的方法を実践していくことが必要です。
①現状を客観的に分析する
②顧客理解を深める
③課題を特定する
④仮説を立てる
⑤施策を実施・検証する
順に沿って解説します。
現状を客観的に分析する
まずは現状分析です。調査時点でのカスタマーエクスペリエンスを書き出してみましょう。カスタマーエクスペリエンスは、不確実な要素が多く定性的に評価しがちですが、客観的に分析するためにも、数値を用いた定量的なデータを取得して分析することが必要です。
たとえば、「居心地が良いと感じる顧客が多い」ではなく、「居心地が良いと感じた顧客は70%、そのうち男性は30%」のように具体的に分析できます。また、顧客アプローチの費用対効果、時間対効果も数値化が必要です。数値によって客観的に把握することで、カスタマーエクスペリエンスを向上させる具体的なアイデアが生まれやすくなります。
顧客理解を深める
現状を分析した後で、顧客についての理解を深めます。顧客がどのような人物で、どのような体験を好み、どのようなカスタマーエクスペリエンスを希望しているのか、具体的に割り出していきましょう。また、商品・サービスのどの要素を気に入っているのか正確に把握することで、カスタマーエクスペリエンスの改善を進めやすくなります。
顧客理解は、アンケートやインタビューなどで深めることが一般的です。普段から自社商品・自社サービスを愛用し、何度かリピートしているロイヤル顧客を対象に、調査を実施してください。
アンケートやインタビューの参加者を探すときは、次の方法を検討してみてください。
- SNSで自社商品・自社サービスについて発信している顧客とコンタクトを取る
- 自社商品・自社サービスの購入時に参加を促す
- メールマガジンで参加者を募る
- ファンコミュニティで参加者を募る
ロイヤル顧客が集うファンコミュニティを運営している場合は、アンケートやインタビューの参加者を直に募れるため、比較的短時間で調査を実施できます。
課題を特定する
現状分析と顧客理解を進めることで、カスタマーエクスペリエンスにおける課題が明らかになります。たとえば、次のような課題を特定できるかもしれません。
- オンラインで商品・サービスを購入した顧客の満足度が低い
- サポートサービスに対する新規顧客の満足度が低い
- オンラインチラシを閲覧している顧客の単価が低い
課題を特定するためには、顧客に関する情報を一元管理していることが前提となります。顧客の情報が適切に管理されていないときは、後述するCRMなどのツールを導入し、均質に情報管理することからはじめてください。
仮説を立てる
現状分析した結果と抽出された課題から、仮説を立てていきます。オンラインで商品・サービスを購入した顧客の満足度が低い場合なら、店舗での接客に相当するような体験を提供することで、満足度向上を実現できるという仮説を立てられるかもしれません。
たとえば、次のようにより具体的な仮説を立ててみましょう。
- オンラインで購入した顧客だけに試供品やノベルティをプレゼントすると、顧客満足度が向上する
- 送料無料で利用できるサイズ交換サービスを提供すると、顧客満足度が向上する
仮説を立てるときには、商品・サービスに対する顧客の気持ちの変化を細かく反映することが大切です。また、具体的な数値目標(KPI)があると、より仮説を検証しやすくなります。売上目標やECサイトの訪問者数、購入率などを具体的に数字で明記し、取り組みを進めていきましょう。
施策を実施・検証する
仮説に基づいた施策を決定し、実施・検証します。施策を実施する際には費用がかかることがあります。たとえば、ノベルティをプレゼントするなどの施策には、デザイン費や制作費が必要です。施策を実施する前に関連する部署に相談しておきましょう。
施策を実施した後、効果を測定します。期待した効果が得られないときには、仮説を再度打ち立て、施策の再実施・再検証を進めていきます。
カスタマーエクスペリエンスを向上させるためには、仮説構築・施策実施・検証を何度も繰り返すことが欠かせません。時間はかかりますが、丁寧に仮説構築・施策実施・検証を繰り返し、より良いカスタマーエクスペリエンスを提供できるようにしていきましょう。
CXを向上させるときの注意点
カスタマーエクスペリエンスを向上させる施策を実施するときには、次の点に注意が必要です。
- 顧客目線で施策を立てる
- 一貫性があるか定期的に確認する
- パーソナライズされた体験を提供する
- 定期的に現状を見直す
それぞれの注意点を解説します。
顧客目線で施策を立てる
仮説から施策を立てるときは、顧客目線でアイデアを出すことが大切です。「自分が顧客であれば、どのようなサービスを提供してほしいか」という視点に立つことで、よりカスタマーエクスペリエンスを向上させるアイデアが浮かびやすくなります。
たとえば、ECサイト経由で購入する顧客の満足度を向上する施策を考える際なら、「次回のショッピングで利用できる割引券」は顧客目線で嬉しい施策といえるかもしれません。しかし、お試し的に購入する顧客にとっては、次回利用できる割引券よりも、今回のショッピングで割り引かれるほうが嬉しいでしょう。
また、すでにブランドや企業のファンである場合なら、ノベルティのプレゼントは嬉しい施策です。しかし、ファンではない顧客にとってはノベルティはあまり魅力的とはいえず、ほかの施策のほうが良い可能性があります。購入のリピート度合いによってプレゼントを変えるなど、顧客に受け入れられやすい施策を検討しましょう。
一貫性があるか定期的に確認する
カスタマーエクスペリエンスを向上させる施策を実施するときは、一貫性があるかどうか定期的に確認するようにしましょう。たとえば、タッチポイントごとに異なるメッセージを発信しているなら、顧客は企業やブランドに対してのイメージをつかめないだけでなく、「信頼できない企業だ」と判断するかもしれません。
まずは顧客情報を一元管理し、顧客のカスタマーエクスペリエンスも一元的に把握できる状態にしておきます。複数のタッチポイントで情報に接する顧客もいることを想定し、矛盾のない情報を発信するようにしましょう。
パーソナライズされた体験を提供する
情報の内容には一貫性が求められますが、顧客体験は画一的なものが好ましいとは限りません。顧客の興味の対象やニーズ、今までの購入履歴などから顧客に適した体験を分析し、パーソナライズされたものとして提供することが必要です。
パーソナライズされた体験を提供すれば、顧客は特別感を覚えるだけでなく、自分について深く理解している企業・ブランドだと考えるようになります。企業・ブランドのファンになり、リピート購入するかもしれません。
なお、顧客にパーソナライズされた体験を提供するには、顧客の行動履歴や属性などのデータを収集し、分析・反映することが必要です。後述するCRMなどのツールを導入し、データ収集や分析に活かしましょう。
定期的に現状を見直す
カスタマーエクスペリエンスを高水準に維持するためにも、定期的に現状を見直すことが必要です。適切なカスタマーエクスペリエンスを構築しても、顧客のニーズは流動的なため、いずれは不適切になる可能性があります。
定期的に現状を見直すことで、常に効果のある施策を実施できるようになります。費用対効果が低い施策を回避でき、販売コストの削減も実現できるでしょう。
会社全体で取り組む
企画やマーケティングの部署が一方的に施策を推進せず、全社でポイントを共有し、現場の理解を得ることが重要です。顧客と直接的な接点を持つ営業や、カスタマーサクセスからの理解を得られないと、顧客体体験の向上はなかなか実現しません。
CXには、購入後も含めた継続した価値の提供が不可欠です。1人ひとりにカスタマイズしたメルマガの配信や、手厚いアフターサポートを行うには、全社規模での対応が求められます。
また、現場が吸い上げた顧客からの意見を施策に反映させることも大切です。施策のポイントを伝えるとともに、営業部門によるフィードバックの収集も平行して行いましょう。
CX向上に役立つツール
カスタマーエクスペリエンスの向上には、適切なツールを使い、効率良く施策を実施していくことが必要です。役立つツールを紹介します。
CRM
CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客情報や購買履歴、アプローチの履歴などを一元管理するツールです。顧客がどのような体験を求めているか分析する際には、顧客に関する詳細な情報が必要です。CRMを活用して一元管理しておけば、異なる接点によって知りえた顧客の情報も全てまとめて整理でき、カスタマーエクスペリエンスの向上に役立てられます。
CRMの中には、顧客分析や商品情報管理などの機能が搭載されているものもあります。必要な機能をピックアップしてから、自社に合うCRMを選びましょう。
MA
MA(Marketing Automation)とは、その名の通り、マーケティングを自動化するためのツールです。見込み顧客の集客段階から関心を高める段階、購買に導く段階へと、顧客を適切に育成(リードナーチャリング)できます。
MAでは見込み顧客のWeb閲覧履歴や、アプローチとリアクションの履歴なども蓄積できるため、簡単にニーズ分析を行えるようになるというメリットがあります。CRMと連携すれば、見込み顧客と顧客の情報をまとめて管理でき、より一貫したカスタマーエクスペリエンスの提供が可能になるでしょう。
Web解析ツール
自社サイトに訪問したユーザーの行動を分析する、Web解析ツールの使用も効果的です。PV(ページビュー)数やUU(ユニークユーザー)数、離脱率などが瞬時にわかり、施策の効果や改善の必要性、対策の方向性を決める際に役立ちします。
代表的なツールには、アクセス後のユーザーの行動を把握できるGoogleアナリティクスや、Web上での見え方を測定するGoogleサーチコンソールが挙げられます。数値を集計・分析することで、客観的な施策の立案・評価が可能です。
Web接客ツール
Webサイトに訪れたユーザーに対応する、Web接客ツールの導入も一つの手です。サイトにチャットボットを実装すれば、簡単な相談や疑問に回答できます。
オペレーターに繋ぐ前の一次的な窓口を担うため、カスタマーサポートの負担軽減や人件費の削減に役立ちます。
あらゆる領域で産業が高度に発展した現在、ユーザーのニーズも多様化しました。Web接客ツールを活用すれば、1人ひとりの異なる悩みや疑問にも細やかな対応が実現し、CXの向上に寄与するでしょう。
CXを向上させた企業の成功事例
CX向上につながる施策を行っている企業を3社ご紹介します。
エポスカード
エポスカードは、「好きを応援するカード」をコンセプトにさまざまなアニメやゲーム・キャラクター等のコンテンツとコラボしたクレジットカードを発行しています。CXの向上を目指しファンコミュニティを立ち上げました。
ファンコミュニティにはキャラクターカードの所有者が集い、顧客が投稿を行ったり、他者の投稿にいいねをつけるなど、クレジットカードの利用シーンにとどまらない顧客体験を提供しています。
ファンコミュニティ内では、ログインや投稿に対するいいねなどのアクションによってポイントが付与され、顧客ランクが上がっていく仕組みをとっており、顧客ロイヤリティの向上に貢献しています。
導入事例インタビューはこちら▼
ユーザー視点での最適なUI/UXがcoorum導入の決め手に。更なる顧客満足度の向上を目指して、コミュニティ施策に力を入れ、オンライン上での顧客接点の強化を実施。
b8ta Japan
b8ta Japanは「発見と体験と提供するストア」として、スタートアップ企業の商品や他の店では見かけない革新的な商品など幅広い商品を取り扱っています。b8taのストアには複数のブランドが出品しており、顧客が商品と出会い体験する場として利用されています。
顧客に良質な体験を提供するだけでなく、ストア内の定量・定性データがブランドに提供される仕組みで、各ブランドのCX向上施策にも活きるストアになっています。
エノテカ
ワインの輸入販売を行うエノテカでは、全国に60店舗以上のワインショップを構え、質の高い接客ができるようさまざまな取り組みを進めています。その一方で、ECサイトでの購入体験の向上にも力を入れており、購入環境を問わず好みのワインに出会えるよう工夫がなされています。
ワインは詳しい人でなければ自分に合ったものを選ぶのは難しい趣向性の高い商品ですが、オンラインでも自分の好みに近いワインを見つけられるような機能が充実しています。具体的には購入したワインを記録し好みを可視化できる「マイワイン」や購入傾向をレポート表示する「パーソナルレポート」など店頭でスタッフがヒアリングする情報がアプリに集約され、オンラインショップでの購入の際に参考にできる仕組みです。
京セラ
耐久性に優れる携帯端末を提供する京セラは、顧客との交流の促進を目的に、コミュニティサイトの構築を決断しました。導入前はお客様の意見を集める場がなく、タッチポイントが少ないことに課題をもたれていました。
さらにサービスに関するメディアが乱立し、運用リソースの確保が難しく、十分な活動ができず悩んでいたようです。
自社コミュニティ「TORQUE STYLE」をリリースしたあとは、運用工数を抑えつつ、ユーザーとのコミュニケーションが活発なメディアの運営に成功しています。顧客からの声を収集し、社内にシェアすることで従業員のモチベーションの向上にも役立てています。
導入事例インタビューはこちら▼
コミュニティにメディアを集約してお客様との交流に注力。仲間に出会える「TORQUE STYLE」
クラシエホームプロダクツ
クラシエホームプロダクツは、ファンコミュニティ「mä & më time」を運営する日用品・化粧品メーカーです。コミュニティでは、お子さんとのお風呂での出来事や商品の感想が飛び交い、盛り上がっています。
成功の背景として挙げられるのは、ブランドの立ち上げ時から愛用するリピーターを初期メンバーに迎え入れたことや、担当者自身も一メンバーとしてコミュニティを楽しんでいることです。
テレビCMをはじめ、マス向けのマーケティングでは幅広い顕在顧客や潜在顧客にアプローチできる反面、発信側と受信側という一方的な関係が生まれます。オンラインコミュニティの場合、ブランドを提供する側も中に入り込めることがメリットです。
企画やマーケティングを担う企業側の人間と、顧客が常にコミュニケーションをとれる環境が実現し、商品の改善につながるポイントの発見に役立てているようです。
導入事例インタビューはこちら▼
親子のヘアケア&スキンケアブランド「mä&më(マーアンドミー)」がファンとの共創を目指すコミュニティを始めた理由
おわりに
顧客の感情的価値を指すCXについてご紹介しました。購入前の情報収集から、使用時、アフターサポートまで商品に関する全ての体験に目を向けるCXは、向上に向けて取り組むことで顧客ロイヤリティを高めリピーターを増やすことにつながります。CXの改善においては、ロイヤル顧客を深く知り、コミュニケーションを取ることが有効に働きます。その方法のひとつとしてブランドとしてファンコミュニティを持つのも有益な手となるでしょう。

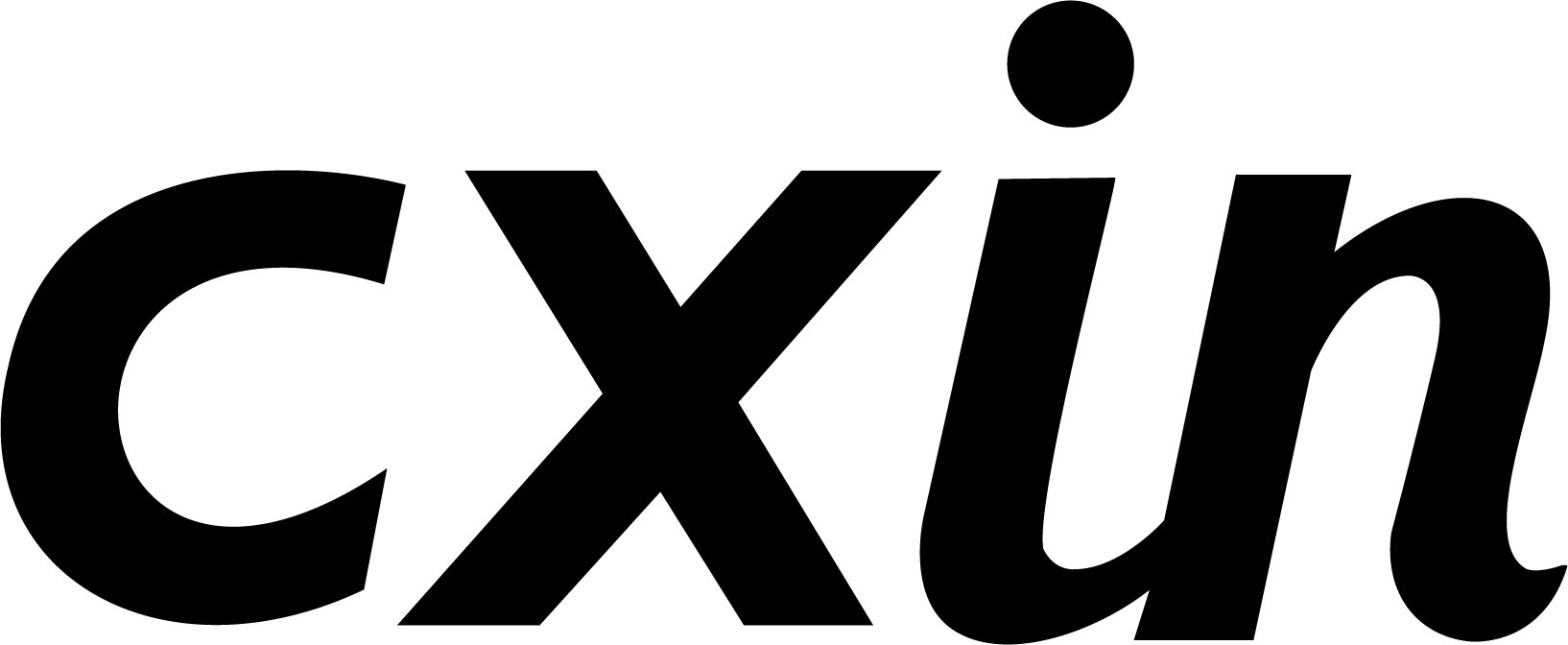

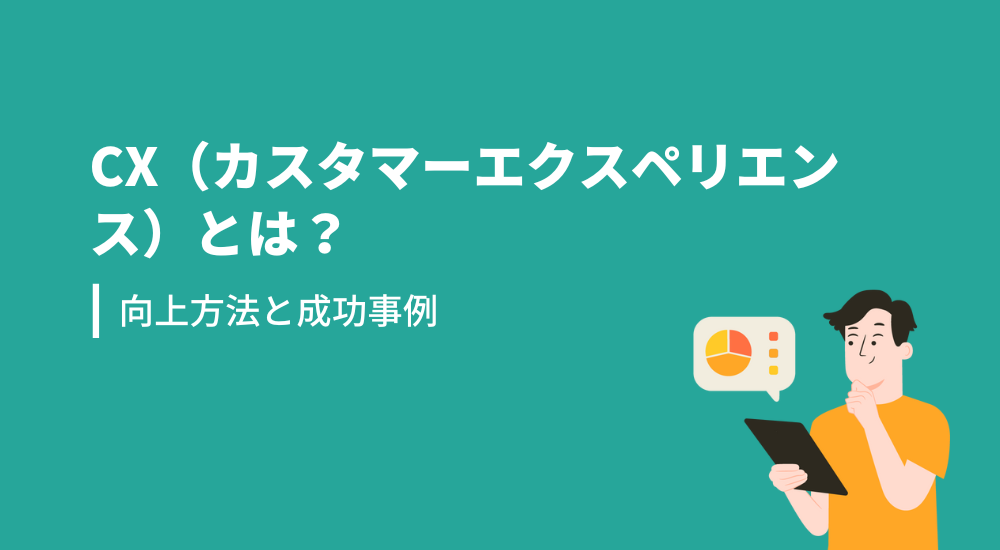


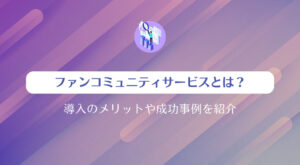
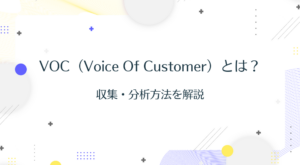
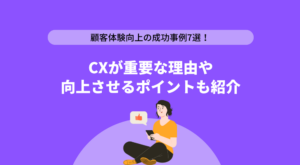
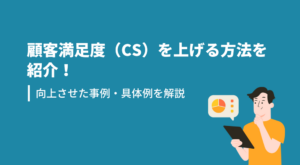
![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)