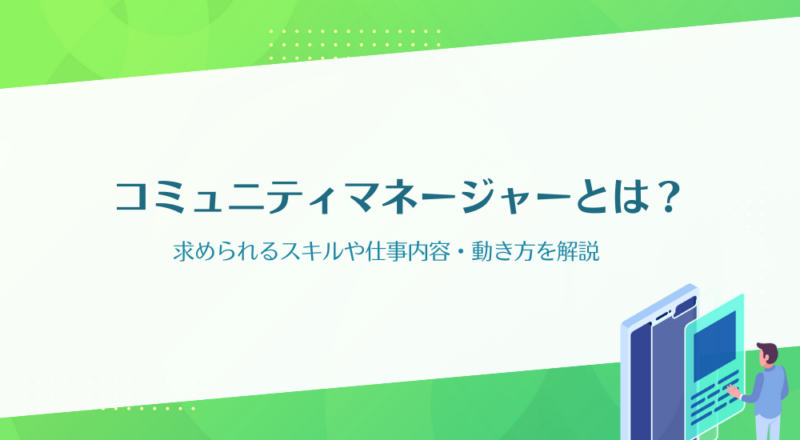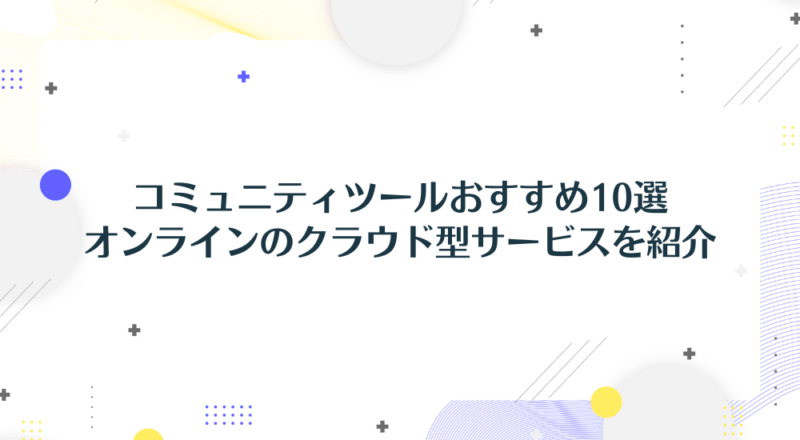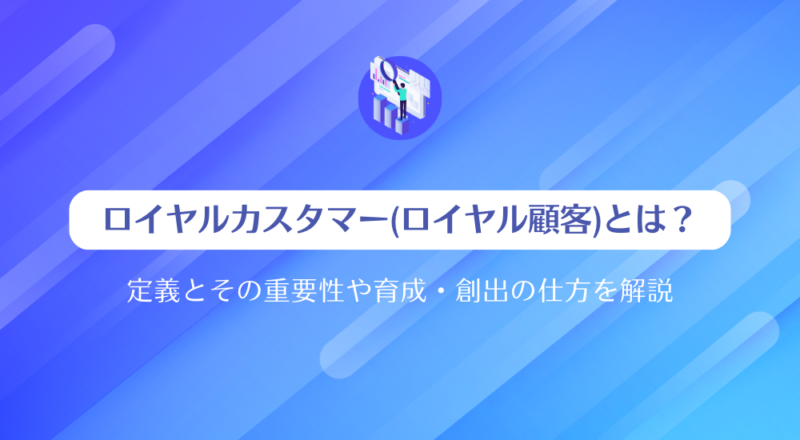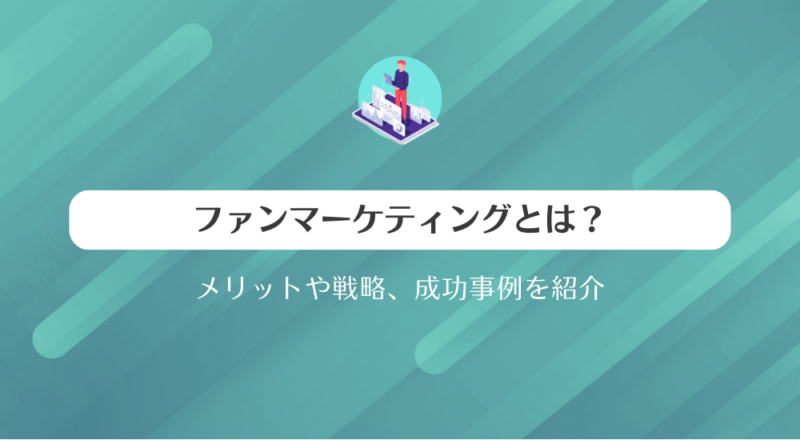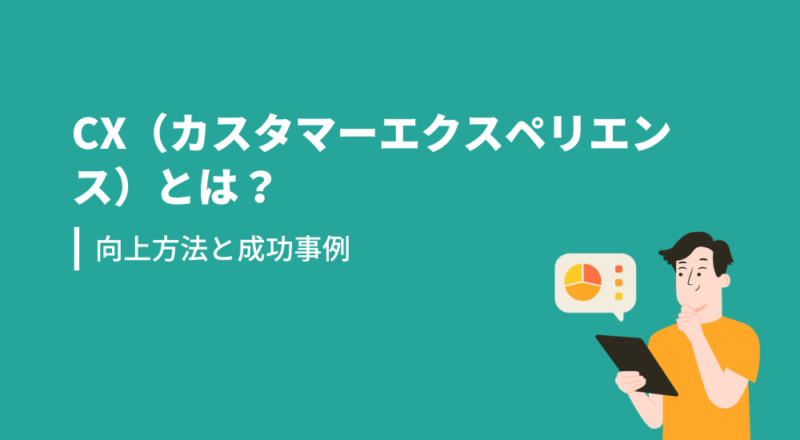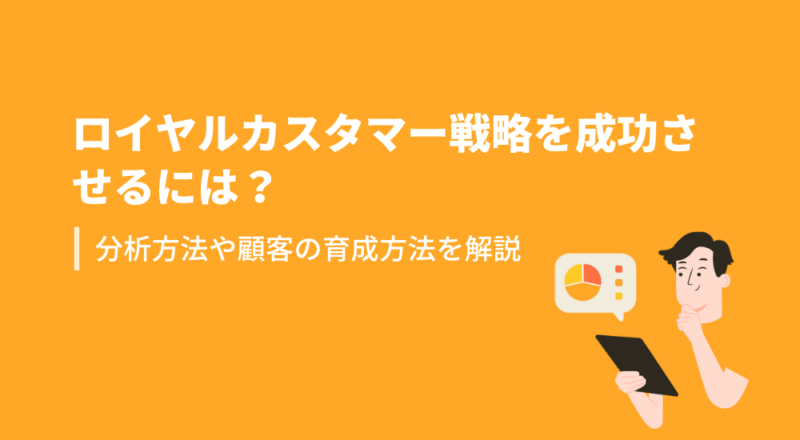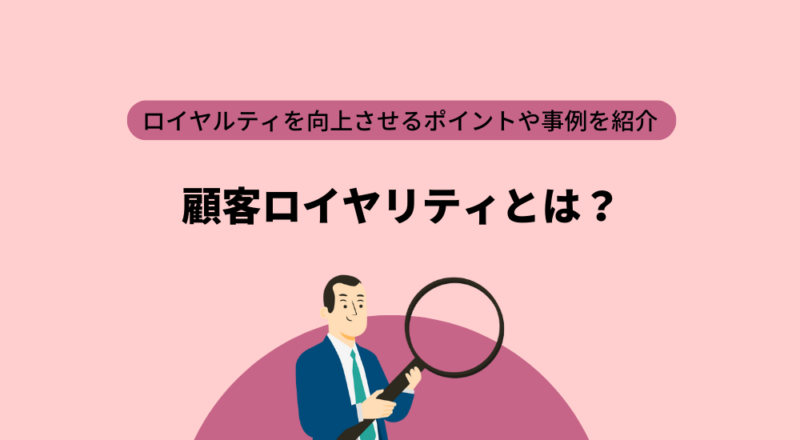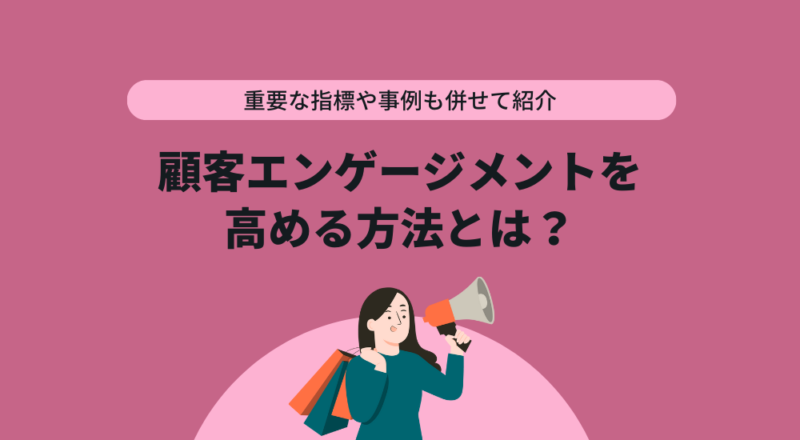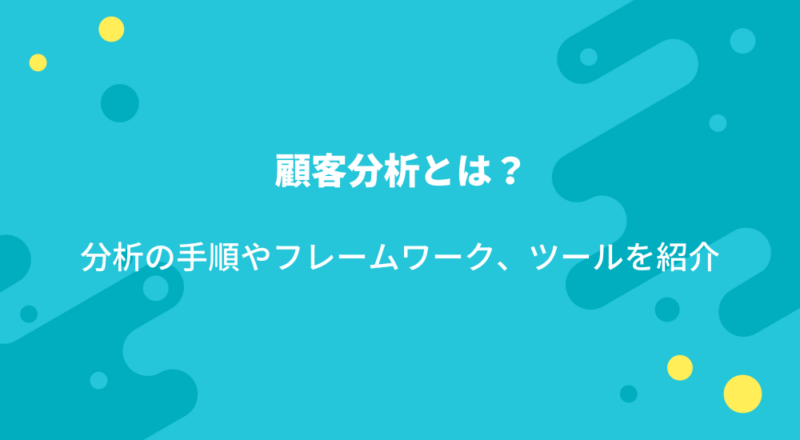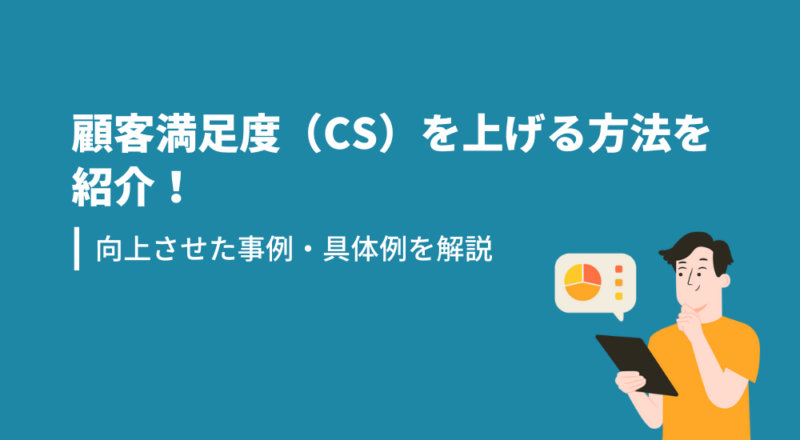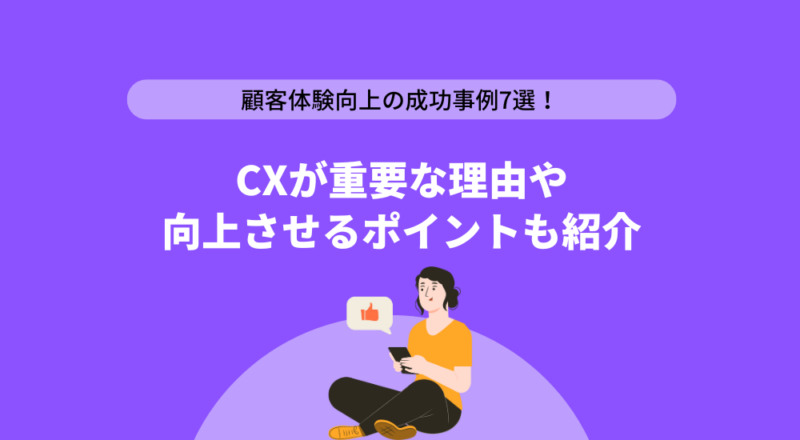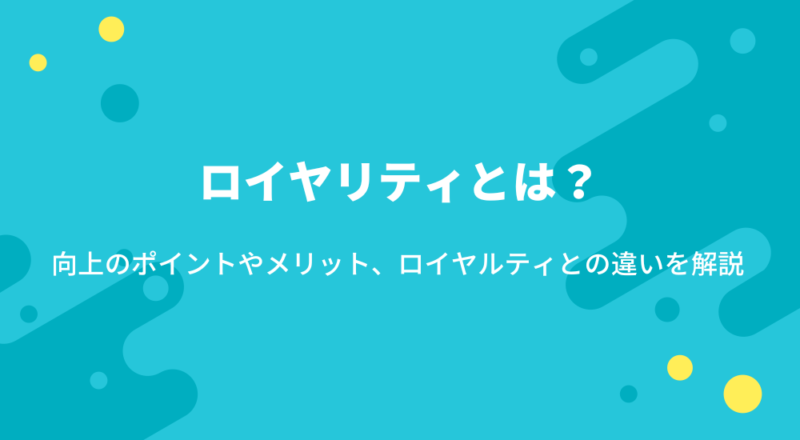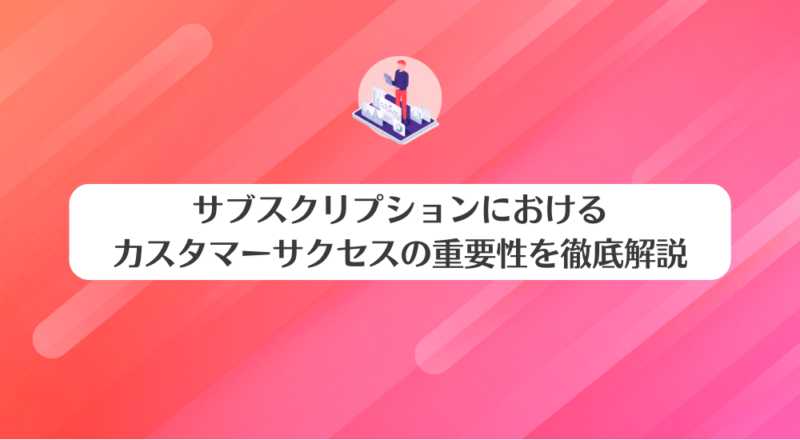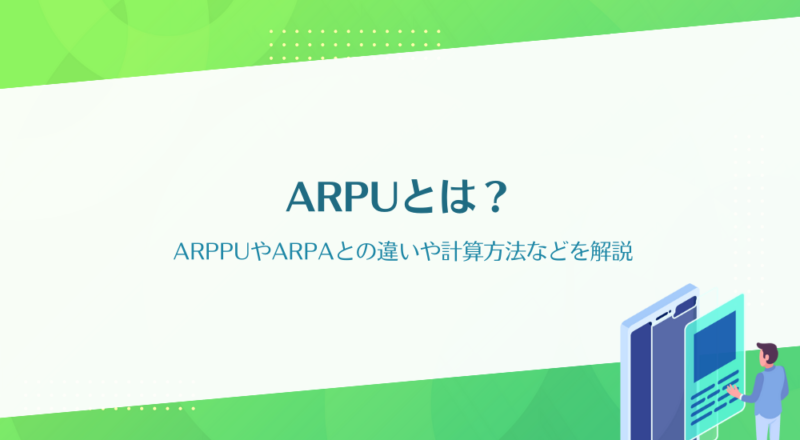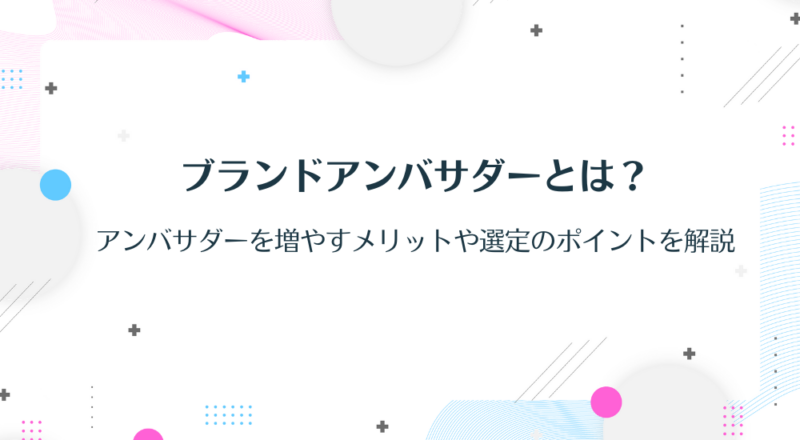
近年変わりゆく消費行動とマーケティング環境により、ファンコミュニティに興味を持つ企業が増えてきました。
そこで本記事では、ファンコミュニティを通して企業がやりたかったこと、どんな世界を目指しているのかについて、具体的な事例を交えながらご紹介します。

ファンコミュニティを導入する理由について
ファンコミュニティに興味を持っている方の中には
「みんなファンコミュニティを導入しているのか」
「ファンコミュニティをなぜ導入したのか」
と気になっている方もいると思います。
いろんなご支援をさせていただいていますが、ファンコミュニティの期待は企業によってさまざまです。
そこでまずは、各企業がどういった期待を持ってファンコミュニティを導入したのか、その背景について3つの事例を交えてご紹介します。
事例①月額会員制ジムの場合
まず1つ目の事例は、月額会員制のジムを経営する企業です。こちらの企業は、24時間通い放題のジムを経営しており、再注力の事業として店舗数と売上高を伸ばしています。
しかし24時間制ジムという業態や店舗数の増加に伴い、サポート体制の整備で人的リソースをかけた顧客フォローが難しいことが課題でした。
ビジネスを大きく成長させたいが、顧客満足度も高めたいというところで、事業のスケール拡大を目指しつつ、質の高い顧客体験を提供できるファンコミュニティを導入しています。
ファンコミュニティの活用方法
こちらの企業はファンコミュニティを活用し、顧客の力を借りて顧客同士の相互補助を通じて、ジム利用の課題解決や利用促進を目指しました。
実際にオンラインコミュニティを立ち上げ、「健康習慣をモチベートしあう場所」というコンセプトのもとファンコミュニティを運営。KPIとして、入会から最初の1か月でどれだけ定着するのかを重要な指標としています。
ファンコミュニティ内では、入会時に1か月の目標を宣言し合ったり、日本全国のいろんな店舗にいる顧客と繋がることでお互いを励ましあったりなど、みんなで頑張ろうとする空間を作りました。
現在の進捗について
現在のファンコミュニティでは、投稿数と会員数が大きく伸びてきています。
投稿内容としては次のような内容が挙げられ、コンセプトである健康習慣をモチベートする場につながっています。
ファンコミュニティ上での投稿内容
- 今日行ったことの報告
- 自分の記録の報告
- 「頑張ります」や「応援メッセージ」
実際にファンコミュニティの効果測定も初めていますが、登録している顧客は週2回以上ジムに通う方が多いということが分かってきました。
またファンコミュニティのおかげで、最初の1か月を乗り切ることができたという顧客も多いため、最終的な事業貢献にも結びついているか検証を進めています。
事例②園芸メーカーの場合
2つ目は、園芸メーカーの事例についてご紹介します。こちらの園芸メーカーは、花苗の製造販売や、小売店に取り扱いの営業を行っています。
もともとファンコミュニティを運営しているCRM部という部署を中心に、SNSによるプロモーション活動や認知を広げるための活動に注力。過去にはアンバサダー施策を行っており、実際に「もっと他のアンバサダーの方と交流したかった」「自宅の庭を見てもらいたい」といったような声が集まったことで、顧客の反応に手ごたえを感じていました。
そこで、SNS上でバラバラだった熱量の高いアンバサダーを集め、SNSのコミュニケーションの一歩先へということで、ファンコミュニティをはじめています。
ファンコミュニティの活用方法
実際に園芸メーカーでは、ガーデニングが好きな顧客の情報交換や交流をする場所として、ファンコミュニティを活用しています。ファンコミュニティへの期待は、次の3つが挙げられます。
ファンコミュニティへの期待
- 顧客の声を店頭販促物や営業資料に転用
- 顧客の意見を商品開発などに還元
- 最終的にはLTVへの寄与を期待
まず1つ目の期待は、顧客の声を店頭販促物や営業資料に転用することです。実際、花苗を小売店で取り扱っていただくために営業に行くと、担当者から顧客の声を聞かれます。特に花苗は実際に育ててみないと分からないため、情報を顧客の声で保管することが必要です。また顧客の声は、営業活動による棚の獲得や販路拡大において重要な武器になるため、ファンコミュニティを活用し顧客の声を集めたいという狙いがあります。
また2つ目の期待は、顧客の意見を商品開発などに還元することです。例えば終売してしまった商品でも、CRM部と商品開発部が連携して、人気だった商品の情報を顧客の声から吸い上げたいという狙いがあります。
さらに3つ目の期待は、LTVへの寄与です。現在園芸メーカーでは、LTVをアンケートベースに計測しています。例えば、ファンコミュニティを通して、情報交換をしあうことで、花苗を多く購入してもらいたいという狙いがあります。
現在の進捗について
ファンコミュニティを運営し、開始1か月でユーザーは300程度に対し、総投稿数が2500件。いいねも含めたユーザーアクションが2万件に届く勢いで伸びてきています。
実際に、2500件の投稿の中には花苗の再販希望の声もあり、現在商品開発部と連携して具体的な話を進めていらっしゃいます。
今後は、アンケートをベースにLTV(再購買数)のヒアリング調査の実施を進めていきます。
事例③外食の場合
最後は外食店の事例をご紹介します。こちらの外食店がファンコミュニティを導入した背景は、人口減少や市場の縮小・成熟による外的要因が影響としてあります。また情報過多の時代により、企業側からの発信がより届きにくくなったため、新規顧客獲得よりもロイヤル顧客の育成が重要性を増しました。さらにロイヤル顧客の重要性が増したことにより、フロー型ではなくストック型のビジネスモデルへの転換を目指すことを決断し、ファンの力を借りて、ファンを育成するファンマーケティングを推進するために、ファンコミュニティが導入されました。
ファンコミュニティの活用方法
ファンコミュニティを構築し、ストック型のビジネス(持続的な事業の成長)を目指すにあたり、ファンと繋がり力を借りるコミュニケーションの拠点を作りました。
こちらの外食店のファンコミュニティへの期待は、次の3つが挙げられます。
ファンコミュニティへの期待
- ファン理解の深耕
- ファンとの共創実績の創出
- 従業員エンゲージメントの向上→LTVへの貢献へ
まず1つ目の期待は、ファンの理解を深めることです。なぜファンになってくれたのか、一般顧客とは何が違うのかなどを、ファンコミュニティで直接接点を作ることで深く知りたいといった狙いがあります。
また2つ目の期待は、ファンとの共創実績の創出です。ファンと何か共創した実績をPRや広報などで取り上げたいという狙いがあります。
最後3つ目は、従業員エンゲージメントの向上です。従業員に伝わりきらなかった顧客が感じる喜びを、ファンコミュニティを通して伝えたいという狙いがあります。また最終的に、従業員エンゲージメントが向上することで、LTVの貢献も目指しています。
売上効果について
こちらの外食店は、ファンコミュニティを始めたらすぐにLTVに結びつくとは考えていません。下記の画像のようなロジックを持って、ファンコミュニティへの事業投資を決断していただいています。

まずはファンコミュニティを構築することで、ファンとの共創実績創出や理解が進み、マーケティングの意思決定の質と速度が向上すると考えています。それにより、ブランドイメージが上がることで顧客体験が良くなり、再来店頻度が増加してLTVが向上するというロジックの流れになっています。
ファンコミュニティは目的を整理することが重要
ここまで、ファンコミュニティを導入いただいた企業の事例についてご紹介をしました。
ご紹介した3つの企業だけでも、いろんな目的の元にファンコミュニティを導入いただいていることが分かっていただけたと思います。
ここからはファンコミュニティを運営するにあたり、重要な目的の整理についてご紹介します。
可能性は無限、だからこそ目的を整理しよう
ファンコミュニティは、活用方法次第で可能性は無限です。そのため、ファンコミュニティを導入する際は目的の整理が重要になります。
いろんな企業の話から、ファンコミュニティを運営する目的は8つに分かれることが分かりました。

上記の画像は、ファンコミュニティの8つの目的を表したものになります。
例えば、先ほどご紹介した園芸メーカーでは、アンバサダーとの接点を強化することで、外への発信を促すことを目的としています。この目的を優先順位の1番目におくことで、アンバサダー施策の延長として始められました。
各企業において目的は分かれますが、ファンコミュニティを導入することで直接いくら購買してもらえるのかも大切な観点になります。
加えて販促やPR、商品開発、社内エンゲージなど、コミュニティで顧客と直接繋がることで、何ができるのかも目的の1つとしてあると整理しやすいです。
関わる人が多いからこそ、目的の整理をしよう
ファンコミュニティ施策は、顧客と何かを一緒にできるという点で、いろんな人の期待が込められるため、関わる人が多くなります。
そのため、ファンコミュニティを運営する場合は、関係者が何を期待しているのかを整理することも、施策の全体像を把握する上で大切です。

例えば、営業部を担当する方は、販促に活かせるような顧客の声を集めたいという期待をしています。しかし一方で、CMOは世の中に対するインパクトのある新しい施策を実施することを期待している場合もあります。
このように、関係者によってファンコミュニティに対する期待がさまざまなため、施策を始める際は、施策の関係者が誰でそれぞれどんな期待をしていているのかを整理しましょう。
まとめ
本記事では、現場担当者が語る!企業のリアルな課題とコミュニティで解決したかったことについてご紹介してきました。
今回3つの事例でご紹介したとおり、ファンコミュニティへの期待はさまざまです。
また活用方法によって、可能性は無限なので目的の整理がとても重要になります。整理をする際は、関わる人の期待が何かを整理しましょう。目的が整理できれば、半年後の成果の検証をしやすくなります。