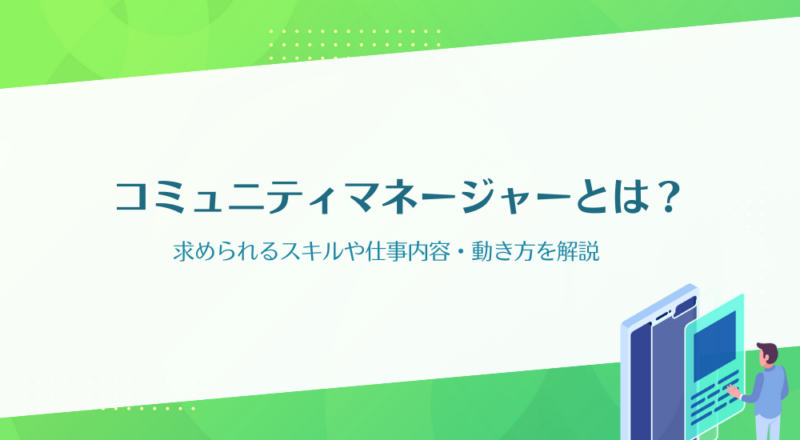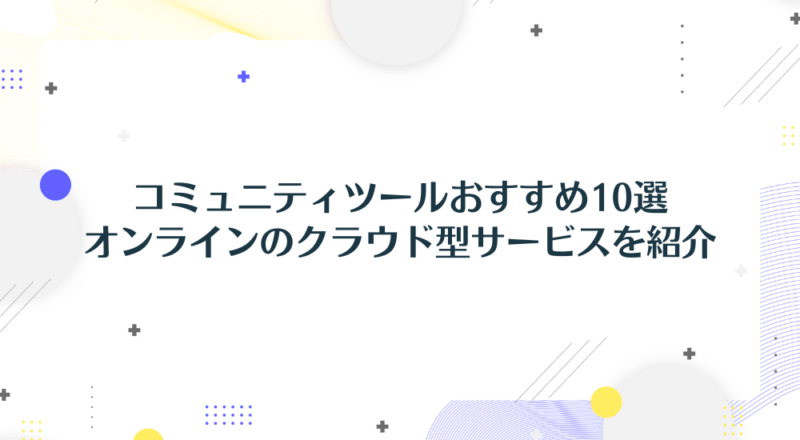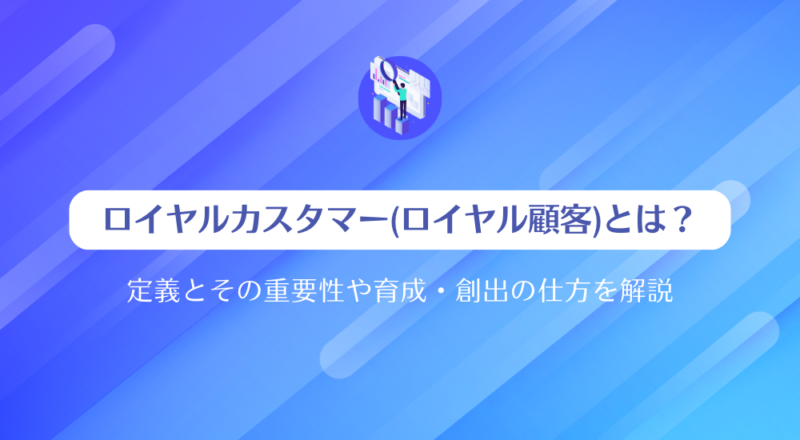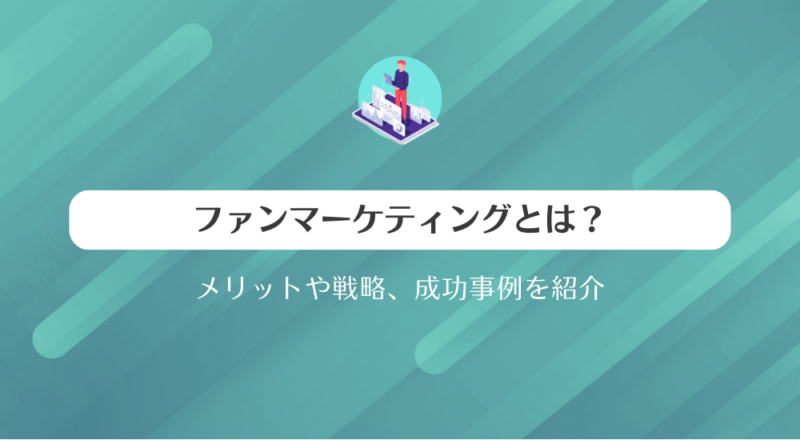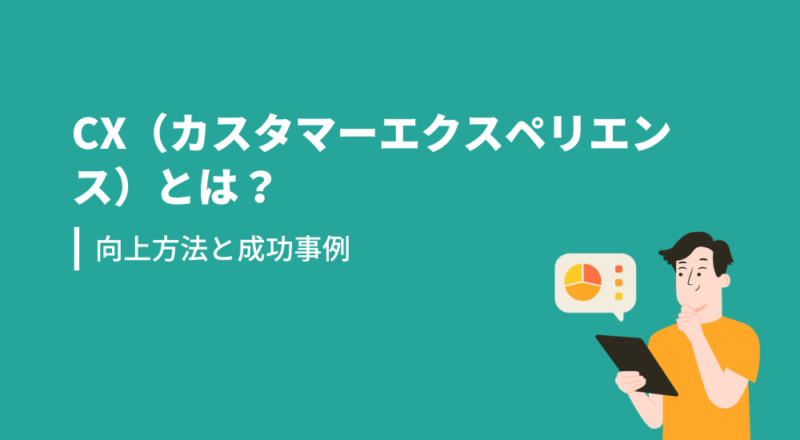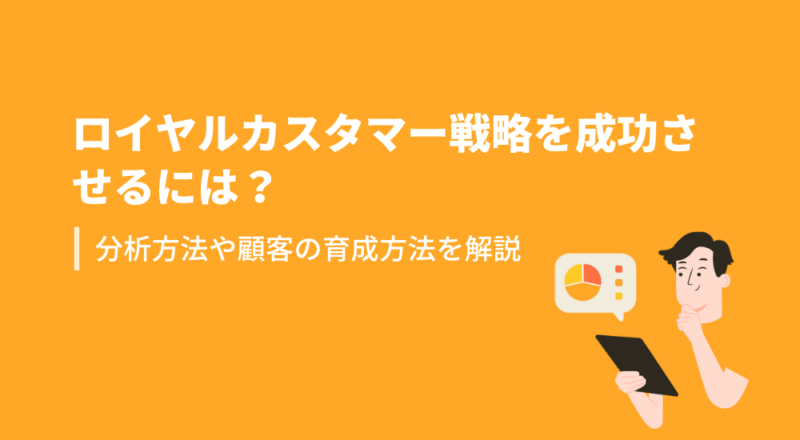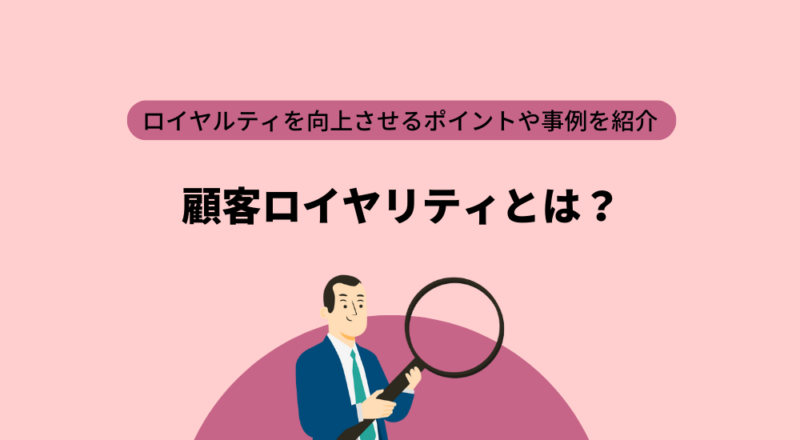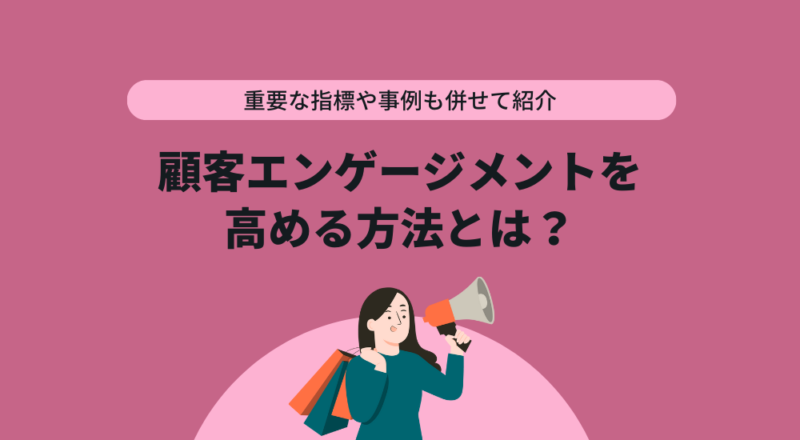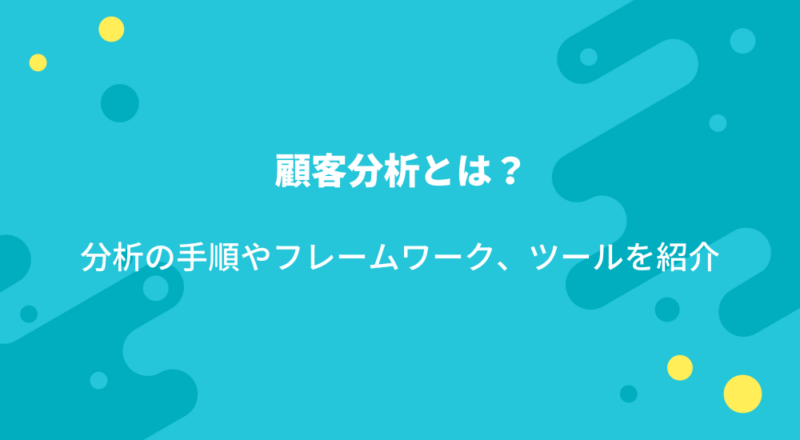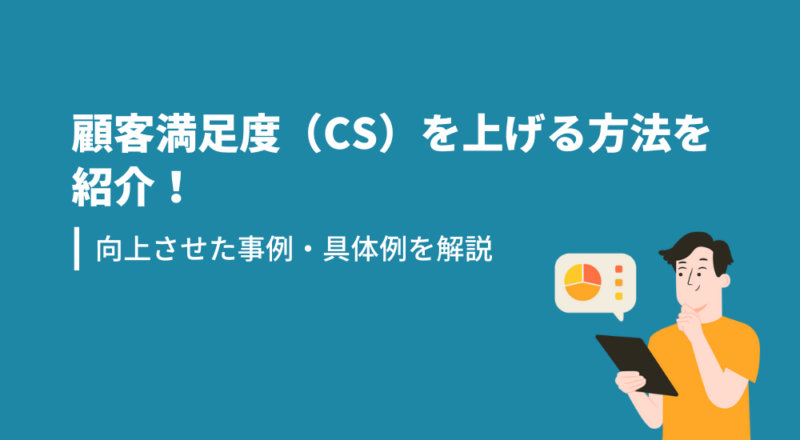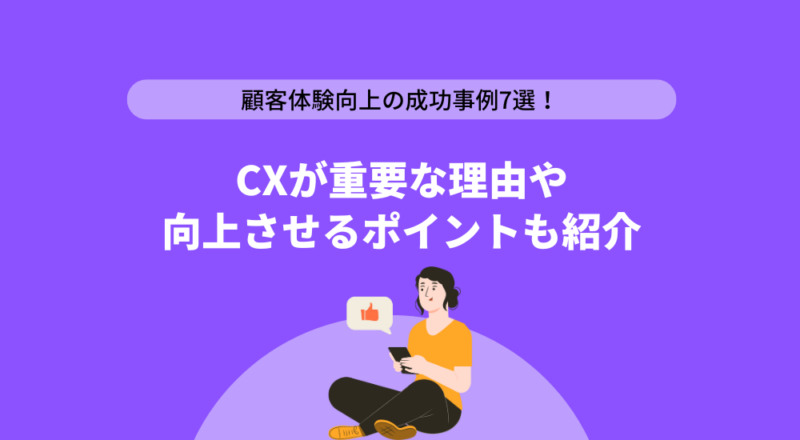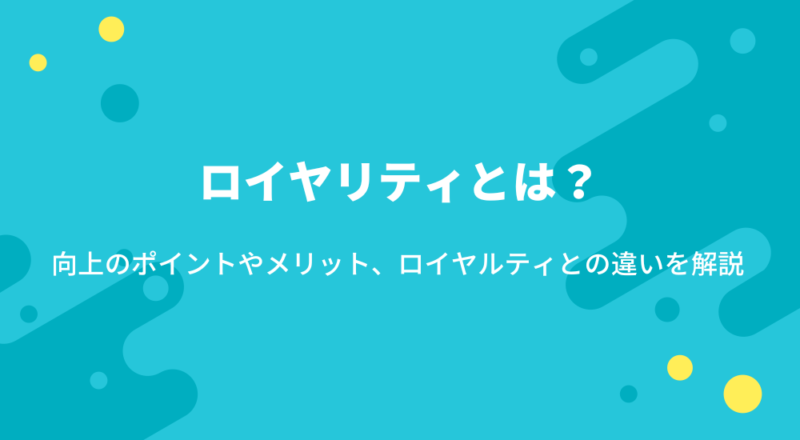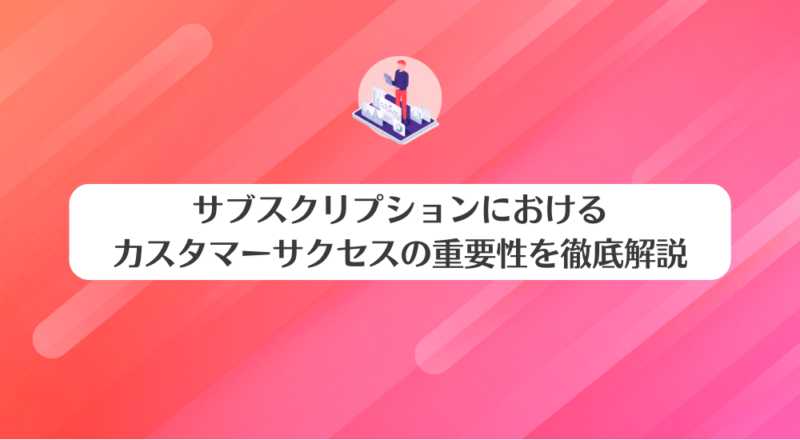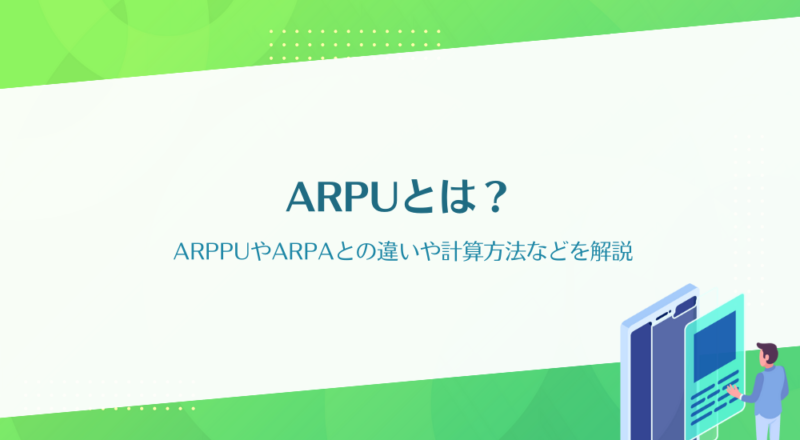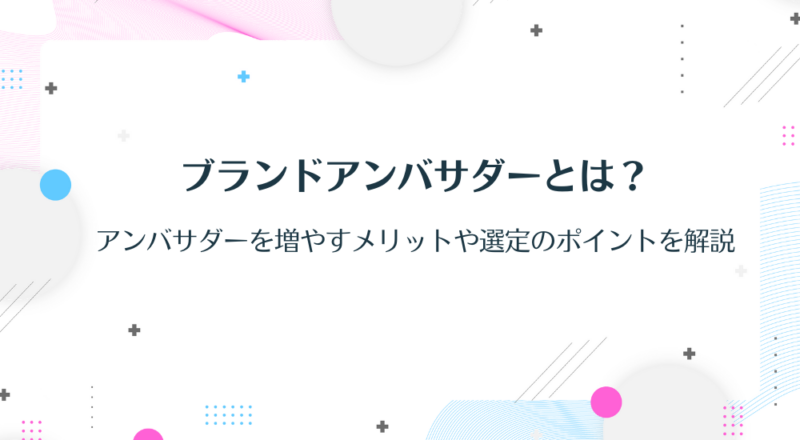
人口減少やコロナウイルスによる影響、技術革新のスピードアップにより、顧客の購買行動に変化が生まれています。それに伴い、企業はロイヤル顧客を増やすことを重要視するようになりました。
そこで本記事では、ロイヤル顧客が求められる理由や事業インパクト、データの活用方法についてご紹介します。
ロイヤル顧客と社会の変化
最近、以下のようなご相談を受けることが増えてきました。
- ロイヤル顧客の育成がうまくできない
- どんな施策を打てばいいか分からない
- ロイヤル顧客増加の検証方法が分からない
- ロイヤル顧客を育成し売上を上げるためのデータ戦略がない
その背景として、真のロイヤル顧客を増やしたいという企業が増えてきたことが挙げられます。
そもそもロイヤル顧客を増やす方法として、ポップアップやWEB接客といった顧客体験の改善を行うツールを活用することができます。ですがこれらの方法では、真のロイヤル顧客を増やすことに繋がらないと企業側が感じはじめているのです。
そんな中「ロイヤル顧客とは誰なのか」「どう増やしていけばいいのか」そういった課題に企業は関心が移ってきています。
製品・サービスに好意的な認識を持ち、かつ契約や購買の面で長期的に売上に貢献してくれる真のロイヤル顧客を増やすことが重要と考えているのです。
真のロイヤル顧客が求められる理由
では、なぜ真のロイヤル顧客の重要性が上がってきているのでしょうか。
それは以下の3つの理由が挙げられます。
理由①衝動的な購買行動の減少
まず1つ目の理由は、コロナウイルス拡大の影響が挙げられます。コロナウイルス以降、顧客の衝動的な購買数が減少しました。
ですがその代わり、「この会社でこのサービスだから購入したい」といった購買行動が増えてきたため、企業から真のロイヤル顧客が求められるようになったのです。
理由②人口減少、少子高齢化
2つ目の理由は、人口減少や少子高齢化社会により、中長期的に新規のお客様が減少しているということが挙げられます。
ターゲットとしている市場人口が減少している中で、既存の顧客に継続して購買していただける形にならないといけないと考える企業が増えてきたためです。
理由③成熟市場で機能勝負だけでは困難
そして3つ目の理由は、成熟市場の技術革新のスピードが、以前と比べ圧倒的に早くなっているということが挙げられます。インターネットのスピードの速さによって、機能価値や価格といった選択肢の幅が増えました。
そんな中で、機能的価値はすぐに真似されてしまうため、中々競合優位を築くことが難しくなってきているという背景があります。
販売促進を中心とするマーケティングの限界
今ご説明した3つの理由から、企業は真のロイヤル顧客が求められているにも関わらず、日本ではマーケティング活動や顧客育成の活動が全くされていないという状況です。
先ほどお話したポップアップやWEB接客の場合は、顧客にとっての購入のしやすさだったり、クーポンやセールを行うことでまず最初に購買してもらったりという点では重要です。
ですがそれらの施策は、短期的な売上には繋がっても長期的なブランドの棄損をしてしまったり、ファンが育成できるわけではないので売上がストック化しないだったりといった課題があります。そのため、企業が真のロイヤル顧客を増やしていきたいと思う大きな背景となっているのです。
【実態】withコロナで明らかになった勝者の正体
実際に、withコロナになり明らかになった勝者がいます。その勝者の正体は、ロイヤル顧客の収益比率が高い企業です。
勝者からは「この会社から買いたい」「そのサービスだから好きで購入する」といった顧客の購買行動が見られ、企業や製品・サービスが生き残っていく理由となっています。
逆にこのような理由がなかった企業は、コロナウイルスによる影響を大きく受けました。
結果として、ロイヤル顧客を増やすというところに経営をシフトしていくことに、企業は重要性を感じています。
ロイヤル顧客を増やした先にあるものは?
ロイヤル顧客が重要視されるようになった背景を踏まえ、実際にロイヤル顧客を増やした先にあるものや、どこを目指せばいいのかについてご説明します。
明確に進行するゲームチェンジ
今までは売上至上主義というところで、データにより販売の最適化をしようという動きが少しずつ出来てきています。ですが、デジタルマーケティングが発展してきた中で、データを活用し売上を改善したとしてもロイヤル顧客は育たないため、長期で売上が改善していく仕組みを作ることが難しいということが明らかになりました。
そういったことから、1回の購入よりもちゃんと製品・サービスに愛着を持ってもらったうえで、継続して購入してもらう活動が重要になります。
さらに、顧客に愛着を持ってもらうために、データを活用しどう改善をするかというところにマーケティングの重要性がシフトしていっています。
狙いの整理
真のロイヤル顧客を増やそうとする狙いは、以下の3つが挙げられます。
- LTVへの貢献
- VOCの収集の強化
- UGCを創出する
この3つの狙いの通り、長期的にロイヤル顧客が生まれる仕組みを構築することが重要なのです。それでは1つずつ解説していきます。
狙い①LTVへの貢献
まず1つ目の狙いは、LTVへの貢献です。
コロナウイルスの状況下で経営が不安定になった企業がある一方、指名買いが多かった企業が注目されるようになりました。
その背景としては、ロイヤル顧客の売上比率が高いといった点が挙げられます。
ロイヤル顧客の売上比率が高いと、コロナウイルスのような外部環境の影響が少なく、売上が安定的で持続的な成長を目指しやすいという利点があります。
そのため企業は、ロイヤル顧客に支えられた売上の重要性に狙いを変えてきています。
狙い②VOCの収集の強化
2つ目の狙いは、ロイヤル顧客から真の顧客の声を集めるといった、VOCの収集の強化になります。
そもそもなぜVOCの収集が重要かというと、真のロイヤル顧客はその製品・サービスをなぜ気に入っているのかを言語化ができる点がポイントになります。
真のロイヤル顧客の声を集めることによって、市場のニーズを反映した製品・サービスを作ることができ、また競合優位を築いていくことに繋がるのです。
狙い③UGCを創出する
3つ目の狙いは、UGCを創出し、長期でロイヤル顧客が生まれる仕組みを構築すること挙げられます。
近年ではSNSが発達し、マスマーケティングによる情報拡散よりも、信頼できる人の情報発信の方が購入しやすいといったように、消費行動の意思決定プロセスが変化しています。
そのため何を発信するかより、誰が発信しているのかが重要なポイントになります。
企業は真のロイヤル顧客を育成しUGCを創出することで、信頼できる立場の人が言っているから購入するという人達をいかに増やすかという方向性に狙いをシフトしてきています。
ロイヤル顧客と事業インパクト
ここからは実際に、ロイヤル顧客と事業インパクトに関してデータでどのように保管するのかやその活用方法について、先ほどお話した3つの狙いを踏まえてご説明していきます。
ロイヤル顧客の事業インパクトをデータで捉える
まずロイヤル顧客の事業インパクトをデータで捉えるために、下記のポイントを押さえることが重要になります。
- ロイヤル顧客のUGCと経営インパクトを可視化
- ロイヤル顧客のVOCと経営インパクトを可視化・測定
- ロイヤル顧客がどのくらい事業貢献しているかのLTVの可視化・測定
この3つのポイントをデータで捉えることで、ロイヤル顧客の現状を把握することができます。
事業インパクトを出すための具体的ステップと戦略
次に、データベースでロイヤル顧客を捉え、具体的にどんな戦略の元で何をするかについてご紹介します。
事業でインパクトを出すための具体的なステップは以下の4つです。
- コミュニティを形成し、ロイヤル顧客が集まる場所を作る
- データでコミュニケーションの質的拡大を促進する
- ロイヤル顧客に関するデータを連携・統合する
- ロイヤル顧客化のトリガーを発見し、量的拡大を推進する
上記の4つのステップを推進するためには、先ほどお話したまずロイヤル顧客が誰なのかを明らかにすることが重要なポイントになります。
継続して購入はしても、他社で新しいサービスが出た時にそちらへスイッチングしてしまう方々は、ロイヤル顧客ではありません。
想定していたロイヤル顧客と認識がずれてしまう恐れがあるため、数か月単位ではなく、年単位でしっかりと長期的にデータを見て、囲い込んでいく必要があるのです。

データでコミュニケーションの質的拡大を促進する
ここからはデータを活用して、コミュニケーションの質的拡大を推進していく方法をご説明していきます。
まずコミュニケーションの質的拡大を推進していくうえで、前提としてロイヤル顧客の交流こそがコミュニティの価値を最大化させることが重要なポイントになります。
その理由は、ロイヤル顧客の交流がコミュニティに定着することで、以下のような構造が完成するからです。
- ユーザーが定着しUGCが形成され、企業にとって価値のある投稿が増える
- UGCが形成されると、VOCの収集や顧客育成を通じたLTVに寄与する
このような構造を作るために、コミュニケーションの質的拡大を推進するうえで、ロイヤル顧客同士の交流の総量をいかに増やすのかが重要なのです。
コミュニケーションの質的拡大のために重要なこと
ロイヤル顧客同士の交流を増やすうえで、コミュニティの量的拡大として登録者数を追ってしまいがちです。ですが、ロイヤル顧客の量的拡大はコミュニティ以外でも増やすことができるため、まずはロイヤル顧客を発見する必要があるのです。
今からは、コミュニティの質的拡大を推進する上で重要とされる、以下の2点についてご説明いたします。
- コミュニケーションバランスが保たれた状態かをデータで可視化する
- ロイヤル顧客同士のコミュニケーションが拡大しているかデータで可視化する
まず前提として、「コミュニティ運営における数値指標」と「コミュニティの事業貢献の数値検証」は指標として分けて考える必要があります。
以下の画像は「ロイヤル顧客が定着しやすいコミュニケーションバランスが保たれているかデータで可視化する」、そして「ロイヤル顧客同士の交流の総量が適切に伸びてきているかデータで可視化する」といった2点を表したものになります。

1つ目の画像は、コミュニティ自体の状態が健全かどうかを表したものです。
コミュニティの中にどういう方々がなんの役割をはたしているのか、そのバランスを上記の画像のように追いかけていく必要があります。
特に積極的にアクションをしてくれる方々と、見守った形でいつも見ているという方々のバランスが非常に重要です。
そのバランスがどういう風に進捗しているのかを、コミュニティの中で数値として見ていく必要があります。

2つ目の画像は、事業貢献できる状態になっているかの健全性を確認するものです。
これは、簡単にいうと「ロイヤル顧客同士の交流の総数」つまり「コミュニティの熱量」になり、この部分がきちんと拡大しているかどうかが、非常に重要なポイントになります。
上記の画像を見ると、赤い部分が数値として大きくなると事業貢献できる状態というのが確認できるようになっています。
ロイヤル顧客に関連するデータを連携・統合する
ロイヤル顧客プラットフォーム「コーラム」では、コミュニケーションの質的拡大を推進できる状態を作ると同時に、ロイヤル顧客に関するデータを連携統合する作業を行っています。
コーラムはコミュニティの機能だけでなく、外部データを連携統合する仕組みをもっており、CRMやMAといった統合済みのデータだったり、ECやSNSデータといった未統合のデータだったりも簡単に連携することができます。
またデータを自動収集して、ロイヤル顧客に関するデータを全て連携統合することもできます。これにより、ロイヤル顧客がどんな状態にあるのかを、まずは見える化するプロセスを踏んでいます。

上記の画像は一部の例で、ロイヤル顧客に関するデータを統合することで、実際顧客がどうなっているのかを可視化していきます。
またコミュニティの中にいるロイヤル顧客の状態が分かると、コミュニティの中のロイヤル顧客はもちろん、コミュニティの中に含まれない顧客を含め実態がどうなっているのかを可視化することができます。
心理的ロイヤリティーの高い顧客を捉える
コーラムの高評価ポイントは、コミュニティに存在する顧客は心理的ロイヤリティーが高いということです。
いろんな顧客体験の改善ツールがありますが、心理的ロイヤリティーの高い顧客を捉えることは、実は本当は難しかったりします。ですがコーラムの場合、コミュニティに来る顧客は、心理的ロイヤリティーが高い方しか逆に来ません。
またコーラムは、「データ統合機能」と「データの自動収集機能」をセットで提供しています。そのためコミュニティに存在する顧客データを購買データを含め、アクティビティのデータを統合し、定性と定量の2軸からなぜロイヤル顧客になってくれたのか、事業貢献してくれるかどうかを明らかにすることができます。
ロイヤル顧客化のトリガーを発見し、量的拡大を促進する
最後は、ロイヤル顧客のトリガーを発見し、量的拡大を促進することについてご説明します。
100社以上の様々なお客様の支援から、ロイヤル顧客化のトリガーとなる体験があることが分かってきました。そこでコーラムでは、最後にトリガーとなる体験を見つけるプロセスを取っています。
とある化粧品メーカーの事例
とある化粧品メーカーでは、最初ロイヤル顧客は美容液を購入してくれる方と思っていました。ですが、実際にロイヤル顧客を発見しデータで遡ったところ、接客での詳細説明により洗顔製品の購入をしていることが最初のトリガーとなっていると分かりました。またその次に、個室で接客を受け化粧水の購入するというプロセスを踏んでおり、この2つを体験した方が結果的にロイヤル顧客になっていたのです。
美容液はロイヤル顧客が最後に購入するもので、ロイヤル顧客を象徴する製品ではあったもののトリガーではありませんでした。
こういった事例から、ロイヤル顧客のトリガーもしっかりと見える化し利用することで、他の顧客接点を順番に改善していくことができるのです。
まとめ
今回は、ロイヤル顧客が求められる理由や事業インパクト、データの活用方法についてご紹介しました。
まとめると、コミュニティを形成することは、ロイヤル顧客が集まる場所を作ることやどういった方なのかを発見するということです。その中で、コミュニティの質的拡大を通して大きくしていくことで、ロイヤル顧客が集まる仕組みを作ることができます。
またコミュニティの質的拡大と並行し、ロイヤル顧客に関するデータを連携統合することで、データ上でロイヤル顧客がどういった方々なのかを明確にしていくことが大切になります。
さらに、ロイヤル化したトリガーを明らかにすることで、メカニズムの言語化ができ、再現性を持ってロイヤル顧客を増やして行くことができるのです。
ロイヤル顧客の育成や施策、検証方法に悩んでいる方は、今回の内容をぜひ参考にしてみてくださいね。